「サーベイを実施しているものの、思ったような効果が出ていない」と悩んでいる経営者や、人事担当者の方もいるのではないでしょうか。
サーベイで得られた情報を有効活用するためには、従業員との対話によるフィードバックが欠かせません。
しかし、調査結果を施策に反映できていない場合、サーベイ後に行うフィードバックの方法や手順に問題がある可能性があります。
そこで本記事では、従業員との対話を重視した「サーベイフィードバック」の概要に加え、以下の内容を詳しく解説します。
- サーベイフィードバック実施による4つの効果
- 対話の質が向上!サーベイフィードバックの具体的な手順
- 人事領域で活用されているサーベイ【企業事例あり】
この記事を読むことで、サーベイ後のフィードバックの質を高め、組織の課題を従業員と共有しながら改善につなげる具体的な方法がわかります。
また、エンゲージメントサーベイを活用した組織づくりや、離職率を改善する方法をまとめた資料もご用意しています。無料でダウンロードできますので、本記事と合わせてぜひご活用ください。
>>「【実例から学ぶ】エンゲージメントサーベイによる組織構築」の資料をダウンロードする
サーベイフィードバックとは?【対話重視のフィードバック】

サーベイフィードバックとは、調査結果をもとに、組織の課題や解決策を従業員との対話(フィードバック)を通して考える手法のことです。
企業が行うサーベイは、組織に対する満足度やエンゲージメント、仕事へのモチベーションを定量的に測定し、組織全体の状態を把握するために実施します。
その結果をもとにチーム内や従業員個人と対話し、「理想の未来」や「アクションプラン」を決めることが、サーベイフィードバックの特徴です。
たとえば、サーベイの結果から、社内のコミュニケーション不足が明らかになった場合、フィードバックを通じて以下のような対策が打てます。
- メンバー同士で気軽に会話できる時間を設ける(コーヒーブレイク など)
- リアルタイムの情報共有が可能な「社内ポータルサイト」を構築する
フィードバックを通じて現場のリアルな声を直接聞くことで、組織内の見えない課題が浮き彫りとなり、より実効性の高い施策を検討できます。
サーベイフィードバックが必要とされる理由

近年、働き方や価値観が多様化し、従業員一人ひとりが求める職場環境も大きく変化しています。
そのなかで、従業員の声を的確に拾い上げ、施策に反映する手段として「サーベイフィードバック」の重要性が高まっているのです。その他にも、以下のような理由が挙げられます。
- 多様化する人材を一つにまとめるため
- エンゲージメントを高めて、離職率の低下を図るため
- 管理職の武器として活用するため
サーベイフィードバックでもっとも重要なプロセスは「従業員との対話」です。従業員の意見や感じていることを丁寧に引き出さなければ、エンゲージメントを高める取り組みは実現できません。
日本経済団体連合会の調査によると、214社に「社員のエンゲージメントが低い層」を質問したところ、約3〜5割は「中堅層」「若手層」と回答しました。
参考:2024年人事・労務に関するトップ・マネジメント調査結果(P27)|日本経済団体連合会
中堅・若手社員のエンゲージメント低下は、将来的な人材流出や組織力の低下につながるリスクもあるため、早い段階で手を打つ必要があります。
つまり、企業はサーベイフィードバックを実践し、従業員とともに組織改善に取り組むことが求められています。
エンゲージメントサーベイ導入における課題や対策を確認したい方は、以下の記事をご覧ください。サーベイフィードバックを含めた運用フローを紹介しています。

サーベイフィードバック実施による4つの効果

サーベイフィードバックを実践することで、以下の4つの効果が期待できます。
サーベイの効果を最大限に引き出すためには、従業員と真剣に向き合い、課題解決に向けた対話を重ねることが重要です。
以下より、それぞれの効果を詳しく解説します。
エンゲージメントの向上によって離職防止につながる
サーベイフィードバック実施による効果の一つは、従業員の意見やニーズを踏まえた組織改善によって、エンゲージメントが向上する点です。
自社への愛着が生まれ「この会社で働き続けたい」と感じる従業員が増えることで、結果として組織全体の離職防止につながります。
ただし、サーベイの結果だけを鵜呑みにして施策を行っても、期待した効果は得られません。
サーベイの結果を従業員に提示し、「どのような取り組みをしたら働きやすい環境になると思うか」と対話を重ねることが重要です。
株式会社リーディングマークの調査によると、大企業を対象に「若手社員の離職対策で効果を感じたもの」を質問したところ、フィードバックに関連する施策の回答が多く見られました。
- 定期的な1on1面談の実施(36.8%)
- フィードバックを重視した評価制度の導入(9.0%)
- エンゲージメントを測る調査ツールの活用(6.1%)
組織は現場の声を真剣に受け止めることで、従業員自身も意見を受け入れられたと感じ、組織への忠誠心を持つようになります。
以下の記事では、離職防止のアイデアや施策を多数紹介しています。「離職の原因がわからない」と悩んでいる人事担当者の方は、ぜひ参考にしてみてください。

現状と課題を「見える化」し、改善策を立案できる
サーベイフィードバックの実践によって、普段の面接やミーティングではわからない、組織の現状と課題が浮き彫りになります。
従業員との対話を通じて、課題の背後にある原因を追求することで、表面的な取り組みではなく、根本的な課題の解決につながる施策の立案が可能です。
「表面的に見えるもの」と「潜在的に隠れているもの」を説明する際には、以下の図のような「氷山モデル」がよく用いられます。
組織における「氷山モデル」の具体例は、以下のとおりです。
| 氷山の上 (表面的に見えるもの) | ・従業員の能力 ・職場の労働環境 ・仕事内容 |
| 氷山の下 (潜在的に隠れているもの) | ・コミュニケーションの取り方 ・意思決定に対する納得感 ・社内の暗黙的なルール |
このように、サーベイフィードバックは氷山の上に見える「結果」だけでなく、水面下に隠れた「原因」を明らかにする有効な手段と言えます。
従業員同士の良好な人間関係を構築できる
従業員との対話やミーティングを通して、活発なコミュニケーションを取ることで、従業員同士の信頼関係を構築できます。
サーベイフィードバックでは、従業員同士の対話やチームミーティングがもっとも重要なプロセスです。
チーム内の人間関係が構築され、悩みや不安を気軽に相談できるようになることで、従業員のストレスや心理的な不安も軽減されます。
ただし、チームミーティングにおいては、課題や問題の原因となる人物を特定したり、相手を見下したりするような発言は避ける必要があります。
サーベイフィードバックは、従業員が感じている本質部分を引き出すことを目的としているため、親身に話を聞く姿勢(傾聴)を示すことが大切です。
以下の記事では、社内コミュニケーションを活性化させるアイデアを多数紹介しています。企業の成功事例も紹介していますので、本記事と合わせて確認してみてください。

管理職のマネジメント能力が向上する
サーベイフィードバックでは、管理職がアドバイスや今後の方針を説明し、部下やチームメンバーの行動を促す必要があります。
フィードバック時に、「どのように課題を伝えるか」「どうすれば納得してもらえるか」を考えることで、管理職のマネジメント能力の向上につながるのです。
社会や組織、個人の考え方は常に変化しており、管理職の「勘」や「経験」だけに頼ったマネジメントでは効果を引き出せません。
しかし、サーベイフィードバックを実践することで、裏付けされた情報に基づいたマネジメントが可能になります。その結果、管理職は客観的かつ説得力のある判断を下せるようになるのです。
また、定量的なデータから「経年変化」を用いて対話することで、従業員一人ひとりの状況に合わせて仮説を立てながらマネジメントができます。
参考:ミキワメ ウェルビーイングサーベイを活用したマネジメント手法
部下との信頼関係を深める方法については、以下の記事でも詳しく解説しています。管理職のマネジメントに課題のある企業は、本記事と合わせてぜひご活用ください。

サーベイフィードバックの手順【5ステップ】

ここからは、サーベイフィードバックの手順について、立教大学の中原教授が執筆した書籍を参考に解説します。
※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください
| 基本ステップ | 手順 | |
|---|---|---|
| 第1フェーズ | 見える化 | サーベイを実施する |
| 結果の集計・分析を行い、組織状態を可視化する | ||
| 第2フェーズ | ガチ対話 | データを提示し、社内で対話する |
| 未来づくり | アクションプランを検討・実行する | |
| 定期的なサーベイで組織状態を確認する |
参考書籍:「データと対話」で職場を変える技術 サーベイ・フィードバック入門 これからの組織開発の教科書|株式会社PHP研究所
調査・分析しただけでは、現状把握で終わってしまいます。そのため、従業員との対話を通して、組織の潜在的な課題を把握することが重要です。
以下より、各ステップを一つずつ解説します。
1.サーベイを実施する
まずは、サーベイの目的や対象者を決めて、自社に合った調査方法を選定します。
調査目的を決めるときは、職場の問題や課題を従業員からヒアリングして、事前に組織全体の現状を把握しておきましょう。
目的が不明確なままだと、本質を突くような質問ができず、データを分析しても具体的な施策につなげられません。
また、調査・分析を自社で行う場合は、サーベイツールの導入が必要です。以下のポイントを検討しましょう。
- 目的に合致しているか
- スマホやPCでの回答に対応しているか
- 従業員の性格に応じた設問を設定できるか
- 集計・分析機能は充実しているか
- 簡単にレポート出力・共有ができるか
- 予算内で導入できるか
サーベイを行うときは、従業員に対して目的や調査方法を周知し、必ず理解を得てから実施する必要があります。
2.結果の集計・分析を行い、組織状態を可視化する
続いて、サーベイの結果を集計・分析し、組織の状態や傾向を可視化します。
組織全体の状態だけでなく、部署ごとや属性ごと(年齢、役職 など)に比較・分析することで、特定の層だけに見られる課題を把握できます。
データの集計や分析を正確かつ効率的に行うために、適切なツールやソフトウェアを活用し、データの整合性を確保しましょう。
分析結果は、誰でもひと目で判断できるように可視化し、組織・個人それぞれの課題や改善策をわかりやすく伝えることがポイントです。
サーベイツールの『ミキワメ ウェルビーイングサーベイ』では、組織(部署)ごとに調査結果を表示できるため、他部署との比較が容易に行えます。

組織状態の可視化によって、「どの部署に課題が集中しているのか」「どの属性の層で不満が出ているのか」を直感的に把握できます。
サーベイ結果の分析方法を詳しく知りたい方は、以下の記事を確認してみてください。分析結果の活用方法や、企業の取り組みをわかりやすく解説しています。

3.データを提示し、社内で対話する
ここからは、基本ステップの第2フェーズ「ガチ対話」です。
具体的には、サーベイで得られた情報を従業員に提示し、対話やチームミーティングを通してフィードバックを行います。
対話の手法として、目的説明からアクションプランの決定までを行う「フィードバックミーティング」が効果的です。以下の6ステップで行います。
※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください
| 手順 | 内容 | |
|---|---|---|
| 1 | 目的説明 | 職場やチームに関係するすべての人を集め、ミーティングの目的やアジェンダを説明する |
| 2 | ミーティングルールの提示 | 従業員が本音の対話をできるように、ミーティング内で守るべきルールを決める |
| 3 | データの提示 | シンプルかつわかりやすい調査データをメンバーに提示する |
| 4 | データに対する解釈 | データに対して従業員一人ひとりが日頃から思っていることや、感じていることを発言してもらう |
| 5 | 「未来」に向けた話し合い | 組織や自分自身の現状と「これからの未来はどのようにありたいのか」を話し合う |
| 6 | アクションプランづくり | 明日から実行できる具体的なアクションプランを決める |
話し合いをするときは、従業員の意見に対して感情的な反応や批判を避け、親身になって耳を傾ける姿勢が重要です。
4.アクションプランを検討・実行する
フィードバックミーティングで、「理想を実現するために、どのような行動をすべきか」を議論し、実際のアクションプランに落とし込んでいきます。
アクションプランの検討・実行においては、以下のポイントを押さえておきましょう。
- メンバー全員が関わるアクションプランを立てる
- 達成可能な中長期のステップを決める
- フォローし合いながらアクションプランを進める
- 達成後はチーム内でねぎらいの言葉をかける
プラン実行時はチームリーダーを決めた上で、スケジュールの設定やリソースの確保が必要です。
また、週次や月次で進捗確認を行い、計画より遅れている場合は軌道修正するなど、柔軟に対応できる体制を整えておきましょう。
5.定期的なサーベイで組織状態を確認する
サーベイフィードバックは、一度で終えるものではなく、定期的に繰り返すことで効果を発揮します。
組織・個人の状態は常に変化するため、定期的にサーベイを実施し、継続的なモニタリングが必要です。
【モニタリングのポイント】
- 同じ設問を繰り返し、前回のデータと比較する
- 数値だけでなく、自由意見やコメントも確認する
- 改善施策とスコアの関連性を検証する
- 結果を共有し、次のアクションに反映する
定期的に調査を行う場合は、週1回・月1回といった高頻度の調査が可能な「パルスサーベイ」が適しています。
ただし、調査を頻繁に行いすぎると、従業員の負担が増える可能性があります。一方、実施間隔が長くなると、スコアの変化を迅速に把握できません。自社の状況に合わせて、適切な頻度とタイミングを検討しましょう。
『ミキワメ ウェルビーイングサーベイ』では、カスタマーサクセスチームのサポートを受けながら、サーベイの運用体制を構築できます。現在、無料トライアルも実施中ですので、お気軽にお問い合わせください。
人事領域でよく活用されている4種類のサーベイ【事例あり】

人事領域でよく活用されているサーベイとして、以下の4種類が挙げられます。企業の活用事例も合わせて解説します。
※以下の表は右にスクロールできます
| 種類 | 概要 | 活用事例 | |
| 効果 | 企業名 | ||
| エンゲージメントサーベイ | 従業員のエンゲージメント(組織への貢献意欲)の状態を把握するための調査 | 仕事を休む従業員が「1日3〜4人」から「月1〜2人」まで減少 | 未知株式会社 |
| パルスサーベイ | 週1回や月1回の高頻度で、従業員の満足度やコンディションを測定する調査 | 「ケアすべき人」を把握し、面談や業務調整によって離職を防止 | 嘉穂無線ホールディングス株式会社 |
| 従業員サーベイ | 従業員に対してエンゲージメントや満足度などを総合的に測定する調査 | 離職の傾向がある従業員をいち早く察知し、適切なケアができる体制を構築 | 株式会社フォーラス&カンパニー |
| ESサーベイ (従業員満足度調査) | 職場環境や人間関係に対する満足度を測定する調査 | 休職者数が四半期で「5〜6人」から「1〜2人」に減少 | 株式会社ラクスパートナーズ |
以下より、各サーベイの特徴を詳しく解説します。自社の目的と照らし合わせながら、最適なサーベイを選択してみましょう。
なお、サーベイの名称は、測定の対象・内容・方法によって命名されています。上記以外の種類を詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
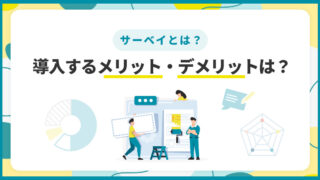
エンゲージメントサーベイ
エンゲージメントサーベイは、組織に対して「従業員がどの程度の愛着や貢献意欲を持っているか」を測定する調査です。エンゲージメントを中心とした質問を行い、組織の状態や傾向を可視化することを目的としています。
そもそもエンゲージメントは、以下の2種類に分類されており、それぞれ概念が異なります。
| 種類 | 概念 |
|---|---|
| 従業員エンゲージメント | 「組織のために貢献したい」と感じる意欲のこと |
| ワークエンゲージメント | 仕事に対してポジティブな感情を持ち、充実した心理状態であること |
実際の調査では、「組織のビジョンや価値観に共感しているか」「仕事へのやりがいを感じているか」といった質問で、組織との関係性を把握します。
また、従業員が内に秘めている問題や課題を浮き彫りにすることで、他部署でも同じ事象がないか確認するなど、社内での横展開も可能です。
| エンゲージメントサーベイの活用事例 |
|---|
| 未知株式会社では、従業員のエンゲージメントが低下し、仕事を休む人が1日3〜4人も発生する時期がありました。 そこで同社は、サーベイで従業員の状態を把握し、「会社への愛着」や「人間関係」などの項目ごとに改善アクションを実行しています。具体的な施策は、以下のとおりです。 ・ポジティブな発信を促す「うれしいねLINE」 ・誰かの好きなポイント紙に書いて渡す「お紙(推しとかけている)」 改善策を実行した結果、従業員とのコミュニケーションが活発になり、仕事を休む人が「月に1〜2人」まで減少しました。 事例:サーベイの結果から改善アクションを実施し、エンゲージメントが劇的に改善|未知株式会社 |
エンゲージメントサーベイの詳細については、別の記事で詳しく解説していますので、本記事と合わせて確認してみてください。
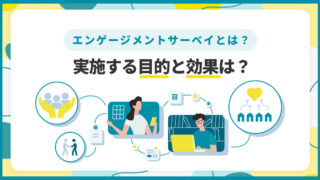
パルスサーベイ
パルスサーベイは、従業員の満足度やコンディションを「週1回」や「月1回」といった、高頻度で調査を行う方法です。質問数も「約5〜15問」と少なく、従業員の負担を軽減できる点も特徴の一つです。
短いスパンかつ定期的に調査が行えるため、施策後の効果・検証や、従業員の状態変化の把握に活用できます。
たとえば、調査結果から従業員のスコア低下がみられた場合は、その原因を早期に特定し、迅速な対策やサポートができます。
パルスサーベイは、その名称のとおり、脈を測るように「組織の健康状態」を定期的に確認できる点が大きな特徴です。
| パルスサーベイの活用事例 |
|---|
| 嘉穂無線ホールディングス株式会社では、離職者を減らすための施策として、従業員の心理状態の確認やケアができるパルスサーベイを導入しています。 各店舗の店長は、サーベイで可視化された「心の状態」を確認し、従業員一人ひとりとコミュニケーションを取るように、対応方法を改善しました。 その結果「ケアすべき人」をひと目で把握できるようになり、対象者との面談や業務調整を通じて、離職の防止につながっています。 事例:従業員の状態を可視化し、個々の強みを活かせる組織に|嘉穂無線ホールディングス株式会社 |
以下の記事では、パルスサーベイの概要や導入による効果を詳しく解説しています。よく利用されているツールも紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
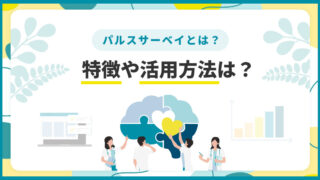
従業員サーベイ
従業員サーベイは、職場環境や制度など幅広いテーマの質問を通じて、従業員の状態を総合的に測定する調査です。主な調査項目は、以下のとおりです。
- 従業員満足度
- エンゲージメント
- ストレス
- モチベーション
- コミュニケーション
- 職場環境
従業員サーベイの目的は、従業員の率直な意見やニーズを収集し、その結果を組織改善に反映させることです。また、従業員の心理状態を数値化し、メンタル面の課題を発見することも目的の一つです。
サーベイの結果をもとに施策を実行することで、従業員は「自身の声が反映された」と実感します。その結果、組織の目標達成に貢献しようという意欲が高まり、より主体的に働くようになります。
| 従業員サーベイの活用事例 |
|---|
| 株式会社フォーラス&カンパニーでは、入社3年目を中心とした若い世代の離職が続いており、残った従業員への負担も増加していました。 そこで同社は、サーベイの結果をもとに「ケアが必要な人」を把握し、対象の従業員から詳しい心境を聞くように店長に伝達しています。 サーベイを導入したことで、組織・個人の状態が可視化され、離職の可能性がある従業員をいち早く察知できるようになりました。 また、「どのような手を打つべきか」がわかるようになり、適切なケアができる体制も構築できました。 事例:会社の未来を担う若い世代の離職の減少を目指す|株式会社フォーラス&カンパニー |
従業員サーベイの概要を詳しく知りたい人事担当者の方は、以下の記事をご覧ください。導入から活用までの手順も解説しています。

ESサーベイ(従業員満足度調査)
ESサーベイ(従業員満足度調査)は、職場環境や人間関係などに対する満足度を測定し、その結果を職場環境の改善に活用するための調査です。
調査結果を分析することで、従業員が「どのような点に不満や不安を抱えているのか」を把握できます。
たとえば、評価制度に対する不満が多く見られた場合、評価基準の明確化や、成果に応じたフィードバック面談などの施策を導入できます。
従業員にとっても「自分の意見が職場環境の改善に活かされている」と実感することで、モチベーションやエンゲージメントの向上につながるのです。
| ESサーベイの活用事例 |
|---|
| 株式会社ラクスパートナーズでは、休職する従業員が増加するなか、ケアを求めている人を把握できず、適切なサポートができていない状況でした。 サーベイ導入後は、月1回のアンケートで「ケアを必要としている従業員」をアラートで把握し、本人との1on1面談を実施しました。必要に応じて、営業担当やマネージャーと情報を共有しながら組織的に対応しています。 サーベイを軸とした施策によって、休職者数は四半期で「5〜6人」から「1〜2人」に減少するなど、大きな効果が得られました。また、管理職が従業員に声かけをするようになり、信頼関係の強化にもつながっています。 事例:ケアを求める社員をサポートし、休職者数の減少を実現|株式会社ラクスパートナーズ |
以下の記事では、ESサーベイの概要や測定項目を詳しく解説しています。効果を最大化させる実施のステップも紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

サーベイフィードバックで失敗しないためのポイント

サーベイフィードバックで失敗しないために、以下の3つのポイントを押さえておきましょう。
事前に従業員への説明を丁寧に行い、「なぜサーベイを実施するのか」「結果をどのように活用するのか」を明確に伝えることが重要です。
以下より、実施時のポイントを解説します。
結果を放置せず速やかにフィードバックする
従業員との対話を通して速やかにフィードバックすることで、従業員は組織や自身の問題、改善点を把握し、具体的な行動につなげられます。
調査結果を共有せずそのまま放置してしまうと、職場環境の変化やチームメンバーの入れ替えによって、情報が古くなってしまいます。
サーベイは、従業員の協力を得てはじめて実施できるものであり、結果を速やかにフィードバックすることが基本です。
迅速なフィードバックを行うことで、問題の早期発見と対処が可能となり、従業員のモチベーション向上にもつながります。
収集データを絞って作業負担を軽減させる
サーベイで収集する情報が多くなってしまうと、データの集計と分析に時間がかかり、人事部や管理職の作業負担が増加してしまいます。
そのため、調査目的と照らし合わせながら「質問すべき項目」を選定し、必要なデータだけを収集することが重要です。
収集データを絞ることで、集計作業を担当する人事担当者の負担が軽減されるだけでなく、結果を受け取る従業員や管理職に向けて「わかりやすい情報」を提供できます。
一度のサーベイでは、すべての情報を収集することは困難なため、質問数の少ないサーベイを複数回に分けて実施するなど工夫が効果的です。
長期的な視点で繰り返し行う
サーベイフィードバックを通じてアクションプランを実行したとしても、すぐに効果が現れるわけではありません。
定期的にサーベイを実施し、組織の状態や従業員のニーズを把握することで、改善の進捗や新たな課題を把握できます。このプロセスを繰り返すことが、持続的な組織運営や従業員満足度の向上につながるのです。
また、短期的な効果を期待して施策を行ったとしても、時代や環境の変化に対応しきれず、課題が解決されないまま深刻化する恐れもあります。
サーベイを継続的に行い、変化に合わせてフィードバックしていくことが、長期的な組織運営に欠かせない取り組みと言えます。
サーベイフィードバックを実践している企業の事例

サーベイフィードバックを実践している企業について、2社の取り組みをご紹介します。
※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください
| 取り組み | 実施による効果 |
|---|---|
| 定量的な数値をもとに「改善の必要性」をフィードバック | 組織改善の方向性について、社長や役員の「目線合わせ」がしやすくなった |
| パーパス(存在意義)浸透に向けた「1on1」の対話を実施 | エンゲージメントが向上し、従業員一人ひとりのチャレンジ意識も高まった |
他社の事例を参考にすることで、自社でも同様の取り組みを実施できるか、その判断材料となります。
以下より、各企業の取り組みを解説します。
定量的な数値をもとに「改善の必要性」をフィードバック|ウェブソア
インターネット広告代理業を行うウェブソア株式会社では、月1回サーベイを配信し、従業員の心理状態の変化を踏まえて、組織の課題を抽出しています。
サーベイの結果を社長と役員が確認できるように設定した上で、主に役員が「ケアを求めている社員」をサポートします。
また、事業部長に対して、組織全体の結果をフィードバックする取り組みも実施しました。
良いところも悪いところもフィードバックするため、ストレスを与えてしまうこともありましたが、前向きな取り組みとして継続中です。
組織やマネジメントのフィードバックは難しいですが、サーベイを活用することで、定量的な数値をもとに「改善の必要性」をフィードバックできています。その結果、組織改善の方向性について、社長や役員の「目線合わせ」がしやすくなりました。
事例:社員一人ひとりが理想的な状態で働ける会社であり続ける|ウェブソア株式会社
パーパス(存在意義)浸透に向けた「1on1」の対話を実施|SOMPO
SOMPOホールディングス株式会社では、中長期的につながる企業価値の向上を目指し、パーパス(存在意義)浸透の取り組みを行っています。
「人的資本への投資」の取り組みとして、従業員一人ひとりの「MYパーパス」に基づく対話を行い、エンゲージメントの向上を図りました。
同社では、組織内での対話や共有を重要視しており、とくに多様な価値観を認め合うための「1on1」に重点を置いています。
従業員との対話が多い組織ほど、エンゲージメントが高い傾向が確認されており、従業員一人ひとりのチャレンジ意識も高まっています。
参考:未実現財務価値の向上に向けて|SOMPOホールディングス株式会社
以下の記事では、マネジメント理論に基づく1on1のやり方を詳しく解説しています。組織と従業員の関係性のフェーズごとに、具体的な方法を紹介していますので、本記事と合わせて確認してみてください。

まとめ:サーベイフィードバックは従業員との対話が成功のカギ

サーベイフィードバックは、従業員の声を「見える化」し、対話を通じて課題解決につなげる重要な取り組みです。具体的な手順を改めて確認しておきましょう。
【サーベイフィードバックの手順】
定期的にサーベイを実施することで、組織と従業員個人の課題を把握し、働きやすい職場環境にするための施策を検討できます。
しかし、サーベイの結果だけでは「表面的な課題」しか把握できません。水面下に隠れている「潜在的な課題」を把握するには、対話によるフィードバックが必要です。
人事担当者の方は、長期的な視点でサーベイの運用計画を策定し、従業員との対話を通して組織改善に努めていきましょう。

従業員のメンタル状態の定期的な可視化・個々の性格に合わせたアドバイス提供を通じ、離職・休職を防ぐエンゲージメントサーベイ。無料トライアルの詳細は下記から。



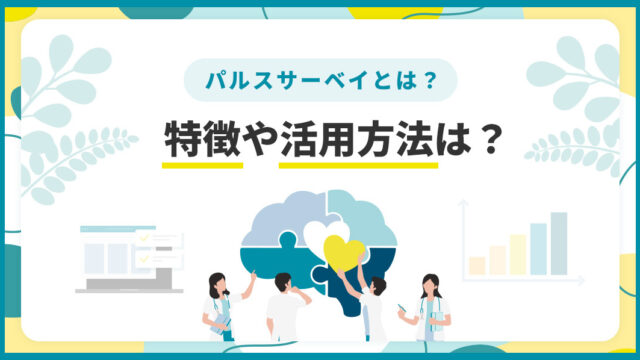


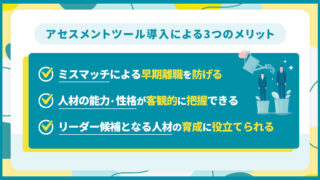





 ランキング1位
ランキング1位 
 ランキング2位
ランキング2位 
 ランキング3位
ランキング3位 