社員の声を組織改善に活かすため、エンゲージメントサーベイの導入を検討している方も多いのではないでしょうか。
しかし、サーベイには数多くの種類があるうえに、質問項目や調査方法もさまざまです。そのため、導入目的を明確にし、どのような観点でサーベイを選ぶべきか検討する必要があります。
そこで本記事では、エンゲージメントサーベイの具体的な選び方や導入時の確認ポイント、よくある失敗例までわかりやすく解説します。
- 自社に合ったエンゲージメントサーベイの選び方 5ステップ
- 導入時に確認すべきポイント【チェックリスト付き】
- サーベイ導入によるメリットとデメリット
この記事を読むことで、自社の目的に合ったサーベイを導入できるようになり、「社員の声を活かす組織改善」の仕組みが整えられます。ぜひ最後までご覧ください。

エンゲージメントサーベイの導入目的とは?

エンゲージメントサーベイの目的は、社員の組織に対する考えや気持ち(エンゲージメント)を可視化し、個人・組織の課題を早期に把握することです。
多くの企業では、離職率の上昇や社員のモチベーション低下など、さまざまな「人」に関する課題を抱えています。その背景には、社員が抱える悩みや不満に対し、組織として十分な対応ができていないことが考えられます。
しかし、エンゲージメントサーベイを活用し、社員の心理状態の変化(サイン)を数値として把握することで、問題が深刻化する前に対処が可能です。
具体的な調査項目として、以下が挙げられます。
- 職場環境に対する満足度(働きやすさ、設備・制度面)
- 上司や同僚との関係性(信頼関係、コミュニケーションのしやすさ)
- 仕事への意欲・やりがい(業務の目的理解、成長実感)
- 会社への信頼・共感(経営理念への共感度、会社の方向性への納得感)
- キャリア・評価への満足度(評価の公平性、将来への期待感)
導入目的や実施手順を詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。実際にエンゲージメントサーベイを活用し、離職率が改善した企業の成功事例も紹介しています。
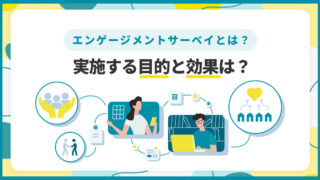
エンゲージメントサーベイ導入前に知っておきたい選び方【5ステップ】

エンゲージメントサーベイは、ツールごとに測定項目や調査方法などが異なります。機能や特徴を理解したうえで、自社の目的に合ったサーベイを導入しましょう。
ここでは、導入前に知っておきたい選び方を5ステップで解説します。
以下より詳しく見ていきましょう。
1:導入目的・活用方法を明確にする
エンゲージメントサーベイを導入するときは、まず「何のためにサーベイを行い、どのような場面で活用するのか」を明確にしましょう。
目的が曖昧なままサーベイを導入しても、「調査して終わり」という状態になりかねません。調査結果が活かされないと社員は不満を抱き、次回以降のサーベイに協力してくれない可能性があります。
まずは、サーベイを通じて「組織の何を把握したいのか」「どのような組織を目指すのか」を具体的に定義することが重要です。
たとえば、組織診断で課題を明らかにしたいのか、社員個人へのケアを強化したいのかで、選ぶべきツールは異なります。以下の表に、目的に応じた選び方をまとめます。
※以下の表は右にスクロールできます
| 目的 | 適したサーベイ | おすすめツール |
|---|---|---|
| 離職率を改善する | ・離職の予兆を捉えるために、個人の心理状態にフォーカスしたサーベイ ・短期的に繰り返し実施できるパルスサーベイ | ミキワメ、Geppo、LLax forest |
| 組織課題を見える化する | ・部署、職位、年代別に比較分析できるサーベイ ・スコアを可視化する機能(グラフなど)が充実しているサーベイ | Wevox、モチベーションクラウド、ラフールサーベイ |
| 人事施策に活用する | ・人事評価、育成、配置などの人事データと連携できるサーベイ ・エンゲージメントスコアを人材マネジメントの指標として活用できるサーベイ | カオナビ、SmartHR、HRBrain |
以下の資料では、エンゲージメントサーベイの活用方法や企業の成功事例を紹介しています。無料でダウンロードできますので、本記事と合わせてご活用ください。
>>「エンゲージメントサーベイによる組織構築」の資料をダウンロードする
2:測定項目・設問設計を確認する
エンゲージメントサーベイの測定項目には、社員の「意欲」や「満足度」だけでなく、組織との関係性を多面的に測定する要素が含まれます。
そのため、サーベイの導入目的や活用方法に合った要素が測定できるかを、導入前に確認することが重要です。たとえば、測定項目を目的別に整理すると、以下のような違いがあります。
※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください
| 目的 | 重視すべき測定項目 |
|---|---|
| 離職率を改善する | ・上司のマネジメント ・キャリアの方向性、将来の展望 ・業務負担、働きやすさ ・心理的安全性(意見を言いやすい環境) |
| 組織課題を見える化する | ・チームワーク、人間関係 ・組織文化や理念への共感 ・情報共有、コミュニケーションの質 |
| 人事施策に活用する | ・評価や報酬への納得感 ・成長やスキルアップに対する支援 ・人員配置やキャリアパスの妥当性 |
また、科学的根拠に基づいた設計になっているかも確認しておきましょう。心理学や組織行動論に基づいた調査でなければ、結果の信頼性を確保できず、正しい分析や組織改善につなげにくくなります。
エンゲージメントサーベイの測定項目について詳しく知りたい方は、以下の記事も確認してみてください。項目ごとに具体的な質問例も紹介しています。
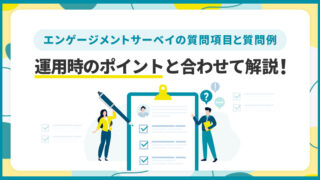
3:調査方法・実施頻度を検討する
エンゲージメントサーベイの調査方法には、年1回の大規模な調査(センサス)と、月1回など高頻度の調査(パルスサーベイ)の2種類があります。
それぞれ目的や質問数、収集するデータが異なるため、自社の課題や運用に合わせて最適な方法を選びましょう。各調査方法の具体的な特徴や実施頻度は、以下のとおりです。
※以下の表は右にスクロールできます
| 調査方法 | 特徴 | 実施頻度 | 質問数 |
|---|---|---|---|
| センサス (大規模な調査) | 組織全体の傾向を把握し、職場環境の改善や制度の見直しを行う | 年1回、半期に1回 など | 30〜100問程度 |
| パルスサーベイ (高頻度の調査) | 社員の心理状態の変化を把握し、短期的な改善アクションを行う | 月1回、週1回 など | 5〜15問程度 |
多くの企業では、組織の傾向を把握するためにセンサスを導入し、パルスサーベイで組織の状態を定点観測するといった方法を取り入れています。
ただ単にサーベイを実施しても、調査結果を活かせなければ意味がありません。まずは、改善策を打ち出すまでのプロセスを検討し、無理のない実施頻度と運用体制を整えましょう。
4:分析・レポート機能を確認する
サーベイを導入するときは、あらかじめ「結果をどのように分析するか」「どのような形で社員にフィードバックできるか」を確認しておきましょう。具体的には、以下のような機能が備わっていると理想的です。
※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください
| 分析・レポート機能 | 内容 |
|---|---|
| 属性別の分析 | 部署・職種・年齢・勤続年数などの属性ごとにスコアを分析する |
| 時系列の分析 | 前回の調査と比較し、上昇(または低下)した項目や、その要因を分析する |
| ダッシュボード | 組織全体の状態をスコアやグラフで表示する |
| 自動レポート作成 | 調査結果をPDFやスライドに自動で出力する |
| 改善策の提案(AIなど) | スコアの低い項目に対し、具体的な改善アクションを提案する |
また、分析結果を社員にフィードバックするときは、「なぜその結果になったのか」「次に何をすべきか」を一緒に伝える必要があります。
次のアクションが提案されるサーベイを導入することで、上司(マネージャー)は結果を確認しながら、即座に行動につなげられます。
エンゲージメントサーベイ結果の分析方法を詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。相関関係の分析など、具体例を用いてわかりやすく解説しています。

5:サポート体制・導入実績を確認する
エンゲージメントサーベイを導入するときは、機能面だけでなく、導入後のサポート体制がどの程度整っているかも必ず確認しましょう。
初めてサーベイを導入する場合は、調査の設計や分析方法、フィードバックの手順で迷ってしまうケースも少なくありません。そのため、導入支援から運用・改善までを一貫してサポートしてくれるかが重要です。
サポート内容の具体的なチェックポイントは、以下のとおりです。
- 初期設定や運用フロー設計のサポートがあるか
- 結果の分析方法や改善策の立て方をアドバイスしてもらえるか
- 専用のサポート窓口(チャット・メール・電話など)があるか
- 不具合やデータ連携エラーに迅速に対応してもらえるか
- 定期的な運用相談やミーティングなど、フォローアップ体制が整っているか
また、導入実績が豊富なツールであれば、同業他社の成功事例を参考にしながら組織改善のアプローチを検討できます。
『ミキワメ ウェルビーイングサーベイ』では、導入企業からの問い合わせ対応だけでなく、1社に1人カスタマーサクセスチームの担当者が活用まで伴走・支援します。
無料トライアルも実施中ですので、ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。
>>『ミキワメウェルビーイングサーベイ』の問い合わせはこちら
エンゲージメントサーベイでよくある失敗例・注意点

多くの企業で導入されているエンゲージメントサーベイですが、目的や運用方法に合わないツールを選んでしまうと十分な効果を得られません。
ここでは、導入時に陥りやすい失敗例と注意点を紹介します。
以下より詳しく見ていきましょう。
また、以下の記事では、エンゲージメントサーベイは「意味がない」と言われる理由や、すぐに実践できる具体的な対策を解説しています。本記事と合わせて確認してみてください。

調査自体が目的になってしまう
エンゲージメントサーベイの失敗例の一つは、「調査を行うこと」が目的になってしまい、組織改善に結果を活かせていないケースです。
サーベイを実施しても、「スコアが低い」「満足度が低下した」といった表面的な情報を把握するだけでは、組織改善に向けた具体的な行動につながりません。その結果、社員が不信感を招き、次の調査への協力を得られなくなります。
エンゲージメントサーベイの本来の目的は、社員の声をもとに組織の課題を可視化し、働きがいのある職場をつくることです。
そのためには、調査設計の段階で「どのような課題を調査し、結果をどのように活用するのか」を明確にしておく必要があります。
質問数が多すぎて回答率が下がる
質問数が多いエンゲージメントサーベイは、一見すると多くの情報を収集できそうに見えます。しかし、実際には回答率が低下し、有益な情報を得られない可能性があります。
とくに、繁忙期や決算期に長時間かかる調査を実施すると、途中離脱や未回答が増え、データの信頼性も低下しかねません。
従業員体験プラットフォームを提供するSimpplr社によると、アンケートに回答する時間の長さは、回答率(参加率)に大きく影響するとしています。同社が示すアンケート設計時のポイントは、以下のとおりです。
- 回答完了までの時間は、5~10分に設定する
- 質問は曖昧な表現を避け、明確でわかりやすい内容にする
- スマートフォンやタブレットで回答できる仕様にする
参考:Survey benchmarks: understanding survey response rates|Simpplr
このように、短時間・シンプル・モバイル対応を意識することで、回答率を高めつつ、より質の高いデータを収集できます。
調査結果を社員にフィードバックしていない
エンゲージメントサーベイのよくある失敗例として、「サーベイを実施したにもかかわず、調査結果を社員にフィードバックしていない」というケースが挙げられます。
サーベイの目的は、組織の状態を把握するだけでなく、会社が「その状態をどう受け止め、どう改善につなげるか」を示すことにあります。
しかし、調査結果を共有しないまま放置すると、社員は「回答しても意味がない」と感じ、サーベイそのものへの信頼も失われかねません。
このような事態を防ぐには、調査後のフィードバックを「迅速かつわかりやすく」行うことが重要です。たとえば、組織の傾向をまとめたレポートを共有したり、職場のよい点と改善点を話し合ったりする方法があります。
以下の記事では、社員との対話を重視した「サーベイフィードバック」について詳しく解説しています。具体的な手順や企業の活用事例も紹介していますので、本記事と合わせて確認してみてください。

改善施策の実行が遅れ、社員の不満が増える
サーベイ実施後に改善施策の実行が遅れてしまうと、社員の期待を裏切る結果となり、エンゲージメントの低下を招く恐れがあります。たとえば、以下のようなケースです。
- サーベイの結果を共有したものの、会社が何のアクションも起こさない
- 改善計画を立てたが、部署間の調整に時間がかかり実行に移せない
- 会社から「検討中」「準備中」といった説明が続いている
このような状況が続くと、社員はサーベイを「形だけの取り組み」と捉え、徐々に協力的な姿勢が見られなくなってしまいます。結果として、回答率が低下し、率直な意見を得られなくなる可能性が高まってしまうのです。
改善施策の実行を遅らせないためには、調査結果を分析する段階で「重要度の高い施策を検討する」など、スピード感のある意思決定と行動が必要です。
継続的にサーベイを実施していない
継続的にエンゲージメントサーベイを実施していないことも、導入時のよくある失敗例の一つです。一度の調査だけでは、前回からの変化を把握したり、施策の効果を検証したりできません。
たとえば、一年前の調査で「上司とのコミュニケーションに課題がある」と判明した場合、その後の施策が有効だったかどうかを確認するには、同じ指標で再度サーベイを行う必要があります。
「一度調査したから大丈夫」と放置してしまうと、時間をかけて収集したデータが活かされず、組織状態の変化を正しく評価できません。
エンゲージメントサーベイの目的は、現状を把握するだけではなく、組織の状態を継続的にモニタリングし、改善のサイクル(PDCA)を回すことです。その結果、長期的なエンゲージメント向上と健全な職場づくりにつながります。
エンゲージメントサーベイ導入時の確認事項【チェックリスト付き】

エンゲージメントサーベイを選ぶときは、導入前に確認すべきポイントが7つあります。チェックリストで紹介しますので、導入時に活用してみてください。
※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください
| 確認事項 | チェックリスト |
|---|---|
| 目的に合った調査項目があるか | ・エンゲージメントの要素を多角的に調査できるか ・組織文化や理念の理解度を確認できる項目があるか ・人事施策に活用できる項目があるか |
| 科学的根拠に基づく設問設計になっているか | ・エンゲージメントの構成要素が定義されているか ・設問が抽象的ではなく、行動・体験ベースで設計されているか ・設問の妥当性と信頼性が検証されているか |
| 回答しやすい仕様になっているか | ・回答時間が短めに設定されているか ・実施頻度や設問数を柔軟に変更できるか ・質問文がシンプルで理解しやすい内容になっているか |
| 実名・匿名どちらの回答方法か | ・目的に応じた回答方法(実名・匿名)になっているか ・匿名回答でも、部署・年代・職位など属性別の分析ができる仕様か ・実名回答の場合、回答内容の取り扱い方法が明記されているか |
| 集計・分析機能が充実しているか | ・調査結果を可視化できるダッシュボード(管理画面)があるか ・部署、職種、年齢層など属性別にフィルタリングできるか ・前回調査との比較や分析が可能か |
| 導入後のサポート体制が整っているか | ・導入支援があるか ・調査結果の読み解き方や改善策のアドバイスをしてもらえるか ・専任のカスタマーサクセスチーム担当者がつくか |
| 導入実績や成功事例があるか | ・自社と同じ業種や規模の企業での導入実績があるか ・導入企業数やリピート率が公表されているか ・具体的な成功事例が紹介されているか |
以下より、それぞれの確認事項を詳しく解説します。
目的に合った調査項目があるか
エンゲージメントサーベイを選ぶときは、自社の目的(離職率の改善など)に合った調査項目があるかを確認する必要があります。具体的なチェックポイントは以下のとおりです。
- エンゲージメントの要素を多角的に調査できるか
- 組織文化・理念の理解度を確認できる項目があるか
- 上司の指導やフィードバックに関する項目があるか
- チームワークや人間関係に関する項目があるか
- 心理的安全性を把握できる項目があるか(発言のしやすさ など)
- 人事施策に活用できる項目があるか(評価・報酬 など)
年1回などの大規模な調査を行う場合は、部署や年齢ごとに集計・分析を行い、属性別の傾向を把握します。そのため、全社員に同じ調査項目・質問を設定するのが望ましいです。
しかし、心理状態の把握に重きを置いたパルスサーベイでは、性格を踏まえた質問が自動設定されるなど、カスタマイズ性のあるツールがおすすめです。
科学的根拠に基づく設問設計になっているか
そもそもエンゲージメントとは、社員が「組織(仕事)に対して、どの程度の信頼(熱意)を持っているか」を示す心理的な概念です。
そのため、エンゲージメントサーベイは感情的・主観的な設問ではなく、心理学的理論や統計的根拠に基づいた設計であることが重要です。具体的なチェックポイントは以下のとおりです。
- エンゲージメントの構成要素(熱意・没頭・貢献意欲 など)が定義されているか
- 設問が抽象的ではなく、行動・体験ベースで設計されているか
- 設問の妥当性と信頼性が検証されているか
- 他社や過去データとの比較・分析が可能か
- 回答者の主観に左右されにくい設問設計になっているか
- 設問数と内容のバランスが取れているか
たとえば、幸福な状態を示す「ウェルビーイング」を測定指標とする場合、心理学者マーティン・セリグマンが提唱した「PERMAの法則」に基づいた設計が適しているでしょう。
そのほかにも、ワークエンゲージメントを学術的に研究した「仕事要求度ー資源モデル(JD-Rモデル)」や、アメリカのギャラップ社が提唱した「Q12」などがあります。
サーベイを選ぶときは、どの理論に基づいて設計されているかを確認し、信頼性の高い調査を行うことが大切です。
以下の記事では、ウェルビーイング推進の専門的なポイントを、臨床心理士がわかりやすく解説しています。サーベイ導入時の参考にしてみてください。
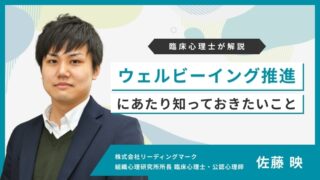
回答しやすい仕様になっているか
エンゲージメントサーベイでは、質問数が多すぎたり操作が複雑だったりすると、回答率が下がり正確なデータを収集できません。
そのため、サーベイの仕様が「誰でも、短時間で、迷わず回答できる設計」になっているかが重要です。具体的なチェックポイントは以下のとおりです。
- 回答時間が短めに設定されているか(目安:5〜10分以内)
- 実施頻度や設問数を柔軟に変更できるか
- 質問文がシンプルで理解しやすい内容になっているか
- スマートフォンやタブレットからも回答できるか
- 選択肢の幅が適切に設定されているか(例:5段階・7段階 など)
- 途中保存ができる仕様になっているか
また、直感的に回答できる仕様になっているかも確認しておきましょう。冒頭に回答しやすい質問を配置したり、1問ずつスクロールで進む画面構成にしたりと、回答者に配慮された仕様が理想的です。
実名・匿名どちらの回答方法か
エンゲージメントサーベイの回答方法には、実名式と匿名式の2種類があります。どちらを採用するかによって、得られるデータの正確性や活用範囲が変わるため、自社の目的に合わせて慎重に検討することが大切です。
実名式のメリットは、社員一人ひとりの状態を把握し、ピンポイントでフォローできる点です。一方、匿名式は率直な意見を集めやすく、組織全体の傾向を把握するのに適しています。
エンゲージメントサーベイを導入するときは、以下の点をチェックしてみましょう。
- 目的に合わせた回答方法(実名・匿名)になっているか
- 回答者に対して、匿名性の扱いを明確に説明できるか
- 匿名回答でも、部署・年代・職位などの属性別に分析できるか
- 実名回答の場合、回答内容の取り扱い方法が明記されているか
- 自由記述欄の内容から個人が特定されない仕様になっているか
- 匿名・実名を切り替えられる仕組みがあるか
実名式のサーベイでは、結果が関係者以外にバレてしまうことを懸念し、調査に協力しない人が一定数いるのも事実です。
しかし、実際に導入した企業では、「関係者以外には調査結果を共有しない」「人事評価には影響しない」と繰り返し伝えたことで、ほぼ100%の回答率を実現しています。
事例:ミキワメの導入により離職の改善が進んだ事例|株式会社笑美面(えみめん)
このように、回答することへの安心感を与えることが、エンゲージメントサーベイの効果を最大限に引き出すコツです。
以下の記事では、匿名式サーベイ・実名式サーベイそれぞれの特徴を詳しく解説しています。どちらの方法を採用するか悩んでいる人事担当者の方は、ぜひ導入時の参考にしてみてください。

集計・分析機能が充実しているか
エンゲージメントサーベイを導入するときは、集計結果を可視化するダッシュボード機能や、部署・職種などの属性別に分析できる機能があるかを確認しましょう。
単に組織の状態を把握するだけでなく、調査結果をもとに職場環境の改善につなげることがサーベイの役割です。そのため、集計・分析機能が充実しているかどうかが、サーベイの実用性に大きく影響します。
具体的なチェックポイントは以下のとおりです。
- 調査結果を可視化できるダッシュボード(管理画面)があるか
- 部署・職種・年齢層など属性別にフィルタリングできるか
- 前回調査との比較や分析が可能か
- 自由記述のテキスト分析が可能か
- グラフやレポートを自動生成する機能があるか
- 次のアクションを提案する機能があるか
実際に『ミキワメ ウェルビーイングサーベイ』を利用している企業は、以下の分析機能に魅力を感じて導入を決めています。
- 社員一人ひとりの性格を16タイプに分類
- サーベイの結果を天気予報で可視化
- AIによるデータ分析やアドバイス
集計・分析機能が充実したサーベイを選ぶことで、データを「見る」だけでなく「行動」につながる運用が可能になります。
導入後のサポート体制が整っているか
エンゲージメントサーベイの導入当初は、初期設定の方法や分析レポートの読み解き方など、運用面で戸惑うことも少なくありません。
そのため、サーベイ実施から調査結果の分析、改善策の提案までをスムーズに進めるには、導入後のサポート体制が整っているかどうかが重要です。サーベイ導入時は、以下の点を確認しておきましょう。
- 導入支援があるか(初期設定・調査設計のサポート など)
- 調査結果の読み解き方や改善策のアドバイスをしてもらえるか
- 専任のカスタマーサクセスチーム担当者がつくか
- 問い合わせ対応のチャネルが複数あるか(電話・メール・チャット など)
- 定期的なフォローアップがあるか(例:勉強会、ユーザー会 など)
サポート体制が充実しているツールを導入することで、調査結果の活用に悩むことなく、スムーズに組織改善につなげられます。
導入実績や成功事例があるか
エンゲージメントサーベイを選ぶときは、他社の導入実績や活用事例(効果・成果)があるかを確認しておきましょう。
自社と同じ業種・規模の事例があれば、導入後の活用方法や効果がイメージしやすくなります。具体的なチェックポイントは以下のとおりです。
- 自社と同じ業種・規模の企業での導入実績があるか
- 導入企業数やリピート率が公表されているか
- 具体的な成功事例が紹介されているか(例:離職率改善、満足度向上 など)
- 導入事例では、具体的なデータが含まれているか
- 公的機関や大手企業での導入実績があるか
- 公式サイトやSNSで導入事例が公開されているか
また、導入事例を確認するときは、課題に対し「どのようなプロセスで効果が得られたのか」に注目しましょう。事例を通じて、「課題の発見・分析・改善策・効果検証」といった一連の流れが確認できます。
以下の資料では、おすすめのエンゲージメントサーベイ10選を一覧にまとめています。無料でダウンロードできますので、比較検討をするときの参考にしてみてください。
>>「エンゲージメントサーベイツール一覧と比較10選」の資料をダウンロードする
エンゲージメントサーベイの動向・最新トレンド

近年、エンゲージメントに関する指標は、モチベーションや生産性だけでなく、社員の包括的なウェルビーイングが重視されるようになりました。
SaaSプラットフォームを提供するLumApps社の資料によると、活気のある職場を実現するためには、以下のような取り組みが重要だとしています。
- メンタルヘルスのサポート強化
- ワークライフバランスを積極的に支援する取り組み
- 心身の健康や幸福に向けたウェルネスプログラム
これらの個人にフォーカスした取り組みに欠かせないのは、AIなどのテクノロジーを活用したデジタルツールです。
たとえば、高い頻度で調査を行うパルスサーベイを導入することで、組織は社員の心理状態をタイムリーに把握し、素早く懸念事項に対処できるようになります。
デジタルツールやプラットフォームをうまく活用すれば、離れた場所で働くメンバーとの距離を感じることなく、スムーズな連携が可能です。
参考:Essential Employee Engagement Trends for 2025|LumApps
エンゲージメントサーベイとパルスサーベイの違いがよくわからない方は、以下の記事を参考にしてみてください。従業員満足度調査(サーベイ)との違いも解説しています。

エンゲージメントサーベイを導入する4つのメリット

エンゲージメントサーベイは社員の満足度を把握するだけでなく、組織の状態を「見える化」し、経営判断に活用できるツールです。導入するメリットとして、以下の4点が挙げられます。
以下より、それぞれのメリットを詳しく見ていきましょう。企業の活用事例も合わせて紹介します。
離職リスクを早期発見できる(定着率の向上)
エンゲージメントサーベイを導入する大きなメリットは、休職や離職につながる要因をいち早く察知できる点です。
社員のエンゲージメントが低下すると、仕事への意欲や活力が失われ、パフォーマンスにも影響が出てきます。その状態を放置すると、心身の不調やストレスの蓄積につながり、最終的には休職や離職といった深刻な事態を招きかねません。
エンゲージメントサーベイを定期的に実施することで、「上司との関係性」や「業務負担」といった設問を通して、社員の心理状態の変化を把握できます。
実際に、離職率が高い状態にあったクリーンハウス株式会社では、エンゲージメントサーベイの導入によって、離職率が25%から20%まで減少しました。
以前は、離職率が「高い事業所」と「低い事業所」にはっきりと分かれていました。施設長の社員一人ひとりとの接し方に差があり、人間関係に関する悩みが離職の大きな要因となっていたのです。
サーベイ導入後は、調査結果を施設長が確認したうえで、状態が悪い社員に対しては、声かけや面談をするようにしています。また、人事は施設長の「ケアの仕方」の相談に乗るなど、組織としてのフォロー体制を強化しました。
サーベイを導入したことで、社員一人ひとりの状態に合った接し方ができるようになり、結果として離職率の改善につながっています。
このように、エンゲージメントサーベイは離職リスクを早期に察知し、具体的なアクションにつなげるための重要な取り組みと言えます。
組織課題が見える化され、優先順位が付けやすくなる
エンゲージメントサーベイを導入することで、感覚的に把握していた組織の課題をエンゲージメントスコア(数値)として可視化できます。
さらに、部署・職務・年齢など属性ごとにスコアを比較すれば、課題の傾向がより明確になり、優先順位を付けながら改善策の検討が可能です。
実際に、産業機械の開発・製造などを行う株式会社ソディックでは、エンゲージメントサーベイを通じて課題を見える化し、社員のケアを強化しています。
以前は、年1回の従業員満足度調査を実施していましたが、言語化されていない課題が多く、マネジメント層の感覚的なコミュニケーションに頼っていました。
サーベイを導入してからは、「先月は晴れだったのに今回は曇り」といった心理状態の変化が見える化され、マネジメント層のケアの平準化につながっています。
また、日々のコミュニケーションのきっかけとしても活用するようになり、今では業務の中で「頼れる存在」となりました。
このように、主観や感覚に頼っていた部分をサーベイで補うことで、優先度の高いテーマから順番に改善策を実行できるようになります。
エンゲージメントスコアの概要や計測方法を詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。スコア向上に向けた取り組みや企業事例も紹介しています。

生産性(業績)が向上する
エンゲージメントサーベイは、エンゲージメントの低い部署を特定し、具体的な課題とその要因を明確にできます。調査結果をもとに、課題に応じた改善策を行うことで、業務効率や生産性の向上につなげられます。
アメリカの調査会社であるギャラップ社によると、エンゲージメントが高い上位25%の企業は、下位25%の企業よりも生産性(売上高)が18%高いことがわかりました。
つまり、エンゲージメントの状態を継続的に把握・改善するサーベイは、組織の生産性を高めるための重要な経営施策と言えます。
さらにサーベイの結果を経営判断に活用することで、「どの部署にどのような支援が必要か」「どの施策が成果につながっているか」を客観的に評価できます。
エンゲージメントと業績の関係を詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。調査機関のデータをもとに、具体例を交えてわかりやすく解説しています

人事トラブルを未然に防ぐことにつながる
エンゲージメントサーベイは、職場での「不満」や「不公平感」を早期に察知するなど、人事トラブルの予防策として活用できます。
職場内の対立や人間関係の悪化、ハラスメントなどの問題は、表面化する前に調査結果で「スコアの低下」として現れる場合があります。たとえば、以下のようなケースです。
- 「上司との関係性」に関するスコアが低下している
→ 指導方法に対する不満が蓄積している可能性がある - 「チームワーク」「心理的安全性」のスコアが低下している
→ 部署内での孤立や人間関係の悪化が懸念される
実際に、離職者の増加が課題だった未知株式会社では、個人へのアプローチに重点を置いたサーベイを導入したことで、個別の離職防止対策を打てるようになりました。
具体的には、社員一人ひとりのスコアの変化をもとに、「得点のつけ方の特徴」を理解しつつ、個々に合ったケアの方法を検討しています。
以前は職場のコミュニケーションが少なく、お互いの状態もよくわからない状況でした。サーベイ導入後は、デジタル・対面両方のコミュニケーションが活発になり、組織としてのエンゲージメントも向上しています。
事例:サーベイの結果から改善アクションを実施し、エンゲージメントが劇的に改善|未知株式会社
このようにエンゲージメントサーベイを定期的に実施することで、スコアの変化が可視化され、人事トラブルの兆候を早期に把握できるようになります。
エンゲージメントサーベイを導入するデメリット

エンゲージメントサーベイには多くのメリットがある一方で、以下のようなデメリットも存在します。
サーベイを導入するときは、デメリットも含めて検討しましょう。
以下より詳しく解説します。
「サーベイ疲れ」を引き起こす可能性がある
エンゲージメントサーベイを頻繁に実施したり、質問数を多くしたりすると、社員が回答する意欲を失う「サーベイ疲れ」を引き起こす可能性があります。
サーベイ疲れが起きた場合、回答率の低下や回答内容のばらつきが発生し、組織改善に活かすための正確なデータが得られません。
とくに、毎月のように長時間かかる調査を実施すると、社員は「どうせまた同じ質問だ」と感じ、無難な回答をする可能性があります。
サーベイ疲れを引き起こさないためには、調査の目的や内容を明確にし、実施のタイミングや質問数を適切に設計することが重要です。
運用・分析には一定のコストや時間がかかる
エンゲージメントサーベイを導入すると、調査の設計や実施、集計・分析といったプロセスが必要になり、一定のコストや時間がかかります。
とくに初めて運用する場合は、「どのような設問を設定するか」「結果をどう活用するか」といった検討事項が多く、担当者の負担も大きくなりやすいです。
また、調査後の分析も同様に時間を要します。サーベイ結果は数値として可視化されますが、それを「どのように読み解き、施策に落とし込むか」は専門的な知見を必要とします。
このような課題を解決するためには、サーベイの設計から分析、改善までを一貫してサポートしてくれるツールの活用がおすすめです。
近年では、質問設計のテンプレートがあらかじめ用意されたツールや、回答結果を自動で分析・可視化してくれるダッシュボード機能を備えたツールも増えています。導入前に、運用コストと効果のバランスをよく検討しましょう。
エンゲージメントサーベイの費用相場が気になる方は、以下の記事を参考にしてみてください。各ツールの料金を一覧表で紹介しています。

エンゲージメントサーベイのおすすめサービス一覧・比較表

エンゲージメントサーベイには数多くのツールがあり、それぞれ特徴や強みが異なります。導入時は、各ツールの調査項目や料金体系、サポートの有無などを確認し、比較検討してみましょう。
以下の表は、代表的な6つのサービスを目的別に整理したものです。導入するときの参考にしてみてください。
※以下の表は右にスクロールできます
| 検査タイプ | サービス名 | 特徴 | 費用(税込) |
|---|---|---|---|
| 離職リスクを察知し、予防策を検討する | ミキワメ ウェルビーイングサーベイ | ・ケアが必要な社員を可視化できる ・社員の性格や心理状態を踏まえた対話方法が提供される | 要問い合わせ |
| Geppo | ・シンプルな設問でエンゲージメントを把握できる ・選び抜かれた3問で社員のコンディションを確認できる | ・初期費用:0円 ・利用料:2万2000円〜 | |
| 組織診断で課題を見える化する | Wevox | ・3分間のサーベイで回答者に負担をかけない ・9つの項目を可視化して多角的な分析ができる | 月額330円〜/人 |
| モチベーションクラウド | ・組織状態の診断と変革のサイクルで課題を解決する ・エンゲージメントスコアを期待度と満足度の2軸で可視化する | 要問い合わせ | |
| 人材データベースと連携し、人事業務を集約する | カオナビ | ・人材データベースと照合し、評価や面談履歴の比較ができる ・調査データに基づいた最適な設問が設定されている | 要問い合わせ |
| SmartHR | ・人材データベースを活用して効率的にサーベイを配信できる ・目的別に設計されたサーベイで導入後すぐに実施できる | 要問い合わせ |
各ツールの特徴については、以下の記事で詳しく解説しています。上記6種類を含めた14種類のサービスを徹底比較していますので、本記事と合わせて確認してみてください。
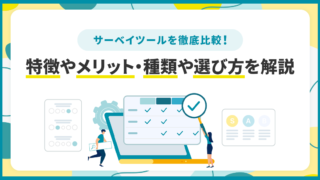
エンゲージメントサーベイの選び方に関するよくある質問

エンゲージメントサーベイの選び方に関する「よくある質問」について、以下の2点に回答します。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
エンゲージメントサーベイの大手ツールは何?
エンゲージメントサーベイの大手ツールには、株式会社リーディングマークが提供する『ミキワメ』や、株式会社リクルートの『Geppo』などがあります。前述の比較表でも紹介したように、以下も実績豊富なサーベイツールです。
- Wevox(株式会社アトラエ)
- モチベーションクラウド(株式会社リンクアンドモチベーション)
- ラフールサーベイ(株式会社ラフール)
- カオナビ(株式会社カオナビ)
- SmartHR(株式会社SmartHR)
- HRBrain(株式会社HRBrain)
たとえば、ミキワメは「総受検者数150万人」「累計利用企業5000社」に達しており、豊富な導入実績と信頼性のあるツールと言えます。
エンゲージメントサーベイの市場規模は?導入率はどのくらい?
エンゲージメントサーベイの市場規模は、矢野経済研究所の調査によると、2024年の売上高ベースで118億円の見込みになっています。2025年から2028年にかけては、さらに市場規模が拡大する見通しです。
その背景として、「人的資本の情報開示」が義務化され、自社のエンゲージメントを把握する企業が増加していると考えられます。
また、日本の人事部の調査によると、エンゲージメントサーベイの導入率は約3〜4割です。市場規模の拡大が予測されていることから、今後さらに導入率が上がる可能性があります。
以下の記事では、エンゲージメントサーベイの導入率について詳しく解説しています。サーベイ導入における課題や対策も紹介していますので、本記事と合わせて確認してみてください。

まとめ:エンゲージメントサーベイで組織の状態を可視化しよう

エンゲージメントサーベイは、仕事への意欲や組織に対する貢献意欲を数値化し、課題を明確にするための有効なツールです。
ただし、サーベイツールによって設問設計や分析機能、サポート体制が大きく異なります。サーベイ導入時は、以下のポイントを事前に確認しておきましょう。
エンゲージメントサーベイは、一度実施して終わりではありません。定期的にサーベイを行い、前回からの変化を比較・分析することで、施策の効果検証や新たな課題の発見につながります。
自社の課題や目的に合ったサーベイツールを選定し、社員がいきいきと働ける組織づくりを実現しましょう。

従業員のメンタル状態の定期的な可視化・個々の性格に合わせたアドバイス提供を通じ、離職・休職を防ぐエンゲージメントサーベイ。無料トライアルの詳細は下記から。



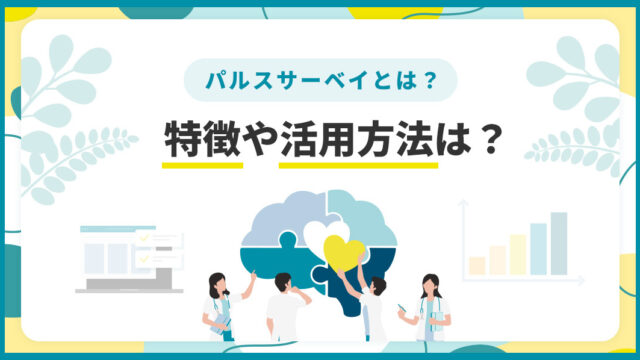








 ランキング1位
ランキング1位 
 ランキング2位
ランキング2位 
 ランキング3位
ランキング3位 