採用活動において「なかなか自社に合う人材が見つからない」「採用してもすぐに離職されてしまう」といった悩みを抱える企業が増えています。
そうした状況のなか注目されているのが、将来の採用候補者となり得る人材をデータベースで管理し、継続的に関係を築くことで自社にマッチする人材を確保する「タレントプール」という採用戦略です。
本記事では、タレントプールの基本から具体的な運用方法、課題や注意点、導入事例までをわかりやすく解説します。
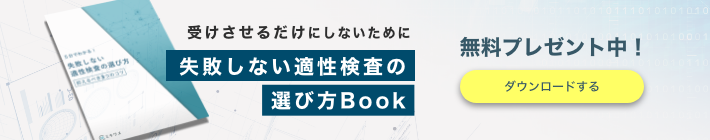
タレントプールとは?言葉の意味や手法について解説
タレントプールとは、将来的に採用候補となる人材(=タレント)の情報を事前に蓄積(=プール)しておくデータベースや、その運用に基づいた採用戦略のことです。
企業はデータベースに登録した採用候補者に対して、メルマガ配信やセミナーの案内を通じて定期的にコミュニケーションをとり、あらかじめ関係性を築いておくことで、双方にとって最適なタイミングで採用のアプローチができます。
タレントプールの概念は、マッキンゼー・アンド・カンパニーが1990年代後半に提唱した「有能な人材の獲得こそが企業の競争優位に直結する」といった、タレントマネジメントの概念やデータベースリクルーティングの手法とも密接に関連するものです。
タレントプールの運用もまた、単なる採用効率化の手段ではなく、優秀な人材の確保を通じて企業の持続的成長を実現するという戦略的な採用の手法といえるでしょう。
出典:日本労務学会誌 Vol. 18 No. 1:21 – 43(2017)「戦略的タレントマネジメントが機能する条件とメカニズムの解明」
タレントプールの対象者
タレントプールに登録すべき対象者は、今すぐの採用には至らなくても、将来的に自社での活躍が期待できる優秀な人材です。
選考辞退者や不採用だった応募者も含め、幅広い候補者を長期的な視点で捉えることで、戦略的な人材確保につながります。
具体的には、次に当てはまるのがタレントプールの主な対象者です。
- 書類選考や面接で好印象だったが、別の候補者が内定を得た応募者
- 採用時期や条件が合わず、内定を辞退した応募者
- インターンやアルバイトとして優れた成果をあげた経験者
- 社員紹介(リファラル採用)などで接点を持ったが、すぐの採用に至らなかった人物
- 自社イベント・セミナー・SNSなどを通じて接点を持った潜在的な転職希望者
これらの人材はすでに企業との接点があるため、まったく新規の候補者よりもアプローチのハードルが低く、再接触によって採用につながる可能性が高い存在です。
タレントプールが注目される理由・背景
タレントプールが注目される理由や背景としては、次の3つが挙げられます。
- 少子高齢化により労働人口が減少している
- 人材の流動性が高まっている
- 採用のミスマッチによる早期離職が問題視されている
それぞれ解説します。
少子高齢化により労働人口が減少している
タレントプールが注目される理由・背景として大きいのが、少子高齢化の加速による労働人口そのものの減少です。
日本では15〜64歳の生産年齢人口が下降の一途を辿っており、国立社会保障・人口問題研究所のデータでは、2040年に65歳以上の高齢者が全人口の34.8%にのぼるとされています。
さらには「5人に1人が75歳以上」になるという見通しもあり、採用市場の競争は今後いっそう激化すると予測されます。
出典:国立社会保障・人口問題研究所「日 本 の 将 来 推 計 人 口 (令和5年推計)」
こうした状況のなかで、限られた人材をめぐる採用競争を勝ち抜くには、将来の候補者と早期に関係性を築いておくことが重要です。
人材の流動性が高まっている
人材の流動性が増すなか、タレントプールの重要性はますます高まっています。
現代は終身雇用が前提だった時代と異なり、転職・副業・フリーランスなどを選ぶ人が増え、優秀な人材が常に流動している状態です。
さらに、リモートワークの普及により、地域や国境を超えた人材移動も一般化しています。
たとえば、社内で期待されていた人材がキャリアチェンジや家庭の事情などで突然離職するケースも珍しくありません。
こうした人材の流出リスクに備えるには、いざというときにアプローチできる「候補者リスト」を持っておくことが有効です。
タレントプールはその基盤となる施策といえるでしょう。
採用のミスマッチによる早期離職が問題視されている
採用後のミスマッチがもたらす早期離職の問題も、タレントプールが注目される理由のひとつです。
入社後に「こんなはずではなかった」と、理想と現実のギャップが原因で離職するケースがあとを絶ちません。近年では、入社3年以内の離職率が3割前後を維持するなど、業種や企業規模を問わず採用現場の課題となっています。
出典:新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します|厚生労働省
採用のやり直しにはコストと労力がかかるうえ、社内に残るメンバーのモチベーションやチームの士気を下げるといった悪影響も無視できません。
タレントプールの運用は、企業と候補者が継続的に相互理解を深められるため、採用のミスマッチを防ぐ手段として注目されています。
タレントプールを活用するメリット
採用活動において、タレントプールを活用することには次のメリットがあります。
- 採用活動が効率化されコストを削減できる
- 優秀な人材を確保できる
- 離職率の低下と人材定着率の向上につながる
それぞれ解説します。
採用活動が効率化されコストを削減できる
タレントプールの活用により、採用活動の効率化とコスト削減を実現できます。
タレントプールの手法はすでに接点のある候補者に対して再アプローチするものであり、求人広告費やエージェント手数料といった初期コストがかからないためです。
また、自社インターンへの参加者や過去に辞退した応募者などをデータベースで管理しておけば、ポジションが空いた際にすぐ声をかけることができ、選考期間の短縮や対応の効率化にもつながります。
このように、タレントプールは限られた予算のなかでも成果を上げやすい採用手段です。
優秀な人材を確保できる
転職市場では、優秀な人材ほどすぐに他社に採用されてしまいます。タレントプールの運用により、活動を本格化する前の「潜在層」へ早期接触しておくことで、優秀な人材をいち早く確保できる可能性が高まります。
たとえば、過去に応募歴のあるハイレベルな人材や、企業に興味を示したイベント参加者に対して定期的な情報提供をおこなっていれば「まだ転職は考えていないが話を聞きたい」という段階での関係構築が可能です。
結果として、まだ市場に出回っていない逸材に先手を打ってアプローチできることが、タレントプールを運用する大きなメリットです。
離職率の低下と人材定着率の向上につながる
タレントプールの運用には、採用後の早期離職を防いで人材の定着率を高める効果もあります。
なぜなら、企業と候補者が採用前から継続的にコミュニケーションを重ねることで、相互理解が深まるためです。
たとえば、タレントプールに登録された候補者に対し、定期的な会社情報の提供やイベント案内を通じて企業文化や仕事内容を具体的に伝えておけば「思っていた会社と違った」という採用のミスマッチを防げます。
また、タレントプールの運用を通じて関係性を構築してきた候補者は、入社前から企業に対して好印象を抱いていることから、実際に入社したあとのエンゲージメントやロイヤルティも高く、職場に定着しやすい傾向があります。
タレントプールの運用方法
タレントプールを効果的に運用する手順は次のとおりです。
- 自社に必要な人材の要件を定義する
- 人材のデータベースを構築する
- グループ分けをする
- コミュニケーションを継続しアプローチをはかる
ここでは、タレントプールの運用方法をステップごとに解説します。
1.自社に必要な人材の要件を定義する
タレントプール運用の効果を最大化するには、まず自社にとって必要な人材の定義が不可欠です。採用したい人物像が曖昧なままだと、プールすべき人材の選定がブレてしまいます。
たとえば「営業経験3年以上」「チームマネジメント経験あり」「ITリテラシーが高い」など、求めるスキルや経験を定量的に整理するだけではなく、「成長志向が強い」「共感力が高い」などの定性的な要件も言語化することで、より的確な母集団形成が可能です。
あらかじめ人材要件を明確にしておくことで、その後のデータベース構築やアプローチの質も高まるでしょう。
2.人材のデータベースを構築する
次に、候補者情報のデータベース化をおこないます。
データベースには、過去のインターン参加者、選考辞退者、イベント参加者、社員のつながりなどから得た候補者情報を、以下の項目に沿って記録していきます。
| 登録項目 | 記載すべき情報 |
|---|---|
| 基本情報 | 氏名、年齢、性別、居住地、連絡先、最終学歴、SNSアカウント(LinkedInやWantedlyなど) |
| 職務情報 | 所属企業、業種、職種、役職、勤続年数、スキルセット |
| 接点履歴 | イベント参加、メルマガ開封など |
| 過去の接点情報 | 応募日、応募職種、選考フェーズ、選考評価、辞退・不合格理由、選考担当者、履歴書・職務経歴書の評価など |
| レコメンド理由 | 現職社員から高評価である、辞退理由が「時期や家庭都合」などポジティブだったなど |
| 転職の意欲度 | 現在の意欲を高・中・低などに分けて記載(最終更新日を併記) |
データベース化にはエクセルやGoogleスプレッドシートなどの汎用ツールを用いるほか、LinkedInやタレント管理ツールを活用することで、属性情報・連絡履歴などの一元管理が可能となります。
3.グループ分けをする
データベースを構築したあとは、候補者ごとの「転職の意向度」によってグループ分けをおこないましょう。
なぜなら、候補者はそれぞれ転職希望時期や関心度が異なり、全員に同じアプローチをかけることは採用活動において非効率だからです。
具体的には、以下のような2つのセグメントに分類する運用が推奨されます。
- タレント認定プール:転職意欲が顕在化しており、今すぐに採用アプローチが可能な層
- タレント潜在プール:まだ転職の意思が明確ではないが、将来的な可能性を見込んで関係構築しておくべき層
たとえば「タレント認定プール」の候補者には、ダイレクトスカウトやカジュアル面談の打診をおこないます。
一方で「タレント潜在プール」の候補者には、メルマガ配信やセミナー招待などを通じたコミュニケーションを継続します。
セグメントごとの対応により、候補者の従業員エクスペリエンス(EX)を損なわず、自社への関心を継続的に高められる点がタレントプールの魅力です。
4.コミュニケーションを継続しアプローチをはかる
それぞれの候補者に対してコミュニケーションを継続し、適切なタイミングで採用のアプローチをおこなうことがタレントプールの運用の肝です。
転職意欲が顕在化しているタレント認定プールの候補者に対しては、直接的な採用のアプローチが有効です。たとえば、以下の手法が挙げられます。
- ダイレクトスカウトメールの配信
- カジュアル面談の打診
- ポジションが空いたタイミングでのオファー連絡
一方、まだ転職意欲が明確でないタレント潜在プールの候補者に対しては、将来に向けて良好な関係性を育むコミュニケーションが求められます。代表的な施策は以下のとおりです。
- メールマガジンの定期配信(キャリア情報・採用情報など)
- オンライン/オフラインの採用イベント・セミナーへの招待
- SNSやLINEでの発信によるライトな接点づくり
こうしたコミュニケーションにより、候補者の転職意欲が高まった際にアプローチできる関係性を築けます。
タレントプール運用における課題と注意点
タレントプールの運用にはメリットが多い反面、課題もあります。具体的には次の点に注意が必要です。
- データベースの管理・活用に工数がかかる
- 候補者へアプローチすべきタイミングの見極めが困難である
- 発信する情報やコンテンツの質が問われる
ここからはタレントプール運用における課題と注意点について、対策とともに解説します。
データベースの管理・活用に工数がかかる
タレントプールを効果的に運用するには、データベースの管理と活用に相応の工数がかかります。
登録されている候補者の情報は時間とともに変化します。属性や連絡先、転職意欲の度合い、過去の接点履歴などを適宜アップデートしながら、整理された状態で管理しなければなりません。
たとえば、過去の選考辞退者やイベント参加者など多様な経路から蓄積された情報を統合し、検索・抽出・アプローチがしやすいように整理する作業には、手間や専門的な知識が必要です。
そのため、エクセルなどの汎用ツールに依存した属人的な管理では限界があります。タレント管理ツールや採用管理システムの導入によって業務の効率化をはかることが推奨されます。
候補者へアプローチすべきタイミングの見極めが困難である
タレントプールの運用を成功させるには「いつ採用のアプローチをおこなうべきか」のタイミングを見極めることが重要ですが、候補者の転職意欲の高まりを正確に把握することは困難です。
タイミングを誤ると採用につながらないどころか、企業への印象を損ねるリスクさえあります。
たとえば、自身のキャリアに満足しているタレント潜在プールの候補者に対して繰り返し採用のアプローチをおこなうと、煩わしさから情報提供の停止を希望されるケースも考えられるでしょう。
逆に、転職検討中のタイミングを逃すと、他社に先を越される可能性が高まります。
採用のベストタイミングを逃さないためには、候補者の関心度や行動ログを可視化できるタレント管理ツールの導入を検討するとよいでしょう。
発信する情報やコンテンツの質が問われる
候補者との関係を維持するうえで、発信する情報やコンテンツの質は非常に重要です。なぜなら、候補者は自分に関係のない情報や、魅力に欠ける内容に触れ続けると、企業に対する興味を失いやすくなるからです。
汎用的な採用メールや更新のないSNSアカウントよりも、キャリアに役立つ情報や社内のリアルな雰囲気を伝える記事、限定イベントの案内などのほうが好感を得やすいでしょう。
タレントプールを導入している企業事例3選
タレントプールの活用は、企業規模や業種を問わず、戦略的な採用活動の手段として広がりを見せています。
ここでは、SmartHR社とDell Technologies、オーケー株式会社の3つの事例を紹介します。
SmartHR社
クラウド人事労務ソフトで知られるSmartHR社は、タレントプールの構築によって採用母集団の質と量を大幅に改善しました。
これまで人材紹介に頼っていた採用チャネルを、自社メディアとSNSで強化する戦略に転換し、年間約3,700名の登録者をデータベースに蓄積することに成功。
複数人向けのコミュニケーションだけではなく、個別での接触もおこなうことで、自社によりマッチした人材へのアプローチを実現しています。
出典:ナイル渡邉が気になる、あの会社の採用広報 #1 SmartHR瀧田成紗氏|採用広報のカギは“カルチャー”を発信すること
Dell Technologies
Dell Technologiesはタレントプールを活用して応募者のエンゲージメントを向上させ、低コストで採用候補者を確保することに成功しています。
ジョブアラート登録フォームやSNS連携機能を採用し、候補者との接点を継続的に維持しているためです。
Facebook・LinkedInアカウントと連動した登録により、候補者の転職意向を察知しやすく、広告費を抑えつつ母集団を形成できます。
出典:海外タレントプール事例Vol.2 DELL編 | タレントプール採用マーケティングシステム|株式会社タレントクラウド(TalentCloud Inc.)
オーケー株式会社
小売チェーン企業のオーケー株式会社は、退職者や選考辞退者をカムバック採用の候補としてタレントプール化することで、採用効率を改善しています。
具体的には専用ツールを導入し、旧接点候補者との復帰を促進する体制を整備。結果として、導入から半年で100名以上をデータベースへ登録し、そのうち7名の即戦力採用を実現しました。
タレントプールを運用して優秀人材の確保・定着を目指そう
タレントプールの運用は、採用候補者との継続的な関係構築を通じて、企業にフィットする人材を中長期的に確保する有効な手段です。
しかし、いくら母集団を形成しても、自社に合わない人材を闇雲に採用してしまえば、ミスマッチによる早期離職や人材定着率の低下を招きます。結果として、採用コストの増大や組織の生産性低下につながりかねません。
タレントプールの運用を成功させるには、自社で活躍する人材の傾向をデータで可視化するツールとの併用が効果的です。
『ミキワメAI 適性検査』は、自社で定着・活躍している人材の特徴を分析し、カルチャーや職種との相性を可視化します。
タレントプールとの併用で、データベースに蓄積された候補者を、より正確かつ効率的に選別でき、採用基準の策定と精度向上にも貢献します。
母集団形成から選考、定着までを一貫して設計する取り組みが求められるいま、タレントプールと適性検査の併用は、採用の質を劇的に変える手段となるでしょう。
『ミキワメAI 適性検査』の詳細は以下からご覧ください。
ミキワメAI 適性検査は、候補者が活躍できる人材かどうかを見極める適性検査です。
社員分析もできる無料トライアルを実施中。まずお気軽にお問い合わせください。





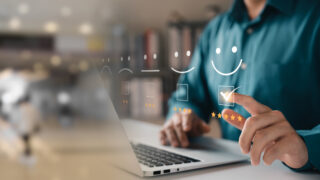

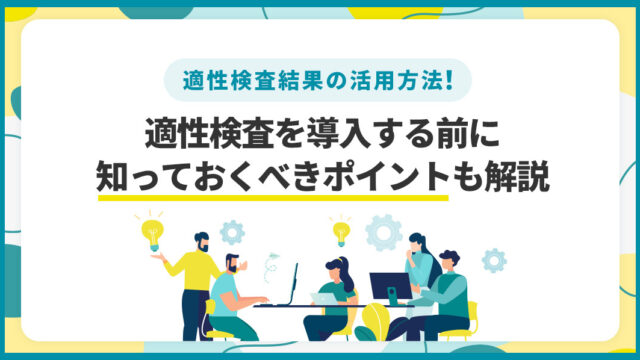








 ランキング1位
ランキング1位 
 ランキング2位
ランキング2位 
 ランキング3位
ランキング3位 