2015年12月に義務化されたストレスチェックですが、現場では「結果をどう活用すればいいのかわからない」「実施するだけで終わってしまう」といった声をよく耳にします。
ストレスチェック制度が整備されていても、集団分析の結果を有効活用しなければ、従業員のメンタルヘルス対策や職場環境の改善にはつながりません。
そこで本記事では、ストレスチェックの活用事例をもとに、具体的な活用のポイントをわかりやすく解説します。
- ストレスチェック制度の基本的な流れ
- ストレスチェックの活用事例【人事主導型・従業員参加型】
- 集団分析の結果を活用するときのポイント
この記事を読むことで、自社に適したメンタルヘルスの施策が明確になり、従業員が安心して働ける職場環境を整えられます。ぜひ最後までご覧ください。
ストレスチェックは組織的に取り組むことが重要

ストレスチェックを実施するときは、従業員のストレス状態を把握するだけでなく、メンタルヘルス対策として組織的に取り組むことが重要です。具体的には、以下のPDCAサイクルに沿って、継続的に運用する必要があります。
※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください
| 手順 | ポイント |
|---|---|
| Plan(計画) | ・ストレスチェックの目的や活用方針を明確にする ・職場環境の改善を見据えた実施計画を立てる |
| Do(実施) | ・ストレスチェックを実施し、個人結果と集団結果を収集する ・集団分析を通じて、職場環境の問題点やストレス要因を特定し、改善策を実施する |
| Check(評価) | ・ストレスチェックの各プロセスを定期的にフォローアップする ・うまくいった点や課題を整理し、次回以降の活動に反映する |
| Act(改善) | ・実施後は再度ストレスチェックを実施し、効果検証を行う ・職場改善活動の成功事例など、他部署へ情報を共有する |
とくに、集団分析に基づく職場改善活動は、従業員のメンタルヘルス不調を未然に防ぐための一次予防として重要なステップとなります。
ストレスチェックを運用する人事・メンタルヘルス担当者は、経営層や産業医と連携しながら、組織的に従業員の健康維持・増進に取り組むことが重要です。
以下の記事では、ストレスチェックの検査内容や実施手順をわかりやすく解説しています。本記事と合わせて確認してみてください。

ストレスチェックの効果的な活用方法【4ステップ】

ストレスチェックの結果を有効活用するためには、検査の実施から職場環境改善までの流れを把握しておく必要があります。具体的な手順は、以下のとおりです。
※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください
| 活用方法 | ポイント | |
|---|---|---|
| 1 | 基本方針に基づく実施体制の整備 | ・ストレスチェックの目的・対象者・実施方法などを検討し、衛生委員会などで審議する ・実施者と事務従事者の役割を明確にし、個人情報の取り扱いルールを決める |
| 2 | ストレスチェックの実施・集団分析 | ・調査票(57項目)をもとに、3つの要素(仕事のストレス要因・心身の反応・周囲のサポート)を測定する ・部署ごとで集団分析を行い、ストレス要因の傾向や課題を把握する |
| 3 | メンタルヘルス不調者の発見・対応 | ・高ストレス者を選定し、必要に応じて医師による面接指導を勧奨する ・面接指導の受診は本人の意思に基づいて行う(強制や不利益な取り扱いは禁止) |
| 4 | 集団分析結果を活用した職場環境の改善 | ・集団分析で明らかになった課題について、具体的な改善策を立案する ・改善活動は、衛生委員会・産業医・人事が連携し、PDCAサイクルで進める |
以下より、各ステップを詳しく解説します。
1:基本方針に基づく実施体制の整備
ストレスチェックを効果的に運用するためには、まず基本方針に基づいた実施体制を整備する必要があります。
基本方針を策定するときは、厚生労働省の「労働安全衛生法に基づく実施マニュアル」を参考に、自社の業種・規模・働き方に合ったストレスチェック制度を設計します。
ストレスチェック制度の基本方針が決定したら、以下のような点を検討し、実施体制を整えましょう。
※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください
| 検討事項 | 内容 |
|---|---|
| 実施者・事務従事者の選任 | ・医師、保健師などから実施者を選任する ・人事担当者などから事務従事者を選任する(人事権を持つ人は従事できない) |
| 実施方法・頻度の検討 | 実施媒体(紙・Web など)を選択し、1年に1回以上の頻度で実施できるよう計画する |
| 対象者の選定 | ストレスチェックの対象となる従業員(常時雇用されている労働者)を明確にする |
| 結果の取り扱い・ルールの決定 | 結果通知の方法、医師面談の勧奨方法、集団分析結果の活用方針などを決める |
また、個人情報の管理体制を整え、従業員が安心してストレスチェックを受けられる環境をつくることも重要です。結果の閲覧権限を明確にし、人事評価や異動などに不当に利用されないよう明文化しておきましょう。
2:ストレスチェックの実施・集団分析
社内の実施体制が整ったら、対象者に調査票を配布してストレスチェックを実施しましょう。
一般的には、厚生労働省が推奨する「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」を用いて検査を行います。主なチェック項目は、以下の3点です。
※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| 仕事のストレス要因 | 仕事量・仕事の進め方・対人関係など、職場環境における心理的負担の原因を把握する |
| 心身のストレス反応 | イライラ・疲労・不安など、ストレスによる心身の自覚症状を確認する |
| 周囲のサポート | 上司・同僚・家族からの支援の有無を把握する |
検査後は回答データを集計し、個人結果をまとめた「ストレスプロフィール」を作成します。個人結果をもとに集団分析を行い、部署ごとのストレス傾向や職場環境の課題を把握しましょう。
『ミキワメ ストレスチェック』では、一般的な57項目に加え、組織分析にも活用できる全80項目の検査を採用しています。
調査票の配布や集計、結果の通知などの機能を無料で利用できます。詳細をまとめた資料をご用意していますので、ご興味のある方はぜひダウンロードしてご活用ください。
3:メンタルヘルス不調者の発見・対応
結果から一定の基準を満たす従業員を「高ストレス者」として抽出し、必要に応じて医師による面談やフォローアップを行いましょう。
高ストレス者の選定においては、単にスコアが高い人を抽出するのではなく、複数の視点から総合的に判断します。主な要件は以下のとおりです。
- 「心身のストレス反応」の評価点数の合計が高い人
- 「心身のストレス反応」の評価点数が一定以上、かつ「仕事のストレス要因」や「周囲のサポート」の評価点数の合計が著しく高い人
高ストレス者に対しては、医師による面接指導を受けてもらうよう勧める必要があります。ただし、面接指導は本人が希望する場合のみであって、企業側が強制したり、面接を拒否した従業員に不利益を与えたりすることは禁止されています。
4:集団分析結果を活用した職場環境の改善
集団分析の結果をもとに、部署ごとのストレス要因や傾向を把握します。具体的な課題が見つかった場合は、速やかに改善策を検討しましょう。
職場環境の改善を進めるときは、以下のような手順を踏むと効果的です。
※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください
| 手順 | 内容 | |
|---|---|---|
| 1 | 体制づくり | 職場環境改善の目的と方針を明確にし、関係部署と協働できる体制を構築する |
| 2 | 状況の把握 | 「仕事のストレス判定図」などをもとに、職場ごとの課題を可視化する |
| 3 | 改善計画の立案 | 優先度の高い課題を抽出し、施策の実行計画を立てる |
| 4 | 実施と進捗確認 | 改善策を実行し、定期的に進捗や課題を確認する |
| 5 | 効果の評価と見直し | ストレスチェックやアンケート調査を通じて、改善策の効果検証を行う |
このPDCAサイクルを継続的に回すことで、従業員がやりがいを感じられる職場づくりを実現できます。
【経営・人事主導型】ストレスチェックの活用事例4選

ここからは、経営・人事主導で進めたストレスチェックの活用事例を4つ紹介します。組織の課題を見える化し、職場環境の改善や人材マネジメントに活用している点が特徴です。
※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください
| 取り組み内容 | 効果 |
|---|---|
| サーベイとの併用で「ケアが必要な社員」への声かけが可能に | ・組織の状態がひと目でわかるようになった ・「ケアが必要な社員」への声かけが可能になった |
| データに基づいたフィードバックで組織状態の理解度が向上 | ・経営と事業部門の間で、目線を揃えて組織課題に取り組めるようになった ・データをもとに、組織やマネジメントのフィードバックができるようになった |
| 職場環境改善の取り組みで総合健康リスクが減少 | ・職場環境改善の提案件数が、50件から463件に増加した ・総合健康リスクが「110」から「98」に減少した |
| 集団分析に関する研修を行い、職場環境改善に対する認知度が向上 | ・各事業場で集団分析の目的や重要性への理解が深まった ・事業所単位で職場環境改善に取り組めるようになった |
それぞれの事例を詳しく見ていきましょう。
サーベイとの併用で「ケアが必要な社員」への声かけが可能に
企業向け業務システムの開発を行う株式会社リアルソフトでは、社員数が40人から80人程度まで増えたことで、徐々に一人ひとりとのコミュニケーションが難しくなりました。
経験の浅い若手社員が多いこともあり、自分のストレスや悩みに気づけず、体調を崩してしまうケースも出始めていたのです。
そこで同社は、ストレスチェック機能を搭載した『ミキワメ ウェルビーイングサーベイ』を導入し、ストレス状況に加えてエンゲージメント(仕事への意欲)の測定も行いました。具体的な取り組みは、以下のとおりです。
- 月に1回の頻度でサーベイを実施
- 調査結果を経営・人事部門が確認
- ケア対象となる従業員に面談やフォローアップを実施
- 管理職や人事が「最近どうですか?」と個別に声かけ
これらの取り組みによって、組織の状態がひと目でわかるようになり、マークしていない社員の「大変そう」という心理状態も把握できるようになりました。
サーベイとストレスチェックを同じシステムで運用できるため、社員の負担も抑えられ、人事・管理職側のフォロー体制も確実に強化されています。
事例:企業拡大に伴ってのコミュニケーション課題をミキワメで解決|株式会社リアルソフト
サーベイの概要や調査項目を確認したい方は、以下の記事をご覧ください。具体的に活用方法や事例を解説しています。
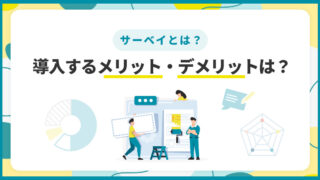
データに基づいたフィードバックで組織状態の理解度が向上
Web広告・メディア業を行うウェブソア株式会社では、社員数が50人に増えたことで、社員一人ひとりの状況を正確に把握するのが難しくなっていました。
組織が拡大する中で、従来のストレスチェックだけでは、個々の状況に応じたフォローが不足していたのです。
そこで同社は『ミキワメ ウェルビーイングサーベイ』を導入し、月1回のアンケート調査で社員の状態を定点観測する運用を始めました。
具体的には、経営トップと役員が調査結果にアクセスできるように設定し、部門ごとの数値を見ながら事業部長にフィードバックしています。
サーベイを導入したことで、組織の課題が明確になり、経営・事業部門の間で目線を揃えて社員へのケアができるようになりました。
また、客観的なデータをもとに組織やマネジメントのフィードバックができるようになり、組織に対する役員・事業部長の理解度向上にもつながっています。
事例:社員一人ひとりが理想的な状態で働ける会社であり続けるために|ウェブソア株式会社
職場環境改善の取り組みで総合健康リスクが減少
電気機器製造業のある企業では、従業員の疲労やストレスを軽減するために、「職場環境の改善」と「従業員の健康意識を高める活動」を積極的に推進しています。
具体的には、産業医が実施者としてストレスチェックを年1回行い、以下の調査票(指標)を用いて職場のストレス状況を多面的に分析しました。
※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください
| 指標 | 概要 |
|---|---|
| 職業性ストレス簡易調査票 | 仕事上のストレス要因やストレス反応、周囲のサポート状況などを測定する調査票(厚生労働省推奨) |
| ワークエンゲージメント | 仕事に対して積極的に取り組み、活力を得ている状態を評価する指標(活力・熱意・没頭の3要素) |
| 努力報酬不均衡モデル | 仕事における「努力・報酬」をもとに、慢性的なストレス状況を把握する理論的モデル |
| メンタルヘルス風土尺度(WIN) | 建設的な話し合いを通じて職場環境改善を行うために、職場のポジティブな側面に着目して評価する指標 |
分析後は、管理者向けの説明会で産業医が結果を解説し、現状と今後の対策について管理者と意見交換を行いました。管理者は、職場環境の改善に向けた取り組みを検討し、安全衛生委員会で報告・評価する流れです。
これらの取り組みの結果、職場環境改善の提案件数は、50件(2003年)から463件(2014年)に増加し、総合健康リスクも「110」から「98」に減少しました。
参考:労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(P93)|厚生労働省
集団分析に関する研修を行い、職場環境改善に対する認知度が向上
製造業のある企業では、各事業場へ集団分析結果を提示していたものの、産業保健スタッフが常勤していない拠点も多く、結果を適切に活用できていない状況でした。
この課題を解決するために、健康管理部門において「集団分析読み方ワークショップ」を主催し、集団分析の見方や結果の解釈方法を実践的に学ぶ機会を設けました。
講師には労働衛生機関の臨床心理士を招き、参加者のレベルに応じて「基礎編」と「応用編」に分けて研修を実施しています。
理解度の高い参加者には、より深い分析手法や活用事例を紹介するなど、段階的に知識を定着させる仕組みを取り入れています。
こうした研修を実施した結果、各事業場で集団分析の目的や重要性への理解が深まり、事業所単位で職場環境改善に取り組めるようになりました。
参考:ストレスチェック制度の効果的な実施と活用に向けて(P21)|厚生労働省
【従業員参加型】ストレスチェックの活用事例4選

続いては、従業員参加型のストレスチェック活用事例を4つ紹介します。従業員が主体的に職場改善活動に参加し、具体的な取り組みを検討している点が特徴です。
※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください
| 取り組み内容 | 効果 |
|---|---|
| 職場環境改善の検討会を通じて、心身のストレス反応が低下 | 従業員主体の検討会を実施したことで、組織活力が向上し、心身のストレス反応の低下が確認された |
| 「職場ドック」の実施で、ポジティブ志向の職場環境改善を実現 | 職員一人ひとりが「自分の職場をよりよくしよう」とポジティブな考えを持つようになった |
| 仕事のしにくさの原因に基づいた改善で、従業員のストレスが軽減 | 従業員でも気づかなかった「仕事のしにくさ」の原因が判明し、ストレスの軽減につながった |
| 従業員参加型ワークショップの実施によって改善策の実行力が向上 | 自分たちで決める「スモールチェンジ」が浸透し、行動へのハードルが下がった |
以下より、それぞれの取り組みを詳しく見ていきましょう。
職場環境改善の検討会を通じて、心身のストレス反応が低下
大手製造業のある企業(従業員約4万5000人)では、「全社心の健康づくり方針」を策定し、ストレスチェックに基づく職場環境改善を進めています。
具体的には、産業保健スタッフと人事・安全衛生部門が連携し、全従業員が参加して意見交換を行う「職場環境改善検討会」を実施しました。
【検討会の流れ】
- 管理監督者との事前打ち合わせ(30分)
- 検討会での参加者への趣旨の説明(30分)
- グループ討議のファシリテーション(60分)
- 討議結果の全員での共有(30分)
従業員主体の検討会を実施した職場では、翌年に「組織活力の向上」と「心身のストレス反応の低下」が確認されました。
このように従業員が自ら意見を出し合う「参加型の職場環境改善」は、ストレス要因を排除するだけでなく、組織の一体感を高める効果があると言えます。
参考:労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(P94)|厚生労働省
「職場ドック」の実施で、ポジティブ志向の職場環境改善を実現
高知県では、職員のメンタルヘルス対策の一環として始まった取り組みが、参加型の職場改善活動「職場ドック」として定着しました。
職場ドックは、全身の健康状態をチェックする人間ドックのように、「職場の健康状態を自分たちで点検する」という発想から名づけられました。職場ドックの具体的な流れは、以下のとおりです。
- 年度計画に基づき対象の職場を選定する
- 自分の職場のよい点・改善点をメモする
- 各職場で60〜90分程度の検討会やグループワークを実施する
- 職場単位で改善計画を作成し、実行に移す
- 改善の成果を報告し、職場内ニュースなどで周知する
職場ドックの実施によって、職員一人ひとりが「自分の職場をよりよくしよう」とポジティブな考えを持つようになり、職場改善活動が活性化しました。
また、複数の職場で情報共有を行うことで、改善活動の促進にもつながっています。
参考:労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(P95)|厚生労働省
仕事のしにくさの原因に基づいた改善で、従業員のストレスが軽減
電気設備工事業を営むある企業では、従業員が8人と少ないこともあり、ストレスチェックの集団分析結果をフィードバックしていませんでした。
そこで、従業員の健康確保や生産性向上にも役立てようと経営者に働きかけ、ストレスチェック結果に基づく従業員参加型のグループワークを実施しています。
厚生労働省の「職場環境改善のためのヒント集」を用いて、職場のよい点と改善が必要な点などを意見交換し、ストレスの要因になっている問題を洗い出しました。
その結果、倉庫内の道具置き場の整理が必要だとわかったため、全員で協力して倉庫の整理整頓を行い、工具掛けを設置するなどの改善を実施しています。
取り組み後、従業員からは「工具掛けが想像以上によい完成度だった」「全員参加で達成感があった」といった声が上がりました。
従業員でも気づかなかった「仕事のしにくさ」の原因が判明したことで、職場環境改善を通じて従業員のストレス軽減につながりました。
参考:労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(P97)|厚生労働省
従業員参加型ワークショップの実施によって改善策の実行力が向上
光ファイバ部品などの製造・販売を行う三菱電線工業では、トップダウンで進めてしまいがちだった職場改善活動において、従業員参加型のワークショップを実施しました。
ワークショップでは、問題解決型のアプローチではなく、ポジティブな変化を引き出すAI(Appreciative Inquiry)手法を取り入れました。
ある部署では、スモールチェンジの考え方を大切にしながら、「業務の助け合いについて」のグループワークを実施しています。
【主なテーマトーク】
- 自分たちの職場の強みは何だと思うか
- 過去によかったと思ったことはないか
- どのような工夫があったのか
- 何をすればもう一歩進めると思うか
- スモールチェンジ(小さな一歩)としてみんなでできることを何か
このように、誰かに言われてやるのではなく、自分たちが決めて小さな行動を起こすことで、従業員一人ひとりが「できた」と実感できます。
従業員参加型のワークショップを通じて、従業員が自ら考え、行動する文化が少しずつ浸透しました。自分たちで決める「スモールチェンジ」を積み重ねることで、行動へのハードルが下がり、実行力も高まりつつあります。
参考:職場のメンタルヘルス対策の取組事例(三菱電線工業株式会社)|厚生労働省
ストレスチェック結果を活用するときのポイント

ストレスチェックを実施しても、検査結果を職場改善活動につなげなければ意味がありません。ここでは、ストレスチェック結果を活用するためのポイントを紹介します。
以下より詳しく見ていきましょう。
経営層にも主体的にかかわってもらう
ストレスチェックを実施するときは、経営層にも主体的にかかわってもらい、組織が一体となって取り組まなければなりません。
経営層がストレスチェックの目的と効果を理解し、自らの言葉で基本方針を発信することで、従業員の職場改善活動に取り組む姿勢が大きく変わります。
単に義務的にストレスチェックを行うのではなく、従業員の健康を守るメンタルヘルス対策として位置づけることが重要です。
また、職場改善活動を現場に任せきりにせず、経営層が進捗を確認できる仕組みをつくりましょう。経営的な視点からアドバイスをして、全社的な施策につなげることも可能です。
経営層が主導してメンタルヘルス対策を推進することで、「従業員の健康」と「企業の持続的な成長」を両立できる職場環境が実現します。
集団分析の活用方針を明確にする
ストレスチェックの集団分析を行うときは、まず「なぜ分析を行うのか」「どのような取り組みに活用するのか」を明確にすることが重要です。
目的や活用方針が曖昧なままだと、職場のストレス状況や傾向などを把握するだけで終わってしまいます。
集団分析は、個人のストレス状態を評価するものではなく、職場単位でストレスの傾向や課題を把握し、職場環境の改善につなげるための作業です。
そのため、分析結果をどのように活かすかを具体的に設計しておく必要があります。
【具体例】
- 部署ごとに職場環境改善の検討会を実施し、課題と改善策を話し合う
- 産業医や人事・安全衛生担当者と連携して改善計画を策定する
- 管理職向けに結果の見方や対応策を学ぶ研修を実施する
上記のように活用方針を明確にしておくことで、職場環境をよりよくするための具体的なアクションを検討できます。
検査結果をフィードバックし、具体的な施策を検討する
ストレスチェックの効果を高めるには、個人結果・集団分析結果の両方を従業員にフィードバックし、自身や組織の状態を正しく理解してもらうことが大切です。
個人結果のフィードバックでは、ストレスの傾向を「気づき」として捉えてもらい、産業医による面談やセルフケアの実践につなげます。ストレス状態をレーダーチャートで出力するなど、視覚的にわかりやすい方法でフィードバックしましょう。
一方、集団分析結果は、部署・チームごとのストレス傾向を把握し、職場環境の課題を明確にすることが目的です。分析結果を踏まえた施策を提案することで、職場のストレス要因を取り除くような改善が可能になります。
ストレスチェックのような調査(サーベイ)では、従業員との対話を通じて職場のよい点・改善点を話し合うことが重要です。
その手法の一つ「サーベイフィードバック」については、以下の記事で詳しく解説しています。本記事と合わせて確認してみてください。

職場環境改善の効果を定期的に確認する
ストレスチェックによる職場改善活動は、一度きりの取り組みで終わらせず、定期的に効果検証を行うことが大切です。
職場環境の課題や従業員のストレス要因は、組織再編や人事異動などによって変化していくため、継続的なモニタリングが必要になります。
【確認ポイント】
- 前回の検査結果と比較し、総合健康リスクやストレス反応の変化を分析する
- 従業員アンケートやヒアリングを行い、現場の実感や新たな課題を把握する
- 産業医や人事・衛生委員会などと連携し、定期的に職場環境改善の方向性を見直す
定期的に効果検証を行うことで、ストレスチェックを軸とした職場づくりが可能となり、従業員の健康維持はもちろん、組織の生産性向上にもつながります。
『ミキワメ ストレスチェック』なら組織分析にも活用できる

株式会社リーディングマークが提供する『ミキワメ ストレスチェック』は、ストレス状態の把握だけでなく、組織分析を通して職場環境改善につなげられるツールです。
ウェブブラウザから簡単に設定・検査ができるうえに、回答データは自動的に集計され、個人結果と集団結果をわかりやすく可視化します。主な機能と特徴は、以下のとおりです。
※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください
| 機能 | 特徴 |
|---|---|
| ウェブブラウザで調査票の配布・回収・集計 | ウェブブラウザ上ですべての操作が完結し、専用ソフトをインストールする必要がない |
| 全80項目の調査に対応 | 一般的な調査票(57項目)に加えて、組織分析に活用できる全80項目の調査票を採用している |
| 組織診断との連携 | 『ミキワメ ウェルビーイングサーベイ』と連携し、エンゲージメントや心理的安全性も含めた分析ができる(有償) |
| 検査結果をCSVファイルで出力 | 集団のストレスチェック集計結果をCSVファイルとして簡単に出力できる |
ミキワメは、労働安全衛生法に準拠した検査はもちろん、ストレス要因の分析や職場改善活動のツールとしても活用できます。
『ミキワメ ストレスチェック』の詳細については、以下の記事で解説していますので、本記事と合わせて確認してみてください。

ストレスチェックの活用に関するよくある質問

ストレスチェックの活用に関する「よくある質問」について回答します。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
Q1:ストレスチェックの結果は誰が見る?人事や上司にバレる?
ストレスチェックの結果は、受検者本人と実施者(医師、保健師 など)、事務従事者の3者のみが確認できます。そのため、人事権を持つ人事担当者や上司が個人結果を勝手に閲覧することはできません。
本人の同意があった場合のみ、産業医や事務従事者が結果を共有し、必要に応じて面談や就業上の措置を行います。
ただし、ストレスチェックの結果のみで勤務時間を短縮したり、人事異動を命じたりするなど、受検者への不利益な取り扱いは禁止されています。
ストレスチェック結果の管理方法について詳しく知りたい方は、以下の記事を確認してみてください。職場環境の改善に活かすためのポイントも解説しています。

Q2:何のためにストレスチェックを実施するの?
ストレスチェックは、従業員のメンタルヘルス不調を早期に発見し、職場環境改善につなげることを目的としています。従業員のストレスの有無を把握するだけではなく、組織の健康リスクを可視化するための検査です。
ストレスチェックは、2015年12月に施行された労働安全衛生法の改正によって、従業員50人以上の事業場での実施が義務化されました。
2025年5月に「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」が公布され、2028年度には50人未満の企業を含むすべての企業で義務づけられる予定です。
こうした流れからも、従業員の健康維持と生産性向上を両立させる手段として、ストレスチェックを活用していくことが求められます。
Q3:ストレスチェックは「意味がない」と言われる理由は?
「ストレスチェックは意味がない」と言われる理由の一つは、検査を実施しただけで、職場環境が一向に改善されないケースです。
たとえば、個人結果を渡しただけでフォローがなかったり、集団分析の結果が改善活動に反映されなかったりすると、従業員は「検査をするだけ無駄」と捉えてしまいます。
ストレスチェックを適切に運用するためには、検査結果を必ずフィードバックし、従業員一人ひとりが自分のストレス状態を理解することが重要です。
組織としても、集団分析を通じて職場ごとの改善策を検討・実行することで、メンタルヘルス対策として有効な取り組みになります。
以下の記事では、ストレスチェックが「無駄」と言われる理由と対策について解説しています。本記事と合わせて確認してみてください。

事例を参考にストレスチェックの活用方法を検討してみよう

ストレスチェックの目的は、従業員の心身の不調を早期に発見し、職場環境改善を通じて健康的に働ける職場をつくることです。
検査結果を活用する方法として、本記事では「経営・人事主導型」「従業員参加型」に分けて具体的な事例を紹介しました。
>>「経営・人事主導型」の活用事例を確認する
>>「従業員参加型」の活用事例を確認する
※記事前半にジャンプします
ストレスチェックは、従業員のストレス状態を把握するだけではなく、組織の成長を支えるマネジメントツールとしても活用できます。
定期的な検査と分析を通じて、従業員が安心して働ける環境をつくり、組織の活力向上につなげていきましょう。
ミキワメAI 適性検査は、候補者が活躍できる人材かどうかを見極める適性検査です。
社員分析もできる無料トライアルを実施中。まずお気軽にお問い合わせください。




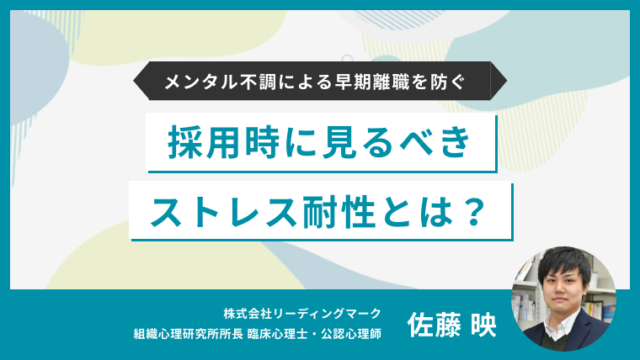







 ランキング1位
ランキング1位 
 ランキング2位
ランキング2位 
 ランキング3位
ランキング3位 