近年、若手社員を中心に「管理職になりたくない」と考える人が増えています。
かつては昇進がキャリアの成功と見なされていましたが、現在では「責任の重さ」や「自信のなさ」などを理由に、管理職を避ける傾向が強まっています。
このような傾向は、企業にとって深刻な課題です。管理職のなり手が不足すれば、マネジメント機能が弱体化し、人材育成や情報伝達が滞るだけではなく、組織全体の成長力や競争力の鈍化にもつながりかねません。
本記事では、管理職になりたくない社員の割合や、なりたくない理由を整理したうえで、企業が取り組むべき具体的な施策について解説します。
管理職になりたくない社員が増えている?
複数の調査結果から、管理職への昇進を希望する社員の割合は非常に低いことが明らかとなっています。具体的な数値を見ていきましょう。
パーソル総合研究所の調査では「現在の会社で管理職になりたい」と回答した人の割合はわずか16.7%にとどまっています(2025年時の調査結果)※1。
また、日本能率協会マネジメントセンターの調査でも、管理職を希望する人は全体の23.4%に過ぎず、約7〜8割の社員が昇進を望んでいないことが示されています(2023年時の調査結果)※2。
なお、いずれの調査も、過去の結果と照らし合わせると管理職志向の割合はほぼ横ばいの状態が続いており、「管理職になりたくない」という意識はすでに常態化していると考えられるでしょう。
また、少子高齢化による人手不足が一層深刻化すると予想されるなか、今後は管理職人材の確保がこれまで以上に難しくなる見込みです。
※1 出典:パーソル総合研究所「働く10,000人の就業・成長定点調査」(2025年)
※2 出典:日本能率協会マネジメントセンター「77%が『管理職になりたくない』【調査レポート】ポジティブな管理職を育てるために人事が押さえたいポイントとは?(2023年)
管理職になりたくない原因
管理職への昇進が敬遠される主な要因は「自身のスキルやキャリアデザインとの不一致」や「業務量・待遇面に対する問題」です。
これらの観点から、管理職になりたくないと考える具体的な理由は、以下のように整理できます。
- 管理職になる自信がない
- 心理的な重圧が大きい
- ワークライフバランスを重視したい
- 給与が下がる
- 現場仕事を続けたい
それぞれの要素について詳しく見ていきましょう。
管理職になる自信がない
多くの社員は、自分には管理職としての資質やスキルが十分ではないと感じています。とくに、部下を指導するリーダーシップや、組織全体を見渡すマネジメント力に不安を抱く人は少なくありません。
プレイヤーとしての業務は得意でも、人をまとめる立場に立つことへの自信が持てず「自分には向いていない」と判断する傾向が見られます。
心理的な重圧が大きい
管理職になると、部署全体の成果や課題に責任を持つ立場となり、心理的な重圧を強く感じる社員は少なくありません。成果が上がらなければ、自分だけではなく部門全体の評価に影響することから、常に大きな重圧に悩まされるようになります。
さらに、部下との信頼関係を築きながら上層部の要求にも応える必要があり、いわゆる「板挟み」の状況に置かれることが多い点も、プレッシャーを感じる要因です。
こうした環境では、部下との日常的なコミュニケーションや調整業務そのものがストレスになり「管理職は精神的に負担が大きい」と感じやすくなります。
ワークライフバランスを重視したい
「ワークライフバランス」を重視する価値観が広がっていることも、管理職を敬遠する人が増えている理由の一つです。管理職は業務量が多く、部下のマネジメントや会議対応などによって拘束時間が長くなる傾向があるため、仕事と生活の両立が難しくなります。
とくに、プライベートの時間を大切にしたい人や、育児・介護といった家庭の事情を抱える人にとっては、その負担感がより大きく映ってしまうでしょう。
その結果、管理職への昇進を「キャリアアップ」とポジティブにとらえるのではなく、「ライフスタイルを損なうリスク」としてネガティブに受け止める傾向が強まっています。
給与が下がる
給与への不満も、管理職になりたくないと感じる要因の一つです。管理職になると時間外手当が支給されなくなる場合があり、実質的に給与が下がるケースがあります。
これは「給与の逆転現象」と呼ばれるものです。実際に月数万円単位の減収につながった事例も報告されており、決して軽視できません。
さらに、昇進によって責任や業務負担は増える一方で、報酬や待遇がそれに見合わないと感じる社員も少なくありません。「管理職になっても待遇が改善するどころか悪化するのではないか」という懸念から、管理職を希望しない社員が増えています。
現場仕事を続けたい
現場の仕事を続けたいがために、管理職になりたくないと考える社員は一定数存在します。マネジメント業務に携わるよりも、日々の実務を通じてスキルを磨き、専門性を高めることに価値を感じているためです。
とくに、技術職や専門職ではこの傾向が顕著で、現場での経験こそがキャリアの核になると考える人が多く見られます。そのような社員にとって、管理職への昇進は「自分の進みたい道を断たれること」に近く、不安や抵抗感の要因となっているのです。
管理職不足が引き起こすリスク
管理職不足は、企業に深刻な影響をもたらします。とくに注意すべき問題は、以下の3点です。
- 管理職の負担が大きくなる
- 経営層の意図が現場に届かない
- 社員の育成が進まない
各課題について詳しく解説します。
管理職の負担が大きくなる
管理職の負担が大きくなることは、管理職の不足によって生じる代表的なリスクです。管理職の人数が足りない場合、既存の管理職が複数の業務やチームメンバーを兼任しなければならず、一人ひとりの業務量が過剰になります。
その状態が続くと、マネジメントの質が低下したり、意思決定のスピードが鈍ったりするなど、組織全体のパフォーマンスにも悪影響を及ぼしかねません。
さらに、過度な負担は既存の管理職の離職やメンタルヘルスの悪化を招くおそれもあります。その結果、管理職の人員がさらに減少し、残された管理職への負担が一層増すという、負のスパイラルに陥るリスクが高まります。
経営層の意図が現場に届かない
経営層の意図が現場に届かないという課題も、管理職不足によって生じる深刻なリスクの一つです。
管理職は、経営層の戦略や方針を現場に正確かつ効果的に伝える役割を担っており、この橋渡しが機能しなくなることで、現場への伝達が不十分になります。
その結果、現場社員の共感や理解が得られず、制度や目標が形骸化してしまうおそれがあります。情報の流れが滞りやすくなり、経営層と現場の間に意識のギャップや分断が生じる点も、大きなリスクといえるでしょう。
社員の育成が進まない
管理職が不足すると、社員の育成が思うように進まなくなる場合があります。
管理職の役割には、業務のマネジメントだけではなく、部下の育成やキャリア支援、チーム内の関係構築といった「人を育てる」機能も含まれます。
しかし、管理職が十分に確保されていない状況では、これらの重要な取り組みが後回しになり、若手社員の成長機会が大きく損なわれかねません。
さらに、指導やフィードバックの機会が乏しい環境では、社員が自らの成長を実感しづらくなり、モチベーションの低下や離職につながるリスクも高まります。
「管理職になりたい」と思える職場にするには?
「管理職になりたい」と思える職場にするためには、管理職の負担を軽減し、働きやすい環境を整えることが重要です。具体的な施策としては、以下の3点が挙げられます。
- 管理職の役割・業務の見直し
- 報酬や評価制度の見直し
- ワークライフバランスの改善
各施策の詳細を紹介します。
管理職の役割・業務の見直し
管理職の役割・業務を見直すことは「管理職になりたい」と思える職場づくりにおいて欠かせない取り組みです。
「責任が重い」「人を管理するだけの仕事」といったネガティブなイメージを払拭するためには、管理職の位置づけや業務内容を再構築し、より前向きにとらえられるようにする必要があります。
たとえば、専門スキルを磨きながらマネジメント力も高められるキャリアパスを整備したり、定型的なマネジメント業務や育成業務をチーム内で分担できる体制を整えたりすることが有効です。
実際に、日本でも管理職の役割を複数人で分担する企業が出始めています。
ある企業では、従来一人の部長が担っていた「業務運営」と「人材管理」の役割を分割し、それぞれに特化したポストを設けることで、役割の明確化と業務の分散を図りました。
その結果、管理職の負担を軽減しつつ、育成や戦略実行に集中できる職場環境を実現しています。
こうした取り組みは、社員の不安や抵抗感を和らげるとともに、管理職というポジションに対する意欲を高める大きな要因となるでしょう。
報酬や評価制度の見直し
報酬や評価制度の見直しも「管理職になりたい」と思える職場づくりには欠かせません。個人の成果だけではなく、チーム全体の成果やマネジメントの質を正当に評価する仕組みを導入することで、管理職としてのやりがいや達成感を味わえるようになります。
業績や役割に応じた報酬制度を整えれば、管理職の責任の重さと報酬のバランスが明確になります。制度面から管理職の価値を正しく伝えることで、昇進に対するモチベーションを高められるでしょう。
ワークライフバランスの改善
フレックスタイム制度やテレワークの導入、さらには一部業務の権限をチーム内で分担する仕組みなど、柔軟な働き方を支える制度を整備することで、管理職の働き方にも選択肢が広がります。
こうした取り組みによって、社員は自身のライフスタイルや価値観を大切にしながら、無理なく管理職としての役割を果たすことが可能です。業務負荷の軽減とプライベートの両立を実現できれば、管理職というキャリアにも前向きな意識を持ちやすくなるでしょう。
若手社員から管理職候補を育てるための施策
若手社員の「管理職離れ」は、管理職の働き方を整えるだけでは解決できません。なぜなら、若手社員が管理職を敬遠する理由の一つに、管理職に対するネガティブなイメージがあるためです。
「管理職は大変そう」「自分には荷が重い」といった後ろ向きな印象を持っている状態では、意欲的に昇進を受け入れることは難しいでしょう。
そこで、若手の段階から管理職の魅力を知ってもらい、不安を払拭する取り組みが必要です。とくに高い効果が期待できる施策は以下の4つです。
- マネジメント教育やリーダーとしての体験
- 管理職との対話の機会を設ける
- キャリアデザインの支援
- 社員の性格や心理の把握
それぞれの施策について、具体例を交えながら解説します。
マネジメント教育やリーダーとしての体験
マネジメント教育やリーダーとしての体験の提供は、若手社員を将来の管理職候補として育成するために欠かせない取り組みです。
たとえば、チームの目標設定や進捗管理、メンバーの育成、時間管理といったマネジメントに必要な実務スキルを体系的に学べる研修を提供することで、若手社員は管理職に求められる判断力や責任感を実践的に養えます。
また、ケーススタディやロールプレイング形式のワークショップを通じて、実際のマネジメント課題に近い状況を経験すれば、より現実的な視点から管理職の役割を理解できるようになります。
さらに、実際にプロジェクトリーダーなどの役割を経験させることも重要です。こうした経験を通じて「人や成果を主体的に動かす」ことの面白さややりがいを体感でき、管理職のような人の上に立つ役割への理解が深まるでしょう。
管理職との対話の機会を設ける
管理職との対話の機会を設けることは、若手社員が管理職という役割をより身近に感じるための有効な手段です。
たとえば、メンター制度や管理職を交えた座談会・食事会などは、若手社員が管理職から業務の実情ややりがいを直接聞く絶好の機会となります。
こうした場を通じて、管理職に対する理解が深まるだけではなく、心理的な距離も縮まり、昇進に対する漠然とした不安や抵抗感の軽減にもつながります。
尊敬できる管理職と接することで「自分もこんなふうになりたい」と思える理想像を描けるようになることも、若手社員にとっては大きなプラスの影響です。
以下の記事では、社員の性格や心理状態を踏まえた対話ができる『ミキワメAI マネジメント』について詳しく解説しています。ミキワメAIは、社員の成長と成果を最大化する仕組みを構築できる1on1ツールです。
「部下と効果的な1on1ができていない」と悩んでいる人事担当者の方は、ぜひ確認してみてください。

キャリアデザインの支援
キャリアデザインの支援は、若手社員が自分の将来像を前向きに描くうえで欠かせない取り組みです。
たとえば、定期的な1on1ミーティングを通じて「この会社でどのように働き、どう成長していけるのか」といったキャリアの方向性を明確にすると、目の前の業務と将来のビジョンを結びつけることができます。
また、管理職への昇進を「責任が増す役割」としてだけではなく「貢献」や「成長」の機会としてとらえられるように働きかけることも重要です。
たとえば、管理職になればより高い視座から事業全体を見渡せるようになり、意思決定に関わる発言力や、チームを自らの判断で動かせる裁量も得られます。
こうした魅力を具体的な体験談を交えて伝えることで、昇進に対する前向きな意識やモチベーションを育てられます。
社員の性格や心理の把握
若手社員の性格傾向や心理状態、適性を的確に把握することは、一人ひとりに合ったキャリア支援やメンタルケアを実現するための重要なステップです。
管理職に対してネガティブな印象を持つ背景を理解することで、適切なサポートの基盤を築けます。
たとえば「自分には能力が足りない」と感じて管理職を敬遠している社員に対しては、管理職同士で相談できる体制や業務負荷の軽減策を用意すると、不安を和らげることができるでしょう。
また、ワークライフバランスの崩れを懸念する社員に対しては、有給休暇の取得促進やフレックスタイム制度の導入など、メリハリのある働き方を支える取り組みが効果的です。
こうした部下の性格や心理状態を客観的に把握するためには、サーベイツールの活用が有効です。性格傾向やコンディション、マネジメントスコアなどを数値として可視化することで、感覚に頼らない個別対応や育成方針の設計が可能となります。
以下の記事では、導入前に知っておきたいサーベイツールの選び方を5ステップで解説しています。すぐに活用できるチェックリストもありますので、本記事と合わせて確認してみてください。

管理職になりたい社員を増やすためには個々の性格に合ったサポートが必要
近年、一般社員の「管理職離れ」が進んでおり、管理職になりたくないと考える社員は、全体の7〜8割に達しているという調査結果も出ています。
その背景には、責任の重さやマネジメント業務の難しさ、業務量の多さといった要因があります。また、責任や業務量に対して報酬や評価が見合っていない点も、管理職を敬遠する一因です。
管理職不足は、生産性の低下や人材の流出を招き、企業の持続的な発展を阻害するリスクをはらんでいます。このような状況を回避するためには、社員、とくに若手社員が「管理職になりたい」と思えるような環境を整えることが重要です。
業務量や役割、報酬体系の見直しに加え、研修や管理職との対話を通じて、管理職としての魅力ややりがいを伝えていく必要があります。また、社員一人ひとりの性格や心理状態を把握し、それぞれに適した指導や支援を行うことも欠かせません。
そのための施策として、社員理解とマネジメント支援を同時に実現できるツール『ミキワメAI マネジメント』の活用を検討してみてはいかがでしょうか。
従業員のメンタル状態の定期的な可視化・個々の性格に合わせたアドバイス提供を通じ、離職・休職を防ぐエンゲージメントサーベイ。無料トライアルの詳細は下記から。





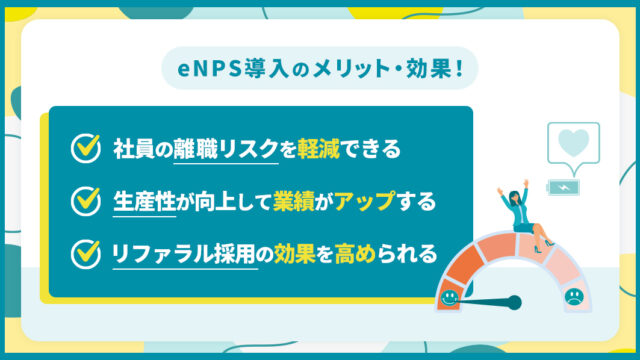






 ランキング1位
ランキング1位 
 ランキング2位
ランキング2位 
 ランキング3位
ランキング3位 