組織力の強化を図っているものの、「なかなか社員の士気やモチベーションが上がらない」と悩んでいる人事担当者の方も多いのではないでしょうか。
社員のパフォーマンスを高めるためには、モラールサーベイの活用が有効です。職場の人間関係や労働条件といった組織・個人の課題を可視化し、改善に向けた具体的なアクションにつなげられます。
モラールサーベイは、組織と社員との関わりを強化し、経営への参加意欲を高める手段としても効果的です。
本記事では、モラールサーベイの概要に加え、以下の内容をわかりやすく解説します。
- モラールサーベイと他のサーベイ種類の違い
- 組織力の強化など、実施による4つのメリット
- 社員の士気が高まる!導入〜活用の手順5ステップ
この記事を読むことで、自社の目的に合った調査方法が明確になり、社員のモチベーション向上に向けた組織改善を実現できます。ぜひ最後までご覧ください。

モラールサーベイとは?そもそもモラールとは何か?

モラールサーベイとは、社員のモチベーションや労働意欲(モラール)を把握・分析するための調査です。日本では、1955年に開発された「従業員態度調査法」が、モラールサーベイの始まりとされています。
参考:NRK方式モラールサーベイ(従業員意識調査)|一般社団法人 日本労務研究会
組織の目標達成に向けて貢献しようとする意欲や態度のこと。企業においては「士気」「労働意欲」「やる気」といった意味で用いられる。
職場の雰囲気や労働環境に関する質問を通じて「社員の働く意欲」を調査し、5分野から組織・個人の課題を分析します。
- 労働条件
- 人間関係
- 管理
- 行動
- 自我
モラールサーベイを導入することで、社員の意見を踏まえた組織改善ができるため、従業員満足度やモチベーションの向上につながります。
モラールサーベイの目的【士気低下の要因を把握】

モラールサーベイを実施する主な目的は、社員の士気やモチベーションを調査し、低下している要因を把握することです。その他にも、以下のような目的があります。
- 組織力の強化
- 社員のパフォーマンス向上
- 待遇や労働条件の問題把握
- 経営層とのコミュニケーション強化
サーベイの結果を踏まえて、職場環境を改善することで、社員の満足度が向上します。また、社員自身も「意見を受け入れてくれた」と実感することで、組織の目標達成に貢献しようとする意欲も高まります。
サーベイを実施するときは、「どのようなテーマで調査するのか」「課題をどのように改善するのか」を明確に決めておくことが重要です。
モラールサーベイと他のサーベイ種類の違い

サーベイには、モラールサーベイの他にもさまざまな種類があります。測定項目や頻度などの違いを理解し、自社の目的に合った方法を選定しましょう。
※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください
| 種類 | 概要 |
|---|---|
| エンゲージメントサーベイ | 仕事への活力や組織への貢献意欲(エンゲージメント)を測定 |
| パルスサーベイ | 心理状態の変化を察知し、タイムリーな改善を行うための調査 |
| 組織サーベイ | 組織の健全性・労働環境を調査 |
| 従業員サーベイ | 労働環境・福利厚生などに対するニーズを調査 |
| ESサーベイ(従業員満足度調査) | 給与・職場環境・人間関係など、組織に対する満足度を数値化する調査 |
以下より、各サーベイの特徴を解説します。
また、サーベイの概要や種類を網羅的に解説した別の記事もあります。詳しく知りたい方はぜひご覧ください。
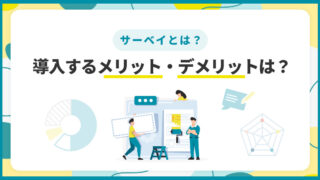
エンゲージメントサーベイとの違い
モラールサーベイとエンゲージメントサーベイは、社員の心理状態を把握する点においては同じ調査方法ですが、以下のように測定項目に違いがあります。
※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください
| 種類 | 主な測定項目 |
|---|---|
| モラールサーベイ | 社員のモラール(士気・労働意欲)を測定 |
| エンゲージメントサーベイ | 仕事への活力や組織への貢献意欲(エンゲージメント)を測定 |
エンゲージメントサーベイは、組織とのつながりにフォーカスした調査ですが、場合によっては、モラール(士気・労働意欲)を含めて測定することもあります。
以下の記事では、エンゲージメントサーベイの目的や実施手順を詳しく解説しています。企業の導入事例も紹介していますので、本記事と合わせて確認してみてください。
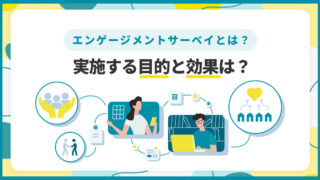
パルスサーベイとの違い
モラールサーベイとパルスサーベイは、以下のように実施頻度や質問数が異なります。
※以下の表は右にスクロールできます
| 種類 | 実施頻度 | 質問数 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| モラールサーベイ | ・半年に1回 ・年に1回 など | 95問(NRK式) | モラール(士気・労働意欲)を中心とした包括的な調査 |
| パルスサーベイ | ・週に1回 ・月に1回 など | 約5〜15問 | 心理状態の変化を察知し、タイムリーな改善を行うための調査 |
たとえば、サーベイツールの『ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ』では、社員のコンディションや心理状態の変化を、自動アラートでいち早く察知できます。この機能を活用することで、社員のメンタル不調やストレスへの早期対応が可能です。
以下の記事では、パルスサーベイの質問項目や結果の活用方法を解説しています。本記事と合わせて確認してみてください。
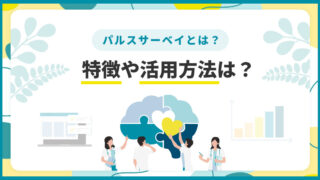
組織サーベイとの違い
モラールサーベイと組織サーベイは、以下のように評価対象や測定項目が異なります。
※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください
| 種類 | 主な評価対象 | 主な測定項目 |
|---|---|---|
| モラールサーベイ | 社員 | モラール(士気・労働意欲)を調査 |
| 組織サーベイ | 組織 | 健全性・労働環境を調査 |
組織のパフォーマンスを高めるためには、社員の満足度向上につながる施策が必要です。モラールサーベイと組織サーベイを組み合わせて実施することで、個人の課題が「組織にどのような影響を与えているのか」をより詳細に分析できます。
以下の記事では、組織サーベイの概要や活用手順をわかりやすく解説しています。調査手法を検討中の人事担当者の方は、本記事と合わせてぜひご覧ください。

従業員サーベイとの違い
モラールサーベイと従業員サーベイは、社員の情報(価値観・考え)を収集する点においては同じ調査方法ですが、以下のように測定項目に違いがあります。
※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください
| 種類 | 主な測定項目 |
|---|---|
| モラールサーベイ | モラール(士気・労働意欲)を調査 |
| 従業員サーベイ | 労働環境・福利厚生などに対するニーズを調査 |
従業員サーベイを活用することで、労働条件や待遇面などの問題点が明らかになり、社員の意見を反映したタイムリーな改善ができます。
以下の記事では、従業員サーベイの目的や実施手順をわかりやすく解説しています。サーベイ導入を検討している人事担当者の方は、ぜひ確認してみてください。

ESサーベイ(従業員満足度調査)との違い
モラールサーベイとESサーベイ(従業員満足度調査)は、どちらも社員の心理状態に関わる調査ですが、測定項目と視点が異なります。
※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください
| 種類 | 主な測定項目 |
|---|---|
| モラールサーベイ | モラール(士気・労働意欲)を調査 |
| ESサーベイ(従業員満足度調査) | 給与・職場環境・人間関係など、組織に対する社員の満足度を数値化する調査 |
ESサーベイは「会社にどれだけ満足しているか」を測定するものですが、モラールサーベイは「満足度」ではなく「士気」にフォーカスした調査です。
満足度が高くてもモチベーションが上がらない社員もいれば、労働条件が厳しくても意欲的に働く社員もいます。モラールサーベイはこのような「やる気の源泉」を測る調査と言えます。
ESサーベイの詳細を知りたい人事担当者の方は、以下の記事をご覧ください。測定項目や実施ステップをわかりやすく解説しています。

モラールサーベイの効果とは?実施する4つメリット

モラールサーベイを実施するメリットとして、以下の4点が挙げられます。
モラールサーベイは、社員の労働意欲や職場の人間関係など、個人の心理状態を包括的に把握できる調査手段です。
以下より、各メリットを詳しく解説します。
組織・社員の課題を可視化できる
モラールサーベイを実施するメリットの一つは、組織・社員が抱えている課題を可視化し、分析や改善ができることです。
たとえば、労働条件に対する社員の不満が出ている場合、勤務体系の見直しや業務量の調整など、具体的な改善策を講じるきっかけになります。
NRK方式の場合、5分野17種目から95問の質問を出題し、さまざまな視点から組織の状態を調査できます。そのため、表面的な問題だけでなく、今まで気づかなかった潜在的な課題の発見も可能です。
以下の資料では、サーベイを活用した組織構築の方法をまとめています。「離職の原因がわからない」と悩んでいる人事担当者の方は、ぜひダウンロードしてご活用ください。
>>「【実例から学ぶ】エンゲージメントサーベイによる組織構築」の資料をダウンロードする
組織力の強化につながる
モラールサーベイを実施する二つめのメリットは、社員の士気や労働意欲の向上によって、組織力の強化につながることです。
サーベイを通じて経営への意見やアイデアを提案することで、社員は組織との関わりを持ち、自らの意志で行動するようになるためです。
たとえば、企業の売上が落ちてきている状況で、社員が感じていることを調査すると、現場では以下のような課題が浮き彫りになります。
- 顧客対応の質が下がっている
- コミュニケーション不足により連携ミスが生じている
- 業務プロセスが煩雑で無駄な時間が多い
サーベイの結果をもとに、現場の意見を取り入れた改善策を打ち出すことで、社員は「自分の声で組織が動いている」という実感を得られます。
その結果、組織全体の士気や労働意欲が向上し、組織と社員との結びつきが強化されるのです。
調査結果を踏まえた人員配置ができる
モラールサーベイを実施する三つめのメリットは、調査結果をもとに社員一人ひとりの状態に応じた人員配置ができることです。
調査する項目には、以下のような人事面や環境面についての質問があります。
- 仕事の負担感や職場環境
- 上司や同僚との人間関係
- 地位や昇進のキャリア形成
仕事の負荷やニーズに応じた人員配置を行うことで、データに基づく組織運営が可能になるのと同時に、社員の働きやすい環境も整えられます。
また、社員の心理状態を考慮すれば、業務効率の向上や離職リスクの低減といった効果も期待できます。
他社と比較し、自社の現状がわかる
モラールサーベイは、自社の状況を客観的に把握するだけでなく、他社との比較を通じて相対的な立ち位置も明確にできます。
近年では、調査結果をベンチマーク(指標)と照らし合わせて分析できるツールも出てきています。とくに同業他社と比較することで、自社の強みや課題をより詳細に把握可能です。
たとえば、「業界平均より社員の帰属意識が低い」という結果が出た場合、他社と比較しながら以下のような課題を把握・分析できます。
- 上司のフィードバックの質に差がある
- 企業理念やビジョンへの共感が得られていない
- キャリアが不透明で将来に不安を感じている
- 働きやすさ(勤務制度・福利厚生)に他社との格差がある
他社との比較データを活用することで、経営層や人事は、データに基づく納得感のある意思決定が可能になります。
モラールサーベイを実施するデメリット

モラールサーベイを実施するときには、以下のデメリットがあることも考慮しておきましょう。
社員の意見を収集し、フィードバックや改善ができる効果的な手段ですが、導入する目的や予算を踏まえた検討が必要です。
以下より、各デメリットを解説します。
導入コストがかかる
モラールサーベイを導入するときは、調査人数に応じたコストがかかります。日本労務研究会が行っている調査の費用は、以下の表のとおりです。
※以下の表は右にスクロールできます
| 方式(調査人数) | 受検方法 | 基本調査費用 (税込) | 分析・診断費用 (税込) | 報告関係費用 (税込) | 合計 (税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| NRK方式 (400人の場合) | Web方式 | 16万5000円 | 27万5000円 | 8万8000円 | 52万8000円 |
| 厚生労働省方式 (50人の場合) | Web方式 | 8万8000円 | 8万8000円 | 17万6000円 | |
上記のように、サーベイ導入には一定のコストがかかります。一方で、専用ツールを利用せず調査しようとすると、設問設計からデータ集計・分析、フィードバックまで、すべての工程を自社で対応しなければなりません。
導入コストと期待される効果のバランスをよく検討し、自社に合ったツールを導入しましょう。
調査が社員の負担になる可能性がある
モラールサーベイは、社員のリアルな意見やニーズを収集することが目的です。
しかし、質問数が多かったり、回答に時間がかかったりすると、社員は調査そのものに抵抗や負担を感じてしまう可能性があります。
NRK方式の場合、質問数が95問あることから「早く調査を終わらせたい」と、曖昧な回答をすることも考えられます。
正確かつ率直な意見を収集するためには、事前に社員に対してサーベイの目的や重要性を説明し、理解を得ることが大切です。
モラールサーベイ2つの実施方式

モラールサーベイには、日本労務研究会が提供している2種類の実施方式があります。
※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください
以下より、2種類の実施方式を解説します。
モラールサーベイのツール以外にも、エンゲージメントを中心に調査を行うツールもあります。以下の記事でおすすめツールを紹介していますので、本記事と合わせてご覧ください。
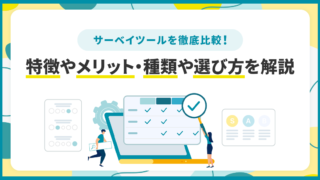
1:NRK方式
NRK方式のモラールサーベイは、主に「社員数300人以上の企業」を対象とした実施方式です。
以下の表のとおり、5分野17種目(95問)から社員の意識を調査し、評価・分析を行います。
| 分野 | 種目 |
|---|---|
| 労働条件 | ・仕事の負担 ・職場の設備 ・給与 ・福利厚生 |
| 人間関係 | ・同僚との関係 ・上司との関係 ・幹部との関係 |
| 管理 | ・上司の行う管理 ・幹部の行う管理 ・意思の疎通 |
| 行動 | ・上司の行動 ・個人の行動 ・育成と心身への配慮 |
| 自我 | ・地位の安定 ・地位についての満足 ・昇進向上の機会 ・会社との一体感 |
出典:NRK方式モラールサーベイ診断内容|一般社団法人日本労務研究会
5つの分野を総合して「士気の総合水準(TML)」を算出し、社員の満足度や働く意欲を評価します。
また、選択式の回答だけではなく自由意見も記載できるため、データだけではわからない社員のリアルな悩みも把握可能です。
NRK方式を実施するときは、調査対象や目的、実施時期などの打ち合わせを行います。そのため、事前に自社の目的や課題を明確にしておきましょう。
2:厚生労働省方式
厚生労働省方式のモラールサーベイは、主に「社員数20〜300人未満の中小企業」を対象とした実施方式です。
以下の表のように、業種に応じた2種類のサーベイがあります。
※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください
| 種類 | 質問数 | 分野 | 領域 |
|---|---|---|---|
| NRCS I (第2次、第3次産業) | 39問 | ・経営方針 ・組織命令系統 ・コミュニケーション ・労働条件 ・仕事のやりがい | ・経営への信頼 ・環境整備 ・指示命令 ・組織管理 ・職場の人間関係 ・下意上通 ・経済的報酬 ・作業条件 ・職務満足 ・教育訓練 |
| NRCS II (サービス業) | 40問 | ・経営への信頼 ・上司への信頼 ・顧客満足 ・労働条件 ・職場生活満足 | ・経営方針 ・人材の育成 ・指示の仕方 ・仕事の進め方 ・顧客尊重 ・職場秩序 ・経済的報酬 ・労働時間 ・職務満足 ・職場の人間関係 |
出典:厚生労働省方式・社員意識調査(NRCS)診断内容|一般社団法人日本労務研究会
この方式は、1957年に労働省(現:厚生労働省)の協力のもと、「中小企業従業員態度測定」を開発したのが始まりです。その後、改良を重ねて現在の「厚生労働省方式」となりました。
参考:一般社団法人日本労務研究会|公式ホームページ
モラールサーベイは、社員の意見を幅広く把握できることから、職場環境の改善策に落とし込みやすい点が特徴です。
モラールサーベイの質問項目
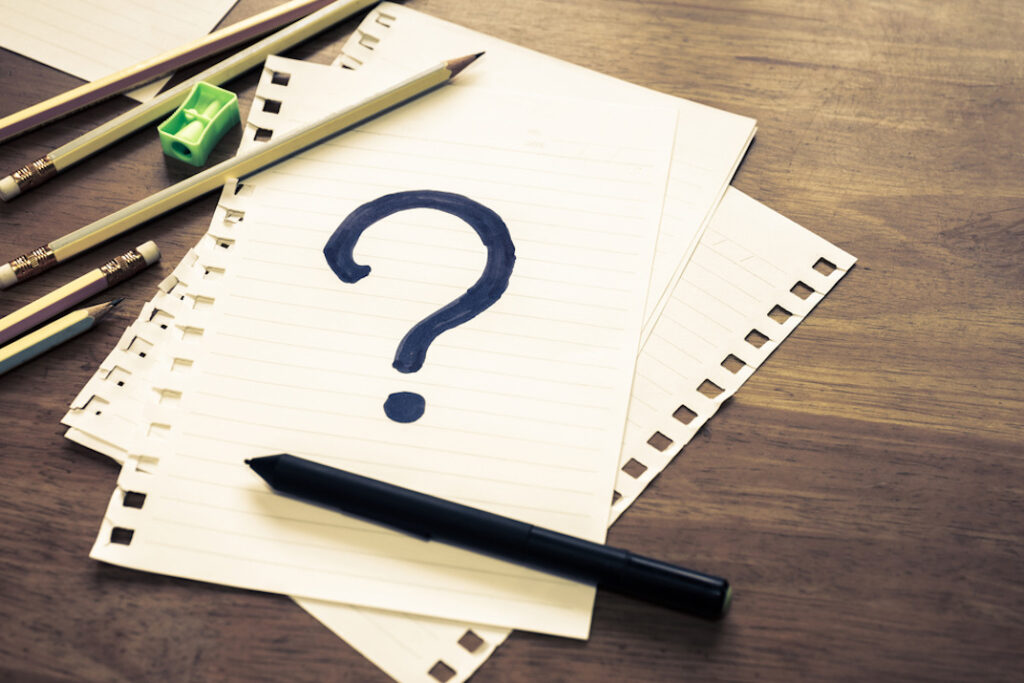
モラールサーベイ(NRK方式)では、以下の5分野17種目の中から、95問が出題されます。
※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください
| 分野 | 種目 | 質問項目 |
|---|---|---|
| 労働条件 | ・仕事の負担 ・職場の設備 ・給与 ・福利厚生 | ・勤務時間 ・災害防止 ・給与の決め方 ・施設と制度 など |
| 人間関係 | ・同僚との関係 ・上司との関係 ・幹部との関係 | ・同僚間の相互援助 ・部下の気持ちの尊重 ・不公平をなくす努力 など |
| 管理 | ・上司の行う管理 ・幹部の行う管理 ・意思の疎通 | ・部下の訓練 ・会社の運営 ・改善提案 など |
| 行動 | ・上司の行動 ・個人の行動 ・育成と心身への配慮 | ・育成への体験 ・意見の積極的表明 ・教育への熱意 など |
| 自我 | ・地位の安定 ・地位についての満足 ・昇進向上の機会 ・会社との一体感 | ・仕事の繁閑に対する不安 ・職場の地位 ・手腕発揮の機会 ・帰属感 など |
出典:NRK方式モラールサーベイ診断内容|一般社団法人日本労務研究会
モラールサーベイは、組織・個人の両面を深く掘り下げる質問構成になっています。そのため、組織課題の特定だけでなく、改善策の優先順位を考える上でも重要な判断材料になります。
以下の記事では、サーベイの質問項目や質問例を多数紹介していますので、設計時の参考にしてみてください。
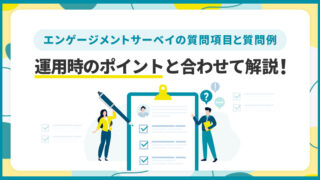
モラールサーベイツール導入から活用までの手順【5ステップ】

モラールサーベイ導入から活用までの流れは、以下の5ステップです。
導入前に調査対象や調査時期、診断方法などを検討し、社員に対して丁寧に説明を行いましょう。
以下より、各ステップを解説します。
1.サーベイの実施方法を検討する
まずは、どのような方法でサーベイを実施するかを検討します。以下の実施方法から自社に合ったものを選定しましょう。
- Web方式(オンライン調査)
- 紙アンケート方式
- 専用のサーベイツールの導入
- 自社独自の調査ツール
- 外部専門機関への委託
外部の調査会社に依頼する場合は、専門的な知識やノウハウが必要ないため、自社のリソースが限られていてもスムーズな運用が可能です。
また、専用のサーベイツールであれば、導入コストを抑えつつ、自動集計や分析ができる実施体制を整えられます。
2.調査目的・対象・時期などを決定する
サーベイの実施方法が決定したら、調査の目的や対象、時期などの基本方針を明確にします。
| 項目 | 具体例 |
|---|---|
| 調査目的 | ・離職の要因を把握したい ・社員の士気低下の原因を特定したい |
| 調査対象 | ・全社員 ・入社3年以内の社員 |
| 実施時期 | ・下期の初め(10月) ・繁忙期を避けた春先(4月) |
| 実施頻度 | ・年1回の定点調査 ・半年ごとの継続調査 |
調査を行うときは、回答可能な期間を長めに設定するなど、社員が回答しやすいように配慮しましょう。
実施前に目的や対象をしっかり固めておくことで、運用がスムーズになり、より有効な分析が可能になります。
3.社員に周知後、サーベイを実施する
サーベイを実施する前に、社員への周知を行いましょう。
「なぜこのサーベイを行うのか」「どう活用されるのか」を伝えていないと、社員は調査に協力的な姿勢を示さず、正確な回答が得られない可能性があります。
以下のような手段を使って周知しましょう。
- 社内メール
- 朝礼・ミーティングでの口頭説明
- 社内ポータル・掲示板
- 管理職からの案内
調査の実施期間中は、回答を促すリマインドメールや管理職による呼びかけを行い、未回答者へのフォローを行います。
4.結果を集計・分析する
サーベイを実施したあとは、得られたデータを集計・分析する工程です。
まずは、全体の傾向を数値化し、どの項目に「高い・低いの評価が出ているか」を確認しましょう。次に部署ごとの違いや職種別の傾向を分析し、具体的な課題や改善ポイントを把握します。
また、自由記述のコメントにも目を通しましょう。数値ではわかりにくい課題の背景が記されている場合は、貴重な定性情報として組織改善に活用できます。
以下の記事では、サーベイ結果の分析方法を詳しく解説しています。本記事と合わせて確認してみてください。

5.分析結果をフィードバックする(PDCA)
調査の分析が完了したら、その結果を社員にフィードバックしましょう。
ただ結果を共有するだけではなく、「どのような傾向があるのか」「それを今後どう活用するのか」を明確に伝える必要があります。
社内会議や資料配布でのフィードバックに加え、社員との対話を通して「ありたい姿」を語り合うことも重要です。
この対話によって、社員は自分の声が組織改善に活かされていることを実感し、組織への信頼感やエンゲージメントが高まります。
改善策やアクションプランを実行したら、その成果を定期的に振り返りましょう。再度サーベイを実施することで、PDCAサイクルの仕組みを構築できます。
以下の記事では、社員との対話を軸とした「サーベイフィードバック」について詳しく解説しています。本記事と合わせて確認してみてください。

モラールサーベイ実施時のポイント

モラールサーベイを実施するときには、以下のポイントを押さえておきましょう。
単なるデータ収集として調査を行うのではなく、具体的な目的やアクションプランを策定し、社員との信頼関係を築きながら組織改善につなげることが重要です。
以下より、各ポイントを詳しく解説します。
社員に調査目的や調査方法を説明する
モラールサーベイを実施するときには、事前に調査の目的を明確にし、社員に対して説明することが重要です。
「職場環境の改善」「コミュニケーションの活性化」といった、具体的な目的を伝えることで、社員は調査に対して協力的な姿勢を示します。また、以下の点も伝えておきましょう。
- 回答は誰が見るのか
- 評価や業績に影響するのか
- 結果は何に活用されるのか
社員への説明が不十分だと、調査への協力が得られないだけでなく、会社に対して不信感を抱く可能性もあります。
「組織改善に活かされる調査」であることを示すことで、社員は安心して回答できるようになります。
調査結果の情報開示は慎重に行う
モラールサーベイで得た結果には、個人的な意見や情報が含まれています。そのため、情報開示を行うときは、関係者以外に情報が漏れないよう配慮が必要です。
万が一、部署名や個人名が公開されてしまうと、社内トラブルが発生したり、情報漏洩で訴えられたりする恐れがあります。
サーベイの結果は、組織改善を行うために必要な情報ですが、信頼関係を構築・維持する上で、個人のプライバシーは必ず守らなければなりません。
調査結果を情報開示するときは、「個人情報保護」と「組織改善の必要性」を考慮し、慎重に判断しましょう。
以下の記事では、「匿名式のサーベイ」と「実名式のサーベイ」の特徴を詳しく解説しています。どちらで実施するか悩んでいる人事担当者の方は、ぜひ参考にしてみてください。

継続的にサーベイを実施する
モラールサーベイは一度実施して終わりではなく、継続的な調査で変化を追い続けることで、「組織が健全な状態であるかどうか」を把握できます。
1回の調査では、時期的な要因や出来事が結果に影響している可能性があります。年に1回や半年に1回など、定期的にサーベイを行うことで、データの偏りなく組織状態の把握・分析が可能です。
また、社員にとっても「自分たちの意見を継続的に聞いてくれている」という実感が得られるため、組織への信頼感や帰属意識の向上にもつながります。
サーベイを継続的に行うことで、社員との信頼関係を築きながら組織改善を進められます。
モラールサーベイの導入・活用事例

実際に、モラールサーベイを導入・活用している2社の取り組みを紹介します。
事例のように、サーベイを継続的かつ戦略的に活用することで、社員の意見を経営やマネジメントに反映する仕組みを構築できます。
以下より、それぞれの取り組みを詳しく見ていきましょう。
社員一人ひとりのモチベーションを把握|ラクスパートナーズ
ITエンジニア派遣サービスを提供している株式会社ラクスパートナーズでは、社員一人ひとりのモチベーションを把握するためにサーベイを活用しています。具体的な流れは、以下のとおりです。
- 全社員に月1回サーベイを配信
- ケアを必要としている社員をアラートで確認
- ケア社員への声かけを実施
- 必要に応じて1on1面談を設定
また、導入した『ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ』では、社員の性格診断の結果を見ながら面談ができます。
サーベイの結果だけでなく、個々の性格にも触れられるため、社員自身が自分に矢印を向ける機会(内省)にもなっています。
サーベイの導入によって、モチベーションの状態に応じたケアが可能となり、四半期の休職者数が「5〜6人」から「1〜2人」に減少しました。
事例:ケアを求める社員をサポートし、休職者数の減少を実現|株式会社ラクスパートナーズ
社員が仕事に対して感じていることを調査|オリックス
生命保険事業などを展開するオリックス株式会社では、仕事に対して「日ごろどのように感じているのか」を調査するため、2004年からモラールサーベイを活用しています。
2024年からはエンゲージメントサーベイとして活用し、従業員エンゲージメントの把握に加え、オリックスグループの目的・文化の浸透状況も調査しています。
調査結果の活用方法は、以下のとおりです。
- 組織マネジメントへの活用
- 人事施策決定の参考情報
- 現在実施している人事施策の効果検証
同社では、全社員が活躍できる働きやすい職場づくりの一環として、モラールサーベイの結果を踏まえた組織改善を行っています。
参考:DE&I(多様性、公平性、包括性)の推進|オリックス株式会社
まとめ:モラールサーベイで社員の士気を向上させよう

モラールサーベイは、社員の士気や職場環境に対する意識を可視化し、組織改善につなげるための有効な手段です。もう一度、期待される効果(メリット)を確認しておきましょう。
調査結果に基づいて組織改善を行うことで、社員の士気や労働意欲が向上し、最終的には組織力の強化につながります。
また、社員の心理状態をリアルタイムに把握できるパルスサーベイと併用することで、社員の労働意欲を高めつつ、心身面のケアも可能です。
経営者や人事担当者の方は、組織の成長と業績向上を図るために、サーベイの活用を検討してみてはいかがでしょうか。

従業員のメンタル状態の定期的な可視化・個々の性格に合わせたアドバイス提供を通じ、離職・休職を防ぐエンゲージメントサーベイ。無料トライアルの詳細は下記から。





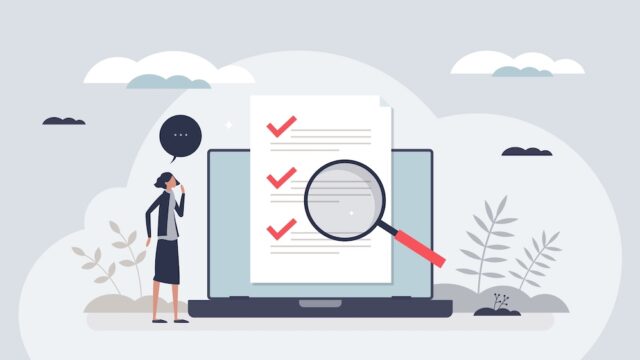
-320x180.png)




 ランキング1位
ランキング1位 
 ランキング2位
ランキング2位 
 ランキング3位
ランキング3位 