- 感情労働が求められる職業と向き不向きが分かれる理由
- 感情労働に向いている人と向いていない人の特徴
- 感情労働のメリット・デメリット
- 感情労働に適した人材配置のコツ
感情労働に向いている人には、感情をコントロールする力やストレス耐性など、共通する特徴があります。
看護や介護、接客などの感情労働の現場では感情の安定が求められ、向き不向きが仕事の継続に大きく関わります。一方で、HSP気質や感情を引きずりやすい人にとっては負担が大きく、バーンアウトのリスクも高まるでしょう。
本記事では、感情労働に向いている人・向いていない人の違いや、適性を見極めるポイントをわかりやすく解説します。
個性に合った人材配置を実現できる適性検査ツールの活用法についても紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。
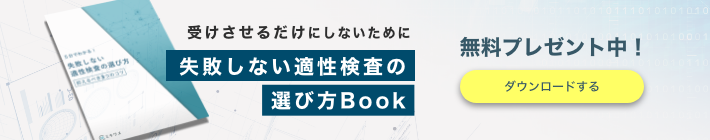
感情労働とは?主な職業と向き不向きが分かれる理由
接客や医療、法律分野など、感情労働が求められる仕事は多岐にわたりますが、じつは誰にでも向いているわけではありません。
ここでは、感情労働が求められる職業と、向き不向きについて紹介します。
適性を見極める第一歩として、ぜひ確認しておきましょう。
以下の記事では、感情労働の基本について詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

感情労働が求められる職業
感情労働が求められる職種としては、看護師や介護職が代表的です。
看護や介護の現場では、身体的ケアだけでなく、患者や利用者の不安や寂しさにも寄り添う力が求められます。患者や利用者、その家族に対して、冷静かつ丁寧に対応しなければなりません。
また、カウンセラーや弁護士も、感情労働が求められます。カウンセラーは相談者の感情を受け止め、心のサポートを行う専門家です。
弁護士は、依頼者の繊細な心情に寄り添いながら、法的手続きを進めていく必要があります。
こうした仕事では、自分の感情を整えたうえで、相手に合わせて表現することが求められます。負担を減らすためには、チームでの情報共有や、メンタル面を支える仕組みづくりが欠かせません。
感情労働に向いている人・向いていない人の違い
感情労働に向いている人は、ストレスに強く、感情を安定して保てる人です。
たとえば、理不尽な言葉を受けても冷静さを崩さず、すぐに気持ちを切り替えられる人は適性があります。共感力があることも重要ですが、感情移入しすぎず距離を保てることが長く続けるコツです。
一方、感情労働に向いていない人は、感情が表に出やすく抑えるのが苦手な人です。
気持ちを切り替えるのに時間がかかる人も、感情の負担を溜め込みやすくなります。
他人の感情に強く影響されやすいHSP(Highly Sensitive Person:感受性が強く、敏感な気質の人)も、精神的な消耗が激しくなる傾向があります。
また、人とのやり取りそのものに強いストレスを感じる人も、日常的な対人業務に不向きと言えるでしょう。
以下の記事では、感情労働のストレスについて詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

感情労働に向いている人の3つの特徴
感情労働の現場では、単なるスキルだけでなく、「人としての強さ」や「柔軟さ」が問われます。では、どのような人がこの仕事に向いているのでしょうか?
ここでは、実際の現場で求められる3つの特徴を具体的に紹介します。
感情労働者に関する採用や配置に参考にできる内容ですので、確認しておきましょう。
感情を切り替えられる人
お客様からきつい言葉を受けても、すぐに気持ちを切り替えて次の相手に笑顔で対応できる人は、感情労働に適しています。気持ちを引きずるタイプだと、業務にも影響が出るほか、本人も疲弊してしまうでしょう。
採用段階でこの適性を見極めるには、面接時に「大変だった状況をどう乗り越えたか」「普段どのように気持ちを切り替えているか」を聞いてみることがおすすめです。ロールプレイ形式で対応力を見るのも効果的です。
人に合わせるのが得意な人
相手の様子や気持ちに応じて、自分の振る舞いを自然に変えられる人は、感情労働の現場で強みを発揮します。たとえば、落ち込んでいるお客様に明るく接したり、緊張している相手に安心感を与えたりと、人に合わせた対応が得意な人に向いています。
採用時は、「誰かに合わせて動いた経験があるか」「相手の気持ちを汲み取って行動したエピソードがあるか」を聞くと、その適性が見えてくるでしょう。グループディスカッションを通して見極めるのも有効です。
バーンアウト(燃え尽き症候群)を防げる人
感情労働は、知らず知らずのうちに疲労がたまりやすい仕事です。だからこそ、日頃から上手にリフレッシュできる人、前向きに仕事に向き合える人が向いています。
企業側としては、面接でストレス対処法やオフの過ごし方を聞いておくとよいでしょう。
また入社後のフォローとして、メンタルヘルス研修や相談窓口の設置、定期的な休暇取得の推奨など、職場全体での支援体制を整えておくことが欠かせません。
以下の記事では、感情労働のバーンアウトについて詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

感情労働に向いていない人の3つの特徴

感情労働は、対人スキルだけでなく、感情との向き合い方が大きく影響する仕事です。どんなにスキルや知識があっても、感情面での適性が合わなければ、負担が大きくなってしまうこともあるでしょう。
では、具体的にどのようなタイプの人が感情労働に向いていないのでしょうか?
ここでは注意が必要な3つのタイプを取り上げ、それぞれの特徴と適切な対応のヒントを紹介します。
人材配置の判断や自己理解にも役立つ内容ですので、確認していきましょう。
感情を抑えるのが苦手な人
感情労働の現場では、常に冷静な対応が求められます。
たとえば、理不尽な態度の顧客に対しても、怒りを表に出すことはできません。自分の感情が表に出やすい人や、対人関係でストレスを感じやすい人にとっては、こうした状況が大きな負担になるでしょう。
感情を抑えるのが苦手な傾向にある人は、顧客対応の少ない職種に配置することが現実的な選択肢になるかもしれません。
また、企業側が採用時に感情コントロール力を見極めたうえで、本人の特性に合った部署に配置することも大切です。感情の起伏が少ない業務や、専門スキルを活かせる仕事であれば、本人も働きやすく、企業にとってもプラスになると考えられます。
HSP気質の人
HSP気質の人は、感情労働のように細やかな対応を求められる職場で、人一倍強いストレスを感じやすい傾向があります。
HSP(Highly Sensitive Person)とは、刺激に対して敏感で、他者の感情に影響されやすい気質を持つ人のことを指します。
相手の気持ちに寄り添おうとする姿勢はすばらしいですが、過剰に反応してしまうと、心身の消耗につながりかねません。
とはいえ、HSP気質の人がその感受性を活かして、丁寧な接客で高い評価を得ているケースもあるでしょう。
大切なのは、自分の特性を理解して無理のない環境で働くことです。企業としても、静かな作業環境の整備やストレスケアに関する研修など、HSP気質の人が安心して働ける体制づくりが求められます。
参考:企業で働く Highly Sensitive Person はストレスを感じ, 共感しやすいか|J-STAGE
繊細で共感力が高すぎる人
共感力が高いことは、対人支援において強みになる一方で、感情労働では負担になることもあります。他者の感情に深く入り込みすぎてしまうと、自分が抱える以上のストレスを背負い込んでしまいやすいためです。
顧客の怒りや悲しみをまるで自分のことのように感じてしまうと、心理的に消耗しやすくなります。そうなると、適度な距離感を保つことが難しくなり、感情労働に不向きな場面が増えてしまいます。
可能であれば、採用の段階で、共感性の強さとストレス耐性のバランスを確認しておきましょう。
もし採用する場合には、直接的な接客ではなく、共感力を活かしながらも感情的な負荷が少ない業務を任せるのがよいでしょう。
たとえば、顧客の声を分析して改善に活かす部署や、チーム内の調整を担うサポート業務などが向いているかもしれません。
知っておきたい感情労働のメリット・デメリット
感情労働は、相手の気持ちに寄り添いながら働く繊細な仕事です。やりがいや成長も大きい一方で、心身に負担がかかりやすい側面もあります。
では、感情労働にはどのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか?感情労働の本質を理解するために、実際の現場で感じやすいプラス面とマイナス面を具体的に紹介していきます。
働くうえでの納得感や適性判断のヒントとして、ぜひ参考にしてみてください。
感情労働のメリット
ここでは、感情労働の主なメリットを紹介します。
感情労働には、働く中で得られるスキルややりがいなど、成長につながる多くのメリットがあります。詳しく確認していきましょう。
対人スキルが高まる
感情労働では、相手の感情や状況に応じた対応が日常的に求められます。そのため、自然と傾聴する力や伝える力、的確な受け答えといったコミュニケーション能力が磨かれていくでしょう。
難しい要望やトラブルに冷静に対応することで、交渉力や問題解決力も身につきます。こうした対人スキルは、職場だけでなくプライベートの人間関係にも役立つ場面が多く、長期的に見ても自身の成長に大きく貢献する実践的な力となるでしょう。
感情をコントロールする力が養われる
感情労働では、自分の感情をコントロールし、求められる感情を演じる必要があります。日々その訓練を積むことで、感情の波を客観的にとらえ、落ち着いた対応ができるようになるでしょう。
これは「EQ(情動的知能)」とも呼ばれ、感情の自己管理や他者との関係構築においても重要なスキルです。日常生活でも感情に振り回されることが減り、冷静な判断力が身につくため、精神的な安定にもつながっていくのは大きなメリットと言えます。
働きがいを感じやすい環境になる
感情労働の魅力は、相手の喜びや感謝をダイレクトに受け取れることです。自分の対応が相手の満足や安心につながったと実感できたとき、働く意義やモチベーションが自然と高まります。
また、チームで協力し合う場面も多く、感情的なつながりや一体感を得やすいのも特徴です。こうした経験を重ねることで、仕事への愛着ややりがいが育まれ、ポジティブな気持ちで日々の業務に向き合えるようになるでしょう。
感情労働のデメリット
一方で、感情労働には以下のようなデメリットもあります。
感情を扱う仕事ならではの負担やリスクがあるため、注意しましょう。詳しく解説します。
感情を抑えることでストレスが蓄積する
感情労働では、本音を抑え、役割に沿った振る舞いを続ける必要があります。
不快な感情を抱えても、表情や言動をコントロールすることが求められるため、そのギャップが大きなストレスになることもあるでしょう。
自覚のないまま感情を押し殺し続け、気づいたときには心身に影響が出ているケースも少なくありません。企業側はこうした負担を軽減するため、従業員の声に耳を傾け、早めのストレスケアを行うことが大切です。
人間関係のストレスが大きくなる
感情労働の現場では、顧客だけでなく同僚や上司とのやり取りも多く、人間関係のストレスが増しやすい傾向があります。
多様な価値観を持つ人々と接する中で、誤解や衝突が起こることもあり、精神的な負担になるケースもあるでしょう。
とくにクレーム対応やネガティブな感情と向き合う場面では、相手の感情を受け止めながら自分の感情も抑える必要があります。そのため、相当なエネルギーが求められます。
このように、配慮と調整の連続が疲れの原因になりやすいでしょう。
健康やプライベートに悪影響を及ぼす
感情を使い続ける業務では、精神的な疲労が蓄積しやすく、身体的にも影響を及ぼすことがあります。仕事で感情を消耗するため、家でも気力が湧かず、趣味や人間関係を楽しむ余裕がなくなってしまうこともあるでしょう。
結果として、睡眠の質や生活リズムが乱れ、慢性的な疲れが取れにくくなるといった悪循環に陥る恐れがあります。プライベートの充実が難しくなれば、人生全体の満足度も下がってしまうため、定期的なケアとリフレッシュが欠かせません。
適性検査で見極める!感情労働に最適な人材配置のコツ

感情労働は、個々の性格や感情特性が業務パフォーマンスに大きく影響する仕事です。そのため、経験や勘に頼った人材配置だけでは、早期離職やミスマッチのリスクが高まります。
これらを防ぐためには、適性検査を用いて感情労働に向いている人を見極め、最適な人材配置を行う必要があります。ポイントは以下のとおりです。
事例や活用法を交えながら解説しますので、採用や配属における判断材料として、ぜひご活用ください。
ストレス耐性や対人スキルを客観的に評価する
感情労働の職種では、ストレスに対処する力や対人関係に適応する力が、業務の成否を大きく左右します。
しかし、これらの資質は履歴書や面接では判断が難しく、経験や直感に頼った人材配置では、早期離職や職場不適応といったリスクが伴うでしょう。こうした課題を解消する手段として注目されているのが、適性検査の導入です。
たとえば『ミキワメ 適性検査』では、感知能力や回避能力、ストレスの経験など、ストレス耐性に関する項目を科学的に分析できます。数値化された客観的データとして可視化できるため、感情労働に関する適性を明確に把握することが可能です。
ここでは、『ミキワメ 適性検査』の活用によって、個性を活かし伸び伸び働いてもらえる環境づくりにつながった事例を紹介します。
【株式会社プロレド・パートナーズの事例】
同社では、事業の拡大に伴い、社員に共通する判断基準=「軸」を明確にする必要性を感じていました。そこで導入したのが、『ミキワメ 適性検査』です。
この検査によって、同社が創業以来大切にしてきた価値観(以下)が明確に言語化され、配置や評価の基準として活用されるようになりました。
- 「COMPASSION(思いやり)」
- 「BE PROFESSIONAL(プロ意識)」
この「軸」をもとに、社員の個性や強みに合わせた役割を任せることが可能になり、それぞれが自分のスタイルで能力を発揮できる環境が整いつつあります。
過度な同調や型にはめるようなマネジメントではなく、個人の多様性を尊重した働き方が推進されているのです。
価値観に基づく適性の見える化と活用は、社員が安心して自分らしさを発揮できる職場づくりに直結する大きな一歩と言えるでしょう。
参考:「COMPASSION」と「BE PROFESSIONAL」を両立しながら組織を拡大。多様性を活かす組織での適性検査の活用方法。
このように、客観的な診断結果に基づいた判断は、感情労働に適した人材を見極め、組織全体の安定と成長を支える有効な手段となります。
適性検査を活用してストレス耐性を見極めるポイントは、以下の記事で解説しています。本記事と合わせて参考にしてみてください。
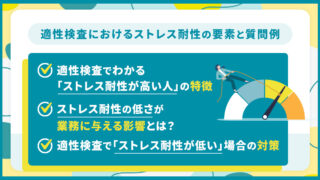
感情労働に適した人材を見極める
感情を扱う業務では、共感力やストレス耐性、感情の切り替え力を求められますが、こうした資質は履歴書や面接だけでは見極めが難しいものです。
『ミキワメ 適性検査』では、これらの特性を数値化し、個人の傾向を可視化することが可能です。たとえば、共感性が高すぎる人には適切なフォローを、安定性が高い人には責任ある役割を任せるなど、特性に応じた配置が行えます。
ここでは、感情労働を対象とした『ミキワメ 適性検査』の具体的な活用法を紹介します。
感情労働人材を対象とした『ミキワメ 適性検査』の活用法
『ミキワメ 適性検査』は、ストレス耐性を「感知能力」「回避能力」「処理能力」「転換能力」「ストレスの経験」「ストレスの容量」の6要素で測定します。
従業員の長期的なパフォーマンス予測や職場環境への適性の判断に活用可能です。
とくにストレス耐性の高い人材は、仕事の状況変化への柔軟な対応力や冷静な判断力を持つため、責任の重い業務や変化の多い環境への適性を見極めるのに役立ちます。
適性検査の結果を踏まえ、面接でさらに掘り下げた質問や、入社後の研修・トレーニングによるフォローも可能です。
『ミキワメ 適性検査』は、ストレス耐性という観点から、より適した人材配置をサポートするツールと言えます。
選考初期から適性を把握しておくことで、採用後のミスマッチも防ぎやすくなり、従業員の定着や活躍にもつながるでしょう。
『ミキワメ 適性検査』ついて詳しく知りたい方は、下記の記事を参考にしてみてください。

感情労働の負担を軽減するためのサポート体制を整える
感情労働は感情のコントロールを通じて価値を提供する働き方であり、サービス業を中心にその重要性が高まっています。
一方で、感情を抑え続けることは精神的な負担になりやすく、企業には適切な対策が求められるでしょう。厚生労働省は、労働者のストレス状況を把握する「ストレスチェック制度」の活用を推奨しています。
ここでは、ストレスチェック制度の活用法を紹介します。
ストレスチェックの活用法
職場全体のストレス状況を把握するだけでなく、部署や職種ごとの集団分析を行うことで、どの環境要因が負担の原因となっているかを明らかにできます。
分析結果から課題を特定したうえで、業務内容の見直しや人員配置の調整など、実際の環境改善につなげていくことが重要です。
こうした取り組みによって、感情労働による負担を軽減し、従業員のメンタルヘルスを守ることが可能になります。
職場の実態に基づいた具体的な対策は、表面的な対応にとどまらず、より効果的で持続可能なメンタルヘルス支援へとつながっていきます。
あわせて適性検査を活用することで、従業員ごとの特性に応じた支援が可能です。
たとえば、ストレス耐性が低い人にはメンタルケア研修を、感情の切り替えが苦手な人には実践的トレーニングを行うなどの対応が有効です。
関連記事:ストレスチェックの活用方法と事例8選|集団分析結果の活用ポイントも解説|ミキワメラボ
これにより「働きやすい環境づくり・離職防止・企業の成長」が期待できます。ストレス耐性が高い人と低い人の特徴は以下の記事で確認してみてください。

感情労働の適性を見極め、最適な人材配置を実現しよう!
本記事では、感情労働に向いている人・向いていない人の特徴から、適性診断による見極め方、職場でのサポート体制づくりまでを解説しました。
感情労働はやりがいや成長機会も多い一方で、心の負担を抱えやすい仕事です。だからこそ、従業員一人ひとりの適性を把握し、個性に合った配置や支援が欠かせません。
感情労働における適材適所を実現するには、感情の安定性やストレス耐性といった「見えにくい力」の把握が重要です。こうした感情労働の見極めには、適性検査サービスの活用が有効になります。
『ミキワメ 適性検査』なら、感情労働に関するストレス耐性の見るべき特性を科学的に分析・可視化できます。個性に合った配置や定着支援に活用できる人事の強い味方です。ぜひこの機会に導入を検討してみてください。
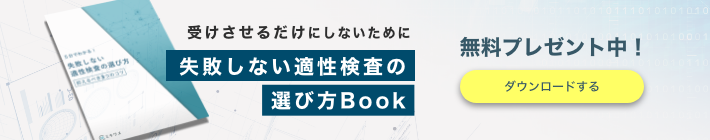











 ランキング1位
ランキング1位 
 ランキング2位
ランキング2位 
 ランキング3位
ランキング3位 