- 効率がよい仕事の進め方のコツ
- 仕事の進め方が上手な人の9つの特徴
- 仕事がうまく進まない原因と対策
「部下が思うように動かない」「自分も毎日業務に追われている」、そんな悩みを抱える方も多いのではないでしょうか。実は、多くの仕事を抱えながらも、着実に成果を出す人には共通点があります。
本記事では、マネジメント層や忙しいビジネスパーソンに向けて、仕事を効率よく進めるためのコツと、チームの成果を最大化する方法を紹介します。
さらに、仕事がうまくいかない原因や部下指導のコツ、チーム全体の生産性を上げるポイントもまとめました。
この記事を読むことで、仕事の進め方が上手な人とそうでない人の違いが明確になり、自分やチームの課題を見つけやすくなります。
仕事の進め方を改善することは、チーム全体のパフォーマンス向上にも直結するため、本記事の内容を参考にして、ぜひ日々の業務に取り入れてみてください。
【5ステップで劇的改善】効率的な仕事の進め方のコツとは?

効率的に仕事を進めるには、いくつかのコツがあります。とくに意識したいのが、以下の5つのステップです。
上記の5つのステップを実践することで、仕事の進め方に迷いがなくなり、無駄な作業が減って成果につながりやすくなります。各ステップごとに詳しく見ていきましょう。
1. 目的・ゴールの明確化
仕事に着手する際は、目的と達成すべき成果(ゴール)を明確にしましょう。目的やゴールが曖昧なままでは途中で軸がぶれてしまい、余計な作業や手戻りが発生しやすくなります。
たとえば会議の資料を作成する場合、「意思決定のための比較資料」と「進捗報告としてのサマリー資料」では、構成や記載内容が大きく変わります。
目的や目標をより具体的にするには、目標設定のフレームワークである「SMART」の活用が有効です。
SMARTは明確な目標を立てるための指標で、以下の5つの頭文字をとっています。
- Specific(具体的):何を達成したいのか、明確に記述されているか
- Measurable(測定可能):成果を数値で測定できるか
- Achievable(達成可能):現実的に実現可能な目標になっているか
- Relevant(関連性がある):業務や組織の目的に関連しているか
- Time-bound(期限がある):達成すべき期限が明確か
SMARTは目標を設定する際に役立つだけでなく、目標が達成できたかどうかを評価しやすくなる点も特徴です。
SMARTは目標を設定する際に役立つだけでなく、目標が達成できたかどうかを評価しやすくなる点も特徴です。
たとえば、「売上を上げる」という漠然とした目標ではなく、「今月中に新規顧客を10社獲得する」といった形にするイメージです。行動計画が立てやすくなり、業務の優先順位づけや進捗管理もしやすくなります。
上記の5つの観点を意識することで落とし込みやすくなるので、参考にしてみてください。
2. やるべき業務の棚卸し・可視化
目的が定まったら、必要なタスクをすべて書き出して全体像を整理しましょう。業務を棚卸しして可視化することで、タスクの抜け漏れを防ぎ、優先順位や配分の判断がしやすくなります。
業務の棚卸しと可視化には、以下のような方法があります。
※以下の表は右にスクロールできます
| 方法 | 概要 | メリット |
|---|---|---|
| ToDoリスト | やることを一覧にして順番に消していく方法 | 手軽で管理しやすい |
| カンバン方式 | 「未着手」「進行中」「完了」などのステータスに分けて、タスクを動かしながら管理する方法 | タスクの進捗がひと目でわかる |
| マインドマップ | 中央にテーマを置き、関連タスクを枝のように広げて整理する方法 | タスクを分解しやすく、全体の関係性が見えやすい |
新入社員や業務経験が浅い方など「そもそも自分のやるべきタスクがわからない」という場合には、厚生労働省の職業情報提供サイトが提供している「タスク整理」の活用もおすすめです。
職種ごとの主な業務内容が可視化されており、タスクの洗い出しはもちろん、業務の理解を深める助けにもなります。ぜひ参考にしてみてください。
参考:厚生労働省 職業情報提供サイト(job tag)|タスク整理
3. 優先順位をつける
業務を整理したら、すべてを同時に進めようとせず、タスクごとの優先順位を明確にしましょう。限られた時間で最大の成果を出すために、非常に重要な工程です。
タスクの分類には、「アイゼンハワーマトリクス」を使うと視覚的にも整理しやすく便利です。
アイゼンハワーマトリクスとは、タスクを「緊急」と「重要」の2軸で整理し、やるべきことを4つの領域に分ける考え方を指します。
「今すぐ取り組むタスク」「あとで対応するタスク」「人に任せるタスク」「やらないタスク」の4つに分けることで、優先順位を判断しやすくなります。
※以下の表は右にスクロールできます
| 領域 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 緊急かつ重要 | 今すぐ取り組むタスク | 顧客対応のトラブル、今日が締切のレポート |
| 緊急ではないが重要 | あとで対応するタスク | 来月のプレゼン準備、スキルアップの学習 |
| 緊急だが重要ではない | 人に任せるタスク | 会議の調整依頼、単純なデータ集計 |
| 緊急でも重要でもない | やらないタスク | 不要な通知のチェック、SNSの閲覧 |
参考:asana|アイゼンハワーマトリクスの領域と実践時のコツを解説(「アイゼンハワーマトリクスとは?」より)
4. 実行と共有
やるべきタスクと優先順位が明らかになったら、いよいよ実行フェーズです。計画通りに実行することはもちろん、進捗状況に応じた調整や関係者への報連相も欠かせません。
進捗の共有には、チャットツールやタスク管理アプリを使うと効率的です。SlackやTeamsなどのチャットでこまめに報告し、TrelloやNotionなどで進捗を可視化すると、関係者との認識のズレを防ぎやすくなります。
また、定期的なミーティングや1on1での進捗確認もおすすめです。口頭で共有することで課題やトラブルを早期発見でき、修正もしやすくなります。
5. 定期的な振り返りと改善
タスクを完了させたら、そのまま終わりにせず、必ず結果を振り返る習慣をつけましょう。この一手間が仕事の質を左右するといっても過言ではありません。
「何にどれだけ時間がかかったか」「改善できる手順はなかったか」などの視点で行動を見直すことがポイントです。
想定よりも時間がかかったタスクがあれば、「なぜ時間がかかったのか」「どこにボトルネックがあったのか」を分析しましょう。これを繰り返すことで、自分なりの改善パターンが見えてきます。
また、フィードバックを徹底することで、仕事の精度とスピードが自然と高まっていきます。
仕事の進め方が上手な人の特徴9選

実際に成果を出している人は、ただ「忙しく働いている」だけでなく、目的に沿って効率的に仕事を進める力を持っています。そうした人の特徴を知ることで、自分の業務の進め方に取り入れられるヒントが見つかるはずです。
本章では、仕事の進め方が上手な人の特徴を9つ紹介します。
※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください
| 仕事の進め方が上手な人の特徴 | 具体例 |
| タスクの全体像を素早く把握できる | 企画書作成を任された際にただ内容を考えるだけでなく「誰に見せるのか」「何を決めたいのか」「どんなデータが必要か」などの要素を整理している。 |
| タスクを分解して優先順位をつけられる | イベント準備を進める場合、当日までに必要な作業を工程ごとに切り分け、発注やスケジュール調整など優先度の高いものから順に片づけている。 |
| スケジュール管理を適切に行える | Googleカレンダーを活用し、作業ごとに時間をブロックして管理。会議や資料作成などにかける時間を事前に見積もって組み立てている。 |
| 周囲に頼ったり巻き込んだりできる | 納期が迫った案件では、自分だけで抱え込まず、関係部署に早めに相談して業務を分担。必要な情報提供や補助作業を依頼して成果を最大化している。 |
| 報連相を習慣化している | 作業が予定より遅れそうな場合は、早い段階で上司に相談し、次の打ち手を一緒に検討。進捗や変更点をチャットでこまめに共有している。 |
| 振り返り(PDCA)を習慣化している | プロジェクト終了後、所要時間や反省点をメモにまとめ、次回はどこを改善できるかを整理。チームにも共有している。 |
| 完璧主義にこだわりすぎない | プレゼン資料を作成する際、まずは構成と要点だけを押さえて初稿を提出し、フィードバックをもとに調整。完璧を目指すよりスピードと柔軟性を重視している。 |
| 日ごろから情報収集や学びを続けている | 業務に関連するニュースや最新ツールを日常的にチェック。学んだ内容を週報で共有し、チーム全体のアップデートにも貢献している。 |
| ツールを有効活用している | Trelloでタスクをステータスごとに整理し、Notionで議事録と業務メモを一元的に管理。Slackでは進捗報告をチャンネルで共有し、業務の流れを効率化している。 |
それぞれの特徴を具体例とともに紹介し、再現性のある形でまとめました。働き方をアップデートするために、ぜひ参考にしてください。
タスクの全体像を素早く把握できる
成果を出す人は、仕事の指示を受けた段階で素早く情報収集を行い、課題を設定するとともにタスクの全体像を把握しています。断片的な情報の中から全体像を推測し、目標にたどり着くための道筋を素早く描ける点が特徴です。
たとえば、企画書作成を任された際にただ内容を考えるだけでなく「誰に見せるのか」「何を決めたいのか」「どんなデータが必要か」などの要素を整理しています。
関係者や期限を踏まえて設計することで、迷いなくスタートを切ることが可能です。
タスクを分解して優先順位をつけられる
仕事を受けたとき、漠然と取りかかるのではなく、やるべきことを細かく分けて整理している点も特徴です。「やるべきことは何か」「どの順番で進めるべきか」を整理してから動いています。
たとえばイベント準備を進める場合、「日程調整」「備品の発注」「会場レイアウトの確認」といったように、工程ごとにタスクを切り分けています。
そのうえで、期限が早いものや他の作業に影響するものから優先的に着手することで、手戻りや抜け漏れを防ぎ、限られた時間の中でスムーズに進めることが可能です。
スケジュール管理を適切に行える
仕事の進め方が上手な人は、タスクの洗い出しだけでなく「いつやるか」までを明確にしています。
作業の所要時間を見積もったうえで現実的なスケジュールを組み、ゆとりを持って進めることで、突発的な業務にも対応できるように調整しています。
また、優先順位を見直して予定を組み替える柔軟さがあり、遅れや混乱を最小限に抑えていることも特徴です。
スケジュール管理には、以下のようなツールを活用しましょう。
※以下の表は右にスクロールできます
| ツール | 概要 | メリット |
|---|---|---|
| Googleカレンダー | タスクや予定を時間単位でカレンダーに組み込める | 時間の使い方を視覚化でき、予定のブロックを管理しやすい |
| Notion | ワークスペース型でタスクやメモ、進捗などをまとめて管理できる | 情報を一元化でき、タスク・ドキュメントを整理しやすい |
| Trello | カード形式でタスクを「未着手」「進行中」「完了」などに分けて管理する | 進捗がひと目でわかり、チームでも共有・更新がしやすい |
| Asana | プロジェクト単位でタスクを整理・可視化し、スケジュールや担当者も管理できる | 大規模プロジェクト向きで、進捗とタスクごとの依存関係を明確にしやすい |
仕事をスムーズに進めるためにスケジュール管理は欠かせません。自分に合ったツールを見つけて活用しましょう。
周囲に頼ったり巻き込んだりできる
仕事を一人で抱え込まず、適切なタイミングで他者の力を借りる姿勢も重要です。
厚生労働省が公表している「職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート」のチェック項目には、「チームワーク(協調性を発揮して職務を遂行する能力)」について記載されています。
職務遂行のために設けられている基準は以下の5つです。
- 余裕がある場合には、周囲の忙しそうな人の仕事を手伝っている。
- チームプレーを行う際には、仲間と仕事や役割を分担して協同で取り組んでいる。
- 周囲の同僚の立場や状況を考えながら、チームプレーを行っている。
- 苦手な同僚、考え方の異なる同僚であっても、協力して仕事を進めている。
- 職場の新人や下位者に対して業務指導や仕事のノウハウ提供をしている。
仕事をスムーズに進めるためには、チームで協力していく姿勢が重要であるといえます。
仕事の進め方が上手な人は、自分が得意でない部分は相談したり、チーム全体の目的を共有して協力を引き出したりするなど、周囲と連携する意識が強いのが特徴です。
周囲をうまく巻き込めれば、意見の相違やトラブルが起こりにくくなり、タスクの依頼や相談も自然と行えるようになります。
報連相を習慣化している
仕事のできる人は、ホウレンソウ(報告・連絡・相談)を習慣として自然に取り入れており、途中経過の共有や判断の確認を怠りません。
厚生労働省の「職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート」のチェック項目には、報連相に関する内容も記載されています。
「コミュニケーション(適切な自己表現・双方向の意思疎通を図る能力)」の職務遂行のための基準は以下のとおりです。
- 上司・先輩などの上位者に対し、正確にホウレンソウ(報告・連絡・相談)をしている。
- 自分の意見や主張を筋道立てて相手に説明している。
- 相手の心情に配慮し、適切な態度や言葉遣い、姿勢で依頼や折衝をしている。
- 職場の同僚等と本音で話し合える人間関係を構築している。
- 苦手な上司や同僚とも、仕事上支障がないよう、必要な関係を保っている。
報連相を行ううえでは、人間関係も重要な要素であることがわかります。
進捗が悪いときやトラブルが起きたときほど、こまめな情報共有を大切にしましょう。情報共有することで、作業の方向性を誤る前に軌道修正ができ、チーム内の混乱を最小限にとどめられます。
振り返り(PDCA)を習慣化している
仕事を終えたあとには、なぜうまくいったのか、あるいは何が足りなかったのかを必ず振り返っているのも特徴です。成功の要因を特定することで再現性が高まり、次回に活かせます。
また、改善点を洗い出すことで、ミスの発生率も徐々に減っていきます。振り返りの際には、PDCAサイクルを活用するのがおすすめです。
PDCAサイクルとは以下の4つの段階を繰り返し、業務やプロジェクトを継続的に改善していく方法です。
- PLAN(計画):目標の設定とそのための計画づくりを行う
- DO(実行):計画を実施する
- CHECK(評価):実施した結果を評価し、分析を行う
- ACTION(改善):評価結果から、改善や対策を行い、次の計画につなげる
失敗を恐れずにトライアンドエラーを繰り返すことが大切だといえます。
参考:厚生労働省|生産性&効率アップ必勝マニュアル ~マネジメント手法~ PDCAサイクルとOODAループ(「PDCAサイクルとは」より)
PDCAサイクルを習慣化すると、改善に向けたノウハウも蓄積していきます。PDCAサイクルを繰り返し、レベルアップを図りましょう。
完璧主義にこだわりすぎない
すべてを完璧に仕上げようとするのではなく、「100点」に満たない状態でも、スピードを重視して形にしている点もポイントです。まずはアウトラインを固めて早めに提出し、上司やクライアントの意向を取り入れるスタンスを取っています。
たとえば、提案書の作成なら「要点が揃っていて説明できる状態」を一区切りとして、細部の調整は上司のフィードバック後に行うといった判断です。
重要なタスクに時間をかけて、それ以外は効率重視で片付けたり、他の人に振り分けたりと、状況に応じて対応できる柔軟さがあります。
日ごろから情報収集や学びを続けている
担当業務に関する情報を定期的に収集することも重要です。業界の動向や他社の取り組みなどに常にアンテナを張っており、実務に活かす意識を持っています。
厚生労働省の「職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート」のチェック項目にも、情報収集について記載されています。
専門的事項である「マーケティング戦略基礎」における職務遂行の基準は以下の5つです。
- 自社のマーケティング政策やマーケティングの基本的概念を理解している。
- 生産・製品・価格・チャネルなど基本的な市場環境情報を収集・把握している。
- データ収集、作表などポジショニング分析の補助を行っている。
- 資料収集やデータ整理など、市場の評価・選択のための補助的業務を行っている。
- 経営環境や自社能力などから自社の強み、弱みなどを整理し、必要に応じて自分なりの考えを提言している。
情報収集は、自社が市場でどのようなポジションで、どのような強みや弱みがあるのかを把握することにもつながります。
担当領域に関わる知識の量が増えるほど情報同士の紐づけをしやすくなり、作業スピードも向上するため、周囲から「頼れる存在」として見られるようになります。
ツールを有効活用している
現代では、便利なビジネスツールがたくさん登場しています。仕事を進めるのが早い人は、業務を効率よく進めるために、ツールやアプリを積極的に活用していることもポイントです。
チャットやクラウド共有、スケジュール管理ツール、業務の自動化など、業務内容に合ったツールを選び、作業にかかる手間を最小限に抑えています。
ソフトバンク株式会社では、2019年4月から2022年3月に「デジタルワーカー4000プロジェクト」を実施しました。
AIやRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を活用し、「1か月で処理できる仕事量×4,513人」相当の業務時間を創り出すことに成功しました。
この取り組みで創出した時間を新規事業に充てることで、さらなる成長を遂げています。
データの抽出や簡単な資料作成といった業務が定常的にある場合は、自動化を検討してみるのもひとつです。自動化できたらそれをマニュアル化して共有することで、チームや組織全体の作業効率アップにもつながります。
【チェックリスト】仕事がうまく進まない原因

仕事がうまく進まない場合は、主に以下の5つの原因があると考えられます。
※以下の表は右にスクロールできます
| 原因 | ありがちなNG行動 | 改善ヒント |
|---|---|---|
| 計画・準備不足 | ・ゴールが曖昧なまま着手する ・必要な情報や手順を確認しない | 目的や成果を明確にし、タスクと手順を事前に洗い出す |
| 実行内容・作業環境 | ・非効率な方法で進める ・集中できない場所で作業する | 集中できる環境を整え、必要なツールや情報を事前に準備しておく |
| 管理・評価 | ・進捗を把握していない ・成果の基準が曖昧 | タスクを可視化し、定期的に進捗や成果を確認・共有する |
| 人間関係 | ・報連相を怠る ・部下や同僚とのコミュニケーションを怠る | ミーティングやチャットでこまめな情報共有とコミュニケーションを意識する |
| 自己管理 | ・体調不良でも無理をする ・感情をコントロールできない | 睡眠や食事、ストレス管理を意識し、定期的にリフレッシュする |
仕事が思うように進まないと感じたら、まずは「ありがちなNG行動」に当てはまっていないかチェックしてみましょう。もし思い当たる項目があれば、「改善ヒント」を参考に行動を見直すことで、仕事の進め方が大きく改善する可能性があります。
計画・準備不足|ゴールや手順を明確にしないまま着手している
目的や手順が曖昧なまま仕事に取りかかると、思うような成果を出すのが難しくなります。
たとえば、「とりあえず始めてみたものの、必要な資料が足りずに中断した」「ゴールがあやふやなまま進めて、途中で大幅な修正が必要になった」といったケースはよくあります。
こうした事態を防ぐためには、事前の計画と準備が不可欠です。以下の項目を確認することで、仕事をスムーズに進められます。
計画・準備のチェックポイント
- 仕事の目標やゴールが明確になっているか
- 必要な情報や資料が揃っているか
- 作業手順が明確になっているか
- タスクごとの優先順位を整理できているか
- 実行担当者や関係者が明確になっているか
- 所要時間を踏まえて締切を定めているか
- 実行に必要なスキルや知識が足りているか
- 作業に必要なツールや環境が整っているか
タスクごとの担当者や期限が決まっていないと、責任の所在が不明確になり、対応の遅れやミスが起こりやすくなります。最初にしっかり準備することで、その後の業務効率が大きく変わるため、上記のチェックポイントを活用して着実に準備しましょう。
実行内容・作業環境|非効率な方法や集中できない環境で仕事をしている
計画がきちんと立てられていても、集中できない場所で作業していたり、やり方自体が非効率だったりすれば、思うように成果は出ません。
「作業環境が騒がしくて集中できない」「ツールの使い方がわからなくて手間取る」「必要な情報やデータの管理が煩雑」といった状態では、どうしても生産性が落ちてしまいます。
独立行政法人 労働政策研究・研修機構(JILPT)によると、労働環境は仕事の成果に大きく影響するとされています。
具体的には、照明・音・温度・湿度・気流・振動、そして職場のプライバシーといった要因です。
参考:独立行政法人 労働政策研究・研修機構(JILPT)|第3章 仕事環境:仕事や職場の環境面の構造化(p83「(1)物理的および心理社会的仕事環境」より)
こうした背景を踏まえて、使用しているツールや管理方法、プロセスの見直しを行うことが大切です。以下のチェックポイントを参考に、現在の仕事環境を振り返ってみましょう。
実行内容・作業環境のチェックポイント
- 集中力が途中で途切れやすくなっていないか
- 同じミスを何度も繰り返していないか
- 事務処理や連絡対応に時間がかかりすぎていないか
- 必要な情報の共有・伝達が漏れていないか
- 作業環境(音、照明、座席など)に問題がないか
集中できる空間やツールを整えることは、仕事の質やスピードに直結します。日々の業務が滞りがちな方は、一度実行プロセスと作業環境を見直してみましょう。
管理・評価|進捗が把握できず問題への対処が遅れている
タスクの管理や評価の仕組みが整っていないと、進捗の遅れやトラブルへの対応が後手に回ってしまいます。
とくに「プロジェクト全体の進行状況が見えない」「チーム内で情報共有ができていない」といった状態では、問題が起きてもすぐ気づけず、軌道修正のタイミングを逃してしまう可能性があります。
このような状況を避けるには、進捗管理と評価の仕組みを整えることが重要です。以下のチェックポイントをもとに、現在の管理体制を見直してみましょう。
管理・評価のチェックポイント
- タスクの進捗状況をリアルタイムで把握できているか
- 誰が何を担当しているのか、責任の所在が明確になっているか
- 成果を評価するための基準が設定されているか
- 問題や課題を早い段階で発見できる仕組みがあるか
- フィードバックや改善策が適切なタイミングで行われているか
- チームや個人の達成目標が明確に共有されているか
業務の見通しを立てやすくすることで、問題の早期発見やスムーズな対処が可能になります。日々の進行状況を把握できる体制を整え、チーム全体の成果を最大化しましょう。
強い組織をつくる方法や事例を詳しく知りたい方は、以下の記事もぜひご覧ください。

人間関係|コミュニケーションや連携が不足している
「コミュニケーション不足」や「信頼関係の欠如」も仕事が思うように進まない原因のひとつです。指示が曖昧なまま伝わっていたり、連携すべき相手とのすり合わせができていなかったりすると、無駄な作業が発生してしまう可能性があります。
こうしたトラブルを防ぐには、周囲との連携や信頼関係の構築が欠かせません。以下のチェックポイントを参考に、自分やチームのコミュニケーションを見直してみましょう。
人間関係のチェックポイント
- 部下や同僚とのコミュニケーションや指示は十分か
- 上司や取引先との連携が円滑に行えているか
- 意見や相談しやすい職場の雰囲気があるか
- 誤解やすれ違いが起きたときに対話できる関係が築けているか
- チーム内で協力し合う文化や信頼関係があるか
職場に「相談しづらい雰囲気」が漂っていると、ちょっとした行き違いでも業務が滞りやすくなります。仕事は一人で完結するものではなく、人との連携で成り立つため、メンバーとの関係性づくりも重要です。
自己管理|体調や感情のコントロールができず仕事の質が低下している
「集中力が続かない」「気持ちの切り替えができない」「体調がすぐれない」といった状態では、どれだけスキルがあってもパフォーマンスは上がりません。
とくに、生活リズムや感情のコントロールが乱れていると、思考や判断が鈍りやすくなり、仕事の精度もスピードも低下してしまいます。
不調を感じた際はそのまま仕事を続けるのではなく、こまめに休憩したりストレッチしたりするなど、セルフマネジメントを積み重ねることが大切です。自己管理のチェックポイントは以下のとおりです。
自己管理のチェックポイント
- 時間の使い方をうまく管理できているか
- 業務を効率的に進められているか
- ストレスを抱え込みすぎていないか
- 自分の行動や成果を正当に評価できているか
- 睡眠や食事など、生活リズムが安定しているか
働き方の多様化やリモートワークの普及により、上司がメンバーの体調やメンタルの状態を把握しにくくなってきています。実際、コミュニケーション不足が原因で異変に気づけず、問題が深刻化してから初めて対応するケースも少なくありません。
こうした背景から、メンバーの心理状態やストレスの変化を“可視化”し、離職やパフォーマンス低下を未然に防ぐ仕組みが注目されています。
とくに、早期フォローによる離職防止やメンタルヘルスの悪化予防といった、実務的な課題解決につながる点が評価され、導入が進んでいます。
たとえば、『ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ』のようなツールを活用すれば、従業員一人ひとりの心理状態を可視化し、離職防止や生産性向上に役立てることが可能です。
不調を抱えているメンバーをサポートしたい場合は、以下の資料もぜひダウンロードしてみてください。
>>『ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ』がもっとよくわかる!の資料をダウンロードする
また、以下の記事では、『ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ』の特徴や利用できる機能、導入するメリットから注意点まで詳しく解説しています。ぜひあわせてご覧ください。

仕事の進め方がわからない部下に対する指導のポイント

自分の業務だけでなく、部下の仕事の進め方に悩んでいるマネジメント層も少なくありません。「指示を出しても動かない」「進め方を教えたつもりでもなかなか成果につながらない」といった状況が続くと、何度言っても伝わらないと感じてしまいがちです。
しかし、伝え方や環境に原因があるケースも多く、適切にサポートすることで状況は改善します。具体的な指導のポイントは以下のとおりです。
部下が仕事をうまく進められるようになると、自分が手を離して任せられる領域が増えます。結果的にチーム全体のパフォーマンスが高まり、部下の自立・成長にもつながるため、ぜひ意識して実践してみてください。
期待するゴールと進め方を明確に伝える
部下に仕事を任せるときは、「目的」「成果物の完成イメージ」「進め方の方向性」の3点を明確に伝えましょう。抽象的な言葉だけでは、とくに経験の浅いメンバーはイメージを掴めません。
たとえば、「簡単なレポートをつくって」と言うのではなく、「◯日までに、パワーポイントでA社の売上動向をグラフ付きでまとめて、クライアントに提出する資料を作成して」といった形です。
期限・形式・目的を具体的に伝えることで、部下が迷わず動けるようになります。さらに、必要に応じて過去の資料やテンプレートを共有すると、完成イメージが明確になり、質の高いアウトプットにつながります。
実行しやすい環境と仕組みを整える
いくら丁寧に指示を出しても、「相談しづらい」「どう進めればよいかわからない」という状態では、部下は動けません。部下が安心して動ける環境づくりも上司の重要な役割です。
業務フローやマニュアルを整備したり、チャットツールで気軽に相談できる雰囲気をつくったりすることで、主体性のある行動につながります。
また、「ミスをしてもそこから学べばOK」という空気をつくることで、挑戦する姿勢を引き出しやすくなります。
個人と組織、どちらも成長させたい方は以下の記事もご覧ください。

定期的なフィードバックや対話の機会を設ける
部下に仕事を任せたら「あとは本人次第」と放置するのではなく、定期的に対話の機会を設けることが重要です。一方通行の指導では、部下は戸惑いや不安を抱えたまま行動しがちです。
そこで有効なのが、「気づきを引き出す」関わり方です。状況を確認しつつ、自ら考えて動けるようにサポートするスタンスを意識しましょう。
立命館大学人文科学研究所の論文では、「エンパワーメント」と「育成」のバランスが重要であると述べられています。エンパワーメントとは、部下に意思決定や権限を委譲することです。
ただし、丸投げは逆効果なので注意しましょう。「うまく進んでいること」「困っていること」などを聞き出しながら、必要に応じて方向性を調整することが大切です。
参考:立命館大学|立命館大学人文科学研究所紀要(101号)エンパワーメント経営はどの道を歩むべきか(p70「2 構造的アプローチ」より)
1on1ミーティングや週次の振り返りタイムなど、小さくても継続的な対話の場があると、部下は安心して動けるようになります。加えてメンバーの心理状態や業務負荷をリアルタイムに把握できるため、上司も的確にサポートすることが可能です。
部下との1on1をより効果的に進めたい場合は、『ミキワメAI マネジメント』の活用もおすすめです。社員の性格や心身の状態をAIが分析し、一人ひとりに最適なコミュニケーションを提案してくれます。
対話の質が高まれば、チームの信頼関係や生産性も向上します。気になる方は以下の資料もぜひチェックしてみてください。
>>『ミキワメAI マネジメント』がもっとよくわかる!の資料をダウンロードする
なお、1on1ミーティングの効果的な取り組みに関しては、以下の記事で詳しくまとめています。こちらもぜひ参考にしてください。

チームの生産性を上げる4つのポイント

生産性を向上させるには、個人の努力だけでなく、チーム全体の関係性や仕組みの見直しも欠かせません。チームの力を最大限に引き出すためには、以下の4つのポイントを意識しましょう。
チームの生産性が向上すれば組織全体が活性化し、「仕事が回らない」「部下が動かない」といった悩みの解消にもつながります。ぜひ参考にしてください。
メンバー同士の信頼を高める
生産性の高いチームの共通点は、メンバー同士の信頼関係が構築されていることです。「この人なら任せられる」「困ったときに相談できる」といった安心感があることで、日々のコミュニケーションの質も量も自然と高まります。
信頼関係を深めるためには、感謝や成果を言葉で伝える、日常的に小さな成功体験を共有するといった行動が効果的です。何気ない声かけやポジティブなフィードバックの積み重ねが、心理的なつながりを強化します。
アメリカの調査会社ギャラップ社によると、社内に信頼できる上司や同僚がいる人は、そうでない人と比べて在籍期間が長くなる傾向があり、業績に貢献する確率も2倍以上高くなると報告されています。
チーム内の信頼関係を強化することは、目先の業務改善にとどまらず、組織全体のパフォーマンスを底上げする鍵となります。「チームの雰囲気がぎくしゃくしている」「メンバー同士の連携が弱い」と感じている方は、まず信頼構築から取り組んでみましょう。
組織の生産性が低いと悩んでいる方は、以下の記事もご覧ください。
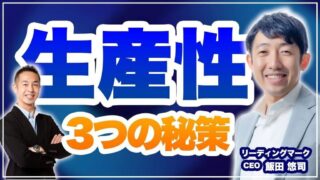
心理的安全性のある職場環境を整える
効率的に仕事を進めるためには、心理的安全性の高い職場づくりが欠かせません。心理的安全性とは、メンバーが安心感を持って意見や提案ができる状態を指します。
周囲の批判に怯えたり、上司の反応が気になったりしてしまうと、メンバーの自発性がなくなるため、高いパフォーマンスを上げることは困難です。反対に、安心して発言・提案ができる環境があれば、チームの動きは活発になります。
心理的安全性の重要性を理解し、実際に制度として取り入れている事例として、株式会社メルカリの取り組みがあります。
株式会社メルカリは、2021年に新たなワークスタイルとして「YOUR CHOICE」を導入しました。個人の判断で出社もフルリモートも選択でき、日本国内であれば住む場所も自由に決められます。
また、フルフレックスのため、働く時間も自分で選択可能です。7割以上が日中に「中抜け」をしているなど、社員一人ひとりのライフスタイルに応じた自由な働き方を実現しています。
多様な働き方が叶う仕組みを整えることで、社員のウェルビーイング(心身の健康)を支え、結果として心理的安全性を高めています。
参考:株式会社メルカリ|メルカリ、多様な働き方を尊重した 「メルカリ・ニューノーマル・ワークスタイル “YOUR CHOICE”」の活用状況を公開
チームの成果を最大化するには、スキルや制度だけでなく「心理的に安心できる環境」を整えることが前提となります。まずは、意見を歓迎する姿勢や、メンバーの声にしっかり耳を傾ける風土づくりから始めてみましょう。
組織全体の生産性向上について詳しく知りたい方は、以下の記事もぜひ参考にしてください。
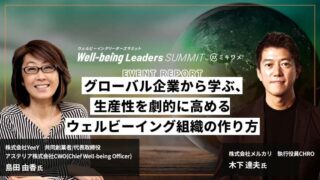
チームの目標や役割を明確にする
チーム全体で成果を出すためには、「目指すべき方向」と「各自の役割」が明確であることが不可欠です。「何のために取り組んでいるのか」「誰が何を担っているのか」が曖昧だと、個々の行動にズレが生じ、結果的に生産性の低下を招きかねません。
チームの目標を具体的に設定し、それを全メンバーと共有することで、目標達成への意識が統一され、行動が自律的になります。
九州大学と株式会社産学連携機構九州の共同研究では、企業組織において「目標を共有し協働するプロセス」が、チームパフォーマンスの向上に大きく寄与することが示されています。
また、チームメンバーとは日常的に関わりながら目標達成に向けて動くため、メンバー同士の心理的な支え合いやこまめな対話もパフォーマンス維持に欠かせない要素です。
参考:心理学研究 2015年 第85巻 第6号|企業組織において高業績を導くチーム・プロセスの解明(p531「本研究の理論的枠組み」より)企業組織において高業績を導くチーム・プロセスの解明
週次でチーム目標を共有したり、進捗を可視化できるツールで共有・確認したりすることで、メンバーが迷わず行動できるようになります。チームが「どこへ向かうか」「誰が何をするか」を共通認識として持ち、組織としての力を最大限に発揮しましょう。
チームの成果と会社への貢献度を可視化する
「自分の仕事がチームや会社にどう貢献しているか」を実感できると、仕事へのやりがいと意欲が生まれます。目の前の業務が組織全体にどう影響しているかを理解できれば、「単なる作業」ではなく「価値を生む行動」として取り組むことが可能です。
そのためには、チームや個人の成果を可視化し、組織への貢献度が実感できる仕組みづくりが欠かせません。たとえば、以下のような取り組みが効果的です。
- 定期的に会社全体への影響や成果を、具体的な数字や実績で共有する
- 社内報や全社ミーティングなどを通じ、チームの成果を広く発信する
- 成果に対する表彰制度や評価制度を活用する
たとえば、「この企画が売上を〇%伸ばした」「この施策で顧客満足度が〇ポイント改善した」といった成果を具体的に示すことで、関わったメンバー全員が自分の役割と価値を実感できます。
まずは小さな成果でも可視化し、共有する文化から育てていきましょう。
仕事の進め方を見直して、成果と信頼を獲得しよう

仕事の進め方を見直すだけで、成果の質やスピードが大きく変わります。すべてを一気に変える必要はありません。いきなり完璧を目指さず、小さな改善を積み重ねていくことが、最終的に大きな成果へとつながっていきます。
まずは、今回紹介した特徴やコツの中から取り入れやすいものを選び、できるところから実践してみてください。日々の働き方に変化が生まれるはずです。
また、部下の仕事のマネジメントにおいては、ツールを導入するのもひとつです。
『ミキワメAI マネジメント』は、部下一人ひとりの性格や価値観を可視化し、1on1での面談内容や話題を提案してくれるクラウド型ツールです。
性格診断を通じて属人的になりがちなマネジメントを標準化し、組織全体のコミュニケーションの質を高めます。ネクストアクションも自動で提示してくれるため、1on1後のやりっぱなしを防ぎ、継続的な部下支援が可能になります。
メンバーの変化にいち早く気づき、適切にサポートしたい方におすすめです。マネジメントにお悩みの方は、ぜひご活用ください。
>>『ミキワメAI マネジメント』がもっとよくわかる!の資料をダウンロードする
従業員のメンタル状態の定期的な可視化・個々の性格に合わせたアドバイス提供を通じ、離職・休職を防ぐエンゲージメントサーベイ。無料トライアルの詳細は下記から。












 ランキング1位
ランキング1位 
 ランキング2位
ランキング2位 
 ランキング3位
ランキング3位 