- 真面目な人が急に辞める心理的背景と4つの理由
- 【深刻度別】辞めるときの具体的な行動と対策ポイント
- すぐに実践可能!離職を防いで長く活躍してもらうための5つの具体策
真面目で優秀な社員の突然の退職に驚かれる方も多いのではないでしょうか。一見、仕事に満足していそうな将来性のある人材が、予告なしに辞表を提出するケースは少なくありません。
突然の退職は、負担増やモチベーションの低下を招くリスクがあり、企業にとって大きな損失となる可能性があります。
しかし、事前に兆候を見抜いて適切な対策を講じることで、このようなリスクを大幅に軽減することが可能です。
そこで本記事では、真面目な人が急に辞める心理や前兆、防止策までを詳しく解説します。読了後には、優秀な人材の離職サインを早期に発見できるようになり、従業員のモチベーションを向上させる施策や、組織の人材流出リスクを最小限に抑える方法がわかります。
ぜひ最後までお読みいただき、貴重な人材を守るための知識を身につけてください。

「真面目で優秀な人ほど急に辞める」は本当?

近年、優秀で真面目な社員の「突然の退職」が増えています。日頃の仕事ぶりに問題がなく、上司や同僚からの信頼も厚い人材が、ある日突然「辞めます」と申し出るケースです。
突然の退職は、残されたメンバーに以下のような影響を与えます。
- 業務負担の急激な増加
- チーム全体のモチベーション低下
- 人材確保・育成コストの発生
- 顧客や取引先への影響
これらの問題は、組織運営においても深刻な影響をもたらします。
真面目な社員が急に辞めてしまう背景には、本人の内面的な不満やストレス、将来への不安が隠れていることも少なくありません。
しかし、真面目で優秀な人ほど、不安や悩みを相談することが少ない傾向にあります。そのため、管理職や同僚が異変に気付けず、結果として突然の退職につながってしまうのです。
真面目な人の「突然の退職」に気付けないのはなぜ?

では、なぜ真面目な人の「突然の退職」に気付けないケースが多いのでしょうか。具体的には以下のことが考えられます。
真面目で責任感の強い人ほど、退職を考えていてもその兆しを表に出さない傾向があります。表情や態度の変化が少ないため、周囲が異変に気付くのは困難かもしれません。
ここからは、真面目な人の「突然の退職」に気付けない理由と背景を解説します。これらを理解することで、日常的なコミュニケーションや業務の中で早期に変化を察知し、フォローにつなげやすくなるはずです。ぜひ参考にしてください。
退職の影響を気にして直前に伝えるため
真面目な人ほど、「自分が辞めてしまうことで周囲に与える影響」を深く気にしてしまい、退職直前まで決断を伝えられずにいることが多いものです。
また、直属の上司や人事部門には手続きとして事前に報告していても、チームメンバーや同僚に黙っているケースも少なくありません。本人としては「波風を立てたくない」「迷惑をかけたくない」という配慮から、あえて周囲には伝えない判断をしていることもあります。
このような場合、本人は計画的に辞める準備を進めているつもりでも、周囲から見れば「突然辞めた」と受け取られてしまいます。
不平や不満を周囲に漏らすことが少ないため
責任感が強く真面目な人は、業務上の不満や悩みがあっても「自分の努力で解決すべき」と考え、上司や同僚に相談することを躊躇しがちです。
そのため、表面的には冷静で安定した働きぶりを見せており、周囲からは「順調に業務をこなしている」と判断されます。
しかし実際には、業務量の過多や人間関係のストレス、キャリアへの不安などが蓄積していることがあります。上司や人事も、目立った相談やトラブルがない限り、サポートの必要性に気付くのは困難です。
そして我慢の限界を超えたとき、周囲がまったく予想しないタイミングで突然の退職につながってしまいます。
真面目な人が急に辞めてしまう4つの理由

真面目な人が急に辞めてしまう背景には、表面化しにくいストレスや不満、将来への不安など、複数の要因が絡み合っています。
ここでは、真面目な人が急に辞めてしまう背景について、代表的な4つの理由をまとめました。
これらの理由を理解しておくことで、適切なフォローや職場環境の改善に取り組みやすくなります。
また、優秀な人材の離職防止や採用コストの削減、チーム全体のモチベーション向上にもつながり、長期的にはよりよい組織文化の構築にも貢献します。ぜひ参考にしてください。
労働環境によるストレスの蓄積
厚生労働省の調査によると、労働者の58%が仕事や職業生活において強い不安やストレスを感じていることがわかっています。
真面目な人は責任感が強く、「周囲に迷惑をかけまい」と過剰に業務を抱え込みやすい傾向にあります。仕事において、小さなことで思い悩んでしまう人も少なくありません。
また、令和5年の厚生労働省の調査では、転職者が直前の勤め先を離職した理由として「労働条件(賃金以外)がよくなかったから」という回答が、27.2%ともっとも多くなっています。
このことからも、真面目な人に限らず、労働条件によるストレスは離職の原因となり得ることがわかります。
正当に評価されない「報われなさ」
正当に評価されない「報われなさ」も理由のひとつです。会社の人事評価内容に納得していないと、モチベーションやエンゲージメントが低下し、離職のきっかけとなることがあります。
特に真面目で一生懸命な人ほど、多くの業務を引き受け、タスクを抱え込んでしまうケースも少なくありません。
しかし「努力が評価制度に反映されない」「定量目標を達成しても昇給がない」といった状況が続けば、次第に不満が蓄積していきます。
さらに、優秀な人材の場合、他社に引き抜かれてしまう可能性もあります。自社よりも条件のよい待遇やポジションを提示され、新しい環境での挑戦を選択するケースは決して珍しくありません。
誰にも相談できず、頼ることができない環境
誰にも相談できない環境も、離職につながる理由となり得ます。
厚生労働省の調査によると、労働者のうち「現在の自分の仕事や職業生活でのストレスについて相談できる人がいる」割合は94.9%です。
しかし一方で、「職場における事業場外資源を含めた相談先がある」割合は86.1%にとどまります。裏を返せば、約14%の人は仕事関係における相談先を持たない状況にあることがわかります。
参考:厚生労働省|令和5年「労働安全衛生調査(実態調査)」の概況(p17「(2)仕事や職業生活に関するストレスの相談状況」より)
真面目な人は弱音を吐くことに罪悪感を覚えやすく、誰にも相談できずに孤立感を深めてしまいがちです。このような状態が続くと、問題が深刻化してから初めて表面化するため、上司や同僚が対応すべきタイミングを逃してしまうリスクが高まります。
将来に対する不安
将来への不安があり、キャリアの見通しが立たないことも、真面目な人にとって離職につながる深刻な理由のひとつです。
厚生労働省の調査によると、転職者が勤め先を離職した主な理由として「会社の将来に不安を感じたから」が上位に挙がっています。
特に男性ではこの理由がもっとも多く、将来性への懸念が離職を後押ししていることがわかります。
参考:厚生労働省|2 離職理由
会社の業績や事業方針に不安を感じると、「このままここにいてよいのか」という迷いが生まれ、より安定した環境や成長性のある企業への転職を検討するようになるのです。
真面目な人が急に辞めてしまうときの前兆

続いて、真面目な人が急に辞めてしまうときの前兆を見てみましょう。真面目な人は責任感が強く、日頃から与えられた業務を着実にこなす傾向にあります。
しかし退職を考え始めると、徐々に言動に変化が現れます。たとえば、以下のような変化です。
- 社内でのコミュニケーションを避けようとする
- 仕事への積極性が低下する
- 有給休暇の取得頻度が増える
- 引き継ぎ準備を始める
ここでは、真面目な人が辞めてしまうときの上記の前兆を「軽度」「中度」「重度」の3段階に分けて解説します。
※以下の表は右にスクロールできます
| 前兆 | 具体的な行動例 | 深刻度 |
| 社内でのコミュニケーションを避けようとする | ・昼食や休憩を一人で取るようになる ・雑談スペースに寄らない ・社内イベントへ参加しなくなる | 軽度(早期のフォローが重要) |
| 仕事への積極性が低下する | ・会議で発言しなくなる ・提案や改善案を出さなくなる ・新しい仕事を引き受けようとしない | 中度(引き止めの余地あり) |
| 有給休暇の取得頻度が増える | ・月2〜3回以上有給を取得する ・連続して休むようになる ・直前の有給申請が増える | 中度(引き止めの余地あり) |
| 引き継ぎ準備を始める | ・マニュアルや手順書を作成し始める ・タスクの整理を始める ・デスク周りを片付け始める | 重度(引き留め不可) |
各段階の兆候を察知し、段階に応じた適切なフォローを行うことで、離職の低減を目指せます。ぜひ参考にしてください。
【油断禁物】社内でのコミュニケーションを避けようとする
退職を考えている人は、徐々に社内での交流を減らす傾向があります。普段は同僚との雑談に積極的だった人がコミュニケーションを取らなくなっているとしたら、注意が必要です。
【具体的な行動例】
- 積極的に挨拶をしなくなった
- 昼食や休憩を一人で取るようになった
- 飲み会など社内イベントへの参加が減った
- 雑談スペースに近寄らなくなった
このような変化は、本人が退職を検討しているサインかもしれません。放置すると状況が悪化し、退職の意思を固めてしまう可能性があります。
1on1などの定期的な面談や日常的な声かけを通じて原因を探り、早期に不安や不満を解消することが大切です。
【要注意】仕事への積極性が低下する
以前は積極的に業務に取り組んでいた社員が、意欲やパフォーマンスの低下を見せている場合、退職を考え始めている可能性があります。
たとえば、以下のような行動が見られた場合は注意が必要です。
【具体的な行動例】
- 離席が多くなった
- 業務への意欲やパフォーマンスが低下している
- 提案や改善案を出さなくなった
- 新しい仕事を引き受けようとしない
- 会議で発言しなくなった
こうした兆しが見えた場合、面談を通じて不満や不安を丁寧にヒアリングすることが大切です。業務内容の見直しやキャリアアップの支援などで、立て直しを図れるかもしれません。
【要注意】有給休暇の取得頻度が増える
勤務パターンに急激な変化が見られる場合、退職を具体的に検討している可能性があります。特に、これまで休まなかった人が頻繁に有給を取得し始めたり、残日数を計画的に消化していたりする場合は要注意です。
【具体的な行動例】
- 有給休暇を月2〜3回以上取得している
- 有給休暇の残日数を計画的に消化している
- 連続して休むようになった
- 直前の休暇申請が増えた
- 残業せず急に定時で帰るようになった
これらの行動は、転職に向けて行動に移している可能性があります。面接や企業説明会への参加、または退職準備として有給を消化しているかもしれません。
この段階では、退職の意思が固まりつつある可能性が高いため、引き止めを検討する場合は迅速な対応が不可欠です。
【引き留め不可】引き継ぎ準備を始める
退職が目前に迫っている社員は、業務の引き継ぎ準備を始める傾向があります。マニュアルや引き継ぎ資料の作成、書類やデータの整理、デスク周りの片付けなどは、退職準備の典型的な行動として注意すべきサインです。
【具体的な行動例】
- 業務マニュアルや手順書を作成し始める
- 担当業務のタスク整理を始める
- 個人ファイルやデータを整理し始める
- デスク周りを片付け始める
この段階ではすでに転職先が決まっている場合も多く、引き止め交渉は困難な状況と言えます。無理に引き止めようとするよりも、退職理由を丁寧にヒアリングし、今後の組織改善や人材定着策に活かすことが重要です。
真面目な人の「突然の退職」を防止する5つの対策

真面目で優秀な社員の退職は、組織にとって大きな損失となります。
一方で、適切な対策によって人材の定着を実現できれば、採用コストの削減、チームの士気向上、組織全体の生産性向上といった大きなメリットを得ることが可能です。
以下では、真面目な人材の離職を未然に防ぎ、長く活躍してもらうための5つの具体的な対策を解説します。
日頃のケアと仕組みづくりを組み合わせることで、突然の退職リスクを減らし、組織の持続的な成長を実現しましょう。
また、以下の記事では離職防止の成功事例について詳しく紹介しています。あわせて参考にしてみてください。

給与や待遇の見直し
真面目な社員の離職を防ぐには、努力や成果に見合った報酬や待遇の提供が欠かせません。定期的な評価制度の運用と報酬体系の透明化により、社員の不満が蓄積するのを防げます。
給与や待遇の底上げはもちろん、明確な評価基準を設けて不公平感をなくすことも重要です。社員の業績や意欲、会社への貢献度などを適切に評価して、昇給・昇進に反映させましょう。
また、社員の納得感を高めるために、評価マニュアルの整備や評価者への研修を実施するのもおすすめです。これにより、評価の一貫性と公平性を担保できます。
コミュニケーションの強化
真面目な性格やおとなしい人の中には、周囲への遠慮や責任感の強さから、悩みや不満を自ら口にしないケースも多く見られます。その結果、問題が深刻化するまで上司や同僚が気付けない状況が発生しがちです。
このような状況を防ぐために、定期的なコミュニケーションの機会を設けることで、早期に退職の予兆を察知できる可能性が高まります。日常的な雑談や声かけに加え、1on1などの活用が効果的です。
フィードバックや意見交換の文化を育て、社員が安心して本音を話せる心理的安全性の高い職場環境を整えましょう。
また、リモートワークの拡大に伴い「マネジメントが難しくなった」という課題も増えています。オンライン環境では、意識的なコミュニケーション設計が重要です。
以下の記事では、テレワークでのコミュニケーションを改善した事例を紹介しています。オンラインでのコミュニケーションにお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
事例:テレワーク時代のコミュニケーション革命。ミキワメが変えた社員ケアの在り方
将来を描けるキャリアパスの提供
明確なキャリアパスを提示し、本人の希望や適性に合わせた成長の道筋を示すことは、人材定着において不可欠です。
「この会社でどのような未来を築けるのか」が見えない状況では、優秀で真面目な社員ほど将来への不安を抱きやすくなります。離職のきっかけになりやすいポイントでもあるため、積極的に対策を行う必要があります。
たとえば、社内での昇進ルートや専門スキルの習得計画、異動や新規プロジェクトへの参加機会など、具体的な成長ステップを設けることが大切です。
また、定期的なキャリア面談を実施し、目標や課題をすり合わせるのも有効です。本人の将来像と会社の方向性を一致させることで、社員の将来に対する安心感とモチベーションを高めることができます。
ワークライフバランスの推進
過労や燃え尽き症候群、疲弊による離職を防ぐには、ワークライフバランスの推進が欠かせません。働き方の柔軟性を高め、社員が仕事と私生活を両立できる環境整備が求められます。
効果的な施策として、フレックス制度やリモートワークの導入、有給休暇の取得促進などが挙げられます。これらの制度により、社員は個人のライフスタイルに合わせた働き方を選択することが可能です。
ワークライフバランスが保たれることで、職場への満足度が向上し、生産性の向上も期待できます。心身に余裕が生まれることで、創造性やモチベーションが高まり、結果として離職リスクの低下につながります。
離職防止ツールの導入
離職を防ぐ仕組みを整えるために、離職防止ツールの導入を検討することも有効な選択肢のひとつです。
離職防止ツールとは、社員の早期離職を防ぎ、定着率を高めるためのシステムです。仕事に対する満足度やストレス傾向、心理的安全性などを数値化して可視化し、離職の兆候を早期に把握できます。
アンケートや行動データの分析を通じて、サポートが必要な社員を客観的に特定し、個別のフォロー体制を構築できることが大きなメリットです。
特に真面目な社員の突然の退職を防ぐには、本人からの自発的な相談を待つのではなく、データに基づく課題の早期発見が重要となります。AIが提示するケア方法や組織課題の分析結果を活用すれば、属人的な判断に頼らず、根拠に基づいた改善策を講じることができます。
こうしたツールは、離職防止にとどまらず、社員のエンゲージメント向上や組織全体のパフォーマンス改善にも効果的です。
なお、具体的なツールについて知りたい方は、以下の記事をぜひ参考にしてみてください。離職防止に特化したサーベイについて、4つのおすすめツールをまとめています。
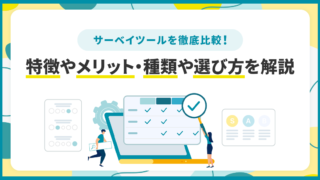
真面目な人の急な退職に関するQ&A
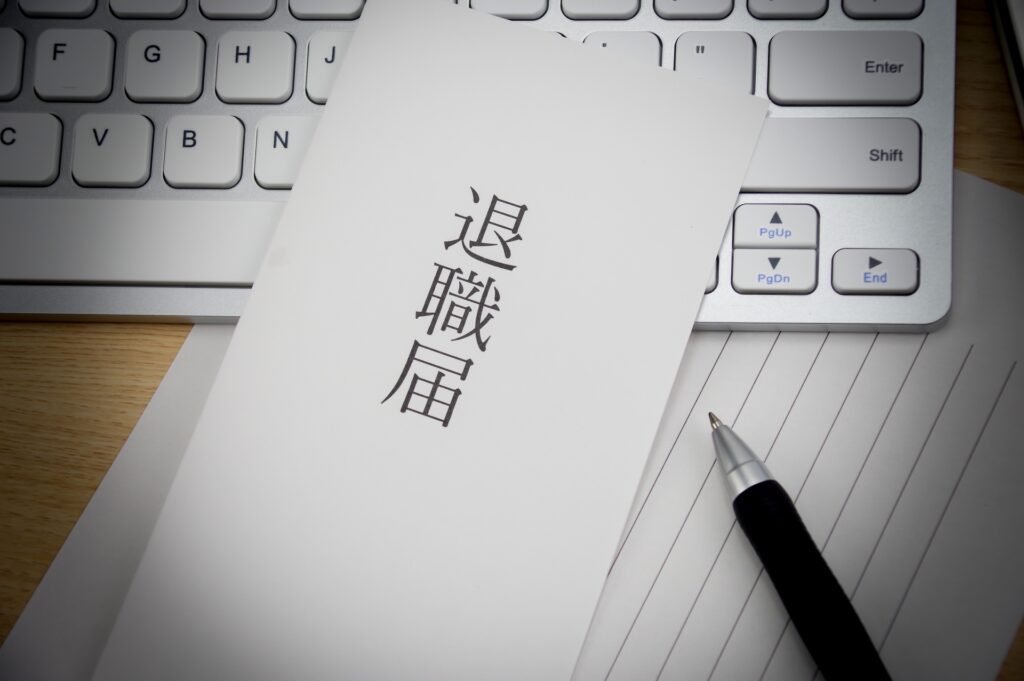
最後に、真面目な人の急な退職に関するQ&Aをまとめました。
疑問の解消にお役立てください。
まともな人が辞めていく職場の特徴は?
離職率の高い企業には、以下の傾向があります。
- 長時間労働やサービス残業がある
- 仕事に対する報酬が見合っていない
- ハラスメントが横行している
- 人手不足が慢性化している
- 社内でのコミュニケーションが少ない
- 人事評価の基準が不明確である
- 尊敬できる上司や先輩がいない
上記のような職場環境では、責任感が強く真面目な人が疲弊しやすく、離職を招きやすくなります。
こうした会社の対応策については、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひあわせて参考にしてみてください。

突然退職するのは非常識?
いきなり退職届を出すことは、場合によっては非常識と受け取られる可能性があります。
ただし民法627条1項では、退職の意思を告げてから2週間で退職できることが明記されています。
職場への影響を考慮した配慮は望ましいものの、2週間以上前に退職届を出していれば、法律上は問題ありません。
『ミキワメ ウェルビーイングサーベイ』で急な退職を防ごう

真面目で優秀な社員の急な退職を防ぐには、前兆や転職のサインを見逃さず、早期に対応策を講じることが重要です。
コミュニケーションの減少や勤務パターンの変化といったわかりやすい兆候だけでなく、日常のやりとりでは可視化されにくい変化にも注意を払う必要があります。
社員の不満や不安を早期に発見するためには、離職防止ツールの導入がおすすめです。特にサーベイツールを活用すれば、現場の声を可視化し、離職リスクの早期発見に役立てられます。
『ミキワメ ウェルビーイングサーベイ』は1回3分で手軽に行えるサーベイなので、月に1回といったように高頻度で調査しやすいのが特徴です。リアルタイムで社員の状態変化に気付けるため、手遅れになる前に必要な対応を行えます。
自社における『ミキワメ ウェルビーイングサーベイ』の活用法をつかみたい方は、ぜひ以下の資料もダウンロードしてみてください。

従業員のメンタル状態の定期的な可視化・個々の性格に合わせたアドバイス提供を通じ、離職・休職を防ぐエンゲージメントサーベイ。無料トライアルの詳細は下記から。












 ランキング1位
ランキング1位 
 ランキング2位
ランキング2位 
 ランキング3位
ランキング3位 