- 感情労働の基本とバーンアウトの関係
- 「表層演技」と「深層演技」の影響
- 感情労働者のストレス対策と予防策
- 企業が取るべき具体的な支援策
「社員の心が疲れているサインに気づいていますか?」
感情労働に従事する社員は、日々の業務で知らず知らずのうちにストレスが蓄積し、バーンアウト(燃え尽き症候群)に陥るリスクを抱えています。
とくに医療・介護職や接客業、教育現場などでは、感情のコントロールが求められるため、精神的な負担が大きくなりがちです。
バーンアウトに関する「表層演技」と「深層演技」の違いを理解し、適切なストレス対策を講じることが、従業員の離職防止や組織の生産性向上につながります。
本記事では、感情労働によるバーンアウトのリスクを分析し、どのように心がすり減るのかのプロセスや、企業が取るべき具体的な対策を詳しく解説します。
ツールを用いた効果的なメンタルヘルス対策も紹介するので、従業員の健康を守り、働きやすい職場環境を整えましょう。ぜひ最後までご覧ください。

感情労働とは?なぜバーンアウトしやすいのか
バーンアウトとは、過度なストレスや精神的な負担により突然意欲を失ってしまう状態です。「燃え尽き症候群」とも呼ばれ、それまで熱心に仕事をしていたにもかかわらず、まるで燃え尽きたかのように意欲を失い、無気力になってしまいます。
感情労働に従事する人は、熱意や意欲を突然失うこのバーンアウトに陥ることがあるので、注意が必要です。
ここでは、感情労働の基本や「表層演技」と「深層演技」との違いに触れながら、なぜ感情労働者がバーンアウトしやすいかを考察していきます。
これらを知ることで、なぜ感情労働がバーンアウトしやすいかの理解を深められるでしょう。
感情労働の基本:ホックシールドが提唱した概念とは
感情労働は、社会学者のアーリー・ラッセル・ホックシールドによって提唱された概念です。ホックシールドは、感情が個人の内面にとどまるものではなく、社会的な規則によって管理される側面があることを明らかにしました。
著書『The Managed Heart(管理される心)』では、労働者が自身の感情をコントロールし、企業の求める感情を表現する必要性について詳しく述べられています。
現代において、感情労働は多くの職種で求められているのが現状です。とくに、接客業・医療・介護・教育の分野では、顧客や患者、生徒の感情に寄り添った適切な対応が不可欠でしょう。
参考:The Managed Heart | caring labor
以下の記事では、感情労働の基本について詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

「表層演技」と「深層演技」がもたらす負担の違い
感情労働には、「表層演技」と「深層演技」の二つの種類があります。
表層演技とは、本心とは異なる感情を表面的に装うことです。たとえば、不満を抱えながらも笑顔で接客するケースが該当します。自分の内面と異なる感情を演じ続けることで、心理的なストレスが蓄積しやすくなるでしょう。
一方、深層演技とは、求められる感情を本当に感じようとする働きかけのことです。顧客の立場に立って共感したり、気持ちを理解しようと努めたりするケースが該当します。
深層演技は表層演技に比べて負担は少ないとされていますが、感情のコントロールが求められるため、精神的なエネルギーを消耗することもあるでしょう。表層演技が長期間続くと、自己の感情が麻痺し、バーンアウトにつながるリスクが高まります。
感情労働に向いている人・向いていない人の特徴
感情労働には、適性のある人とそうでない人がいます。それぞれの特徴を以下の表にまとめました。
※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください
| 特徴 | 感情労働に向いている人 | 感情労働に向いていない人 |
| 性格 | ・ストレス耐性が高い ・気持ちの切り替えが上手い ・相手の感情を理解し、共感する能力に長けている ・自分と他人の境界線を明確にできる | ・共感力が高すぎる傾向がある ・感情を溜め込みやすい ・自分の感情をコントロールすることが苦手である |
| 行動 | ・オンとオフの切り替えができる ・顧客と適切な距離を保ちながら対応できる ・クレームや非難を受け流しやすい | ・仕事とプライベートの区別が曖昧になりやすい ・相手の気持ちに感情移入しすぎる傾向がある ・クレームを人格否定と捉えてしまう |
| 考え方 | ・仕事は仕事と割り切れる ・仕事上の評価と自己の価値を切り離して考えられる | ・相手の感情に深く影響されやすい |
| スキルの種類 | ・高度なコミュニケーション能力を持つ ・感情をコントロールしながら交渉できる | ・ストレスを自覚しにくい傾向がある |
感情労働に向いている人は、ストレス耐性が高く、気持ちの切り替えが上手です。
また、相手の感情を察知し、適切に共感できる人も感情労働に適しています。
一方で、感情労働に向いていない人は、共感力が高すぎる傾向があり、相手の気持ちに感情移入しすぎることが多いでしょう。とくに、自分の感情をうまくコントロールできない場合、精神的な疲労が蓄積しやすくなってしまいます。
ただし、感情労働が苦手でも、適切な対処法を学ぶことで負担を軽減しながら働けます。まずは、適職診断によって感情の傾向を理解し、仕事との向き合い方を見直すことが重要です。
以下の記事では、感情労働に向いている人について、詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

感情労働のバーンアウトプロセス:どのように心がすり減るのか?
感情労働におけるバーンアウトは、徐々に進行するプロセスであり、その過程で心身にさまざまな変化が現れます。ここでは、感情労働のバーンアウトプロセスを解説していきます。
健全な職場環境を維持するためには、バーンアウトがどのような段階を経て進行するのか理解することが重要です。それぞれ確認していきましょう。
「感情の抑圧」と「共感疲労」による心理的負担
感情労働では、従業員は自身の感情を抑え、顧客やクライアントに適切に感情を表現しなければなりません。感情の抑圧とは、怒りや悲しみを押し殺し、表に出さないようにすることです。
たとえば、ストレスを感じても「大丈夫」と振る舞い、周囲に悟られないようにするケースが挙げられます。この状態が続くと、精神的な負担が増し、バーンアウトにつながるおそれがあります。
一方、共感疲労とは、他者の感情に深く共感し続けることで心身が疲弊することです。とくに、医療や介護など人の感情に触れる機会が多い職業では、この傾向が強まります。
共感しすぎると精神的に消耗し、仕事への意欲が低下することもあるため、適度な距離を保つことが重要です。
「脱人格化」が職場の人間関係に与える影響
バーンアウトが進行すると、顧客や同僚への関心が薄れ、冷淡な対応になる「脱人格化」が起こることがあります。
脱人格化とは、クライアントを個人として認識せず、画一的な対応をすることです。たとえば、患者を症状名で呼ぶ、顧客を年齢や性別といったステレオタイプで判断するような行動が典型例でしょう。
脱人格化は、感情的な消耗を防ぐための防衛反応とされています。顧客や同僚と距離を置き、仕事上の関係にとどめようとするのです。しかし、脱人格化が進むと、職場の人間関係が悪化し、孤立感が深まるおそれがあります。
その結果、ストレスが増大し、バーンアウトの悪循環に陥ることもあるでしょう。
「個人的達成感の低下」がモチベーションを奪う理由
「どんなに頑張っても評価されない」といった状態が続くと、モチベーションの低下を招き、離職やメンタル不調につながります。
個人的達成感の低下とは、本来感じられるはずの満足感や達成感が失われることです。たとえば、以前は顧客の感謝の言葉を励みにしていた人が、バーンアウトの影響でやりがいを感じにくくなるといったケースが挙げられます。
この状態を防ぐには、目標設定を見直し、チームで協力しながら成果を実感できる環境を整えましょう。小さな成功体験を積み重ねることで、達成感を得やすくなります。仕事の意義を再確認し、適切なフィードバックを受けることも重要です。
参考:バーンアウト (燃え尽き症候群) | 独立行政法人労働政策研究・研修機構
感情労働のバーンアウト対策

感情労働は、従業員の感情的なエネルギーを大きく消耗させる可能性があります。
ここでは、感情労働のストレスを軽減し、バーンアウトを未然に防ぐために、企業の人事担当者や経営者が実践できる具体的な方法を紹介します。
これらの対策の導入によって、従業員のメンタルヘルスを保護し、より健全な職場環境を実現できるでしょう。自社の環境を考慮しながら、読み進めていきましょう。
オン・オフの切り替え
感情労働によるバーンアウトを防ぐには、仕事とプライベートの境界を意識的に設けることが大切です。仕事と私生活を分けることで、感情的な疲労を軽減し、心の健康を維持しやすくなります。
たとえば、仕事終わりに特定のルーティンを取り入れると、気持ちを切り替えやすくなるでしょう。服を着替える、短時間の散歩をするなど、簡単な行動でもリフレッシュ効果が期待できます。
企業としては、従業員が業務時間外に仕事を持ち込まずに済むよう、適切な休息環境を整えることが求められます。時間外対応の負担を減らし、ワークライフバランスを支援する仕組みを導入するとよいでしょう。
「マインドフルネス」「運動」「休息」の活用
感情労働のストレスを軽減するためには、科学的に効果が証明されているリラックス法を取り入れることが有効です。マインドフルネスは、瞑想や呼吸法を通じて「いま、この瞬間」に意識を集中させることで、ストレスを軽減する効果が期待できます。
マインドフルネスを14週間実践した195人の女子大学生を対象とした研究では、主に以下の効果が得られる可能性が確認されています。
- 授業内外で心身の状態を意識・観察する習慣が身につき、体調管理に活かされる
- 瞑想のルーティン化によって、授業への集中力向上や思考整理に役立つ
- 集中力が高まり、リラックスや落ち着きを感じやすくなり、心理的健康が向上する
- 姿勢維持のための柔軟性と体力が向上し、緊張を和らげる方法を体得することで、身体的健康が向上する
- 継続的な実施により、瞑想に対する印象が変化する
また、運動は心身のリフレッシュにつながり、ストレス解消に役立つ方法の一つです。十分な休息の確保によって、心と体の疲労回復を促し、バーンアウトの予防につながるでしょう。
企業としても、従業員がこれらのリラックス法を実践しやすいよう、休憩時間の確保やリラックスできる空間の提供が求められます。
以下の記事では、感情労働のストレスについて詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

バーンアウトの診断チェック項目(日本版バーンアウト尺度)
ここでは、従業員のバーンアウトを早期に発見し、適切な対策を講じるために、社内で使えるバーンアウトの診断チェック項目「日本版バーンアウト尺度」を紹介します。
| 項目 | 内容 | 区分(※) |
| 1 | こんな仕事、もうやめたいと思うことがある。 | E |
| 2 | われを忘れるほど仕事に熱中することがある。 | PA |
| 3 | こまごまと気くばりすることが面倒に感じることがある。 | D |
| 4 | この仕事は私の性分に合っていると思うことがある。 | PA |
| 5 | 同僚や患者の顔を見るのも嫌になることがある。 | D |
| 6 | 自分の仕事がつまらなく思えてしかたのないことがある。 | D |
| 7 | 1日の仕事が終わると「やっと終わった」と感じることがある。 | E |
| 8 | 出勤前、職場に出るのが嫌になって、家にいたいと思うことがある。 | E |
| 9 | 仕事を終えて、今日は気持ちのよい日だったと思うことがある。 | PA |
| 10 | 同僚や患者と、何も話したくなくなることがある。 | D |
| 11 | 仕事の結果はどうでもよいと思うことがある。 | D |
| 12 | 仕事のために心にゆとりがなくなったと感じることがある。 | E |
| 13 | 今の仕事に、心から喜びを感じることがある。 | PA |
| 14 | 今の仕事は、私にとってあまり意味がないと思うことがある。 | D |
| 15 | 仕事が楽しくて、知らないうちに時間がすぎることがある。 | PA |
| 16 | 体も気持ちも疲れはてたと思うことがある。 | E |
| 17 | われながら、仕事をうまくやり終えたと思うことがある。 | PA |
(※) E:情緒的消耗感、D:脱人格化、PA:個人的達成感
引用:バーンアウト (燃え尽き症候群) ヒューマンサービス職のストレス | 独立行政法人労働政策研究・研修機構
このチェックリストで従業員の状況を把握できれば、より働きやすい職場環境を整備できるでしょう。
企業・職場ができるバーンアウト対策5選

感情労働は、従業員に大きなストレスを与える可能性があります。そのため、企業が従業員のメンタルヘルスを守るには、具体的な対策を講じることが不可欠です。
ここでは、回避策と回復策の両面から、企業ができるバーンアウト対策を解説します。
※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください
| 対策 | 内容 | 期待できる効果 |
| 定期的なストレスチェックによる従業員の負担の可視化 | ・従業員のストレスを数値化し、早期発見につなげる ・集団分析を通じて職場の課題を明らかにする | ・従業員の生産性や労働満足度が向上する ・感情労働に従事する従業員の心身の健康を守る |
| ウェルビーイングサーベイを活用した職場全体のストレスの可視化 | ・社員の満足度や心理状態を定期的に把握し、不調の要因を明確にする ・ケアが必要な社員を可視化し、適切なサポートを提供する | ・離職や休職を未然に防ぎ、組織全体の生産性が向上する ・社員が自身の目標を見つけ、より活躍できる職場環境を構築する |
| 適性検査を用いた感情労働に適性のある人材の見極め | ・感情労働に向いている人材の特性を見極め、適材適所の配置を実現する ・感情労働の適性を測る指標を分析し、採用や人材配置を最適化する | ・ミスマッチを防ぎ、組織全体の生産性を向上させる ・従業員の負担が軽減する |
| カスタマーハラスメント(カスハラ)対策の導入 | ・従業員を顧客の過剰な要求から守るための適切な対策 ・企業事例や法的対応のポイントを踏まえた実践的な対策を検討する | ・従業員と企業の双方にとって、実効性のある施策を講じる |
| 相談窓口とメンタルヘルス支援制度の活用 | ・企業がメンタルヘルス相談窓口を設置し、従業員が安心して相談できる環境を整える ・産業カウンセラーや心理専門職と連携し、専門的なサポートを提供する | ・問題を早期に発見できる ・メンタルヘルス不調を未然に防ぐ ・従業員が気軽に利用できる体制を整え、メンタルヘルスの維持 ・向上を図る |
従業員のウェルビーイングを向上させ、組織全体の生産性を高めるために、ぜひこれらの対策をご参考にしてください。
定期的なストレスチェックによる従業員の負担の可視化
定期的なストレスチェックは、従業員のストレス状態を数値として可視化し、バーンアウトの早期発見につなげる有効な手段です。
ストレスチェックによって、従業員自身が現在のストレス状況を把握できるだけでなく、集団分析を行うことで、職場全体の課題を明らかにすることも可能になります。
とくに感情労働に従事する従業員は、業務特性からストレスを抱えやすいため、早期にストレスを発見し、適切な対策を講じることが欠かせません。
高ストレス者の特定や、ストレス要因の把握を踏まえた職場環境の改善に取り組むことが重要です。
ストレスチェックの適切な活用によって、従業員の生産性向上や労働満足度の改善につなげてみてください。以下の記事では、ストレスチェックができるおすすめサービスも紹介しています。

ウェルビーイングサーベイを活用したストレスの可視化
ウェルビーイングサーベイは、社員の満足度や心理状態を定期的に把握するための有効な手段です。定期的な実施によって、職場のストレス要因を明確にし、問題の早期発見が可能となります。
調査結果を基に、サポートが必要な社員を可視化し、適切なケアを提供しましょう。とくに、社員の心理状態に応じた支援策を講じることで、感情労働によるストレスの未然防止に役立ちます。
また、『ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ』では、AIによる高度な分析を活用し、ケアが必要な社員に対して的確なアドバイスを提供できます。これにより、企業は個々の社員に最適なサポートを行い、職場環境をより効果的に改善できるでしょう。
ここでは、ウェルビーイングサーベイの活用によって、離職を減少させた事例を紹介します。
【株式会社笑美面の事例】
株式会社笑美面では、『ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ』を導入し、従業員の状態の定期的な把握によって、離職率を3/5に減少させました。
最初に取り組んだのは、ケア対象の社員を抽出する作業です。サーベイを実施し、退職の兆候があるメンバーを特定しました。
その後、幹部全員でフォロー体制を構築し、最優先ケア・優先ケアの該当者へ対面やWEB面談、電話でのサポートを実施しています。
さらに、経営会議でサーベイ結果を共有し、経営陣が危機感を持って対応しました。現在も、企業全体で一丸となってフォローを継続し、社員の目標設定と職場環境の改善に努めています。
また、採用段階でのミスマッチ防止にも注力しており、ミキワメAIを採用とリテンションの両面で活用しています。人材の流出を防ぎ、最適な人材配置を実現できる点も、大きなメリットといえるでしょう。
以下の記事では、『ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ』について詳しく解説しています。ぜひ本記事とあわせてご覧ください。

適性検査を用いた感情労働に適性のある人材の見極め
適性検査の導入によって、感情労働に向いている人材の特性を見極め、適材適所の配置を実現できます。
バーンアウトしやすい従業員の特性や、感情労働の適性を測る指標の分析によって、採用や人材配置の最適化が可能です。感情労働には向き不向きがあるため、適性検査の活用によってミスマッチを防ぎ、組織全体の生産性向上を目指せます。
たとえば、『ミキワメAI 適性検査』を導入すれば、客観的なデータを基に適性を評価できるでしょう。最適な人材配置を実現し、従業員の負担を軽減させることが重要です。
以下の記事では、『ミキワメAI 適性検査』について詳しく解説しています。

カスタマーハラスメント(カスハラ)対策の導入
企業が従業員を顧客の過剰な要求、いわゆるカスハラから守るためには、適切な対策が必要です。具体的には、対応マニュアルの作成や専門部署の設置が挙げられます。
また、企業事例や法的対応のポイントを踏まえた、実践的な対策も検討すべきでしょう。
ただし、「カスハラ対策を導入すればすべて解決できる」というわけではありません。「クレームの正当性の判断が難しい」「顧客離れを懸念し、厳しい対応を取りづらい」など、企業側の対応には難しさが伴い、現実的な課題も多く存在します。
従業員と企業の双方にとって、実効性のある施策を講じることが重要です。
相談窓口とメンタルヘルス支援制度の活用
メンタルヘルス相談窓口の設置によって、従業員が安心して相談できる環境を整えられます。早期の問題発見につながり、メンタルヘルス不調を未然に防ぐことが可能です。
また、産業カウンセラーや心理専門職との連携によって、より専門的なサポートを提供できるでしょう。企業内の相談窓口に加え、外部における支援制度の活用も有効です。
ここでは、株式会社友伸エンジニアリングの外部EAP(従業員支援プログラム)機関の活用事例を紹介します。
株式会社友伸エンジニアリングでは、外部EAP(従業員支援プログラム)機関のカウンセラーによる月1回の相談窓口を継続し、社員が気軽に利用できる環境を整えています。
EAPとは、専門家が従業員のメンタルヘルスや職場の悩みを支援する制度です。産業医も精神科医に変更し、早期対応を強化しました。
地方拠点では外部カウンセラーの全員面談を継続し、管理職とともに職場環境の改善に取り組んでいます。
また、若手社員との定期面談や1on1ミーティングを導入し、個別の課題に対応。早期対応と職場復帰支援により、メンタル不調者の回復を促進しています。
相談窓口の利用を促進するためには、従業員に対して定期的な周知や利用しやすい体制の整備が不可欠です。
従業員がストレスを抱え込まず、気軽に相談できる環境を整えることが、メンタルヘルスの維持・向上につながるでしょう。
まとめ:感情労働と上手に付き合い、バーンアウトを防ぐために
本記事では、「感情労働に向いている人・向いていない人の特徴」「適性診断による見極め方」「職場でのサポート体制づくり」について解説しました。
感情労働は、やりがいや成長機会が多い反面、心の負担が大きくなりやすい仕事でもあります。
だからこそ、従業員一人ひとりの適性を把握し、その人らしく働ける環境を整えることが、長く安心して働ける職場づくりには欠かせません。
たとえば、『ミキワメAI 適性検査』を活用すれば、個々の強みや特性を客観的に可視化し、業務適性や配置検討に役立てることができます。さらに、定期的な『ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ』によって、感情労働によるストレスの兆候を早期に発見し、フォローやケアにつなげることも可能です。
従業員の適性把握とストレスケアの両面から、無理なく活躍できる環境を整えることで、定着率向上やパフォーマンス最大化が期待できます。この機会に導入を検討してみてはいかがでしょうか。

従業員のメンタル状態の定期的な可視化・個々の性格に合わせたアドバイス提供を通じ、離職・休職を防ぐエンゲージメントサーベイ。無料トライアルの詳細は下記から。

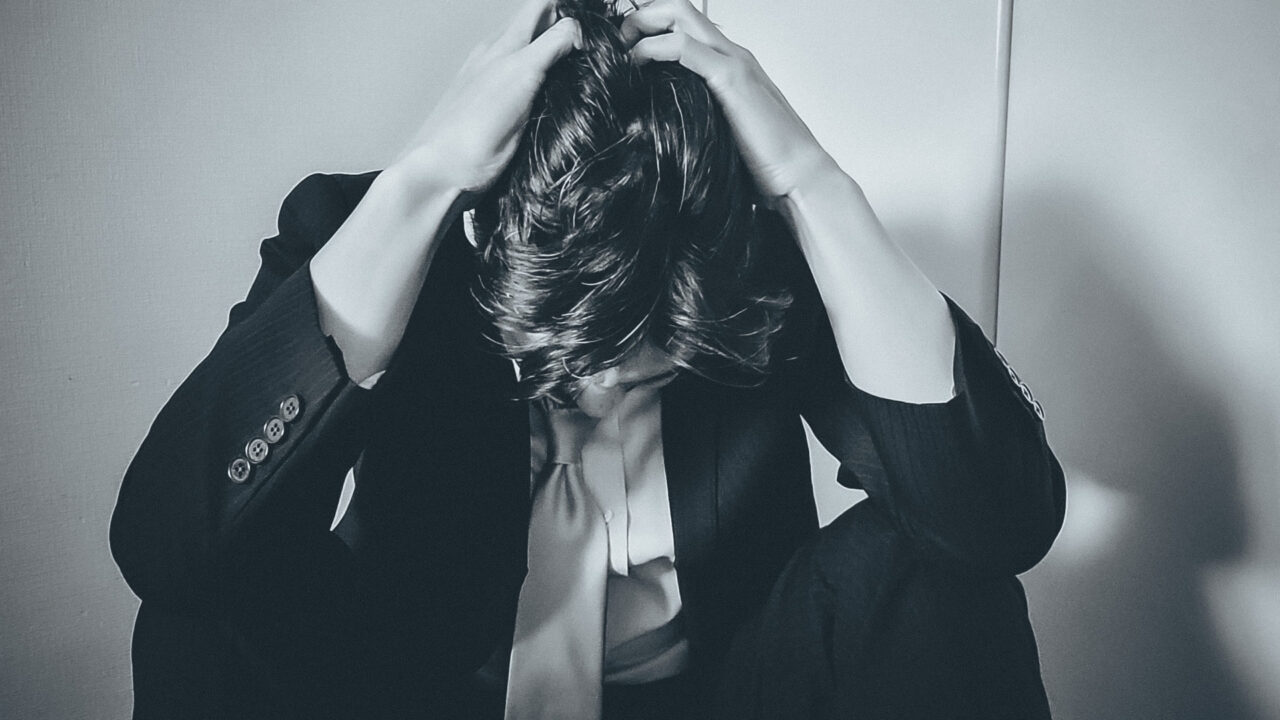









 ランキング1位
ランキング1位 
 ランキング2位
ランキング2位 
 ランキング3位
ランキング3位 