2025年7月15日、株式会社リーディングマークによって開催された「ミキワメユニバーシティ プレミアムサミット in Osaka 2025」において、「挑戦と幸福は、共存できるのか? ~抜擢とウェルビーイングが両立する組織基盤のつくり方~」と題したトークセッションを実施しました。講演要旨は次のとおりです。
| ■登壇者 ・曽山 哲人 氏(株式会社サイバーエージェント 常務執行役員 CHO) ・藤本 宏樹 氏(住友生命保険相互会社 常務執行役員 兼 新規ビジネス企画部長) ■モデレーター ・飯⽥ 悠司氏(株式会社リーディングマーク 代表取締役社⻑) |
「安心×挑戦」が生むウェルビーイングな職場
曽山:私が行き着いた結論は、「まず安心できる環境があって、その上に挑戦の機会があること」こそが最強だということです。
サイバーエージェントでは「実力主義型終身雇用」という考え方を掲げています。これは「働く限り、長く一緒に活躍してほしい」という前提のもと、若手であっても実力があれば積極的に引き上げていく思想です。
この考えに基づき、「挑戦と安心はセット」というテーマを社内ブログで発信したところ、「まさにこういう環境を求めていた」という社員からの反響が多数寄せられました。言葉にしたからには、挑戦の場と安心できる環境、その両方を整える覚悟を持って動く必要がある。そう強く感じた瞬間でした。

登壇者:株式会社サイバーエージェント 曽山 哲人 氏
どちらかに偏る組織が抱える限界
曽山:実際、世の中には「どちらかに偏った組織」が少なくありません。例えば、福利厚生は充実しているものの、新規事業のコンテストが形骸化している企業。逆に、急成長して挑戦は盛んでも、社内がギスギスして不安感が強く、長く続かない企業。
ウェルビーイングを実現するには、やはり「安心できる環境」が不可欠です。瞬間的に業績を伸ばすことはできても、永続的な成長を目指すなら「安心と挑戦」の両立が欠かせない。これが今の私の結論です。
「安心」と「挑戦」の前に立ちはだかるカルチャーギャップ
ー 「安心」と「挑戦」の両立について、藤本さんはどのようにお考えでしょうか?
藤本:私は「安心」と「挑戦」は両立できるものだと思っています。ただ、私たちの場合、その前段階で解決すべき大きな課題があります。住友生命は戦後の成長期に中小企業的なカルチャーを色濃く残した会社です。そうした背景もあり、「我々の価値観は何か?」という問いを投げかけると、管理職からは必ず「経営理念の実現」という答えが返ってきます。
一方で、従業員アンケートを取ると、現場社員からは「誠実さ」や「真面目さ」という回答が非常に多い。つまり、マネジメント層と現場社員との間には、明確な“カルチャーギャップ”が存在するのです。
もちろん、お客様に対して誠実かつ真面目に仕事をすることと、チャレンジする姿勢は両立できるはずです。しかし、このカルチャーギャップのせいで、一部の現場社員は「チャレンジ=誠実さの否定」と感じてしまう場合があるのです。
「真面目さ」と「挑戦」をつなぐ鍵は“安心感”
藤本:サイバーエージェントさんのような企業には、チャレンジ精神が旺盛な方が多いと思います。一方で、私たちのように「真面目で誠実な人」が多い職場では、「どうやってチャレンジを促すか」が本当に難しい課題です。
その鍵になるのが、まさに“安心”です。例えば、失敗しても「罰を受けない」という安心感。これは制度として担保しておく必要があります。
当社にも「新規事業チャレンジ制度」があり、希望者は最長2年間、新規事業に取り組むことができます。しかし、新規事業の成功確率は決して高くありません。実際、2年間チャレンジしても失敗に終わるケースの方が多いのが現状です。
そうなると、次の配属先を社員は当然気にします。もしそのタイミングで「あいつ、どこかに飛ばされたな…」と周囲から見られるようでは、誰も挑戦しようとは思わなくなります。だからこそ、「失敗しても罰せられない」「次のキャリアにきちんと繋がっていく」という制度設計が欠かせません。
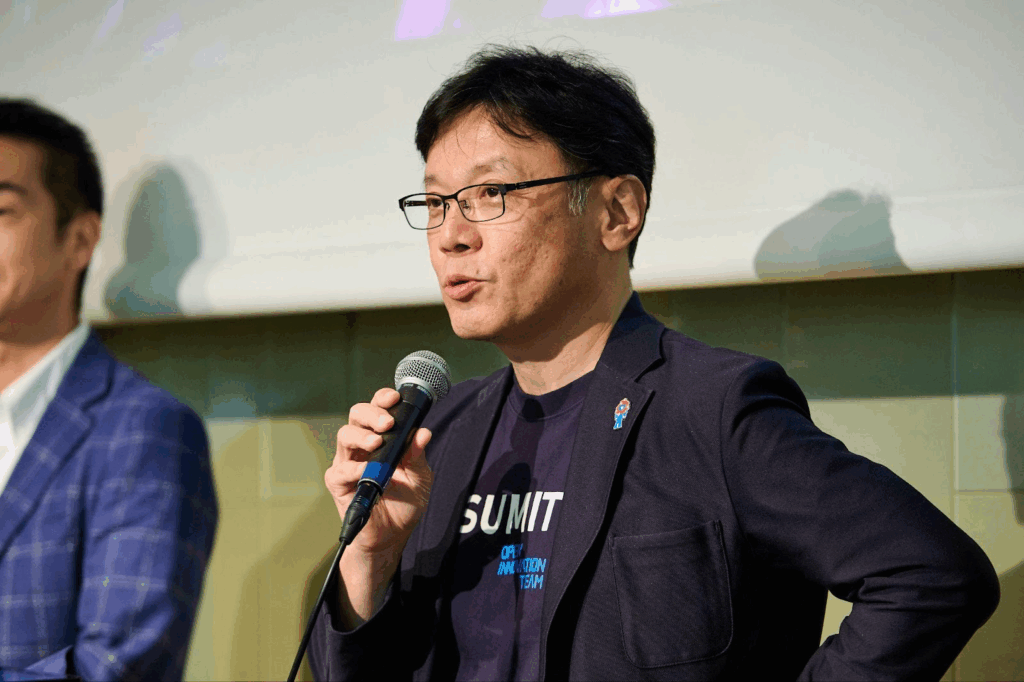
登壇者:住友生命保険相互会社 藤本 宏樹 氏
内向きから外向きへ 〜「ウェルビーイング経営」の進化〜
藤本:私たちが考える「ウェルビーイング経営」は、健康経営、人的資本経営、D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)といったテーマをすべて包括するものです。
従来のウェルビーイング経営は、どちらかというと「内向き」の発想が強いと感じています。つまり、「自社の従業員をウェルビーイングな状態にすることで、エンゲージメントが高まり、生産性が上がる」という考え方です。もちろん、それ自体は非常に重要です。
しかし、私たちが目指すのはそれだけではありません。ウェルビーイング経営が社会全体に広がるのであれば、それに伴って「ウェルビーイング・ビジネス」も確実に広がるはずです。だからこそ、私たちはこの分野を積極的に推進し、新たな事業価値を生み出していきたいと考えています。
その取り組みの中核となるキーワードが、「ウェルビーイング・トランスフォーメーション」です。
ウェルビーイング・トランスフォーメーションとは何か
藤本:ウェルビーイング・トランスフォーメーションとは、あらゆる産業を“生活者のウェルビーイング”という視点でアップデートし、その結果としてビジネスの裾野を広げていくという理念です。
例えば、従来の「病院」は患者に向けたサービスが中心でした。しかし、生活者のウェルビーイングという視点で捉え直せば、来院前の予防、来院後の健康管理、自宅での健康支援など、多様な領域へと事業を拡張できます。
これは生命保険にも当てはまります。従来の「リスクに備える」だけの発想から、「リスクを減らす」発想へシフトしていく。これがウェルビーイング・トランスフォーメーションの考え方です。

安心を基盤に挑戦を促す 〜最初の一歩はどこから?〜
ー 安心しながらも挑戦できる組織をつくるために、最初の一歩として取り組めることは何でしょうか?
曽山:私がおすすめしたいのは、IMD(国際経営開発研究所)の教授が書かれた『セキュアベース・リーダーシップ』という本です。この本は、「心理的安全性」という概念が誤解されがちな現状を踏まえ、その正しい理解と実践方法を示しています。
「セキュアベース」とは、「安心の基盤」や「安全基地」という意味です。この基盤がしっかりと築かれてこそ、人は初めて安心して挑戦に踏み出せる。本書は、その原則を理論と事例で解き明かしています。
セキュアベースを支える「2つの絆」
曽山:「セキュアベース」をどう築くのかというと、鍵になるのは「2つの絆」です。少し日本語としては直訳感がありますが、あえて原語のままお伝えします。
1つ目は 「人との絆」。これはイメージしやすいでしょう。上司や同僚、仲間との信頼関係がしっかり築けていることが、日々の安心感につながります。
2つ目は 「目標との絆」。自分が何を目指すべきか、その方向性が明確であり、その目標が会社のビジョンやパーパスと結びつき、社会的意義を感じられることが大切です。
身体・経済・精神・社会という4つのウェルビーイングの中でも、この「社会的意義」へのつながりは特に重要だと感じます。
最後に
ー 最後に一言メッセージをお願いします。
曽山:私にとって「ウェルビーイング」とは、企業やビジネスの文脈では「働きがい」を意味します。ただし、この「働きがい」は感情であり、あくまで本人が感じ取るもので、外から直接与えることはできません。だからこそ、私たちができるのは、その感情に寄り添うことです。
具体的には、相手を想像し、共感し、労いや称賛、承認を通じて「認めること」。この”想像することと認めること”の2つは、働く人の心にしっかり届く大切な要素です。
もしこれが欠けてしまえば、人は「自分は見られていない」「認められていない」と感じ、関係性が希薄になります。だからこそ、すべての企業がこの姿勢を持って取り組むことで、より良好な関係性を築く組織が増えていくはずです。
これからも皆さんと一緒にウェルビーイングを広げ、盛り上げていければと思います。












 ランキング1位
ランキング1位 
 ランキング2位
ランキング2位 
 ランキング3位
ランキング3位 