組織レジリエンスとは、企業が予期せぬ変化や不測のトラブルに対して柔軟に対応し、迅速に回復・適応していく力です。
自然災害や感染症、急速な社会変化や市場環境の激変など、企業は今、かつてないレベルの「不確実性」にさらされています。
本記事では、組織レジリエンスが注目される背景や、高めるための具体的な方法、実際の企業事例などを解説します。
離職率の高さや組織全体の生産性の低さに悩んでいる企業にとって「逆境に強いチームづくり」に役立つツールもご紹介するため、参考にしてください。

組織レジリエンスとは?レジリエンスとの違いについて
組織レジリエンスとは、レジリエンスの概念を個人ではなく組織運営へ適用させた考え方です。
レジリエンスとは、回復力や弾力(弾性=しなやかさ)、抵抗力などを意味する言葉で、困難な状況やストレスを乗り越えて立ち直る力や折れない心を指します。
たとえば「失敗しても前向きに切り替えて次に活かせる」「ストレスがかかっても休職や退職に至らず、自ら課題解決に取り組む」といった力がレジリエンスです。
組織レジリエンスの場合、個人ではなく「組織(企業)全体」が困難や予期せぬ変化に対して柔軟に対応し、迅速に回復・適応していく力を指します。
自然災害やパンデミック、経営危機や離職の連鎖など、企業を取り巻くリスクは年々多様化・複雑化しており、適切な対応ができるかどうかは組織レジリエンスの高さに大きく左右されます。
組織レジリエンスがビジネスで注目される背景
組織レジリエンスが注目される理由として、ビジネス環境の急激な変化や感染症・自然災害といった予測困難なリスクの影響が深刻化していることが挙げられます。
たとえば、生成AIの登場により、情報流通のスピードが格段に上がった一方で、従来の業務が不要になるケースや、人材の再配置・再教育を迫られる状況が増えています。
また、新型コロナウイルスによるパンデミックでは、多くの企業がリモートワーク導入やサプライチェーンの見直しなど、短期間での大幅な対応を求められました。
とくに日本は外国と比べて自然災害が多く、今後も地震や台風といった自然災害による不測の事態が発生する可能性があります。
こうした状況下で注目されているのが「VUCA時代」というキーワードです。
VUCAとは、Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取った言葉で、現代の経営環境の複雑さと不透明さを表しています。
VUCA時代に企業が生き残るためには、従来のリスクマネジメントに加え、組織レジリエンスを高めることで外部環境の変化に対し、チーム全体が柔軟に対応・復元できる力を身につけることが重要です。
組織レジリエンスが高いチームの特徴
組織レジリエンスが高いチームには次のような特徴が見られます。
- 外部環境の変化に対して臨機応変な対応ができる
- 心理的安全性が保たれている
- 目標達成率や生産性が高い
- 離職率が低く人材が定着しやすい
それぞれ解説します。
外部環境の変化に対して臨機応変な対応ができる
組織レジリエンスが高いチームは、急激な外部環境の変化や突発的なトラブルが発生しても、臨機応変に対応できます。
たとえば、生成AIの普及やDX推進に伴う業務構造の変化、あるいは自然災害・パンデミックといった不測の事態に見舞われた際にも、一人ひとりのメンバーが冷静に状況を見極め、既存のルールや体制を柔軟に見直しながら、最適な行動をとることが可能です。
このような実行力と柔軟性が備わっていれば、業務の継続性(BCP)を確保しやすくなり、企業の信頼性や競争優位性の維持にもつながります。
変化やリスクが常態化するVUCA時代においては、スピーディーな意思決定と柔軟な対応こそが、組織の生存戦略の鍵を握るといえるでしょう。
心理的安全性が保たれている
組織レジリエンスが高い組織は心理的安全性が高く保たれています。
心理的安全性とは、チーム内で「自分の意見を率直に言っても否定されない」「ミスや失敗を責められない」と安心して思える状態です。
この安心感があることで、メンバーは変化やトラブル時にも萎縮せず、積極的に意見を出し合ったり課題解決に協力したりできます。
たとえば、新しい業務フローに適応する際や、トラブル発生時の改善提案なども、心理的安全性の高い組織ではスムーズに共有されやすくなります。
こうした対話のしやすさ・相談のしやすさは、組織レジリエンスの土台を支える要素といえるでしょう。
目標達成率や生産性が高い
レジリエンスの高い組織では、メンバーが困難に直面してもあきらめず、主体的に課題解決へ向かっていける雰囲気が醸成されています。目標達成に向けた実行力が高いため、結果として生産性も高くなる点が特徴です。
たとえば、計画どおりに進まない場面でも「どうすればうまくいくか」と自ら工夫する姿勢があるチームでは、ただ業務をこなすのではなく、成果につながる工夫や改善が自然と生まれます。
さらに、目標設定の背景や意義が共有されていれば、メンバーのモチベーションが高く維持されやすく、新たな価値創造やイノベーションにもつながるでしょう。
こうした文化が根づいた組織は、短期的な成果だけではなく、中長期的にも安定したパフォーマンスを発揮できます。
離職率が低く人材が定着しやすい
組織レジリエンスの高いチームでは、離職率が低く、人材が定着しやすい特徴があります。
心理的安全性や柔軟な働き方を尊重する組織文化が根づいていると、結果として従業員のエンゲージメントが高まりやすく、多様な人材が活躍できる「ダイバーシティマネジメント」も機能するためです。
変化の激しいビジネス環境下でも、社員が安心して意見を言える風土があれば、不安や孤立感を抱えにくくなるでしょう。
また、年齢・性別・国籍・働き方などに関係なく、多様な人材がそれぞれの強みを発揮できる環境では、組織への帰属意識や貢献意欲が高まります。
その結果、働くことへの納得感や意味づけが強化され、短期的な不満やストレスによる離職を防ぎやすくなります。
社員の多様性を受け入れ、エンゲージメントを高める柔軟な組織文化こそが、離職率の低下につながる持続可能な組織運営を支えているのです。
組織レジリエンスを高める方法
組織レジリエンスを高める方法としては、次の5つが挙げられます。
- ミッション・ビジョン・バリューを明確化し浸透させる
- BCPを策定する
- 社員に裁量権を与える
- 安心して発言・相談できる職場環境を整える
- レジリエンス研修を実施する
それぞれ解説します。
ミッション・ビジョン・バリューを明確化し浸透させる
組織レジリエンスを高めるためには、ミッション・ビジョン・バリューを明確化し、浸透させることが重要です。
ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)とは、企業が掲げる使命(Mission)、目指す将来像(Vision)、行動指針となる価値観(Values)を指します。
リクルートマネジメントソリューションズでは、MVVを「理念や価値観を日常業務でどのように実践するかを定めたもの」とし、社員が従うべき行動の軸と位置づけています。
出典:ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)とは? その意味とそれぞれの関係性を紹介
MVVが浸透している組織では、メンバーの一人ひとりに「なぜこの仕事をするのか」「自分たちは社会にどう貢献しているのか」という意識が根づくため、急な方針変更やトラブルが発生した際にもブレずに対応できます。
MVVを明確化・浸透させるには、定期的な1on1や全社ミーティングで自社のMVVを繰り返し言語化する、行動指針を評価指標に組み込む、MVVに基づいた成功事例を全社で共有するといった取り組みが効果的です。
MVVと混同されやすい「パーパス経営」については以下で詳しく解説しています。
BCPを策定する
不測の事態に備えてBCP(事業継続計画)を策定することは、組織レジリエンスを高めるうえで重要なステップです。
計画があれば、緊急時に「何を守るべきか」「どの業務を優先的に継続させるか」が明確になるため、混乱を最小限に抑えられます。
たとえば、地震・水害・感染症などの災害に見舞われた際、BCPに基づいて対応すれば、社員の安全確保・業務復旧・顧客対応などを迅速かつ効率的に進めることが可能です。
BCPの具体的な策定手順は次のとおりです。
- リスクの洗い出しと影響度の分析をする:自然災害やシステム障害など、組織にとって脅威となりうる事象を洗い出し、業務への影響度を評価します
- 重要業務とリソースを特定する:事業の根幹をなす業務と、それを支える人・設備・システムを明確にします
- 復旧手順を設計する:業務停止時における対応フロー、代替手段、優先順位、復旧までの時間目標(RTO)を定めます
- 訓練・見直しを実施する:定期的にBCP訓練を実施し、実行可能性や現実とのズレを検証しながら改善を重ねます
このようにBCPの策定と運用ができている組織は、突発的なリスクに直面しても冷静に対処し、事業を止めない力を発揮できます。
結果として、ステークホルダーからの信頼性向上やレピュテーションリスクの低減にもつながります。
社員に裁量権を与える
組織レジリエンスの向上には、社員一人ひとりに適切な裁量権を与えることも有効です。
トップダウンの意思決定に頼りすぎると、変化の激しい場面で判断が遅れ、対応が後手に回ってしまうおそれがあります。
たとえば、地震や台風などの自然災害が発生した際、社員があらかじめ定められた範囲で判断・行動できるようになっていれば、上司の指示を待たずに安全確保や顧客への連絡、業務フローの一時的な見直しといった初動対応を迅速におこなえます。
実際に物流企業や小売チェーンでは、災害時に現場スタッフの判断で配送ルートを変更したり、避難誘導をおこなったりするケースも多く、被害の拡大を防ぐうえで効果的です。
また、裁量の付与はこうした変化に対応する力を高めるだけではなく、社員一人ひとりの責任感ややりがいにも直結するため、従業員エンゲージメントや主体性の向上につながります。
安心して発言・相談できる職場環境を整える
組織レジリエンスを高めるには、安心して発言・相談できる職場環境を整え、心理的安全性を確保することが重要です。
「こんな提案をしても大丈夫」「困ったときは相談してもいい」と感じられる組織では、ミスや違和感を早期に共有でき、結果として大きなリスク回避につながります。
また、多様な意見が尊重される組織はチームの結束力が強く、イノベーションが起こりやすいというメリットもあります。
具体的には、次のような取り組みを通じて、誰もが安心して発言・相談できる職場環境を構築しましょう。
- 1on1ミーティングやチームレビューの機会を定期的に設ける
- マネージャーが率先して失敗や課題をオープンに語り、部下の発言のハードルを下げる
- 部下の意見を否定せず受け止める傾聴の姿勢を徹底する
- 社員アンケートやピアボイス(同僚からのフィードバック)などの仕組みを導入し、本音・不満を吸い上げて現場に還元する
- ジェンダー・世代・国籍などの多様性を受け入れるマネジメント方針を明文化する
レジリエンス研修を実施する
レジリエンス研修の導入も、社員のレジリエンス力を高めるのに有効です。
とくに、メンタル面や行動特性にアプローチした研修では、自分自身のストレス耐性や行動パターンを可視化することで、回復力や柔軟性を育むきっかけとなります。
ある企業では、折れ線グラフを用いて自身のストレス推移を可視化し、どのように立ち直ってきたかを振り返るワークを導入しています。参加者からは「自分にも回復できる力があると実感できた」という声が多く寄せられました。
このように、個人の成長を支えるプログラムを導入することが、結果的に組織全体のレジリエンス強化にもつながるのです。
組織レジリエンスの高い企業事例3選
組織レジリエンスを高めることは、企業の持続的成長に欠かせません。
実際に日本国内でも、危機に直面しながらも柔軟な対応力で成長を遂げている企業が存在します。
ここでは、全日本空輸株式会社(ANA)とイーグルバス株式会社、パナソニック株式会社の3社を例に、組織レジリエンスを高める取り組みをご紹介します。
全日本空輸株式会社(ANA)
ANAは、新型コロナウイルスによる航空需要の激減という未曾有の危機のなかで、組織レジリエンスを発揮した代表例です。
CA(客室乗務員)や地上職を異業種に出向させる「シェアリングエコノミー型人材活用」を推進し、雇用維持と企業間連携を同時に実現しました。
加えて、ピンチをチャンスに変える姿勢で貨物事業の強化や新規事業開発にも取り組むなど、多角的なリスク分散をおこなっています。
イーグルバス株式会社
埼玉県川越市を拠点とする中小バス会社・イーグルバスは、小さな会社の大きな挑戦を体現するレジリエンス経営の先駆者です。
同社は運転士不足という構造的課題に対し、定年退職後の再雇用や外国人採用など多様な人材戦略を導入。
さらに、運転手の感情をAIで可視化するシステムを開発し、事故防止と職場改善を同時に図るなど、現場起点のテクノロジー活用にも注力しています。
「地域公共交通を守る」という明確なミッションが社員にも共有されており、危機のたびに柔軟な対応と新たな価値創出につなげています。
パナソニック株式会社
大企業でありながら変化対応力を磨き続けているのがパナソニックです。
同社は2010年代以降、事業の選択と集中を進めるなかで「現場起点の経営」への回帰と意思決定の迅速化を掲げ、グループ内カンパニー制を導入。これにより、変化へのスピード対応と社員の自律性が強化されました。
また、BCP(事業継続計画)にも注力しており、国内外の複数拠点で災害訓練を実施するなど、レジリエンス体制の実装を進めています。
加えて、全社的な「Well-being経営」へのシフトにより、心理的安全性や多様性への配慮が組織文化として浸透しつつあります。
組織レジリエンスを高めて変化に強いチームを作ろう
変化の激しいVUCA時代において、組織の持続的な成長と安定を支える鍵となるのが「組織レジリエンス」です。
突発的なトラブルや環境変化に直面しても、柔軟かつ自律的に対応できるチームづくりが求められており、その基盤となるのが従業員一人ひとりのエンゲージメントの高さです。
エンゲージメントが高い従業員が集まる組織では、メンバーが自ら考え、互いに支え合いながら行動できるため、トラブル時にも迅速かつ柔軟な対応が可能となります。
また、日々取り組む業務の意味や意義が明確になっていることで、急な変化に直面してもブレずに行動できる力が備わります。
『ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ』では、組織全体のエンゲージメントや社員の状態を可視化するだけではなく、社員自身によるセルフマネジメントも支援できるため、組織・個人の両面からレジリエンスを高めるアプローチが可能です。
『ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ』の詳細は以下からご確認ください。
従業員のメンタル状態の定期的な可視化・個々の性格に合わせたアドバイス提供を通じ、離職・休職を防ぐエンゲージメントサーベイ。無料トライアルの詳細は下記から。


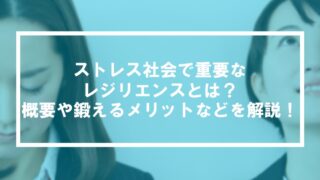
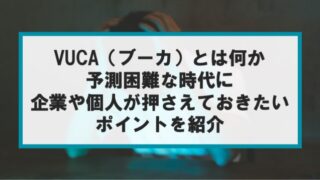


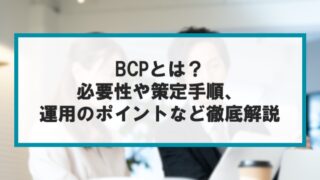










 ランキング1位
ランキング1位 
 ランキング2位
ランキング2位 
 ランキング3位
ランキング3位 