管理職は企業にとって欠くことのできない大黒柱であり、その退職は避けたい事態です。特に、管理職の突然の退職は業務の停滞やチームの士気低下につながり、場合によっては企業の業績にまで影響を与えます。
重要な人材を失わないためには、職場環境の見直しやコミュニケーションの活性化、早めのケアと適切なマネジメントなどにより、管理職が安心して能力を発揮し続けられる組織づくりを目指していくことが肝要です。
今回は、管理職の退職が「やばい」と言われる理由や、管理職が退職を希望する原因、予防・対応策について解説します。
管理職の退職がやばいとされる理由|企業に与えるダメージとは?
管理職の退職は単なる一社員の離職以上のダメージを企業にもたらすため「やばい」と言われることがあります。
管理職の退職が企業に与えるダメージの例は次のとおりです。
- 業務が停滞しプロジェクトの進行が遅れる
- 現場が混乱し離職ドミノが起こる
- 会社の評価が下がる
- 顧客対応に影響が出る
- 後任の採用・育成にコストがかかる
- 外部へ機密情報やノウハウが流出する
ここからは、管理職の退職が「やばい」といわれる理由を、企業に与える影響にフォーカスして具体的に解説します。
業務が停滞しプロジェクトの進行が遅れる
管理職が抜けると、そのポジションが一時的に空白となり、意思決定の遅れや情報伝達の滞りが発生します。
重要な会議の進行や決裁が止まって現場が混乱し、生産性の低下によって業績悪化に直結しかねません。
また、管理職が急に退職した結果、引き継ぎが不十分でプロジェクトの進行が大幅に遅れるケースもあります。
現場が混乱し離職ドミノが起こる
優秀な上司や管理職が突然辞めると、残された部下やチームメンバーの不安は一気に高まります。
「この会社は大丈夫なのか?」「上司が見切りをつけたのだから、自分も転職を考えるべきかもしれない」といった心理が広がりやすく、連鎖的な退職、いわゆる離職ドミノが発生するリスクが高まります。
こうした社内の動揺は組織の安定性を大きく損ね、結果としてさらなる人材流出を招きかねません。
会社の評価が下がる
管理職の退職は社内だけではなく、社外の関係者にも影響を及ぼします。取引先や株主からは「優秀な管理職が相次いで辞める会社は将来性に不安がある」と見られ、信用低下につながるおそれがあります。
特に顧客や外部パートナーは、担当管理職との信頼関係に依存しているケースが多く、その人材が辞めると「この会社は内部で問題を抱えているのでは」と疑念を持たれる可能性もあります。
顧客対応に影響が出る
長年築いてきた取引先との信頼関係が、管理職の退職によって断たれるおそれがあります。
たとえば、営業部門の管理職がライバル企業に転職した場合、顧客がそちらに流れてしまい、取引に影響が出る可能性があります。
顧客から「最近対応が遅いが大丈夫か?」と不信感を持たれると、最悪の場合取引停止や売上減少にもつながりかねません。
後任の採用・育成にコストがかかる
管理職の穴を埋める後任を探すのは容易ではなく、急な退職ほど人材確保が難航します。新任管理職の採用や育成には時間と費用がかかり、その間の組織力低下も避けられません。
特に近年では理職になりたがらない人も多く、後任探しがより困難な状況です。実際、厚生労働省の調査では6割超の社員が「管理職になりたくない」と回答しています。
また、優秀な人材ほど他社から魅力的なオファーが来やすいため、後任候補の確保には一層の苦労を伴います。
出典:厚生労働省「第2-(3)-27図 役職に就いていない職員等における管理職への昇進希望等について」
外部へ機密情報やノウハウが流出する
管理職が退職して競合他社に転職すると、在職中に得た重要なノウハウや人脈が流出するリスクがあります。
特に、引き抜きや競業避止義務違反が絡むと、会社の営業秘密が漏洩し、業務上の大きな損失につながるおそれがあるでしょう。
場合によっては、退職した管理職に対して損害賠償の請求を検討せざるを得ない深刻な事態に発展します。
管理者が退職を検討する原因
管理職クラスの社員が「辞めたい」と感じる背景には、しばしば会社側にも改善余地のある要因が存在します。
「なぜ管理者が辞意を抱くのか」を正しく理解することで、前兆を見逃さずに離職を食い止めるヒントを得られます。主な原因は以下のとおりです。
- 長時間労働が続く、激務である
- 責任やプレッシャーが重い
- 正当な評価や報酬を得られていない
- 部下やチームのマネジメントが難しい
- 会社や経営層と方向性・価値観が異なる
- 自身のキャリアに不安を覚えた
それぞれ解説します。
長時間労働が続く、激務である
管理職になると業務量が膨大になり、残業や休日対応が常態化しがちです。部下のマネジメントや他部署との調整、会議への出席など多くのタスクを同時並行でこなす必要があり、突発的なトラブル対応にも追われます。
その結果、プライベートの時間が削られ心身ともに疲弊して「これ以上は続けられない」と限界を感じ退職を考えるケースが少なくありません。
休日や終業後の呼び出しが頻発し、家族との時間も取れない状態が続けば「人生が仕事だけになってしまう」という不満が高まり、健康リスクも増大します。
実際に管理職を対象とした慶應義塾大学の調査・分析では、管理職に昇進しても主観的な幸福度は上がらず、反対に主観的な健康度が下がる傾向があることがわかっています。
女性では管理職に昇進した2年後、男性では管理職に昇進した1年後以降に、主観的健康度が悪化していました。
出典:管理職での就業は主観的厚生と健康にどのような影響を及ぼしたのか | 慶應義塾大学 パネルデータ設計・解析センター
責任やプレッシャーが重い
管理職には常に高い目標達成プレッシャーがのしかかり、失敗の許されない重責によって精神的に追い詰められることがあります。
経営層からは厳しく数字目標を求められる一方で、部下の育成や成果も自分の責任という板挟みです。
日々の判断一つひとつに重圧がかかる環境で、心が押し潰されそうになり退職を選ぶ管理職も珍しくありません。
実際に「常に結果を出し続けろ」というプレッシャーに耐えかねて心身のバランスを崩し、休職や退職に至る例も見られます。
正当な評価や報酬を得られていない
責任や業務負荷が増えたにもかかわらず、それに見合う給与・待遇を得られないと、管理職は「報われていない」という不満を抱きます。
たとえば、長年の功績が正当に評価されなかったり、他社より明らかに低い報酬水準だったりするとモチベーションは大きく低下します。
不公平感が募ると経営方針への不信にもつながり、やがて「今の会社では自分の価値に見合う待遇は望めない」と転職を検討し始めるでしょう。
実力のある管理職ほど、自分の市場価値を正当に評価してくれる環境を求めて他社へ流出しやすくなります。
部下やチームのマネジメントが難しい
人を率いる難しさに直面し、悩みを抱えるケースもあります。管理職はチーム全体をまとめて成果を出す役割を持ちますが、実際には部下指導・モチベーション管理・評価運用・メンタルケアまで幅広い対応が求められます。
多様な価値観を持つ部下一人ひとりに向き合うには、膨大な時間と労力が必要です。十分な研修もなく管理職に就いた場合、どう部下を導けばよいかわからず苦しむことになります。
思うようにチームを機能させられない無力感から「自分には管理職は向いていない」と感じて辞意を固めてしまうこともあるでしょう。
会社や経営層と方向性・価値観が異なる
会社の経営方針や企業文化に共感できない管理職は、次第に仕事への意欲を失っていきます。
特に、トップダウン色が強すぎて現場の声が届かない組織では、管理職が「自分の存在意義は何か」と疑問を抱きやすくなります。
経営陣との価値観のズレや意思疎通不足により不信感が募り、「この会社でやりたいことができない」と感じて転職を決意するケースも少なくありません。
企業理念やビジョンの共有不足も一因で、「自分の大切にする価値観が理解されていない」と感じると現職に見切りをつけやすくなります。
自身のキャリアに不安を覚えた
管理職まで昇進したあとのキャリアパスを描けず、将来に不安を感じる場合もあります。組織にいても成長の機会が提供されなかったり、「この先のゴールが見えない」と感じたりすると転職を考え始めます。
年功序列でポストが詰まっていたり、実力を発揮してもさらなる昇進機会がない環境では、向上心のある管理職ほど物足りなさを感じるでしょう。
「今の会社にいても将来の展望が持てない」と判断すれば、管理職はキャリアアップや新たな挑戦を求めて会社を去っていきます。
管理職の退職を防ぐ対策
管理職の突然の退職を防ぐためには、日頃からの働きかけと職場環境の整備が不可欠です。
早期の兆候を見逃さず手を打つことで、貴重な人材の流出を食い止められます。企業が取り組むべき具体的な対策は次のとおりです。
- 業務の負担を軽減する
- 定期面談やヒアリングをおこなう
- 評価制度・待遇を見直す
- 経営層とのコミュニケーションを活性化する
- 管理者向け研修・キャリア支援ををおこなう
これらの対策を組み合わせて講じることで、管理職が「辞めたい」と思う前に手を打ち、モチベーション維持と離職予防につなげられるでしょう。
それぞれの対策について具体的に解説します。
業務の負担を軽減する
管理職にばかり業務が集中している場合は、人員配置の見直しや事務作業の効率化を図り、ワークライフバランスを改善しましょう。慢性的な人手不足や過度な長時間労働は管理職を疲弊させ、離職を招きます。
残業削減や有給休暇の取得推進など働き方改革を進め、無理なく成果を出せる体制を整えることが重要です。
たとえば、チームで業務をシェアしたり、権限委譲によって管理職の過負荷を解消したりすれば、心身の負担軽減につながります。
定期面談やヒアリングをおこなう
1on1面談やアンケートを定期的に実施し、本音や悩みを吸い上げる仕組みをつくることも、管理職の退職を防ぐ対策の一つです。
実際に株式会社リーディングマークの調査では、大規模企業の人事担当者の76.9%が「定期的な1on1面談の実施」を若手社員の離職対策として挙げています。
管理職に対しても定期的に面談を設けることで、現場で感じている業務上の不満・ストレスを早期に把握し、必要なサポートを提供できます。
以下の記事では、社員の性格や心理状態を踏まえた対話ができる『ミキワメAI マネジメント』について詳しく解説しています。ミキワメAIは、社員の成長と成果を最大化する仕組みを構築できる1on1ツールです。
「部下と効果的な1on1ができていない」と悩んでいる人事担当者の方は、ぜひ確認してみてください。

評価制度・待遇を見直す
管理職本人が納得できる公正な評価・報酬制度を整えることも離職防止に効果的です。
業績や成果に見合った昇給・賞与、役職手当を用意し、「頑張り損」を感じさせないようにします。不透明で不公平感のある評価体系は、優秀な管理職ほど会社に見切りをつける原因となります。
定量的・定性的な評価基準を明確にし、フィードバック面談で評価理由を丁寧に伝える運用が大切です。また、他社水準と比べて極端に見劣りする待遇であれば、市場相場に合わせた是正も検討しましょう。
適正な評価と処遇によって管理職に「ここで働き続ければ報われる」という安心感を持ってもらうことが狙いです。
経営層とのコミュニケーションを活性化する
経営判断がトップダウン一辺倒にならないよう、経営陣と管理職が双方向に意見交換できる機会を増やすのも、管理職の退職を防ぐ方法として有効です。
経営会議の内容を共有したり、管理職から現場課題を提言する場を設けたりすることで、管理者側に「会社を一緒に良くしている」という実感を持ってもらいましょう。
また、経営層も現場の声に真摯に耳を傾け、必要な支援を速やかにおこなう姿勢を示すことが重要です。
質の高い対話で離職リスクを減らすためには、『ミキワメAI マネジメント』のようなコミュニケーション支援ツールの活用がおすすめ。『ミキワメAI マネジメント』は、社員の性格・心理状態のデータをもとにAIが適切な1on1の話題やネクストアクションを提案します。
このようなデータとAIに裏付けされたツールを活用すれば、従来は見逃しがちな管理職の不安サインも早期に察知でき、フォロー体制を強化できます。
管理者向け研修・キャリア支援ををおこなう
管理職として成長できる環境づくりも大切です。
マネジメントスキル向上の研修やコーチング、他社事例を学ぶ機会を提供して、自信と能力を高めてもらいます。必要な研修を受けずに管理業務を任され戸惑っているケースでは、基礎から学び直す機会が有効です。
また、将来のキャリアパスについて上司と話し合う場を設け、中長期的なビジョンを描けるよう支援します。「数年後には〇〇部長を任せたい」「将来的に経営層に加わってほしい」など具体的な期待や計画を伝えることで、管理職本人のキャリア不安を和らげられます。
管理職が将来に希望を持てるよう、社内公募制度やジョブローテーションで新たな挑戦の場を用意することも有効でしょう。
管理者から突然退職を申し出られた際の対応
万が一、管理職から突然「退職したい」と申し出があった場合でも、適切な対応を取れば企業へのダメージを最小限に抑えることができます。
以下は、管理者の退職が避けられなくなった際に取るべき対応のステップです。
- 退職を希望する理由をヒアリングする
- 実際の退職日を決定する
- 後任の選定をおこなう
- 後任の育成計画を策定する
- 退職まで丁寧なコミュニケーションをはかる
このステップを踏むことで、管理職退職に伴う組織の混乱を最小限に抑えられます。
特に、早期の意思表示と綿密な引き継ぎ計画が肝要であり、退職者・残留メンバー双方に配慮した丁寧な対応を心がけることで、残されたチームの士気低下や業務停滞を防げるでしょう。
ここからは各ステップのポイントを解説します。
1.退職を希望する理由をヒアリングする
まず、管理職本人がなぜ退職を決意したのかを丁寧に聞き出します。個人的な都合なのか、職場の問題や不満によるものなのか、原因を把握しましょう。
ここでのヒアリング内容は、今後の引き留め交渉や社内改善に活かせる貴重な情報源となります。本人の気持ちに寄り添い、決して感情的に責め立てないことが重要です。
2.実際の退職日を決定する
次に、本人の希望を踏まえつつ、会社側と相談して正式な退職日をできるだけ早めに確定します。退職日が不明確なままだと引き継ぎ計画が立てにくく、業務に支障をきたすおそれがあります。
具体的な退職日を設定したうえで、そこから逆算した引き継ぎスケジュールを作成しましょう。
3.後任の選定をおこなう
実際の退職日が決まったら、早急に後任候補を選びましょう。社内の適任者を洗い出し、経験・能力・部下からの信頼などを考慮して後継者を指名します。
後任の選定が遅れると引き継ぎ期間が短くなり、業務に滞りが生じるリスクが高まります。適任者が社内にいない場合は、外部からの採用も検討してください。
なお、早めに「あなたに次を任せたい」と社内発表することで、部下の動揺を和らげる効果も期待できます。
4.後任の育成計画を策定する
新任の管理職がスムーズに業務を引き継いでいけるよう、引き継ぎ期間と教育計画を立てます。可能であれば、退職する管理職と後任者が一定期間一緒に働き、OJT形式でノウハウ伝承するのが理想です。
引き継ぎ完了日までの詳細なスケジュールを作成し、業務マニュアルや顧客情報など必要資料を整理して渡します。
また、必要に応じて管理職研修やコーチングを実施し、新任者が自信を持って役割を遂行できるようサポートしましょう。
5.退職まで丁寧なコミュニケーションをはかる
退職日までの間、辞める管理職とも誠意を持って接し続けます。
引き継ぎ状況の確認や業務フォローだけではなく、労いの言葉をかけることも大切です。円満な退職となるように配慮し、退職後も必要に応じて連絡・相談できる関係を保っておくと安心です。
退職者との良好な関係を維持しておけば、あとから不明点が出た場合でも助言を得られ、急なトラブル対応もスムーズにおこなえます。
最後の勤務日にはこれまでの貢献に感謝を伝え、送り出す姿勢を示しましょう。
管理職の退職で損害賠償請求をおこなうべきケース
一般的に、労働者には退職の自由が保障されており、管理職が辞めることで会社が損害賠償を請求できるケースは多くありません。
しかし、以下のような場合には、例外的に損害賠償請求が検討されます。
- 引き継ぎに一切協力せず退職し重大な損害を与えた
- 競業避止義務や機密保持契約に違反した
- 会社に対して背信的行為をおこなっていた
各ケースについて解説します。
引き継ぎに一切協力せず退職し重大な損害を与えた
管理職が何の引き継ぎもおこなわずに突然退職し、その結果会社の業務が長期間停止するような深刻な被害が出た場合です。
たとえば、重要プロジェクトが頓挫して多大な損失が発生した場合、会社は「信義則違反による損害」として退職者に賠償を求める可能性があります。
実際に「管理職が引き継ぎをせずに辞めたせいで顧客対応が滞り損害が出た」として訴訟に発展した例もあります。
競業避止義務や機密保持契約に違反した
雇用契約や就業規則で定められた競業避止義務に反し、退職後すぐに競合他社に転職して社内の営業秘密を利用したケースがこれに当たります。
会社の機密情報・ノウハウを持ち出して外部で漏洩・悪用した場合、不正競争防止法違反等で損害賠償請求の対象となり得ます。
退職時に署名した機密保持契約(NDA)に違反して重要データを持ち出した場合も同様です。
会社に対して背信的行為をおこなっていた
退職前に部下や取引先を引き抜いていた、在職中に私的流用や横領など重大な不正行為が発覚したケースでも、損害賠償請求がおこなわれる可能性があります。
これらは単なる退職というよりも在職中の背信行為ですが、結果的に退職に至った際には、会社側が被った損害について法的措置を検討するでしょう。
管理職を適切にマネジメントし突然の退職を未然に防ごう
管理職の退職は、組織全体に深刻な影響を及ぼします。業務停滞による業績悪化、人材流出の連鎖、社内外の信頼低下など、放置すればドミノ倒し的にダメージが広がりかねません。
一方で、多くの場合、管理職が辞める原因には「過度な負担」「評価や待遇への不満」「人間関係の摩擦」「成長実感の欠如」など改善可能な要素が含まれています。
企業側が早期に兆候を察知し、適切な対話と施策を講じれば、突然の退職は未然に防げる可能性があります。
そのためには、普段から管理職のコンディションや意見に気を配り「辞めたいサイン」を見逃さないこと、そして感じている不安や不満に迅速に対処することが不可欠です。
近年では、1on1ミーティングやエンゲージメントサーベイなどの仕組みを活用して、管理職を含む社員の状態を客観的データで把握する企業も増えています。
『ミキワメAI マネジメント』はAIが管理職の離職リスクを早期に察知し、最適なコミュニケーション方法や改善アクションを提案するコミュニケーション支援ツールです。
このようなツールの導入により、属人的な勘や経験だけに頼らず、データとAIの力を借りて管理職を支える体制を構築すれば、離職予防の精度と継続性が格段に高まるでしょう。
従業員のメンタル状態の定期的な可視化・個々の性格に合わせたアドバイス提供を通じ、離職・休職を防ぐエンゲージメントサーベイ。無料トライアルの詳細は下記から。




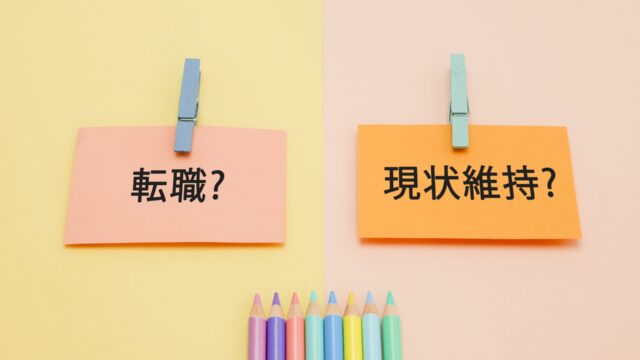







 ランキング1位
ランキング1位 
 ランキング2位
ランキング2位 
 ランキング3位
ランキング3位 