人的資本開示は、株主や顧客、さらには求職者に対して自社の価値を伝えるうえで重要な要素です。
人的資本の評価にはさまざまな指標が用いられますが、なかでも重視されているのが「ウェルビーイング指標」です。
ウェルビーイング指標が高い企業は、社員が安全で快適な環境のもと、生き生きと働いていると見なされるため、企業イメージやブランド価値の向上につながります。
今回の記事では、人的資本開示におけるウェルビーイング指標の重要性やその収集方法を解説します。

人的資本開示とは
人的資本開示とは、人を、そのスキルや経験によって企業活動に利益をもたらす「資本」ととらえ、その人的資本に関する情報を社内外に対して報告・開示することを指します。
人的資本は、モノ・カネ・情報と並ぶ経営資源であり、企業の持続的発展やリスク管理に深くかかわる重要な指標として、世界的に注目を集めています。
日本においても2023年3月期決算より、有価証券報告書を発行している大手企業約4,000社に対し、人的資本の情報開示が義務付けられました。
人的資本開示が求められる7分野19項目
以下にご紹介するのは、内閣府に設置された「非財務情報可視化研究会」が作成した「人的資本可視化設計」において公表された、人的資本開示に関する7分野19項目の指標です。
これらの項目については、すべてを網羅的に開示するよう法令で義務付けられているわけではありません。しかし、自社の強みや特徴を効果的に伝えるために、適切な指標を組み合わせて任意に開示することが推奨されています。
| 分野 | 項目 |
|---|---|
| ①育成 | リーダーシップ |
| 育成 | |
| スキル/経験 | |
| ②従業員エンゲージメント | 従業員エンゲージメント |
| ③流動性 | 採用 |
| 維持 | |
| サクセッション(後継者育成) | |
| ④ダイバーシティ | ダイバーシティ |
| 非差別 | |
| 育児休業 | |
| ⑤健康・安全 | 精神的健康 |
| 身体的健康 | |
| 安全 | |
| ⑥労働慣行 | 労働慣行 |
| 児童労働/強制労働 | |
| 賃金の公正性 | |
| 福利厚生 | |
| 組合との関係 | |
| ⑦コンプライアンス/倫理 | コンプライアンス/倫理 |
人的資本開示を行うメリット
人的資本開示は「社員の働きやすさに対する自社の取り組み」を社内外に発信する行為でもあります。そのため、さまざまな立場のステークホルダーに対して良好な印象を与え、企業の競争力強化や従業員エンゲージメントの向上にもつながります。
具体的なメリットは次のとおりです。
- 投資家・株主からの信頼獲得
- 優秀な人材の確保と採用力の強化
- ブランド価値の向上
- 従業員エンゲージメントの向上
それぞれのメリットについて詳しく解説します。
投資家・株主からの信頼獲得
人的資本開示は、投資家や株主からの信頼を獲得する手段となり得ます。財務諸表や有価証券報告書からは把握しきれない「ヒト」という無形資産の価値を明示することで、企業情報の透明性が高まるためです。
さらに、人的資本開示は、投資家や株主との建設的なコミュニケーションを促進するきっかけにもなります。会議やインタビューなどを通じて、人的資本に関する取り組みについて意見を交わすことで、より深い信頼関係の構築が可能です。
優秀な人材の確保と採用強化
人的資本開示は、企業の採用力強化にも寄与します。人的資本に関する指標は、企業の「働きやすさ」や「将来性」といった要素を可視化する役割を果たすためです。
とくに、福利厚生や人材育成に関する項目は、求職者が企業を選ぶうえで重視するポイントとなります。
これらの情報を適切に開示し、これまでの取り組みや今後の目標をわかりやすく伝えることで、企業の魅力を効果的に発信でき、優秀な人材の確保と採用活動の強化につながります。
ブランド価値の向上
人的資本開示は、自社のブランド価値を高める手段としても有効です。社員の働きやすさや快適な職場環境を重視する姿勢は、顧客や取引先からの好印象につながります。
また、人的資本開示を通じて「社員を大切にする企業」というイメージが広く認知されることで、企業としての信頼性や社会的評価が高まり、ブランド価値の向上にも寄与します。
競合他社との差別化を図り、独自の企業価値を築くうえでも、人的資本開示は重要な役割を果たすでしょう。
従業員のエンゲージメント向上
人的資本開示は、従業員のエンゲージメント向上にも好影響を与えます。開示項目のなかには、人材育成や健康保持といった、社員の幸福度や満足度に直結する要素が数多く含まれているためです。
人的資本開示を通じて、自社が社員を大切にし、成長や働きやすさに配慮している姿勢を示すことで、社員の信頼感が高まり、結果としてエンゲージメントの向上が期待できます。
人的資本開示が義務づけられた背景や重要性については以下の記事をご参考ください。
ウェルビーイング指標とは
ウェルビーイング指標とは、心身の健康、経済的安定、社会的つながりなど、人の幸福度を構成する要素を測定するための指標であり、「幸福の物差し」ともいえる存在です。
人的資本開示においても、こうしたウェルビーイングに関する指標はとくに重要視されています。ウェルビーイング指標の数値が高い企業は「社員の幸福度が高い企業」として評価されやすく、社員が幸福感を持ちながら生き生きと働ける環境が整っていると見なされます。
こうした企業では、生産性の向上や人材の定着率改善が期待できるほか、組織全体の活力も高まります。企業の持続的な成長可能性を測るうえで、ウェルビーイング指標は欠かせない要素です。
ウェルビーイング指標が重要視される理由
先述のとおり、ウェルビーイング指標は企業の持続的成長の可能性を評価するための重要な指標となっています。その理由は以下のとおりです。
- 働き方の多様化に対する取り組みを発信できる
- 生産性の向上に役立つ
- メンタルヘルスへの認識が深まる
- 採用力の強化につながる
詳しく見ていきましょう。
多様な働き方への対応力を示せる
テレワークやフレックスタイム制など、多様な働き方が普及するなか、企業にはあらゆる働き方を選ぶ従業員が公平に働ける環境を整える責任があります。
ウェルビーイング指標は、企業がその環境整備にどのように取り組んでいるかを外部に示す手段として注目されています。
生産性の向上に役立つ
ウェルビーイングの水準が高い職場では、従業員の主体性や創造性が引き出されやすくなります。心身の健康が保たれ、心理的安全性が確保された環境では、従業員が自ら考えて積極的に行動することが促進されるためです。
結果として、チーム内での協働や問題解決の質が高まり、生産性の向上や組織へのエンゲージメント強化が期待できます。
メンタルヘルスへの認識が深まる
従業員のメンタルヘルス不調による休職や離職は、企業にとって見過ごすことのできない重要な経営リスクです。
企業がこのリスクにどう向き合い、健康経営をどのように実践しているのかを示す「可視化された指標」として、ウェルビーイングに関する情報開示は注目を集めています。
こうした取り組みは、企業の持続可能性や組織の健全性を測る判断材料として、投資家からの評価対象にもなりつつあります。
採用力の強化につながる
働きやすさや心理的安全性への関心が高まる現代において、ウェルビーイングへの積極的な取り組みを開示している企業は、優秀な人材にとって魅力的です。
人材の獲得や定着が進み、安定した成長やイノベーションの実現など、経営全体における好循環へとつながります。
このように、ウェルビーイング指標は従業員満足度を測る指標だけではなく、企業のマネジメントの質や価値観を社会に伝える重要な手段にもなり得ます。
そのため、人的資本開示のなかでウェルビーイング指標を積極的に公開する意義は、今後ますます高まっていくでしょう。
人的資本開示において注目されるウェルビーイング指標の具体例
人的資本開示における指標には「社員の働きやすさ」や「幸福度」、すなわちウェルビーイングに関連する項目が多く含まれています。
なかでも、とくに関連性が高いとされる以下の4項目について、具体例や人的資本開示における重要性をご紹介します。
- 従業員エンゲージメント
- 流動性
- ダイバーシティ
- 健康・安全
従業員エンゲージメント
従業員エンゲージメントとは、社員が企業の理念やビジョンにどれだけ共感し、満足感や愛着を持って働いているかを示す指標です。
エンゲージメントの高い社員が多い企業では、生産性や定着率が向上し、経営の安定やイノベーションの創出につながります。また、エンゲージメント向上に積極的に取り組む企業は、社内外からの評価も高まり、ブランドイメージの確立も期待できるでしょう。
主な開示内容としては、エンゲージメントサーベイや従業員満足度調査の結果などが挙げられます。さらに、人的資本に関するほかの情報も、間接的に従業員エンゲージメントを評価する材料となり得ます。
たとえば、多様な価値観が受け入れられている職場(ダイバーシティ)や、心身ともに安心して働ける環境(健康・安全)が整っていれば、社員の帰属意識や意欲は自然と高まるはずです。
こうした相互作用を踏まえた情報開示によって、より深みのある人的資本のストーリーを伝えられます。
流動性
流動性とは、採用や離職といった人員の入れ替わりに関する動きを示す指標です。この分野は、以下の3つの観点に分類されます。
- 採用:新たな人材を確保し、組織に迎え入れる活動
- 維持:既存の社員が長く働き続けられるようにする取り組み
- サクセッション(後継者育成):将来の管理職や重要ポジションに備えて人材を計画的に育成・配置すること
企業の持続的な発展のためには、優秀な人材の確保と育成が不可欠です。現状維持にとどまらず、長期的な視点で人事戦略を構築する姿勢が求められます。
この分野での有効な開示項目には、以下の内容が含まれます。
- 離職率や離職者数
- 定着率
- 新規雇用の比率や人数
- 採用および離職にかかるコスト
- 後継者の有効率・カバー率・準備率※
- 人材の確保・育成に関する施策や方針
※後継者に関する指標について
| 指標 | 内容 | 計算方法 |
|---|---|---|
| 後継者有効率 | 重要ポジションに対する、外部からの採用者に対する内部昇進者の割合 | 社内後継者数 ÷重要ポジションの全後継者総数 × 100% |
| 後継者カバー率 | 総数に対する後継者の平均の数 | 後継候補者数 ÷ 重要ポジション数 × 100% |
| 後継者準備率 | スキルギャップを把握しながらすでに後継者として準備が整っている数 | 【A】すでに準備が整っている後継者の総数÷重要ポジション数 × 100%※【A】は1〜3年に準備が整う後継者数、4〜5年ほどあれば準備が整う後継者数があてはめられる場合もある。 |
ダイバーシティ
ダイバーシティ(多様性)とは、性別、人種、国籍、事情などが異なる多様な人材を受け入れる制度が整備されているかを示す指標であり、以下の3つの観点に分類されます。
- ダイバーシティ(多様性):性別や年齢、国籍、障がいの有無など、多様な人材を受け入れ、活かす考え方
- 非差別:性別や人種などによる不当な扱いをなくし、すべての社員に公平な機会を提供すること
- 育児休業:子育てのために一定期間仕事を休む制度。その取得状況や復職支援も含まれる
とくに、多様性の受容が重視されている現代において、これらの項目に関する開示は「必須」といえるほど注目されています。以下のように具体的な情報の開示により、自社の多様性に対する取り組みを社外にアピールすることが可能です。
- 男女間の給料差
- 育児休暇取得率と男女の比率
- 育児休業後の復職率
- 正社員・非正規社員等の福利厚生の差
- 外国人従業員の構成比
- 障がい者雇用率
- 上記の項目における課題を是正するために企業が講じた措置
健康・安全
社員の健康や安全に関する指標は、以下の3つの観点に分類されます。
- 精神的健康:心の健康状態。ストレスや不安、うつ症状などの有無やその予防・改善のための対策
- 身体的健康:生活習慣や疾病予防、体力維持などを含めた、身体の健全な状態全般
- 安全:職場内での事故や災害から社員を守るための環境や仕組みが整備されている状態
社員の心身の健康と安全を守ることは、企業にとって基本的な責任です。近年では、メンタルヘルス不調による休職・離職の増加が深刻な課題となっており、社員へのメンタルケアに積極的に取り組む姿勢は、企業の持続的な発展に不可欠な要素といえます。
そのため、これらの指標は、投資家や株主にとっても企業の将来性や経営の健全性を判断するうえで重要な評価材料となっています。
社員の健康・安全に関する開示内容例は以下のとおりです。
- 労働災害の発生率・割合・死亡数など
- 欠勤率・休職率・離職率
- 健康診断やストレスチェックの受検率
- 健康・安全に関する研修の実施状況(受講回数や受講率など)
- 喫煙者率
- ハラスメントに関する情報(発生率や対応状況)
- 社員の健康や安全に関する企業の取り組み
ウェルビーイング指標の収集法
ウェルビーイング指標を収集するには、アンケート調査を実施したり、既存データを活用したりする方法があります。
- アンケートやサーベイツールの活用
- 労務データの活用
- 社員の「声」から拾う
それぞれの収集法について詳しく解説します。
アンケートやサーベイツールの活用
アンケートやストレスチェック、健康診断の結果、ウェルビーイングサーベイなどによって、社員の満足度や健康状態を計測し、それらをウェルビーイング指標とする手法があります。
この方法は、収集に大きな手間がかからず、多くの社員からの意見やデータを一元的に集約・分析できる点が特長です。
とくにウェルビーイングサーベイは、心身の健康、職場環境、働きがいといった多角的な要素を網羅的に測定できるため、単なる満足度調査にとどまらず、職場全体の課題や改善ポイントを幅広く可視化するのに適しています。
さらに、取得したデータは一元的に集約・分析できるため、結果をもとにした施策の立案や効果測定を効率的に行える点も大きなメリットです。また、サポートがとくに必要な社員を早期に発見し、適切な対応につなげることで、休職や離職といったリスクを未然に防ぐ効果も期待できます。
一方で、過度な調査は社員の「アンケート疲れ」を引き起こすおそれがあります。そのため、実施頻度や質問内容を精査し、社員の負担とならないような仕組みを工夫することが重要です。
労務データの活用
有給休暇の取得率、時間外労働時間、離職率、勤続年数といった労務データをもとに、ウェルビーイング指標を収集・分析する手法があります。
社内で管理されている既存データを活用するため、社員に回答の負担をかけることなく、効率的に必要な情報を収集できる点が特長です。
しかし、既存の労務データは、あくまで数値の羅列にすぎません。自社の強みや独自性、戦略的な取り組みをステークホルダーに伝えるためには、これらの数値に「意味」や「背景」を持たせることが重要です。
なぜその数値なのか、どのような方針や施策によって実現されたのかといった根拠を示すことで、情報開示に説得力を加えられます。
社員の「声」から拾う
1on1ミーティングや離職面談の内容、社内SNSなどを通じて、社員の意見や要望を収集する手法です。
データの収集や分析に手間がかかり、定量化が難しいという課題はありますが、社員一人ひとりの人的資本情報に「ストーリー性」を持たせる手段として有効です。
アンケートやウェルビーイングサーベイ、労務データなどの定量的な情報と組み合わせることで、より立体感のある人的資本開示を実現できます。
ウェルビーイング指標を開示する際の注意点
ウェルビーイング指標は、単なる「数値」としてとらえ、開示そのものに注力するだけでは十分な意味を持ちません。自社の強みや取り組みを社内外に発信し、企業価値を高めるための「武器」として活用できるものであると理解し、選定や運用方法を慎重に検討することが重要です。
また、ウェルビーイング指標は社員から収集する情報である以上、データの取得や活用にあたっては、社員への配慮も欠かせません。
とくに注意すべき点は以下の3つです。
- 指標を「戦略の伝達手段」として活用する
- 指標に「ストーリー性」を持たせる
- 社員のプライバシーに十分配慮する
詳しく解説します。
指標を「戦略の伝達手段」として活用する
先述のとおり、人的資本開示において使用する指標に法的な定めはありません。そのため、どの数値を開示すれば自社の魅力や強みを的確に伝えられるかを精査することが非常に重要です。
このときに意識すべき視点として「ステークホルダーのニーズ」と「自社独自の企業戦略」の2つが挙げられます。
まず、投資家や顧客、求職者などのステークホルダーが何を重視しているのかを把握し、それに対応するウェルビーイング指標を選定する必要があります。
同時に、競合他社との差別化を図るためには、自社のビジョンや戦略が色濃く反映された独自性のある指標を取り入れることも効果的です。
こうした視点で指標を選ぶことで、単なる数値の羅列にとどまらず、自社の魅力を訴求する「戦略的な情報開示」として機能させられます。
また、指標はできるだけ定量的に整理し、過去との比較や目標とのギャップが一目でわかる形式に整えることも大切です。
指標に「ストーリー」を持たせる
指標は、単体ではあくまで数値に過ぎません。重要なのは、その数値に「ストーリー」を持たせることです。
たとえば、以下のような2社があるとします。
| A社(有給休暇取得率90%)有給休暇取得率を上げるための施策として、休暇取得日を指定し、その日は必ず休暇を取るよう義務付けています。 |
| B社(有給休暇取得率80%)有給休暇取得率を上げるための施策として、結婚記念日や誕生日など、個人にとって意味のある日に休暇を取得することを奨励しています。 たとえ繁忙期であっても、社員同士が業務をサポートできるように、タスク管理ツールや業務引き継ぎマニュアルを活用し、柔軟に代替体制を整える仕組みを導入しています。 |
このように、指標と施策、さらには企業理念との関係性を明確に説明することで、情報開示に説得力を持たせられます。
単なる数値の羅列では、企業の価値を正確に伝えられません。その数値がどのような背景や方針により達成できたのかをあわせて説明しなければ、かえって不信感を招くおそれがあるため注意が必要です。
社員のプライバシーに配慮する
ウェルビーイング指標には個人の健康情報や人事情報などが含まれるため、開示する情報については十分に配慮し、個人情報の流出や誤用を防ぐことが重要です。
指標を活用した改善に向けての具体的なアクション
人的資本開示は、指標を公開すればそれで完了ではありません。開示を通じて得られたステークホルダーからのフィードバックを活用し、企業としての課題を整理し、改善策を具体化していくことが重要です。
とくに、外部の第三者から寄せられる客観的かつ率直な意見は、自社では気づきにくい課題の明確化や、より実効性のある経営戦略の立案に役立つ貴重な情報源となります。
人的資本開示後に企業が取り組むべきアクションは、以下の3つのステップに整理できます。
- フィードバックを収集する
- フィードバックの共有と課題の策定
- 改善サイクルの確立
各ステップについて詳しくご紹介します。
フィードバックを収集する
まずは、人的資本開示の内容に対するステークホルダーからのフィードバックを収集することから始めましょう。フィードバックを得ることで、自社の取り組みがどのように受け止められているかを客観的に把握できます。
具体的な収集方法としては、株主総会や説明会などでの意見交換、投資家や顧客へのインタビュー、社内外向けのアンケート調査などが挙げられます。
フィードバックの共有と課題の策定
収集したフィードバックは、単に蓄積するだけではなく、組織全体で情報を可視化し、意見を交わすプロセスが重要です。
経営層や各部署の管理職、人事部門などの社内関係者と共有し、自社の人的資本に関する課題を洗い出す材料として活用しましょう。
そのうえで、明確になった課題に対しては、具体的な解決策を考えていきます。
たとえば、離職率が高いという課題が見つかった場合、業務負担の見直しやメンタルケアの強化といった施策を検討するなど、課題に応じた対応策を現場と連携しながら練ることが求められます。
改善サイクルの確立
改善策を実行したあとは、再度ウェルビーイング指標を収集し、状況が改善されているかを確認しましょう。その結果を人的資本開示として公開し、さらにフィードバックを受けて次の改善に活かすことで、PDCAサイクルを継続的に回し、企業の持続的な発展を目指します。
こうしたプロセスは、より効果的な経営改善を実現につながるだけではなく、改善に取り組む姿勢そのものが多方面から評価され、ブランディングの構築や従業員エンゲージメントの向上にもつながります。
人的資本開示におけるウェルビーイング指標を把握するためには社員の状態把握が重要
人的資本開示は、無形資産である人的資本の価値を評価し、企業の経営状況や将来性を判断するために重要な制度です。適切な開示を行うことで、社内外のステークホルダーからの信頼を獲得でき、エンゲージメントの向上やブランディングの構築にもつながります。
ウェルビーイング指標に関する情報を収集するには、1on1ミーティングなどを通じた社員との対話、データの分析、ツールを活用した客観的な評価が重要です。
また、得られた指標は人的資本開示に利用するだけでなく、第三者からのフィードバックをもとに、課題の抽出と改善策の策定を行うことも求められます。
こうした指標の把握や改善効果の測定においては、社員のエンゲージメントやメンタルの状態を定量的に評価できる「ミキワメ ウェルビーイングサーベイ」の導入を検討してみてはいかがでしょうか。
興味のある方は、以下より詳細をご覧ください。
従業員のメンタル状態の定期的な可視化・個々の性格に合わせたアドバイス提供を通じ、離職・休職を防ぐエンゲージメントサーベイ。無料トライアルの詳細は下記から。






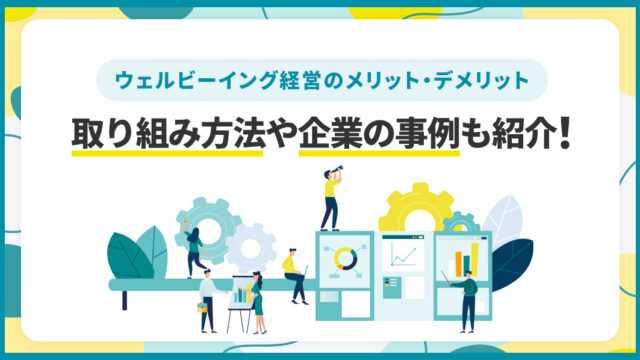

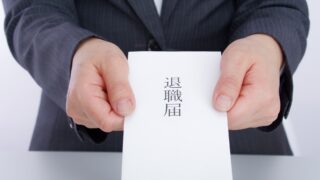




 ランキング1位
ランキング1位 
 ランキング2位
ランキング2位 
 ランキング3位
ランキング3位 