自宅やカフェ、コワーキングスペースなど会社以外の場所で業務を行うリモートワークは、2020年の緊急事態宣言を受け、感染リスクを軽減する手段として多くの企業に導入されました。
現在も、通勤時間や交通費の削減、ワークライフバランスの向上に寄与する働き方として注目されています。
一方で、リモートワークは社員の孤立感や、管理職による過干渉を招き、メンタルヘルスの悪化を引き起こす要因となることも少なくありません。
本記事では、リモートワークに伴うメンタルヘルスの課題と解決策について解説します。

リモートワーク時のメンタルヘルス対策が重要である理由
企業にとって、社員のメンタルヘルスを守ることは重要な人事施策の一つです。メンタル不調による生産性の低下や休職・離職の増加は、業績悪化に直結します。
リモートワークを導入する企業は、とくにメンタルヘルスケアに注力しなければなりません。物理的な距離があることで、社員の様子や労務上の問題を把握しづらく、体調不良の兆候を即座に察知できないケースが多いためです。
その結果、気づかないうちにメンタルの不調が進行し、休職や離職につながるリスクがあります。
こうした背景から、リモートワークにおけるメンタルケアの重要性は広く認識されており、厚生労働省も「テレワークにおけるメンタルヘルス対策のための手引き」を公開するなど、国を挙げた対策が進められています。
リモートワークがメンタルヘルスに与える悪影響
リモートワークがメンタルヘルスに与える悪影響は、以下の3つに大別されます。
- 労働環境上の問題
- 労働時間や業務内容上の問題
- 人間関係上の問題
各項目について詳しくご紹介します。
労働環境上の問題
リモートワークにおける課題の一つに、労働環境の問題があります。自宅やカフェなど、オフィスとは異なる環境で業務を行うため、照明や空調、騒音、家具の使い勝手といった点で劣る場合も多く、それがストレスの原因となることがあります。
以下で具体例を見ていきましょう。
仕事とプライベートの切り替えが難しい
リモートワークにおける労働環境の大きな課題として「仕事とプライベートの切り替えが難しい」点が挙げられます。
とくに自宅で業務を行う場合、家族に話しかけられたり、訪問者が来たりすることで、仕事と私生活の境界があいまいになりがちです。その結果、気持ちの切り替えがうまくできず、作業に集中できないと感じる人も少なくありません。
作業環境が悪い
オフィスは、快適かつ効率的に業務を進められるよう整備されています。しかし、自宅やカフェでは「椅子が体に合わない」「必要な書類をすぐに確認できない」など、設備面で業務に支障をきたすことがあります。
思うように仕事が進まないストレスから、メンタルに不調が生じる社員もいるでしょう。
また、セキュリティや予算の制約により、必要なシステムやデータをオフィス外で使用できない場合、業務効率が低下するおそれもあります。
運動不足になりやすい
運動不足になりやすい点も、リモートワークの課題の一つです。
オフィスに出社する場合は、駅までの移動などで自然と身体を動かす機会が生まれますが、リモートワークでは通勤がなくなるため、歩く機会が大幅に減少します。
また、リモートワークの普及によりオンラインでの打ち合わせが増えると、外出や訪問などの移動も減少し、結果として日常的な活動量が低下しがちです。
筑波大学の研究では、長期間テレワークをしている人は慢性的に運動不足であり、そのことへの危機感も低い傾向があると報告されています。こうした運動不足は、健康面への悪影響だけではなく、メンタルヘルスにも関係するようです。
厚生労働省のガイドラインでも、身体活動の多い人はうつ病をはじめとするさまざまな疾患のリスクが低いとされ、少しでも多く体を動かすことが推奨されています。
そのため、リモートワーク環境でも意識的に身体を動かす工夫を取り入れることが、心身の健康を維持するために不可欠です。
参考:厚生労働省 健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023
労働時間や業務内容上の問題
リモートワークを導入する際は、労働時間や業務内容に関する課題も慎重に検討する必要があります。
作業時間や担当業務の可視化が難しくなることで、気づかぬうちに過重労働に陥るケースも少なくありません。さらに、慣れない働き方による戸惑いやストレスも見過ごせない問題です。
以下に、よく見られる課題例を挙げます。
労務管理が難しい
オフィス勤務の場合、タイムカードや勤怠システムを用いて労働時間を正確に管理できます。
しかし、リモートワークではそうした管理が難しくなり、作業時間や休憩時間の実態を正確に把握することが困難です。
また、通勤時間が不要になったことで、その時間を作業に充てたり、終業の区切りがつかめず、だらだらと仕事を続けたりするケースも少なくありません。
このような長時間労働は、上司や人事担当者が気づきにくいという特性もあり、放置されることで慢性化するリスクが高まります。
その結果、心身の不調を引き起こし、やがて休職や離職といった深刻な事態につながるおそれがあります。
業務分担に不均衡が生じる
リモートワークでは、お互いの業務内容や担当範囲が見えにくくなります。役割分担や業務量に偏りが生じやすいため、負担の不均衡が発生するおそれがあります。
「仕事が多くて誰かと分担したい」と感じた場合でも、ほかのメンバーの業務状況を把握しづらいため、誰に頼めばよいのか判断するのは困難です。そのため、仕事を一人で抱え込んでしまうこともあります。
このような状況が続くと、業務を処理しきれなくなり、プレッシャーや疲労の蓄積から心身に不調をきたす危険性もあります。
新しい働き方に慣れるまでストレスがかかる
リモートワークを導入すると、働き方が大きく変わります。「オフィスに通勤して仕事をする」という今までのルーチンワークが崩れることで、戸惑いを感じる人も少なくないでしょう。
また、リモート環境ではチャットツールやクラウド型の業務システム、ビデオ会議ツールなど、さまざまなITツールの活用が求められます。
こうしたツールに不慣れであったり、もともとIT操作に苦手意識があったりする社員にとっては、強いストレスを感じる原因となりかねません。
使い方に慣れるまでに時間がかかることで、業務効率が落ちたり、周囲とのコミュニケーションに支障が出たりするケースもあります。
このようなストレスの蓄積は、メンタルヘルス不調のリスクを高めます。
人間関係上の問題
人間関係の問題も、リモートワークにおける深刻な課題の一つです。物理的な距離があることでコミュニケーションのバランスが崩れ、関係性が希薄になる一方で、過剰な干渉が生じるケースも見られます。
また、自宅で業務を行う場合、家族の理解不足や非協力的な言動が社員のストレスにつながることもあるでしょう。
以下に、人間関係に関する具体的な課題例をご紹介します。
コミュニケーションが不足する
コミュニケーション不足は、リモートワークにおける代表的な課題です。同僚や上司と直接顔を合わせる機会が減ることで、相談や報告のタイミングをつかみにくくなり、業務上の連携が滞るケースもあります。
また、ちょっとした雑談ができなくなる点も見過ごせません。職場での何気ない会話は、ストレスの緩和や気分転換になるだけではなく、相互理解や信頼関係の構築にもつながる重要なコミュニケーションです。
こうしたやり取りがなくなると、孤独感や不安感を抱きやすくなり、メンタルヘルスに影響を及ぼすおそれがあります。
パワハラが起こりやすい
リモートワークには、パワーハラスメントのリスクを高める側面もあります。
「顔を合わせないのに、なぜパワハラが起こるのか」と疑問に思うかもしれませんが、対面でのコミュニケーションがないからこそ、管理や指導が過剰になりやすいのです。
リモート環境では部下の業務状況を把握しづらく、勤務実態が見えないため、管理職が不安を感じやすくなります。その結果、就業時間外の連絡や、進捗への細かな介入といった、度を越えたマネジメントが発生しがちです。
過度な干渉は、部下に強いプレッシャーを与え、メンタルヘルスの悪化を招くおそれがあります。パワハラと捉えられ、労使トラブルに発展するリスクもあるでしょう。
家族からの理解が得られない
自宅でリモートワークを行う場合、家族の存在が意外なストレス要因となることがあります。具体的には、以下のようなケースが挙げられます。
- 業務中に雑用を頼まれる
- 子どもが在宅中の親と遊びたがる
- オンライン会議中に大声を出したり、モニターをのぞき込んだりする
- 一日中家族と同じ空間にいることでストレスが蓄積する
- 「出勤しなくて楽でいいね」など、仕事への理解に欠ける発言がある
このように、家族からの干渉や無理解は、ストレスの増加や業務効率の低下を招く要因となり、家庭内での衝突が増えることでメンタルヘルスに影響を及ぼす可能性もあります。
リモートワーク社員のメンタルヘルス低下のサイン
リモートワークでは、社員の様子が見えにくくなるため、メンタルヘルス不調の発見が遅れるケースも少なくありません。
そのため、業務パフォーマンスや表情、言動などに注目し、社員の変化を注意深く観察することが重要です。メンタル不調の兆しを早期に把握できれば、休職や離職といったリスクを低減できます。
とくに注意すべきサインは次のとおり。
- 作業効率が低下する
- 表情や発言に変化がみられる
- 体調不良を訴える
ここからはそれぞれの具体的な判断基準をご紹介します。
作業効率が低下する
メンタルヘルス不調のサインは、業務パフォーマンスの変化としてあらわれる場合があります。作業がいつもより遅くなったり、ケアレスミスが増えたりするなど、作業効率の低下としてあらわれるケースも少なくありません。
こうした変化は、オンライン環境でも業務の進捗や成果物を通じて把握しやすいため、対面での接点が少ないリモートワークにおいても気づくことが可能です。
表情や発言に変化がみられる
表情や発言の変化は、メンタルヘルスの不調を示すサインである可能性があります。
とくにオンラインミーティングは、社員の微妙な変化を確認できる貴重な機会です。以下のような兆候がみられたら、注意深く様子を見守る必要があります。
- 表情が暗くなった
- 笑顔が減った
- 発言が少なくなった
- ネガティブな発言が目立つようになった
こうした変化を見逃さず、早期にメンタルケアへつなげることで、休職や離職のリスクを低減できるでしょう。また、社員の変化に早期に気づき、さりげなく配慮を示すことで「見守られている」という安心感が生まれ、帰属意識や組織へのエンゲージメント向上にもつながります。
体調不良を訴える
メンタルヘルスの不調は、表情や言動の変化だけではなく、身体的な症状としてあらわれることもあります。
- 倦怠感
- 微熱
- 食欲不振
- 耳鳴り
- 腹痛
このような症状は、一見すると風邪や体調不良と見分けがつきにくく、本人もメンタルとの関連に気づかないことがあります。
しかし、身体的不調はストレスや精神的な負荷が影響している可能性もあるため注意が必要です。
身体的サインを早期に察知し、必要に応じて産業医との連携や相談の場を設けることで、メンタル不調の深刻化を防げます。
リモートワークにおけるメンタルヘルス対策10選
リモートワークでは、コミュニケーションの希薄化や長時間労働が生じやすくなります。加えて、企業側が社員の状態を把握しづらくなることで、孤独感や業務負担が増幅し、メンタルヘルスに悪影響を及ぼすリスクも高まります。
リモートワークの効果を最大限に引き出しつつ、社員の健康を守るためには、リモート環境に適したメンタルヘルス対策をしっかりと講じることが重要です。
- コミュニケーションを活性化する
- セルフケアを促進する
- メンタルヘルス研修を実施する
- 労働時間を適切に管理する仕組みを整備する
- 専門家と連携する
- 相談窓口を設置する
- 労働環境整備をサポートする
- 家族への理解・協力を促す
- ストレスチェックを実施する
- ウェルビーイングサーベイを導入する
以下では、具体的な方法ご解説します。
コミュニケーションを活性化する
メンタルヘルス対策に取り組むうえで、まず重視したいのがコミュニケーションの活性化です。社員同士が会話する機会を増やすことで、気軽な雑談や相談がしやすくなり、孤独感の緩和にもつながります。
なかでも効果的な施策が、オンラインを活用した1on1ミーティングです。リラックスした雰囲気のなかで、管理職と部下が業務の進捗や悩みを共有しやすくなるため、信頼関係の構築にも役立ちます。
また、チャットツールの導入やニュースレター、社内SNSなどの活用も、リモートワーク環境における情報共有と交流の促進に有効です。
リモートワークではどうしてもコミュニケーションが希薄になりがちです。だからこそ、企業が主体的に交流の機会を設け、社員同士がつながりを感じられる環境を整えることが、メンタルヘルスを守るうえで欠かせません。
セルフケアを促進する
社員が心身の健康を維持するためには、自身で意識的にセルフケアに取り組むことも重要です。
たとえば、適度な休憩を取ったり、軽いストレッチやウォーキングなどで身体を動かしたりすることは、集中力の回復や気分転換に効果的です。
また、業務の合間にチャットツールを使って気軽に会話を交わすことも、孤独感の軽減やストレスの緩和に役立ちます。
企業としても、セルフケアの促進に向けた環境整備が求められます。社員に対してセルフケアの方法に関する情報提供を行ったり、休憩や雑談のための時間を明確にルール化したりすることで、社員が安心して心と体を整える時間を確保できるよう支援しましょう。
メンタルヘルス研修を実施する
メンタルヘルス研修の実施も、社員の健康を支えるうえで重要な施策の一つです。研修を通じてメンタルヘルスの重要性やセルフケアの方法を周知することで、社員一人ひとりが自分の状態に意識を向け、早期の気づきと対処につなげる意識づけが期待できます。
とくに、管理職に対しては、部下のメンタルケアに関する研修の実施が欠かせません。不調のサインや基本的な対処法を学ぶことで、現場で適切なサポートを行うスキルが身につきます。
また、過度な監視や時間外の連絡がストレスの原因となりうることや、パワーハラスメントに該当する行為への理解を深めることも、管理職研修の重要な目的です。
労働時間を適切に管理する仕組みを整備する
リモートワークでは、社員一人ひとりの労働時間を正確に把握することが難しく、長時間労働が常態化するリスクがあります。
こうした課題を解決するためには、リモート環境に適した勤怠管理の仕組みやルールの整備が効果的です。
たとえば、以下のような対応が挙げられます。
- 一定時間パソコンを起動し続けるとアラートを表示する仕組みを導入する
- チャットツールのアクティビティログ(操作履歴)を勤怠管理に活用する
- ネットワーク対応型のタイムレコーダーを導入し、正確な打刻を行う
- 業務時間外のメール送信やシステムアクセスを原則禁止する
- リモート勤務中の残業を禁止または事前申請制にする
- 就業規則にリモートワークに関する明確なルールを記載する
これらの仕組みやルールを導入することで勤務実態の透明性が高まり、社員の健康を守るだけではなく、管理職や人事部門の負担軽減にもつながります。
専門家と連携する
社員のメンタルヘルスを守るうえで、カウンセラーや産業医といった専門家との連携は欠かせません。
専門的な立場からの客観的なアドバイスを受けることで、社員の状態をより早期に把握し、適切な対応を行えるようになります。社員にとっても、いつでも相談できる専門家の存在は大きな安心感につながり、心理的な支えとなるでしょう。
さらに、産業医と企業の安全衛生担当者が連携し、社員の健康情報を共有することで、リモートワーク特有の課題を把握し、組織として対策を講じられます。
社員のプライバシーを尊重しながら、問題の早期発見と迅速な対応ができる体制を整えておくことが重要です。
相談窓口を設置する
リモートワークに関する悩みを相談するための窓口を設置することも、効果的なメンタルヘルス対策です。
直属の上司や人事部が相談先となっている場合、評価や待遇への影響を懸念し、相談をためらう社員も少なくありません。
働き方や心身の不調など、リモートワーク特有の課題を一元的に受け付けられる中立的な窓口を設けることで、社員が気兼ねなく相談できる環境を整えましょう。
労働環境整備をサポートする
自宅でリモートワークを行う社員に対して、労働環境の整備を企業がサポートすることは重要な取り組みの一つです。
たとえば、業務用のデスクやチェア、パソコン、周辺デバイスなどを貸与・支給すると作業環境が整い、ストレスの軽減や集中力の向上が期待できます。
また、リモートワーク手当の支給や、備品の購入費を会社が負担する制度の導入も効果的です。こうした支援策により、社員が快適な作業環境を整えやすくなり、業務パフォーマンスの向上にもつながります。
ただし、手当や現物支給を行う場合、それらは給与所得として課税対象となる可能性があります。トラブルを防ぐためにも、事前に社員へ説明して理解と同意を得ることが重要です。
家族への理解・協力を促す
上記で紹介したように、リモートワークに対して家族の理解や協力を得られない場合、社員は大きなストレスを抱えることになります。
こうした家庭内の衝突を和らげるためには、企業側から社員の家族に対してリモートワークへの理解を促す取り組みが有効です。
たとえば、手紙や電話などを通じて、リモートワークの目的や特性、家庭内で起こりやすいトラブルとその回避法、さらに問題が生じた際の相談窓口などを伝えることで、家族の不安を和らげ、企業への信頼感を高められます。
また、オンラインのファミリーイベントや家族向けの職場見学会を実施し、企業や仕事への理解を深めてもらうと、家庭内での協力体制を築くことが可能です。
こうした取り組みは、社員のエンゲージメント向上に加え、企業ブランディングの強化にもつながります。
ストレスチェックを実施する
ストレスチェックとは、アンケート形式で社員の心身の状態を可視化し、データとして分析する仕組みであり、いわば「メンタルの健康診断」です。
ストレスチェックを定期的に実施することで、メンタル不調の兆候を早期に発見し、適切な対応につなげられます。
また、集団分析の実施により、特定の部署やチームにストレスが偏っている傾向を把握できる点も大きなメリットです。
こうした情報から、人員配置や業務内容、職場環境の改善点を見つけ出すことが可能となり、結果的に休職・離職の予防、職場全体のパフォーマンス向上にも寄与します。
以下の記事では、ストレスチェックの具体的な取り組みを、「人事主導型」と「従業員参加型」に分けて詳しく解説しています。検査結果を活用するときのポイントも紹介していますので、本記事と合わせて確認してみてください。

ウェルビーイングサーベイを導入する
ウェルビーイングとは、心身だけではなく、社会的にも良好な状態を意味する概念です。近年では、社員一人ひとりのウェルビーイングを高めることが、持続的なパフォーマンス向上や組織の生産性に直結するという考え方が広まりつつあります。
こうした背景から注目されているツールが「ウェルビーイングサーベイ」です。
ウェルビーイングサーベイでは、社員の心理的・身体的・社会的側面を多角的に測定・分析できます。主観的な感覚だけでは見えにくい「職場の空気」や「心のコンディション」を、客観的に可視化できる点が大きな特徴です。
この仕組みにより、メンタルケアが必要な社員を迅速に把握できるだけではなく、実施中のメンタルヘルス施策がどの程度効果を上げているかを数値で把握できます。
さらに、組織全体の課題や、特定の部署に偏ったストレス要因なども明確化されるため、より的確な改善策を講じやすくなることもメリットです。
以下の記事では、導入前に知っておきたいサーベイの選び方を5ステップで解説しています。すぐに活用できるチェックリストもありますので、本記事と合わせて確認してみてください。

リモートワークはメンタルヘルスがとくに重要。社員の状態を可視化して離職防止に努めよう
リモートワークには生産性の向上や働き方の多様化といったメリットがある一方で、コミュニケーション不足や労働環境の未整備によるストレスから、メンタルヘルスに不調をきたすおそれがあります。
その結果、社員の休職や離職が増え、かえって生産性の低下を招くケースも少なくありません。
こうしたリスクを防ぐためには、企業として社員のメンタル状態を適切に把握し、早期にケアを行う仕組みを整えることが重要です。
効果的な対策として、社員の状態を定期的に可視化・分析できるツールの導入が挙げられます。さらに、メンタルヘルス施策の効果を客観的に評価できる点でも、これらのツールは大きな役割を果たします。
そうした目的に適した手段として『ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ』の導入は非常に有効です。社員の状態をデータとして把握・活用することで、メンタル不調の予防だけでなく、組織全体の健全性や生産性の向上にもつなげられます。
興味のある方は、以下から詳細をご覧ください。
従業員のメンタル状態の定期的な可視化・個々の性格に合わせたアドバイス提供を通じ、離職・休職を防ぐエンゲージメントサーベイ。無料トライアルの詳細は下記から。




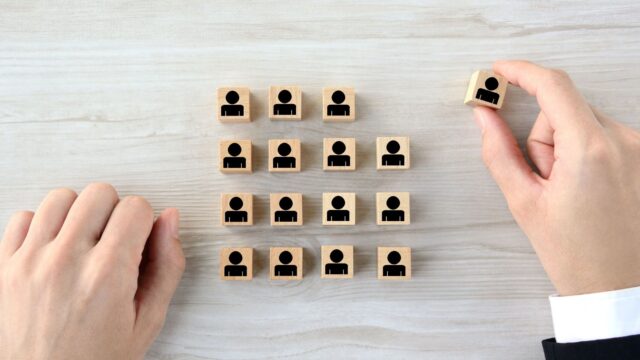







 ランキング1位
ランキング1位 
 ランキング2位
ランキング2位 
 ランキング3位
ランキング3位 