職場環境の改善は、社員の満足度向上に直結します。
オフィスの室温や設備、レイアウト、労働条件など、社員を取り巻くさまざまな要素を見直し、安全かつ快適な環境を整えることで、社員のモチベーションが高まり、社員同士のコミュニケーションも活発になります。
離職率の低下や生産性の向上につながることから、企業の安定的な成長のためには欠かせない取り組みです。
今回の記事では、職場環境を改善するメリットや具体的な取り組みをご紹介します。職場環境の改善に取り組む担当者様は、ぜひ参考にしてください。

職場環境とは?
職場環境とは、職場における物理的、社会的、心理的な環境の総称です。オフィスの広さや照明、空調などのハード面に加え、社内の人間関係や働きやすさといったソフト面も職場環境に含まれます。
職場環境の整備は努力目標ではなく、企業が果たすべき義務です。労働安全衛生法において、事業者には社員の安全と健康の確保が義務付けられているためです。
“事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない”
上記の義務を「安全配慮義務」といいます。安全配慮義務を果たすことで社員の健康と安全を守れるだけではなく、企業としての信頼性も増し、ブランディングの確立につながります。
職場環境を改善するメリット
職場環境の改善には費用や手間がかかりますが、以下のようなメリットを企業にもたらします。
- 生産性が向上する
- 社員の離職を防ぐ
- 優秀な人材を確保できる
ここからは、職場環境を改善するメリットについて、さらに踏み込んで見ていきましょう。
生産性が向上する
職場環境の改善は、生産性の向上に直結します。たとえば、オフィス内の導線や家具を見直すことで書類を探しやすくすれば、作業時間の短縮が可能です。
また、社員同士で円滑なコミュニケーションが取れる環境をつくることで、意見交換が活発となり、新たなアイデアの創出につながるでしょう。
社員の離職を防ぐ
社員の離職防止につながる点も労働環境改善のメリットです。良好な職場環境を整えることで、業務に関するストレスが少なくなり、社員のモチベーションが向上します。
また、企業改善に取り組む姿勢は「この会社は私たちを大事にしてくれる」という安心感を社員に与えることから、帰属意識を高め、定着率の向上をもたらす効果も期待できます。
優秀な人材を確保できる
労働環境の改善は採用面にも好影響を与えます。労働環境の改善に力を入れる企業は、求職者にとっても魅力的です。
そのため、応募者が増えて自社にマッチした優秀な人材を確保できる可能性が高まります。
職場環境を構成する4要素
職場環境は以下の4つの要素から構成されます。
- 物理的要素
- 人間工学的要素
- 人間関係
- 労働条件
各要素について詳しく解説します。
物理的要素
物理的要素は職場環境の基礎となる要素です。具体的には、オフィスの広さやレイアウトに加え、温度、湿度、照明の明るさ、空気の質などが挙げられます。
騒音や悪臭のあるオフィスでは、社員は業務に集中できません。さらには、頭痛や吐き気といった症状を引き起こすおそれもあります。
物理的環境を適切に整備すると、社員の快適性のみならず、集中力が上がることで生産性向上にもつながります。
人間工学的要素
設備や導線の快適性に関わる要素です。オフィスを物理的に構成する点は物理的要素に類似していますが、人間工学的要素は「人が使いやすいこと」に主軸をおいています。
使いやすいオフィス家具やスムーズな導線は、業務効率を上げるだけではなく、ストレスの少ない労働環境を構築します。
人間関係
職場の人間関係も、職場環境を構成する重要な要素です。人間関係が良好で、コミュニケーションが円滑な職場であれば、業務の進行や新たなアイデアの創出がスムーズになります。
社員の心理的健康も維持できることから、メンタル不調による休職や離職が少なくなります。
労働条件
労働条件は社員のモチベーションや心身の健康に大きな影響を与えます。具体的な要素は以下のとおりです。
- 適切な業務分配
- 仕事の自由度や裁量権があること
- 労働内容に見合った賃金設定
- 適切な休日日数
能力や適性に合った業務を分配すると、社員は高いパフォーマンスを発揮できるようになります。
また、適切な裁量権の付与により、社員の自立心や向上心が育まれ、積極的にキャリアアップへ取り組む姿勢が身につきます。
休日数や賃金が適切であることも重要です。待遇が良好な企業は社員のエンゲージメントを獲得しやすく、定着率の向上が期待できます。
職場環境における課題と改善策
職場環境の基礎知識を押さえたところで、次はオフィスでよくある職場環境の問題と改善策を解説します。
オフィスの室温が適切でない
オフィスの室温管理は、業務効率に直結する重要な課題です。オフィスが暑すぎる、もしくは寒すぎると、熱中症や風邪といった健康被害を招きかねません。
また、適温は個々人によって異なります。室温設定をめぐって社員同士のトラブルが生じ、人間関係が悪化することもオフィスの室温にかかわる問題点です。
エアコンが稼働しているにもかかわらず暑すぎる、寒すぎると訴える社員がいる場合は、室温にムラが生じている可能性があります。まずは温度計やセンサーを設置し、場所によってどの程度室温に差があるのかを調べましょう。
室温にムラがある場合は、扇風機やサーキュレーターを活用して、室内の空気を循環させます。状況に応じて断熱シートや遮熱カーテンの活用も検討しましょう。
社員同士のトラブルを防ぐためには、室内温度を定めておくことが重要です。一般的に、職場快適基準として夏季は24〜27℃、冬季は20〜23℃、湿度は50〜60%を保つよう推奨されています。
これを一つの目安としてオフィス内の室内温度を決めておくと、感覚の違いによるトラブルを回避できます。
また、室温の差を考慮した座席配置や、フリーアドレス制の導入も有効な施策です。社員一人ひとりにとって快適な室温環境を整えることで、社員の心身の健康維持と集中力の向上を実現できます。
オフィスが散らかっている
書類の山積みや清掃不足といったオフィスの乱雑さは、職場環境を悪化させる要因です。
散らかったオフィスは、社員の集中力低下や書類の紛失といった問題を招き、業務効率の悪化や情報漏えいをもたらす危険性があります。
見落としがちなのが配線の整理不足です。デスク上やオフィスの床でケーブルが絡み合っていると、雑然とした印象を与えるだけではなく、事故やトラブルの原因になりかねません。
デスクや棚の広さを見直したり、卓上ラックや収納ボックスを活用したりして、整理整頓することが大切です。ケーブルはケーブルホルダーや配線ボックスでまとめて、すっきりさせましょう。
しかし、一度きれいに整えても、その状態を維持できなければ、すぐに散らかってしまいます。書類や備品の配置を明確にし、定期的な清掃をルール化することで、オフィスの美しさを保てます。
若手社員の意見が通りにくい
若手社員の意見が通りづらい雰囲気があると、モチベーションが下がってしまいます。新しいアイデアが創出されづらくなるため、企業としての成長が停滞しかねません。
ミーティングルームやミーティングスペースを設けて、カジュアルにやり取りできる空間をつくると、若手社員も積極的に意見を出せるでしょう。
空間的な制約がある場合には、チャットツールの導入も選択肢の一つです。場所やタイミングを気にせず、気軽に意見交換を行える点もツール使用の大きなメリットです。
また、年功序列の色濃い企業では、若手社員が自らの意見を発信しようとする意識を持ちにくくなります。勤続年数にとらわれず、成果にもとづいて正当に評価する仕組みを導入することで、若手の意欲や積極的な姿勢を引き出せます。
業務量が多く長時間労働になる
業務量が多く、長時間労働が慢性化すると心身に不調が生じ、休職や離職のリスクが高まります。キャパシティを超えた業務を課されることで、ミスや納期遅延が増えて生産性が低下すれば、企業としての信頼性も失われてしまいます。
業務過多の問題を解決するためには、まず業務内容を見直すことが重要です。非効率なタスクを洗い出し、取り止めや見直しを行います。加えて、業務の再分担やタスク管理ツールの導入により、業務の効率化を図りましょう。
業務過多の改善策については、以下の記事でも詳しく解説しています。
職場環境改善のステップ
職場環境を改善するためには、適切なステップを踏むことが重要です。
- 現状把握と課題の整理
- 施策設定と実行
- 評価・改善
各ステップで行うべきタスクと注意点を詳しくご紹介します。
1.現状把握と課題の整理
職場環境の改善を図るためにまず取り組むべきことは、課題の特定です。従業員の満足度を調査し、現状の把握と課題整理を行いましょう。
主な調査方法は以下の3つです。
ストレスチェック
厚生労働省が提供するストレスチェックプログラムです。職場や仕事上のストレスに関する質問に従業員が回答するもので、従業員50人以上の企業では毎年1回の実施が義務付けられています。
ストレスチェック結果の部や課などのグループごとに分析・集計した結果を確認することで、自社の抱える問題を把握できます。
ストレスチェックの具体的な取り組みを確認したい方は、以下の記事をご覧ください。「人事主導型」と「従業員参加型」に分けて、企業の活用事例を紹介しています。

従業員アンケート
従業員に対して行うアンケートです。以下のような項目において満足度を尋ねることで、どの点に問題があるのかを明確化できます。
- 仕事内容
- キャリアパス
- 人事評価
- 上司からの指導や組織の体制
- 職場環境
- 社内風紀
- 経営方針
- 会社への愛着
- 総合的な満足度
アンケートを作成する際は、設問数や内容に配慮しましょう。問題数が過剰であったり、設問が曖昧だったりすると、回答者である社員に負担がかかり、混乱や疲弊を招くおそれがあります。
エンゲージメントサーベイツール
組織や社員の状態を把握・分析できるツールです。業務負荷やストレスレベルを可視化できるため、企業が抱える問題が明らかになります。
改善策の提案や社員のケア方法のサポートする機能を有するツールもあり、客観的かつ効率的に対策できる点が大きな魅力です。
以下の記事では、導入前に知っておきたいエンゲージメントサーベイの選び方を5ステップで解説しています。すぐに活用できるチェックリストもありますので、本記事と合わせて確認してみてください。

2.施策設定と実行
課題が明確になったら、それに適した施策を設定、実行します。担当者だけで決定するのではなく、社内のディスカッションや支援ツールの活用により、多角的な視点で立案することが重要です。
また、組織間の比較や他企業の改善事例も参考にすると、よりよい施策を講じられるでしょう。
3.評価・改善
施策実行後は、必ず効果測定を行って評価を行いましょう。効果の出ない施策をやみくもに実施しても職場環境は改善されず、従業員の不満がたまってしまいます。
状況把握時に使用した手法を用いて施策実施前後の変化を測定し、社員のパフォーマンスを客観的に比較します。十分な成果が見られない施策は、廃止や改善を検討しましょう。
また、成果は社員全員で共有すると、職場環境改善への関心を高めることが可能です。職場環境を良くするためにはどうすればよいか、社員が自主的に考え、行動するきっかけとなります。
職場環境改善のためには社員のパフォーマンス把握が必要不可欠
職場環境を良くすることで、社員の満足度が増し、エンゲージメントの構築や生産性の向上につながります。
改善策を立てるためには、社員のパフォーマンスを把握し、自社が直面する問題点を整理することが重要です。パフォーマンスの把握は職場環境改善策の評価指標としても活用できるため、積極的に行っていきましょう。
しかし、社員のパフォーマンスは数値化が困難です。ストレスチェックやアンケートは時間がかかるうえ、分析や改善策も行わなければならず、多くの手間がかかります。
「ミキワメ ウェルビーイングサーベイ」は社員の満足度やパフォーマンスを一元的に把握、分析できるツールです。パフォーマンスが低下している社員に対してどのようなケアを行えばよいのか、AIによる提案も受けられます。
ミキワメ ウェルビーイングサーベイに興味のある方は、以下から詳細をご覧ください。
従業員のメンタル状態の定期的な可視化・個々の性格に合わせたアドバイス提供を通じ、離職・休職を防ぐエンゲージメントサーベイ。無料トライアルの詳細は下記から。




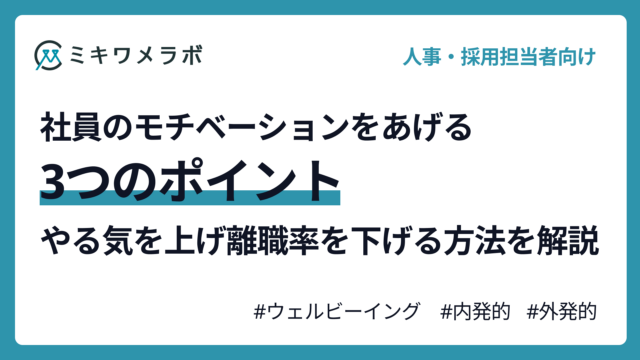
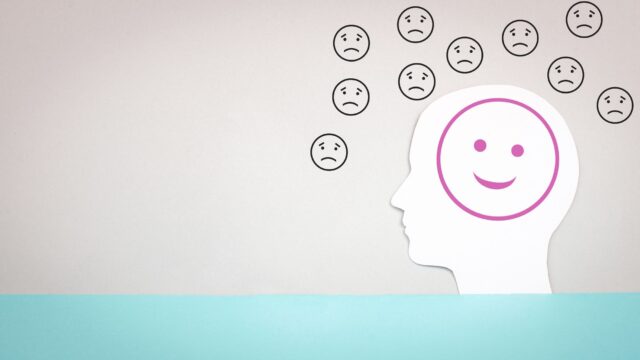







 ランキング1位
ランキング1位 
 ランキング2位
ランキング2位 
 ランキング3位
ランキング3位 