心理的柔軟性とは、自分の思考や感情を受け入れながらも「現在、目の前で起こっていること」や自分の価値観を軸に判断し、行動を選択する力です。
この力を高めることで、社員は失敗を恐れずに新たな挑戦へ踏み出しやすくなり、変化の多いビジネス環境にも柔軟に対応できるようになります。
さらに、組織全体として心理的柔軟性が育まれると、コミュニケーションが活性化し、イノベーションや新たな価値の創出にもつながります。
そのため、社員一人ひとりの心理的柔軟性を高めることは、企業にとって重要な人事施策といえるでしょう。
本記事では、心理的柔軟性を高めるメリットと、企業としてどのように社員を支援できるのかについて、具体的な方法を交えながら解説します。

心理的柔軟性とは
心理的柔軟性とは、自分の価値観や「いま、自分がしたいこと」に目を向けながら、不快な感情や困難な状況を受け入れ、適切な行動を選択できる能力を指します。
この概念は、ACT(アクセプタンス&コミットメント・セラピー)という心理療法の中心的な要素として提唱されました。
「考え方」や「行動原理」に関連する用語ですが、人格を構成する根本的な価値観とは異なり、習得可能なスキルの一種とされています。そのため、トレーニングによって養うことが可能です。
こうした特徴から、心理的柔軟性はしばしば「心の筋肉」にたとえられます。
心理的安全性との違い
心理的柔軟性と似た用語に「心理的安全性」があります。心理的安全性とは、集団や組織のなかで自分の考えや気持ちを話しても、拒絶されたり罰せられたりしないと感じられる状態です。
心理的安全性が「対人関係や信頼感の醸成」といった外的な関係性に関わるのに対し、心理的柔軟性は、自己理解や自己決定といった内面的な要素に関係します。
ただし、この2つはまったく無関係ではありません。心理的柔軟性を育むには、自分の価値観が尊重される環境が不可欠です。そのため、心理的安全性が高い職場では、心理的柔軟性も育まれやすいとされています。
心理的柔軟性が高い人の特徴
心理的柔軟性が高い人は、自分の感情や価値観を大切にしながら、変化に柔軟に対応するしなやかさを持っています。
そのため、ストレス耐性が高く、リスクを恐れず新しいことにも挑戦しやすくなります。
心理的柔軟性が高い人に見られる主な特徴は以下のとおりです。
- 感情を適切にコントロールできる
- 変化に柔軟に適応できる
- 価値観に基づいて行動できる
これらの特徴について詳しく解説します。
感情を適切にコントロールする
心理的柔軟性が高い人は、自分の感情や考えを「情報源」としてとらえます。行動や選択をする際には、それらを重要な判断材料として尊重しつつも、必要以上に引きずられることなく冷静にコントロールできます。
また、怒りや苛立ちといった負の感情についても「あって当然のもの」と受け入れる姿勢を持っており、無理に抑え込もうとはしません。
こうした受容の姿勢があるからこそ、感情に振り回されることなく、自分にとって望ましい行動を選択できるのです。
変化に柔軟に適応できる
心理的柔軟性の高い人は、自身の価値観や感情を大切にしながらも、それらに過度に固執することはありません。
他者の意見や環境の変化を受け入れる柔軟さを持ち、新しい状況にも適応できます。
トラブルが発生した際にも、自分の思考や感情に振り回されることなく「いま、この瞬間」に意識を集中し、冷静かつ適切な対応を取れます。
価値観に基づいて行動できる
自分の価値観を尊重した行動を取れることも、心理的柔軟性が高い人の特徴です。
他者の意見や評価に耳を傾ける柔軟さと、それらに過度に影響されない心の強さを兼ね備えているため、自分の信念に基づいた一貫性のある行動が可能です。
行動の軸を自分の価値観に置いており、たとえ周囲から批判されたり、不安を感じたりしても、動じることなく新たな挑戦を続けられます。
心理的柔軟性が職場で重要な理由
心理的柔軟性は組織内で業務を行うにあたり、重要なスキルの一つです。心理的柔軟性の高い社員が増えると、組織内での意見交換や新しいチャレンジの機会が増え、企業のイノベーションが起こりやすくなります。
心理的柔軟性が高まることで得られる主なメリットは以下のとおりです。
- ストレスやプレッシャーに強くなる
- コミュニケーション能力が向上する
- 新しい価値の創出が促進される
それぞれ詳しく見ていきましょう。
ストレスやプレッシャーに強くなる
心理的柔軟性の高い社員は、ストレスやプレッシャーに強い傾向があります。他者の意見を柔軟に受け入れつつも、自分の価値観を軸に判断・行動できるため、失敗や批判を過剰に恐れることがありません。
たとえ判断が誤っていた場合でも、必要以上に落ち込むことなく、ミスを素直に受け止め、次に活かすしなやかさを持っています。
また、メンタル面での回復が早く、高いパフォーマンスを安定して維持できる点も、心理的柔軟性を高める大きなメリットです。
このような社員が増えることで、組織全体の生産性や社員の定着率が向上し、企業の持続的な発展が期待できます。
コミュニケーション能力が向上する
心理的柔軟性が高まると、コミュニケーション能力の向上も期待できます。自分の価値観や、いま直面している課題を正確に把握できるようになるため、自信を持って自分の意見を伝えることが可能です。
また、対立が起こった際にも感情的にならず、冷静に対話を重ねながら他者の価値観や意見を受け入れる姿勢を保てるようになります。
自分自身の感情を受け入れられると、相手の負の感情にも寛容になり、尊重する態度が自然と育まれるでしょう。
新しい価値の創出が促進される
心理的柔軟性の低い社員が多い組織では、失敗や批判を恐れるあまり、新しい挑戦に消極的になる傾向があります。
討論や意見交換も活発に行われにくく、相互作用による新たなアイデアが生まれづらくなることも、組織にとっての大きな課題です。
一方で、心理的柔軟性が十分に育まれていれば、社員は自分の価値観と周囲の意見をバランス良く取り入れながら、革新的な発想を生み出すことができます。その結果、組織全体としてもイノベーションが促進されやすくなります。
心理的柔軟性強化の成功事例
心理的柔軟性の強化に取り組んでいる企業の事例と、成功のポイントをご紹介します。
上司が「自分の失敗談」を話す
ある企業では、業務上で発生した失敗と、そこから得られた学びを共有するミーティングを定期的に実施しています。
このミーティングでは、まず管理職が積極的に自身の過去の失敗や、それをどのように乗り越えたかというエピソードを率先して共有します。
管理職がこうした姿勢を示すことで、社員も安心して発言できるようになり、組織内の心理的安全性が高まりました。
その結果、社員の心理的柔軟性も向上し、失敗を「当然起こりうるもの」として受け入れながら、より主体的に業務に取り組むようになりました。
マインドフルネスを研修に導入
ある企業では、生産性の向上を目的に、マインドフルネスをマネージャー層向けの研修に取り入れています。
マインドフルネスとは「いま、この瞬間に起きていること」を評価や判断を加えずありのまま受け入れる心の状態で、心理的柔軟性を高める要素の一つとされています。
まず、全マネージャーがマインドフルネスの基本的な考え方を座学で学んだのち、実際のワークを通じて体験的に理解を深めました。
さらに、研修後には学んだ内容を日常業務に取り入れ、習慣化できるよう、1か月間にわたる個人ワークも実施されました。
その結果、参加者の約8割が効果を実感し、リーダーシップの向上や業務に対する仕事への意欲の高まりにつながったと報告されています。
ACTに基づく心理的柔軟性を高めるための6つの要素
冒頭でも触れたACT(アクセプタンス&コミットメント・セラピー)は、心理的柔軟性の向上を主な目的とした心理療法です。
1970年代後半から1980年代にかけて、アメリカの臨床心理学者スティーブン・ヘイズらによって開発されました。
ACTでは、以下の6つの要素に着目し、それぞれの行動を日常的に増やしていくことで、心理的柔軟性の向上を目指します。
- 脱フュージョン
- アクセプタンス
- 「いま、この瞬間」との接触
- 文脈としての自己
- 価値
- コミットされた行為
各要素について詳しくご紹介します。
脱フュージョン
脱フュージョンとは「思考」と「自分自身(現実)」とを切り離して捉える力です。「フュージョン(fusion)」は「融合」という意味で、この文脈では、自分と自分の思考が一体化してしまう状態を指します。
たとえば「自分は劣っている」といった思考にとらわれると、それがあたかも現実の事実であるかのように感じ、自己評価が下がり、新しい挑戦や討論に消極的になってしまいかねません。
脱フュージョンのスキルを身につけることで、そのような思考に対して一歩距離を置き、「これは単なる思考にすぎない」と認識できるようになります。
アクセプタンス
アクセプタンス(受容)とは、不快な思考や感情に心を開き、それらを否定せず、そのままの状態で受け入れることです。
誰しも、苦痛や不快な体験は避けたいと考えるものですが、それを過度に避けようとすると、かえって問題を深刻化させてしまうおそれがあります。
たとえば「職場の人と話すのが怖い」と感じて会話を避け続けたり、不安や恐怖を紛らわせるために過度な飲酒や喫煙に頼ってしまったりすれば、業務上の支障だけではなく、健康面にも悪影響を及ぼしかねません。
不快な感情と正面から向き合い、それをありのままに感じることで、徐々に抵抗感が薄れ、受け入れやすくなります。
その結果、試練に対して柔軟に対処できる力が育まれ、個人としての成長の機会を広げられるでしょう。
「いま、この瞬間」との接触(マインドフルネス)
「いま、この瞬間」との接触とは、現在の現実に意識を向け、その場の体験に主体的に関わる姿勢です。
この姿勢が欠けていると、過去の失敗や未来への不安にとらわれ、目の前の行動や判断に支障をきたすことがあります。
「いま、ここ」に意識を向ける感覚を養うために用いられるのが、マインドフルネスです。呼吸や瞑想などの実践を通じて、思考や感情に気づきながらもそれに巻き込まれず、受け入れて手放す練習を行います。
これにより、過去や未来への執着を手放し、冷静かつ柔軟に行動を選択できるようになります。
文脈としての自己
文脈としての自己とは、自分の感情や思考、行動を客観的に観察する視点です。これに対して、概念としての自己は「自分は〇〇な人間だ」といった固定的な自己イメージを意味します。
この自己イメージは、行動の軸になる一方で、ときに柔軟な対応を妨げる要因にもなり得ます。
たとえば「自分は周囲に頼りにされている存在だ」というイメージを持つことで、積極的に他者と関われるようになる反面、自分が困っているときに人に頼ることができず、孤独を感じるケースもあります。
一方の「文脈としての自己」は、自分を「感情や思考を見守る存在」としてとらえる視点です。
この視点を育むことで、ストレスや不安に過度に影響されることなく、価値観に基づいた行動を冷静に選べるようになります。
価値
ACTにおいては、自分の価値を明確にすること(価値の明確化)が重要なプロセスとされています。
ここでいう「価値」とは、短期的な欲求や目標ではなく、自分が人生を通じて大切にしたいことや、理想とする行動の指針であり、いわば「人生の羅針盤」です。
この価値観が明確でない場合、思考や感情に振り回されやすくなり、不快な体験を避ける行動ばかりが優先されてしまうため、長期的な成長や充実感につながりにくくなります。
一方で、価値を明確にしておくことで、困難な状況においても自分の指針に従って行動を選択できるようになり、一貫性と納得感のある生き方が可能となります。
コミットされた行為
コミットされた行為とは、自身の価値に沿った行動を継続的に選び取ることを指します。
価値に基づかない感情に流された行動や、本来必要な行動を避けるような選択ばかりを続けていると、一時的な安心感は得られても、結果的には自己評価の低下や後悔、停滞感を招きかねません。
一方で、自分の価値に照らして意味のある行動を積み重ねると、たとえ困難や不快な状況に直面していても、長期的な成長や人生の充実感を得ることが可能です。
心理的柔軟性を育むために企業でできること
心理的柔軟性は、一種のスキルであり、トレーニングを通じて高めることが可能です。企業としても、社員がこの力を育めるよう支援することが、組織の持続的な成長につながります。
とくに効果的な施策は以下の4つです。
- 心理的柔軟性に関する研修の実施
- 1on1による対話の促進
- 心理的安全性の高い企業風土の醸成
- 定期的・定量的な評価
それぞれの施策について詳しくご紹介します。
心理的柔軟性に関する研修の実施
社員の心理的柔軟性を高めるためには、まず基盤となる理論や実践方法についての理解を深めることが重要です。
ACT(アクセプタンス&コミットメント・セラピー)やマインドフルネス、自己理解などに関する知識を、研修を通じて体系的に学ぶ機会を設けましょう。
座学だけではなく、マインドフルネスタイムやリフレクションタイムなどのワークを取り入れると、社員が自身の思考や感情、価値観に向き合い、深く振り返る時間を持てるようになります。
こうした研修を継続的に実施することで、個々の内省力が高まり、柔軟で主体的な行動につながります。
1on1による対話の促進
定期的な1on1ミーティングは、社員の心理的柔軟性を育むうえで有効な施策です。
上司や同僚と1対1でカジュアルに対話を重ねることで、社員は「自分に関心を持ってくれている」「安心して話せる」という感覚を得やすくなり、心理的安全性が自然と高まります。
また、業務上の悩みだけではなく、雑談や気づきを共有するなかで、自分の感情や価値観に目を向ける機会が増えます。
こうした対話を通じて、自己理解が深まり、自分の内面と向き合う力や感情への気づきが養われ、より柔軟で主体的な行動につながっていきます。
心理的安全性の高い企業風土の醸成
先述のとおり、心理的安全性と心理的柔軟性は密接に関連しています。そのため、企業として心理的安全性の高い職場環境を整えることは、社員の心理的柔軟性を育む土台づくりとして重要です。
具体的には、以下のような風土や制度がその支えとなります。
- 立場や経験年数に関係なく、自由に意見を言える雰囲気がある
- 成果に対して、感謝や賞賛の言葉、インセンティブが適切に与えられる
- 失敗しても、チャレンジしたこと自体が評価される文化がある
このような企業風土が整うことで、社員の心理的安全性が高まり、たとえ困難な状況でも失敗を恐れず、自分の価値観に基づいた新たな挑戦に取り組みやすくなります。
定期的・定量的な評価
社員の心理的柔軟性を効果的に育てていくためには、心理状態や行動の変化を定期的かつ客観的に把握する仕組みづくりが欠かせません。
ストレスチェックやウェルビーイングサーベイを活用することで、社員のメンタルヘルスや職場環境への満足度、業務に対する意欲などを数値として可視化できます。
これにより、個人やチームの状態を早期に把握し、必要に応じて支援や環境整備を行えるでしょう。
とくに、心理的柔軟性は一朝一夕で高まるものではなく、継続的なトレーニングと振り返りが必要です。
心理的柔軟性はトレーニングで高められる。適切なサポートで強化を促進しよう
心理的柔軟性は、メンタルヘルスの安定やコミュニケーションの活性化、さらには新たな価値の創出にも関わる重要な要素です。
考え方の癖や固定的な価値観とは異なり、心理的柔軟性はトレーニングによって後天的に高めることが可能です。心理的安全性の高い企業風土を整えるとともに、社員が自らの内面と向き合えるような環境や支援体制を整える必要があります。
そうしたサポートを効果的に行うためのツールとして有用なのが『ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ』です。
『ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ』を活用することで、社員一人ひとりの性格傾向やパフォーマンスを定量的に可視化でき、個々の特性に応じた適切なアプローチが可能となります。
心理的柔軟性の向上を組織的に支援する手段の一つとして、『ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ』の導入を検討してみてはいかがでしょうか。
興味のある方は、以下より詳細をご覧ください。
従業員のメンタル状態の定期的な可視化・個々の性格に合わせたアドバイス提供を通じ、離職・休職を防ぐエンゲージメントサーベイ。無料トライアルの詳細は下記から。




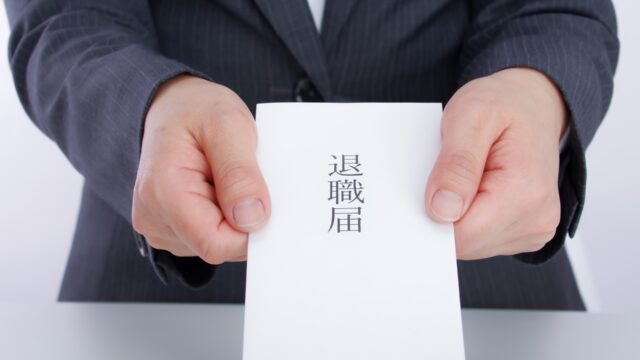







 ランキング1位
ランキング1位 
 ランキング2位
ランキング2位 
 ランキング3位
ランキング3位 