- AIでマネジメント業務はどう変わり、どの領域が効率化されるのか
- 目標設定から人材育成まで、AIが支援できる業務と導入の進め方
- AI時代に管理職が伸ばすべきスキル
AIの進化は、これまで「人間にしかできない」と考えられてきたマネジメント領域にも広がっています。目標設定や評価、キャリア支援といった業務をAIが効率化し、管理職はより本質的な意思決定や人材育成に集中できるようになりつつあります。
一方、現場では依然として属人的なマネジメントによる課題も少なくありません。
たとえば、
「評価基準が上司によって異なり、不公平だと感じて部下が離職してしまう」
「1on1が形骸化し、成長支援が機能していない」
といったことが挙げられます。
こうした課題に対してAIをどう活用していくかが、多くの企業のテーマとなっています。評価の公平性を確保しながら、部下一人ひとりと向き合うことで、結果として人材定着にもつながるからです。
そこで本記事では、管理職や人事担当者の方に向けて、マネジメントの基本領域ごとにAIの活用法を整理していきます。
AI時代に求められる管理職のスキルや、人間だからこそ果たせる役割についてわかりやすくまとめました。「自社のマネジメント業務にAIをどう取り入れるべきか」という視点でお読みいただき、具体的なアクションにつなげてください。
なぜいま「マネジメント×AI」が注目されているのか

マネジメントとは、ヒト・モノ・カネ・情報といった経営資源を活用し、組織のパフォーマンスを高める活動のことです。
以前はAIといえばルーティンワークを任せることが中心でしたが、現在では「意思決定」や「人材育成」といった高度な領域にまで広がっています。
実際に経済産業省の調査でも、AIによって自動化される業務の割合は増えているとの報告があります。
マネジメントや営業などの感情理解や意思決定が必要な業務でも、一部は自動化の余地があるとされているのです。
参考:経済産業省|デジタル/生成AI時代に求められる人材育成のあり方|BOSTON CONSULTING GROUP(p11)
また、Googleの共同創業者セルゲイ・ブリン氏も、権限委譲や昇進などのマネジメント業務にAIを活用していると語っています。
なお、世界のAIの活用率は72%であるのに対して、日本の活用率は51%です。AIを取り入れることで、国内市場での競争力を上げやすくなるといえます。日本ではマネジメントの属人性が障壁になっていることから、AIによる業務改善が期待できます。
マネジメントの5つの基本領域とAIの活用

続いて、マネジメント領域ごとのAIの活用傾向について見てみましょう。ここでは、ドラッカーのマネジメント論で展開される「5つの基本領域」をもとに解説します。
※以下の表は右にスクロールできます
| マネジメント領域 | 概要 | AI活用の具体例 | 実行のポイント |
| 目標・戦略設定 | KPIや戦略を策定する力 | 市場データをAIが分析し、最適なKPIを自動で提案。複数の戦略をシミュレーション。 | 提案を鵜呑みにせず、人間が最終判断を下す。背景をチームに共有して納得感をつくる。 |
| 組織編成と業務配分 | 人員配置や進捗管理 | ダッシュボードで進捗を自動集計し、AIがレポートを生成。リソース配分を最適化。 | データに加え、メンバーの適性やモチベーションも加味して判断する。 |
| 動機付けとコミュニケーション | チームの意欲と関係性を高める力 | サーベイや1on1の内容をAIが分析し、個別フィードバックのヒントを提示。 | 実際の声かけや対話は管理職が担い、AIは補助として活用する。 |
| 評価測定 | 貢献を客観的に測定する力 | KPI達成度や提案数・参加率などをAIが可視化し、公平に評価。 | 事前に基準を共有し、透明性を担保する。 |
| 人材育成 | 個人の成長を支援する力 | AIが業務実績を分析し、必要な教材やキャリアプランを自動で提示。 | 提案を自社の状況に合わせて調整し、本人の意欲と結びつける。 |
AI活用の具体例や実行のポイントも交えてご紹介するので、本章を読むことでマネジメントの実務にも活かしやすくなるはずです。ぜひ参考にしてください。
目標・戦略設定|AIでKPIを自動整理・提案
適切な目標や戦略の設定は、組織の成長に欠かせません。管理職は事業の目標や課題に応じて、膨大なデータを前に基準指標の選定や戦略設定を行う必要があります。
目標・戦略設定の領域では、AIを市場動向や過去の実績の自動分析などに活用できます。KPIの整理もサポートしてくれるため、管理職は意思決定に集中できるようになるのがメリットです。
具体的なツールの例としては、トヨタ社が導入している「Power BI」などがあります。Power BIは、Microsoft社が提供するクラウドベースのプラットフォームで、ビジネスの分析に役立ちます。
また、AIによって複数の戦略シナリオをシミュレーションしたり、リスクとリターンを比較して提示したりすることも可能です。
ただし、AIの提示をそのまま鵜呑みにすることは避けましょう。最終判断は人間が担い、チームに「なぜこの目標なのか」といった背景を共有して納得感をつくることがポイントです。
参考:Microsoft Power Platform|Power BI
組織編成と業務配分|ダッシュボードで可視化し、レポートを自動化
組織編成や業務配分は、チームを効率的に動かすうえで欠かせないマネジメント領域です。管理職は進捗状況やリソースを正しく把握しながら、適切な人員配置と業務分担を行わなければなりません。
AIを活用すれば、プロジェクトの進捗や稼働状況をリアルタイムでダッシュボードに可視化し、レポートも自動で作成可能です。管理職は事務作業に追われることなく、意思決定に集中できるようになります。
実際に、社員の特性を分析して適材適所の配置を支援する「カオナビ」など、AIを活かしたタレントマネジメントツールも登場しています。
一方で、AIはあくまでデータ上の最適化を示すにとどまる点には注意が必要です。部下のリアルタイムなモチベーションやメンバー同士の適性など、ある程度は人間が見極める必要があります。
組織編成と業務配分の領域でも、最終判断は管理職自身が担うことがポイントです。
動機付けとコミュニケーション|AIによるエンゲージメント支援
チームの成果を最大化するには、メンバーのモチベーションを維持し、円滑なコミュニケーションを促進することが大切です。とはいえ、マネージャー1人が部下全員の心理状態を常に把握し続けることは難しいものです。
そこでAIを活用すれば、サーベイの記録をもとに社員の心理的傾向を分析し、最適な声かけやフィードバックのヒントを簡単に得られます。
「サーベイフィードバック」とは、組織で実施したアンケート(サーベイ)の結果を、ただ報告するだけで終わらせず、従業員と対話を重ねながら課題を探り、改善策を一緒に考えていくプロセスを指します。
たとえば、1on1の進め方をサポートする『ミキワメ マネジメント』は、社員ごとの性格や心理状態を可視化してフォローのヒントを提示してくれるサービスです。
こういったツールの活用により、管理職は時間を割くことなく「誰に・いつ・どのように関わるべきか」を把握しやすくなります。
ただし、実際に相手の心に届くコミュニケーションはAIでは代替できません。AIのサポートを受けながら、管理職が自ら行動することで、エンゲージメントの向上が期待できます。
評価測定|データドリブンな判断で公平性を担保
人事評価は組織運営において重要なテーマですが、従来は上司の主観や曖昧な基準に左右されやすいものでした。この評価の不透明さが、社員の不満や離職につながるリスクもあります。
そこでAIを活用すれば、個々のKPIの達成度やチームへの貢献度を数値化し、客観的な評価として反映できます。曖昧だった評価軸をデータで補完することで、公平性と透明性の高い評価が可能になるのです。
実際に一部の人事評価システムではAIの活用が進んでおり、データを基盤にした評価制度が広がりつつあります。
以下の表は、従来の評価とAIによる評価を比較したものです。
※以下の表は右にスクロールできます
| 項目 | 従来の評価 | AIを活用した評価 |
| 評価基準 | 上司や人事の主観に依存しやすい | KPIや行動ログなどのデータを基準化 |
| 公平性 | 評価者によってばらつきが出やすい | 複数のデータを横断して客観的に算出 |
| スピード | 面談・書類作成に時間がかかる | データ自動集計で迅速にフィードバック |
| 納得感 | 「なぜその評価なのか」が不透明になりやすい | 数値をもとに算出するため結果が明確 |
AIを活用する際は、評価基準をあらかじめ社員に共有しておくことで納得感が高まりやすくなります。
また、業務内容によっては数値だけに頼るのではなく、定性的な取り組みにも目を向けなければなりません。AIと人間の評価を組み合わせることで、より精度の高い評価を実現できます。
人事がAIを活用している事例を、以下の記事でも詳しくまとめています。ぜひこちらもご覧ください。

人材育成|最適化されたキャリアプランの提案
人材育成も組織の持続的成長に欠かせない領域のひとつです。人材育成にAIを導入すると、社員の業務実績やスキルデータの分析、必要な研修や教材の選定などを自動化できます。
さらに、キャリアパスのシミュレーションを通じて、本人の希望と組織のニーズを両立した育成プランを提示することも可能です。
たとえば、IBMが提供するWatsonを活用したAIコーチングツールでは、社員一人ひとりに合った成長支援を実現しています。
ただし、キャリアプランもすべてAI任せでは不十分な可能性があります。AIの提案をもとに社員の意欲や価値観を踏まえ、自社特有のニーズや業務プロセスに適応させることがポイントです。
管理職がきめ細やかに関わることで、初めて持続的な人材育成が可能となります。
AI時代の管理職に求められるマネジメントスキル

AIの進化により、マネジメントの在り方が大きく変わりつつあります。
これまで人間にしかできないとされていた「目標設定」「評価」「人材育成」といった業務にもAIが活用され、業務効率化や意思決定の精度向上が進んでいます。
一方で、チームの信頼関係構築や感情理解、変革の推進といった“人間にしかできない役割”は、むしろその重要性を増しています。
AIを取り入れることがゴールではなく、人とAIの共創によって、よりよい組織運営を実現するためのスキルが、管理職には求められているのです。
ここからは、AI時代の管理職に求められるマネジメントスキルを見てみましょう。具体的には以下のとおりです。
本章を読むことで、「AIに任せる領域」と「人間にしか担えない役割」を明確にし、管理職としてどんな力を伸ばすべきかが具体的に見えてきます。
コンセプチュアルスキル|未来を描く力
1955年にロバート・カッツ氏が提唱した「カッツモデル」では、管理職に求められるスキルを「テクニカルスキル」「コンセプチュアルスキル」「ヒューマンスキル」の3つに分けています。
このうち、テクニカルスキル以外はAIでの完全な代替が難しいとされており、とくに「組織全体を見据え、将来の計画や戦略を立てるスキル」であるコンセプチュアルスキルは、上位の管理職になるほど重要視されます。
たとえば、チームの会議でメンバーが沈黙している場面で、「この沈黙は心理的安全性の問題か情報不足か、それとも方向性への迷いか」と構造的に捉える力がコンセプチュアルスキルです。
「何か意見はありますか?」と尋ねて終わるのではなく、「まず前提を整理しましょう」と本質に働きかけます。
部門単位でも「数年後の組織像」や「AI導入後の戦略変更」を描く力が求められており、それを支えるのがまさにコンセプチュアルスキルです。AIが示すシナリオに頼るのではなく、自社のビジョンや文脈に沿って判断する力が問われています。
AIは膨大なデータを処理できますが、「組織全体としてどの戦略を取るべきか」という判断は、いまだに管理職の役割であるといえます。市場の変化を読み取り、AIが提示するシナリオを活かしながら、自社のビジョンに合った戦略を設計する力が必要です。
ヒューマンスキル|信頼関係を築く力
チームのパフォーマンスを最大化するには、信頼と対話の積み重ねが欠かせません。その土台となるのが、メンバーとの関係構築に欠かせない「ヒューマンスキル」です。
AIは心理分析や感情推定を補助できますが、実際に部下との信頼関係を築くことは人間にしかできません。ヒューマンスキルはAIには代替できない、最も人間らしい力といえます。
チームの力を引き出すには、不安を抱えるメンバーに耳を傾けて挑戦を後押ししたり、対立時に個々の意見を聞いて方向性を整えたりすることが必要です。ヒューマンスキルを活かして安心して挑戦できる環境をつくることが、チームの成果につながります。
チェンジマネジメントスキル|変化に適応して推進する力
チェンジマネジメントスキルとは、変化に適応して推進する力のことです。組織が現状から理想の姿へと移行し、成果を得るために欠かせないスキルです。
AIの導入は、多くの組織にとって大きな変革となるため、現場に混乱や抵抗を生むことも珍しくありません。もし背景の共有や巻き込みが不十分なら、「導入したのに使われない」「現場が疲弊する」といった事態にもつながります。
AIをスムーズに導入するには、導入の背景や目的をわかりやすく伝えて、メンバーが前向きに受け入れられるように導く力が欠かせません。
“変化疲れ”を避けながら、前向きな変革を推進するために必要なのが、チェンジマネジメントスキルです。
AIを活用した意思決定力
AIを活用した意思決定力も、これからの時代に求められるスキルといえます。
AIは人間の意思決定をサポートしてくれますが、あくまで人間との協働によって成り立つ「ハイブリッドモデル」として捉えるべきです。
AIが示すデータやシナリオを理解したうえで、どこからを人間が判断するかを切り分けるバランス感覚が問われるようになります。
たとえば、AIが「この社員は異動が最適」と示したとしても、その判断がチームに与える影響や背景を考慮するのは人間の役割です。
データを鵜呑みにせず、文脈や人の気持ちを踏まえて決断する“意思決定力”が、これからの管理職に求められます。
メンバーのモチベーション管理
メンバーのモチベーション管理もマネジメントの重要なスキルです。AIによるサーベイ分析やフィードバック支援は役立ちますが、「なぜその仕事が必要なのか」を伝えるのは、人間の役割です。
1on1などの定期的なフォローを通じて、部下のモチベーションを理解し、個別の価値観に合わせて働きかけることがポイントです。
具体的なモチベーションアップのコツについて知りたい方は、以下の記事をぜひ参考にしてみてください。

世代別|人事評価に期待するポイント

人事評価制度に対して、世代ごとに「何を求めているのか」はやや異なります。
株式会社コーナーは、2025年に「静かな退職と人事の認識ギャップ調査」を実施しています。調査報告によると、同社の社員が人事に期待する取り組みとして、「給与・報酬」「評価基準の透明性」が全年代で重視されていました。
一方で、世代別に焦点を当てると、30代はワークライフバランスや福利厚生の充実を重視し、40代では心理的安全性や雇用の安定といった“安心して働ける環境”を求める声が多く挙がっています。
参考:株式会社コーナー|社員は「給与」人事は「評価」を優先 ー社員と人事のギャップを可視化した最新調査【第2弾】
また、日本能率協会マネジメントセンターの「イマドキ新入社員の仕事に対する意識調査2024」では、若手世代が“努力や勤続といったプロセス”を評価に反映してほしいという意識を持っていることが示されています。
このように、評価制度に対する期待は世代ごとの価値観や働き方の志向が反映されています。AIを活用してマネジメントを行う際も、世代ごとの価値観の違いを丁寧に分析し、個々のニーズに応じた評価基準やフィードバック設計を行うことが重要です。
公平な評価を目指すことはもちろん、各世代が納得できる仕組みを構築できれば、組織のエンゲージメントとモチベーション向上につながります。
AIに代替できない「人間ならでは」の役割

AIはデータ分析や業務効率化をサポートしてくれますが、すべてのマネジメントを代替できるわけではありません。
また、AIが発展するなかで「人間にしかできない役割」がより際立ちつつあります。ここでは、とくに重要な「人間ならでは」の3つの役割を解説します。
上記を理解することは、今後管理職が目指すべきマネジメントの在り方を考えるうえで重要な手がかりとなるはずです。AIに任せるべき領域と人間が担うべき領域を明確にすることで、チームの生産性と働きがいを両立させるマネジメントが実現できます。
信頼関係構築
1つ目は、信頼関係の構築です。確かに、AIは会話のログや行動データから関係性の傾向を分析できます。
しかし、「一緒に時間を過ごす」「ともに困難を乗り越える」といった体験を通じて築かれる信頼までは代替できません。
たとえば、部下が困難に直面したときに寄り添ったり、努力を正しく認めたりする姿勢は、部下の心理的安全性を生み出します。
こうした信頼関係があるからこそ、部下は失敗を恐れず挑戦でき、チームの成果にもつながりやすくなります。AIがどれほど発展しても「人とのつながりに基づく信頼」は人間にしか実現できないのです。
感情理解
2つ目は、相手の感情を理解することです。AIでも、与えられたデータから「相手が怒っている可能性が高い」といった感情を推定することはできます。
しかし、その裏にある文脈や背景までを理解することは難しいのが現状です。
たとえば、沈黙が意味するものや態度の微妙な変化などは、相手の性格や状況をすべて踏まえて初めて読み取れるものです。管理職は日頃の関わりを通じて部下の気持ちをくみ取り、適切な声かけやサポートを行う必要があります。
実際にハーバード・ビジネス・レビューの研究でも「これからのリーダーには共感力が求められる」と示されています。このことからも、感情理解は人間が果たすべき役割ということがわかります。
参考:DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー|これからのリーダーには謙虚さと共感力が求められる
倫理的判断
3つ目は、倫理的な判断を下すことです。AIは、与えられたルールや数値に基づいて最適解を導くのは得意です。
しかし、その判断が「人として正しいか」「組織の価値観に合っているか」までを判断することは難しいとされています。
とくに昇進や人員配置といった意思決定は、効率や成果だけでなく、組織文化や個人の人生への影響も考慮する必要があります。AIの提案を参考にしつつも、最終的な判断を人間が担い、公平性と倫理性を両立させることが重要なのです。
『ミキワメ マネジメント』が実現する新しいマネジメントのカタチ

マネジメントには「信頼関係構築」や「感情理解」など、人間にしか担えない領域があります。一方で、データの分析や客観的な評価、公平性の担保といった部分は人間だけで担うには限界があり、属人化や不公平さを招いてしまうケースもあります。
こうした課題を解決するには、AIと人間の役割を明確に分担しながら活用していくことが欠かせません。とくに、経験や勘に依存してきた企業では、AIを導入することでマネジメントの属人化を防ぎ、再現性の高い意思決定や人材育成が可能になります。
ミキワメでは、組織のパフォーマンス向上を目指す『ミキワメ マネジメント』を展開しています。
『ミキワメ マネジメント』はこのような特徴があり、管理職が本質的なコミュニケーションに集中できるサービス内容となっています。
以下の記事で詳細を解説していますので、マネジメントに悩む方は、ぜひご覧になってみてください。

社員の行動を促すマネジメントを実現
『ミキワメ マネジメント』は、社員の行動を促すマネジメントを実現できるのが特徴です。1on1ミーティングの会話内容を自動で記録し、その内容からAIがネクストアクション(次の行動)を示します。
上司は提案内容を参考にしながら1on1を進めるため、自然な流れで部下の行動を促すマネジメントを実現できるようになります。
アメリカのギャラップ社の調査によると、上司が1週間単位で定期的にフィードバックした場合、1年単位のフィードバックに比べて以下のようなメリットが期待できると報告されています。
- 「有意義なフィードバックを受けている」と強く同意する可能性が5.2倍高い
- 「優れた仕事をしたい」と強い意欲を持つ可能性が3.2倍高い
- 「仕事に熱心に取り組む」可能性が2.7倍高い
参考:More Harm Than Good: The Truth About Performance Reviews|Gallup, Inc.
このことからも、上司の定期的なフィードバックが部下のパフォーマンス向上に影響を与えることがわかります。
上司と部下の相互理解を促進
『ミキワメ マネジメント』では、サーベイや性格検査を通じて、現場の社員の状態(性格・心理状態)を可視化できます。部下の状態を踏まえた「会話内容」や「関わり方」が明確になることで、上司は部下の理解を深めながら適切な1on1を実施しやすくなります。
また、上司と部下の「似ている点・異なる点」も表示されるため、相互理解も深められるのがメリットです。
リクルートマネジメントソリューションズの調査では、1on1ミーティングを導入した企業では、上司と部下の関係性の向上を体感しているという回答が多くみられました。
1on1を導入し意識的にコミュニケーション機会を設けることで、上司と部下の関係性向上に寄与していることがうかがえます。
一方で、上司の「面談スキル不足」や「負荷の高まり」といった点は課題です。
参考:リクルートマネジメントソリューションズ|【調査発表】1on1ミーティング導入の実態調査(「図表4 1on1ミーティングの導入効果」「図表6 1on1ミーティングを進める上での課題感」より)
『ミキワメ マネジメント』には、会話内容を提案する機能や、自動で文字起こしする機能も搭載されています。ミキワメの導入により、上司の負荷を軽減しつつ、部下が安心して話せる質の高いコミュニケーションを実現することが可能です。
マネージャーの面談スキルを向上
通常の1on1では、マネージャー個人の進め方や経験則に頼ってしまうケースも少なくありません。
しかし、『ミキワメ マネジメント』なら、会話の記録や振り返りを体系的に行えます。AIによる進め方のアドバイスや自動生成されるサマリーの活用により、「何をテーマに話すとよいか」「どの話を議事録に残すべきか」が自然と身につくようになります。
また、1on1の終了後に簡単なアンケートに答えるだけで、1on1に対する部下の評価がわかり、マネージャー自身の振り返りにも活用することが可能です。
【ミキワメAIによる振り返り】
※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください
| 項目 | アドバイスの例 |
| 総評 | ・1on1活用度から、今回の1on1は部分的に効果があったことが読み取れます |
| よかった点 | ・上司が部下の課題に対して具体的な解決策を提案しています ・上司が部下の労働環境と健康管理に気を配っています |
| さらによくできそうな点 | ・部下の感情や不安に対して、もう少し共感を示すことができそうです ・部下の長期的なキャリアビジョンや成長目標についても話し合う時間を設けるとよいでしょう |
| 今後の1on1に向けたアドバイス | 今後の1on1では、部下の意見をしっかり聞きつつ、チーム全体の目標とのバランスを取る方法を一緒に考えるようにしましょう |
なお、弊社の調査でも、大企業の人事担当者に「実践している若手社員の離職対策」を質問したところ、76.9%が「定期的な1on1面談の実施」と回答しています。
-1024x709.jpg)
質の高いコミュニケーションで離職リスクを減らすためにも、『ミキワメ マネジメント』のようなツールの導入がおすすめです。
中小企業・スタートアップがAIを導入するときのポイント

AIの導入と聞くと、「大企業向けでコストが高い」というイメージを持つ方もいるかもしれません。
しかし実際には、中小企業やスタートアップでも十分に取り入れることが可能です。
日本政策金融公庫の調査によると、中小企業で2023年度以前にAIを導入した割合は5.4%、2024年度に新たに導入または大幅改修を行った企業は9.2%でした。
また、導入予定があるのは17.8%と、少数ではあるものの着実に導入事例が増えていることがわかります。
参考:日本政策金融公庫|導入予定割合が最も高いデジタルツールはAI(人工知能)(p2「図-3 デジタルツールの導入状況」より)
中小企業やスタートアップにとって重要なのは、「ゼロから自社でAIの仕組みをつくる」のではなく、既存のサービスや仕組みを上手に取り入れることです。
近年ではクラウド型の低コストツールも充実しており、大規模な開発投資を行わなくても導入できる環境が整いつつあります。
たとえば、クラウド型のタレントマネジメントシステムやエンゲージメントサーベイを活用すれば、限られたリソースでも効率的にマネジメントを行うことが可能です。
特に属人化しやすいマネジメント領域では、AIを活用することで意思決定や部下育成の精度を高め、組織の持続的な成長につなげられます。
1on1支援や人材データの可視化を行うクラウド型タレントマネジメントツールでは、月額3万円〜5万円程度から導入可能なものもあります。
実際に『ミキワメ マネジメント』や『カオナビ』『HRBrain』などは、数名規模のチームからでも導入可能。
トライアルプランや段階的な拡張も用意されているため、中小企業やスタートアップでも無理なく取り入れやすい設計です。
エンゲージメントサーベイの導入から活用までの手順は、以下の記事を参考にしてみてください。
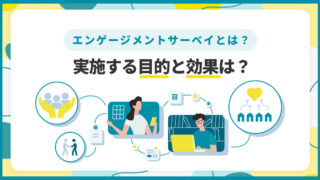
AIの活用で変わるマネジメントの現場|明日からできる一歩とは?

AIを活用したマネジメントは、もはや遠い未来の話ではありません。すでに多くの企業が1on1の記録やフィードバックの自動化、従業員エンゲージメントの可視化などを実践し、成果を上げています。
マネジメント業務では、AIの介入によって精度とスピードが飛躍的に向上し、組織全体のパフォーマンス向上につながります。大切なのは、「完璧な仕組みをいきなりつくる」ことではなく、効果の高いAIの活用方法を少しずつ取り入れることです。
【明日からできるAI活用のチェックリスト】
- まずは小規模プロジェクトでAIツールを試す
- 定期的なサーベイや1on1記録にAIを導入してみる
- 人事評価やフィードバックにデータを活用してみる
- 「人間にしかできない部分」と「AIに任せる部分」を明確に分ける
もし「部下との1on1をもっと効果的に進めたい」「マネジメントを標準化したい」と感じているなら、『ミキワメ マネジメント』 の導入がおすすめです。
『ミキワメ マネジメント』は、性格診断を通じて属人的になりがちなマネジメントを標準化し、組織全体のコミュニケーションの質を高めます。
ネクストアクションも自動で提示してくれるため、1on1後のやりっぱなしを防ぎ、継続的な部下支援が可能になります。ぜひ以下の資料もダウンロードしてみてください。
>>ミキワメ マネジメントがもっとよくわかる!の資料をダウンロードする
従業員のメンタル状態の定期的な可視化・個々の性格に合わせたアドバイス提供を通じ、離職・休職を防ぐエンゲージメントサーベイ。無料トライアルの詳細は下記から。




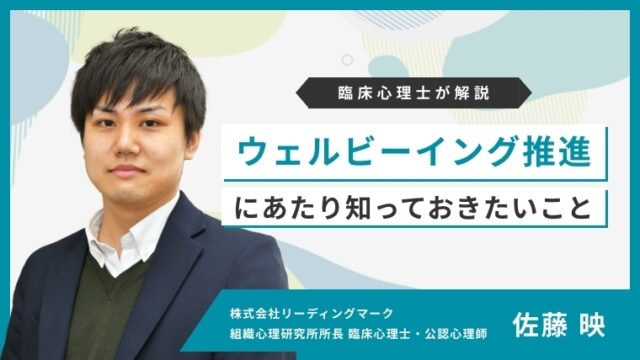







 ランキング1位
ランキング1位 
 ランキング2位
ランキング2位 
 ランキング3位
ランキング3位 