人的リスクとは、企業の関係者によるハラスメントやコンプライアンス違反などのトラブルをまとめて指す言葉です。
現在ではSNSの普及により、企業内の問題が世間に広まりやすくなっており、従業員の士気低下や企業イメージの損失につながることも少なくありません。
さらに、リベンジ退職のように、従業員の「仕返し」が原因で業務が停滞するケースも大きな課題です。
本記事では、人的リスク管理の重要性と具体的な対策について解説します。

人的リスクとは
人的リスクとは、社員や企業関係者の行動や健康状態などに起因して発生するリスクです。代表的な例としては、ハラスメント、メンタル不調、コンプライアンス違反、健康問題などが挙げられます。
現代の企業において、人的リスクの管理は重要なリスクヘッジの一つです。その背景には、主に「仕事観の変化」と「SNSの普及」があります。
- 仕事観の変化:従来の「滅私奉公」という考え方が薄れ、仕事を自己実現の場ととらえる意識が広まっています。社員の感覚は「企業主体」ではなく「自分主体」へとシフトしており、不満を抱えたまま我慢せず声を上げるケースが増えています。その結果、企業内の問題が表面化しやすくなっているのです。
- SNSの普及:InstagramやXなどのSNSにより、誰でも自由に意見や悩みを発信できる環境が整いました。これにより、会社への不満や内部の問題が社外に拡散し、企業イメージを大きく損なうケースも少なくありません。
このように、人的リスクには「顕在化しやすく」「拡散しやすい」という特徴があり、些細な問題でも深刻な事態に発展するおそれがあります。
こうしたトラブルを未然に防ぐためには、まず人的リスクの重要性を正しく理解することが不可欠です。そのうえで、適切な対策を講じることによって、健全な経営の維持につなげられます。
代表的な人的リスクのパターン4選
先ほど述べたとおり、とくに重要性の高い人的リスクは以下の4種類です。
- ハラスメント
- メンタルの不調
- コンプライアンス違反
- 健康問題
詳細を以下にご紹介します。
ハラスメント
ハラスメントとは、身体的・精神的な嫌がらせによって、相手に恐怖や不快感を与える行為の総称です。
上司が部下に対して暴行や脅迫などの行為を行う「パワーハラスメント(パワハラ)」や、性的な嫌がらせを行う「セクシャルハラスメント(セクハラ)」などが挙げられます。
ハラスメントは、被害を受けた社員のメンタルヘルスに深刻な影響を及ぼし、職場環境の悪化による生産性の低下や離職の増加を招く要因となります。
労使間のトラブルへと発展することもあり、企業にとって重大な損失をもたらすリスクも無視できません。
メンタルの不調
メンタル不調は、過重労働や職場の人間関係、ハラスメントなど、さまざまな要因によって引き起こされます。本人にとっては、パフォーマンスの低下や休職・離職といった深刻な影響が出るだけではなく、周囲の社員にも悪影響を及ぼします。
チーム内での連携が取りづらくなったり、雰囲気が悪化したりすることで、職場全体の士気や生産性の低下につながるケースも少なくありません。
企業にとっても、優秀な人材の流出や組織の機能不全を招くリスクがあるため、メンタルヘルス対策は重要な経営課題といえます。
コンプライアンス違反
コンプライアンス違反とは、法律や条例、社内規則などのルール、さらには社会規範や倫理に反する行為の総称です。
具体的には、情報漏えいや差別的な言動、不正行為などが挙げられます。このようなコンプライアンス違反は、組織の信頼を著しく損ね、従業員のエンゲージメント低下や社会的信用の失墜といった深刻な影響をもたらします。
健康問題
社員のケガや病気も人的リスクの一つです。健康は自己管理の問題ともいわれますが、現代では社員の健康を守ることが企業の責務とされています。
長時間労働やストレスの蓄積が原因で健康を損ない、生産性の低下や離職につながるケースも多いため、過重労働の防止やメンタルヘルス対策など、職場環境の改善が必要です。
とくに、業務中に発生した事故は労災として扱われ、安全配慮義務違反に該当する場合もあります。こうしたケースでは企業の責任が問われ、経済的損失や社会的信用の低下といった深刻な影響を及ぼすおそれがあります。
人的リスクが企業に与える悪影響とその具体例
人的リスクは、企業に次のような悪影響を及ぼします。
- リベンジ退職による業務妨害・信用毀損
- 訴訟・法的トラブル
- 人材確保の困難化
- 企業イメージの失墜
- 社員のパフォーマンスと生産性の低下
実際の具体例をご紹介します。
リベンジ退職による業務妨害・信用毀損
近年とくに増加している人的リスクが「リベンジ退職」です。
リベンジ退職とは、社員が会社に対する強い不満や敵意を背景に、組織へ損害を与えるため問題行為を起こして退職することを指します。
具体的には、以下のような行動が見られます。
- 機密情報の持ち出し
- 業務妨害
- SNSやマスコミを通じた内部告発
具体例
2025年に、LED大手企業の社員が退職時に、業務に関わるデータが削除されるようプログラムを設定した事件がありました。
データの消失が発覚したときには、すでに修復不可能となっており、再開発やそのための人件費が必要になったため、企業は大きな損失をこうむりました。
リベンジ退職が起こる原因や防止法については、以下の記事で詳しくご紹介しています。
訴訟・法的トラブル
訴訟などの法的トラブルも、人的リスクが引き起こす問題の一つです。
たとえば、ハラスメントや安全配慮義務違反を理由に社員から訴えられると、企業の信用が傷つき、多額の損害賠償が発生する場合もあります。
また、訴訟対応には時間や手間がかかるため、通常業務に支障が出て、生産性が下がってしまうおそれもあります。
具体例
ある企業で、上司が部下に対して、扇風機の風を執拗に当て続ける、「馬鹿野郎」と暴言を吐く、背中を殴るといったハラスメント行為を継続的に行っていました。このハラスメントを受けた社員3人は、上司および会社を相手取って訴訟を起こしました。
その結果、上司の行為は不法行為と認定され、上司および企業の双方に対して慰謝料の支払いなどの賠償責任が命じられました。
人材確保の困難化
人的リスクは人材確保の困難化を引き起こします。人的リスクが高い職場では離職率が上昇し、優秀な人材が流出しやすくなるためです。
また、企業イメージの悪化により、採用活動にも支障をきたします。結果として、企業に必要な人材を確保できず、企業の持続的成長が困難となるリスクも高まるでしょう。
具体例
2024年、大阪府の認定こども園で、役員によるパワーハラスメントなどの不適切行為が原因となり、保育士が一斉に退職しました。
また、東京都内の保育園では、人材不足による過重労働や労働時間記録の改ざんが横行しており、保育士7人が同時期に退職する事態が発生しました。このような保育士の一斉退職は全国で相次いでおり、深刻な社会問題となっています。
企業イメージの失墜
人的リスクが企業イメージに与える悪影響も、無視できない重大な課題です。ハラスメント問題やコンプライアンス違反がニュースで取り上げられたり、SNSで拡散されたりすると、企業の評判が急落するおそれがあります。
その結果、顧客や株主からの信頼も失われ、利益の減少や株価の下落、さらには投資離れや取引停止といった経済的損失も招きかねません。
具体例
従業員による企業イメージの低下を招く具体例として「バイトテロ」が挙げられます。バイトテロとは、アルバイトなどの従業員が不適切な行動を取り、その様子をSNSで拡散することで企業の評判を著しく損なう行為です。
代表的な例として、2013年に都内の蕎麦屋でアルバイトが不衛生な行為を行い、その様子をTwitter(現・X)に投稿した事件があります。
この投稿は、たちまちインターネット上で炎上し、苦情の電話が相次いだ結果、その店は閉店を余儀なくされるという重大な事態に発展しました。
社員のパフォーマンスと生産性の低下
社員のパフォーマンスや組織の生産性の低下に直結する点も、人的リスクの大きな問題です。
ハラスメントや健康問題に直面した社員は、集中力や判断力が鈍り、本来の能力を十分に発揮できなくなることがあります。
また、パフォーマンスが落ちた社員のいる部署では、ネガティブな雰囲気が周囲に波及することから、連携の停滞や部署全体の意欲減退が生じ、業務遂行に支障をきたすケースがあります。
その結果、企業全体の生産性が低下することも少なくありません。
具体例
滋賀医科大学の矢野教授の研究によると、喫煙者の割合が高い企業は、企業業績に悪影響を及ぼす傾向があると報告されています。
この研究では、経済産業省の健康経営優良法人認定に用いられる健康経営度調査のデータを使用し、健康関連のさまざまな指標と企業利益との相関を分析しました。
その結果、従業員の喫煙率が高い企業では、利益面で相対的に不利な傾向が見られました。
企業が実践すべき人的リスク管理の具体策
不適切行為や心身の不調といった人的リスクは、生産性の低下や人材の流出を招くだけではなく、企業イメージの失墜にも関わる重大な問題です。
こうした人的リスクを軽減するには、リスクの重大性を理解したうえで、適切な対策を講じる必要があります。
とくに優先して取り組むべき対策は次のとおりです。
- ハラスメント・コンプライアンス研修の実施
- 社員のメンタルケアの強化
- 社員の健康管理の推進
- 労働環境の見直しと改善
- 社員の状態の可視化
それぞれ詳しくご紹介します。
ハラスメント・コンプライアンス研修の実施
ハラスメントやコンプライアンスに関する研修は、人的リスク管理において有効な対策の一つです。これらの問題や違反リスクを理解することで、社員一人ひとりが正しい行動を取るようになります。
とくに経営陣や管理職は、率先して不正行為を指摘・指導し、模範を示す役割があります。上層部が規範となって正しい行動を推し進めることで、良好な企業風土が形成されるでしょう。
また、正社員に限定せず、契約社員やパート、アルバイトにも研修を通じて正しい情報を伝えることで、バイトテロをはじめとした不適切行為を抑制できます。
社員のメンタルケアの強化
メンタル不調に悩む社員を適切にケアすることも、重要な人的リスク管理の一つです。適切な対応を怠ると、パフォーマンスの低下や休職、離職につながり、企業に大きな損失を与えかねません。
1on1やメンター制度などにより、先輩や上司に気軽に相談できる機会を提供することで、社員の孤立化を防げます。
また、定期的なストレスチェックや産業医、カウンセラーとの連携により、メンタル面をサポートする体制を整える取り組みも重要です。
ストレスチェックの具体的な取り組みを確認したい方は、以下の記事をご覧ください。「人事主導型」と「従業員参加型」に分けて、企業の活用事例を紹介しています。

社員の健康管理の推進
人的リスクの一つである社員のケガや病気を防ぐための対策も不可欠です。社員の健康維持は企業の持続的な成長に直結するため、積極的な取り組みが求められます。
健康診断や健康管理に関する研修、禁煙支援や運動促進などを通じて、社員の健康を守りましょう。
労災事故を防ぐためには、安全教育や作業環境の点検・整備、熱中症対策など、現場の実態に合わせた対策が必要です。これらの取り組みを徹底することで、人的リスクの軽減が期待できます。
労働環境の見直しと改善
社員が安全かつ快適に業務を行えるよう、労働環境の改善も欠かせません。業務過多や適性に合わない仕事、不快なオフィス環境は、社員の心身の健康を損なう原因となるためです。
オフィスの空調や照明を見直し、快適な環境づくりを目指すとともに、社員の能力や適性に合わせて再配置や業務の再配分を行うことで、社員は生き生きと前向きに働けるようになります。
快適な労働環境は、心身の健康維持に寄与するだけではなく、企業に対するエンゲージメント(愛着)を高める効果もあります。その結果、社員は会社への帰属意識や責任感を強く持つようになるため、不正行為の抑制につながるでしょう。
社員の状態を可視化する
社員の状態の可視化も、重要なリスク管理の一つです。社員の状態を分析・評価することで、人的リスクの兆候をいち早く発見できます。
満足度やパフォーマンスを把握する方法としては、アンケートや1on1による対話が一般的ですが、これらは時間がかかるうえ、定量化が難しいという課題があります。
そうした課題を解消する手段として有効なのが、エンゲージメントツールの活用です。エンゲージメントツールは、社員の会社への愛着や満足度、パフォーマンスを数値化して分析できるサービスであり、リアルタイムでのデータ収集や継続的なモニタリングが可能です。
以下の記事では、導入前に知っておきたいエンゲージメントサーベイの選び方を5ステップで解説しています。すぐに活用できるチェックリストもありますので、本記事と合わせて確認してみてください。

人的リスク管理は「可視化」から。組織の不調を未然に防ごう
仕事観の変化やSNSの普及により、社員を原因とする「人的リスク」の影響は非常に大きくなっています。人的リスクの主なパターンとしては、ハラスメントやコンプライアンス違反、社員の心身の健康問題などが挙げられます。
人的リスクを低減するためには、社員が社会のルールを理解し、安心できる環境のもとで業務に携われるよう対策を講じなければなりません。しかしながら、人的リスクは水面下で深刻化していることも多いため、早期発見が不可欠です。
人的リスクの早期発見のために、社員の満足度やパフォーマンスを分析、評価できる「ミキワメ ウェルビーイングサーベイ」を導入してはいかがでしょうか。
従業員のメンタル状態の定期的な可視化・個々の性格に合わせたアドバイス提供を通じ、離職・休職を防ぐエンゲージメントサーベイ。無料トライアルの詳細は下記から。





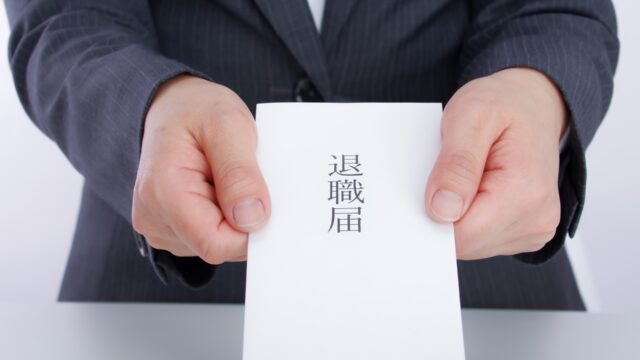


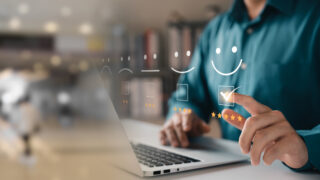




 ランキング1位
ランキング1位 
 ランキング2位
ランキング2位 
 ランキング3位
ランキング3位 