人事部と現場の間に生じる乖離は、多くの企業が直面している課題です。採用・配置・評価といった重要な人事施策が、現場の実情や期待と噛み合わないことで、業務効率の低下や人材の定着率悪化につながるケースも少なくありません。
人事部と現場の乖離を埋めるためには、双方向のコミュニケーションと現場の実情把握が重要です。判断軸を揃えることで一貫性のある人事施策が実現し、エンゲージメントの向上に寄る生産性アップや離職率の低下が期待できます。
本記事では、人事部の視点から、現場との乖離がなぜ起こるのかを整理し、その具体的な原因と実務に活かせる解消策を詳しく解説します。

人事と現場の乖離とは
人事部と現場の乖離(かいり)とは、採用・配置・評価などの人事施策が、現場の実情やニーズとかけ離れている状態を指します。
たとえば、現場が「即戦力となる経験者を採用してほしい」と望んでいるにもかかわらず、企業方針として新卒社員が採用・配置されるケースが挙げられるでしょう。
このようなミスマッチは、教育コストの増大や業務効率の低下を招くだけではなく「人事は現場を理解していない」という不満を生み、従業員のエンゲージメント低下にもつながる可能性があります。
乖離を防ぐには、人事部が現場の状況や要望を正確に把握し、双方向のコミュニケーションを通じて、施策に反映していくことが重要です。
一方で、現場の希望をすべて受け入れてしまうと、中長期的な人材育成や企業戦略との整合性が取れなくなるリスクもあります。
人事部と現場の乖離の具体例
人事部と現場の乖離がとくに起こりやすいのが「採用・配置・評価」のフェーズです。
| フェーズ | 人事部 | 現場 |
|---|---|---|
| 採用 | ポテンシャル採用 | スキル採用 |
| 配置 | ジョブローテーション | 適材適所 |
| 評価 | 評価制度に基づく | 人事評価制度・評価者への不満 |
それぞれの具体例や問題点、対策を詳しくご紹介します。
採用における乖離
採用における乖離として代表的なのが、採用目的の違いによって生じるミスマッチです。
現場は即戦力となる人材を求める傾向があり、スキル採用を重視します。業務に必要なスキルや資格を有する経験者であれば、教育コストを抑えやすく、即戦力として業務に貢献できるため、既存社員の業務負担を軽減する効果も期待できます。
一方で、人事部は中長期的な視点から、将来の幹部候補として育成可能な人材を採用しようとする傾向があります。そのため、企業文化への適応力や成長のポテンシャルを重視する、いわゆるポテンシャル採用を進めることが多いです。
このように、現場と人事部の間には採用目的の違いから生じる認識のズレが存在し、それが人材のミスマッチや業務負担の偏りといった問題を引き起こしています。
乖離によって生じる問題点
採用に関する乖離が生じると、現場の求める人物像とのミスマッチが発生し、結果として教育コストが増加したり、現場の多忙により十分な教育機会の確保が難しくなったりします。
その結果、早期離職につながるリスクも高まり、人材の定着や戦力化に悪影響を及ぼしかねません。
対策例
採用における乖離を埋めるためには、人事部と現場の意見の擦り合わせが欠かせません。
理想とする人物像や、採用後に期待される業務内容について認識を共有し、即戦力となるスキルと将来的な成長を見込めるポテンシャルとのバランスを適切に見極めることが重要です。
また、能力や行動特性、ポテンシャルなどの各項目において採用基準を明確にすることで、採用のミスマッチを軽減できます。
採用基準を明確化するメリットや方法については、以下の記事で詳しくご紹介しています。
配置における乖離
人材配置においても、人事部と現場の間に乖離が生じる場面があります。
人事部は、組織全体のバランスや将来の幹部候補の育成を重視する立場から、社員に多様な経験を積ませることを目的としたジョブローテーションを積極的に取り入れます。
一方で、現場が求めるのは即戦力となる人材です。業務に即応できるスキルや知識を持つ社員を必要としているため、現場にとっては配置のミスマッチが深刻な問題となることもあります。
人事部の配置計画によって、必要なスキルを十分に備えていない人材が配置されたり、現場に不可欠な人材が他部署へ異動させられたりするケースも少なくありません。
乖離によって生じる問題点
採用時の乖離と同様に、配置のミスマッチも現場に大きな影響を与えます。
経験や適性の不一致によって教育コストが増大したり、社員の孤立やメンタル不調を招いたりするリスクがあります。現場の要望と異なる配置が続くことで、人事部への不信感が高まり、信頼関係が損なわれるおそれもあるでしょう。
対策例
人材配置における現場との乖離を埋めるためには、個々の社員に関する情報を収集・把握することが重要です。
スキルや適性に加え、行動特性やキャリア観、要望など幅広いデータを集めることで、より精度が高く、社員自身も納得感を持てる配置を実現できます。
そのための手法としては、1on1による面談やパルスサーベイの活用が効果的です。また、社員の希望に基づく異動を促進することも有効です。自己申告制度や社内公募制度を導入し、社員が自主的に希望する部署へ挑戦できる仕組みを整えるとよいでしょう。
人材配置(人事異動)の決め方や注意点については以下の記事で詳しくご紹介しています。
評価における乖離
評価の段階においても、人事部と現場の間には乖離が生じることがあります。人事部は企業のビジョンや価値観に基づいて設計された人事評価制度に従って社員を評価しますが、その制度自体が現場の実態とかみ合っていないケースも少なくありません。
たとえば、チーム内での細やかな配慮や支援といった貢献が、目に見える成果として評価されにくいといった事例が挙げられます。
「評価者が現場業務を理解していない」「評価者ごとに基準が異なる」といった不満も生じやすく、評価への納得感を損なう要因となります。
乖離によって生じる問題点
努力や成果が正当に評価されない状況が続くと、従業員は自身の貢献が認められていないと感じ、モチベーションやエンゲージメントの低下を招くおそれがあります。
とくに、周囲と比較して不公平感を抱くような評価が行われた場合、その影響はより深刻になります。
このような状態が慢性化すると、職場に対する信頼や帰属意識が失われ、結果として離職者が増加するリスクが高まります。
対策例
評価フェーズにおける人事部と現場の乖離を解消するためには、まず評価制度そのものの見直しが不可欠です。
企業の目的やビジョンに加え、現場の実情や声を反映させながら、より公平かつ納得感のある評価基準を再構築する必要があります。
また、評価の方法自体を見直し、複数の手法を柔軟に組み合わせることも重要です。以下に、実際に有効とされる評価手法をご紹介します。
| 評価手法 | 内容 | 特長 |
|---|---|---|
| MBO(目標管理制度) | 社員がそれぞれ自身で目標を設定し、その達成度に基づいて評価する手法 | ・評価基準が明確・社員の納得感を得やすい |
| コンピテンシー評価 | 企業が求める具体的な行動特性(コンピテンシー)に基づき、行動面を評価する手法 | ・評価基準が明確・行動特性に基づく定量的な評価が可能 |
| 360度評価 | 同僚や部下、上司など、複数の視点から多面的に評価を行う手法 | ・評価の偏りを抑えられる・相互理解とコミュニケーションの活性化が期待できる |
| ノーレイティング | 上司との1対1の対話を通じて目標を設定し、フィードバックや評価を受ける仕組み | ・評価者との信頼関係を構築しやすい・対話を繰り返すことで、成長支援や目標修正を柔軟に行える |
人事部と現場の乖離によって生じるリスク
これまでに述べた採用・配置・評価の各フェーズにおける課題を整理すると、人事部と現場の乖離によって生じる主なリスクは以下のとおりです。
- 社員のモチベーション低下
- 人材育成の遅れ
- 休職や離職の増加
- チームワークの低下
- 組織内の対立や分断
それぞれのリスクについて詳しく解説します。
社員のモチベーション低下
採用や配置にミスマッチが生じ、適性に合わない部署に配属されたり、能力や成果に見合わない評価を受けたりすると、社員のモチベーションは低下しやすくなります。
とくに近年では、仕事に対する価値観が変化しており、企業の方針にただ従うのではなく、職場を自己成長や自己実現の場と捉える人が増えています。
そのため、個人の適性や希望を無視した採用・配置は、大きなストレスや不満につながるリスクがあるでしょう。
人材育成の遅れ
採用や配属にミスマッチが生じると、現場では適性やスキルが不足した社員を育成しなければなりません。教育に時間をかけても十分な成長が見込めなければ、人材育成が滞るおそれがあります。
また、人事部と現場の間に乖離があると、現場の状況把握が不十分になり、適切なフィードバックや評価ができないため、育成の質やスピードにも悪影響を及ぼします。
休職・離職が増加する
採用や配置において人事部と現場の間に乖離があると、人材のミスマッチが生じやすくなります。その結果、モチベーションの維持や円滑なコミュニケーションが難しくなり、チーム全体の士気が低下するリスクがあります。
また、現場の実情に合わない評価制度は、社員の労働意欲を損ねる要因です。適性に合わない部署への配置や評価への不満が蓄積すれば、ストレスによる心身の不調を招くおそれがあり、休職や離職に至るケースもあります。
チームワークが低下する
人事部と現場の乖離は、現場のチームワーク低下を招く要因にもなります。採用や配置のミスマッチにより、適性の低い人材がチームに加わると、教育や指導に時間を取られたり、業務の分担が偏ったりして、既存メンバーの負担が増加してしまいます。
こうした状況が長期化すると、不満やストレスが蓄積し、チーム内の人間関係が悪化するため、チームワークの維持が困難となるでしょう。
組織内で対立が起きる
チーム単位を超えて組織全体の対立を引き起こす要因になりうる点も、人事部と現場の乖離が招く問題の一つです。
採用・配置・評価に関する不満が現場に蓄積されると、人事部に対する不信感が高まり、部署間の信頼関係や連携の構築が困難となります。
このような状態を放置すれば、協働意識の低下やコミュニケーションコストの増加、人材の流出といった深刻な問題につながります。
人事部と現場の乖離が生じる根本的理由
人事部と現場の間に乖離が生じる主な要因は、以下の3つに集約されます。
- ビジョンの共有不足
- 目的の違い
- 情報伝達の不足
それぞれ詳しく解説します。
ビジョンの共有不足
経営層は、企業理念や長期目標に基づいてビジョンを設定し、それに沿った人事施策を立案します。
しかし、現場がそのビジョンを十分に理解していない場合、なぜその施策が必要なのか、実行することで何を達成しようとしているのかを把握できないことも少なくありません。
結果として「上からの一方的な押し付け」と受け取られ、施策への納得感や協力意識を得られないおそれがあります。
目的の違い
企業の目的は、長期的な視点で事業全体を最適化することにあり、人事部はその実現に向けた人事施策を策定します。
一方、現場は「目の前の業務を回すこと」を最優先とし、短期的かつ部分的な最適を追求する傾向があります。
この違いから、両者の間で意見の対立や利害の不一致が生じることも少なくありません。
情報伝達の不足
人事部に現場からの情報が十分に届かないことも、乖離を引き起こす要因の一つです。部署の雰囲気やメンバーの業務内容・適性・性格といった情報を把握できなければ、実態に合わない人事施策が行われてしまいます。
たとえば、自主性が重視される部署に、優秀であっても自己主張が少ない人材を配属すると、ミスマッチにより本来の力を十分に発揮できない事態が起こり得ます。
人事部と現場の乖離を解消するための方法
人事部と現場の乖離を解消するには、以下のような取り組みが効果的です。
- 現場とのコミュニケーションを活発化させる
- データを用いて現場の実情を分析する
- 従業員の満足度や適性を把握する
各施策のポイントを詳しく解説します。
現場とのコミュニケーションを活発化させる
現場の管理職と密にコミュニケーションを取り、ビジョンや経営戦略を共有するとともに、判断軸をすり合わせることが重要です。一方的に人事部の意向を押し付けるのではなく、現場の声を反映しながら優先順位や判断基準を揃える必要があります。
また、定期的に話し合いを行い、施策の効果を測定して改善策を立案したり、状況の変化に応じて制度を見直したりすることも欠かせません。
データを用いて現場の実情を分析する
現場の状況を正確に把握するには、データを用いた定量的・客観的な分析も有効です。離職率・休職率、評価結果、採用充足率など、人事部が把握できるデータを活用することで、各部署の状況を客観的に確認できます。
たとえば、特定の部署だけ早期離職が多い場合は、採用や配置におけるミスマッチ、あるいは教育計画に問題があると考えられます。こうしたデータを現場の声と照らし合わせることで、組織が抱える課題をより明確にできるでしょう。
従業員の満足度や適性を把握する
従業員の満足度や適性を調査によって把握することも、重要な施策の一つです。現場での意見収集は手間がかかるうえ、本音を引き出せるとは限りません。また、数値データだけでは職場の感情や雰囲気を十分に捉えることは難しいのが実情です。
その点、満足度や適性の調査は、こうした施策の「抜け落ち」を補う役割を果たします。アンケートやサーベイツールを活用すれば、可視化が難しい従業員の満足度や適性を一元的かつ定量的に評価できます。
以下の記事では、導入前に知っておきたいエンゲージメントサーベイの選び方を5ステップで解説しています。すぐに活用できるチェックリストもありますので、本記事と合わせて確認してみてください。

人事部と現場の乖離を解消するためには現場把握と意識共有が重要
人事部と現場では、採用・配置・評価といった人事施策において乖離が生じるケースが少なくありません。
その背景には、人事部と現場の目的の違いや、ビジョンや情報の共有不足があります。乖離が著しい場合、生産性の低下や離職率の増加につながるため、早急に改善することが重要です。
乖離を減らすためには、現場の管理職と積極的にコミュニケーションを取り、方向性を擦り合わせることが必要です。加えて、現場の状況をデータ分析やヒアリングといった多様な手法によって多面的に把握する必要があります。
『ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ』では、社員の満足度や適性を把握できます。とくにケアが必要な社員の可視化や、現場で行われたケア状況の一覧化も可能なため、現場の状態を理解しやすくなります。
現場との乖離を埋めるためのツールとして、『ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ』の導入を検討してみてはいかがでしょうか。
興味のある方は、以下より詳細をご覧ください。
従業員のメンタル状態の定期的な可視化・個々の性格に合わせたアドバイス提供を通じ、離職・休職を防ぐエンゲージメントサーベイ。無料トライアルの詳細は下記から。




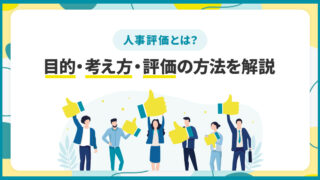










 ランキング1位
ランキング1位 
 ランキング2位
ランキング2位 
 ランキング3位
ランキング3位 