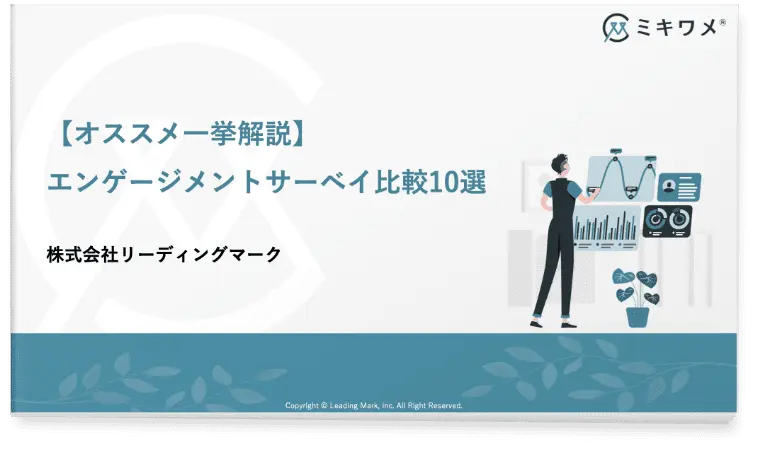近年、労働者が働く時間を自由に決める「フレックスタイム制」を導入する企業が増えていますが、フレックスタイム制における労働時間の考え方や、コアタイム・フレキシブルタイムの違いについてご存知でしょうか。
本記事では、フレックスタイム制の仕組みや導入後のメリット・デメリットについて解説します。
フレックスタイム制とは
フレックスタイム制とは、一定期間の総労働時間の範囲内で、労働者が始業時刻と終業時刻を自由に決められる制度のことを指します。
必ず働かなければいけないコアタイムと、労働者が自由に労働時間を決められるフレキシブルタイムによって構成されていることが一般的で、労働者がその日の都合にあわせて柔軟に働けることが特長です。
フレックスタイム制の導入背景・現状
日本では、1987年の労働基準法改正により、労働時間を国際的な基準に合わせることを目的としてフレックスタイム制が導入されました。
厚生労働省が令和3年に実施した就労条件総合調査によると、フレックスタイム制を導入している企業の割合は6.5%となっています。内訳は、従業員数1,000人以上の企業が28.7%、300~999人の企業が15.6%、100~299人の企業が8.7%、30~99人の企業が4.1%と、従業員数が多い企業ほどフレックスタイム制の導入が進んでいることがわかります。
フレックスタイム制の仕組み
次に、フレックスタイム制の仕組みについて解説します。
コアタイム・フレキシブルタイムとは
前述の通り、フレックスタイム制は労働者が始業時刻や終業時刻を決められる制度ですが、一般的にはコアタイムとフレキシブルタイムが設定されているため、24時間いつでも自由に働けるというわけではありません。
コアタイムとは、労働者が必ず働かなければならない時間帯のことです。例えば、10時から16時までをコアタイムに設定している場合、その時間は対象となる従業員全員が勤務する必要があります。コアタイムを設定することで、従業員同士の情報共有やコミュニケーションが円滑となり、共同作業もスムーズに行えるといった効果があります。
一方、フレキシブルタイムとは、労働者が始業時刻と終業時刻を自由に調整できる時間帯のことです。例えば、10時から16時までをコアタイムに設定している場合、8時から10時と16時から20時をフレキシブルタイムと設定するなど、コアタイムの前後にフレキシブルタイムを設けることが一般的です。
なお、企業によってはコアタイムを設けないスーパーフレックスタイム制を採用しているケースもあります。
清算期間・総労働時間とは
フレックスタイム制を導入するためには、一定の期間(清算期間)で働かなければならない総労働時間を労使協定で定める必要があります。
これまでのフレックスタイム制では、清算期間の上限が1カ月に設定されていましたが、2019年の法改正により上限が3カ月に延長されたため、より柔軟な働き方ができるようになりました。
総労働時間は企業によって異なりますが、1週間の労働時間が40時間以内(労働者が常時10人未満の特例措置対象事業所の場合は44時間以内)となるよう定める必要があります。
休憩時間の仕組み
フレックスタイム制を導入していても、労働時間が6時間を超える場合は最低45分、8時間を超える場合は最低1時間の休憩時間を確保する必要があります。
コアタイムを設けていない場合でも休憩時間が必要となるため、注意しましょう。
残業の仕組み
また、フレックスタイム制を導入していても、時間外労働が発生した場合は残業代を支払う必要があります。
一般的に、時間外労働とは法定労働時間を超えて働くことを指しますが、フレックスタイム制を導入している場合は、清算期間内の総労働時間を超えて働くことを指します。例えば、清算期間が1カ月、総労働時間が160時間であるにもかかわらず、実際には1カ月で190時間働いた場合は、30時間分が時間外労働とみなされ、残業代が発生します。
なお、実際に働いた時間が総労働時間に達しなかった場合は、不足時間分を次の清算期間に繰り越すことが認められています。
休日出勤の仕組み
休日には、労働基準法で週に1日もしくは4週間に4日以上の取得が義務付けられている法定休日と、それ以外の法定外休日があります。
フレックスタイム制を導入している企業の従業員が法定休日に勤務した時間は総労働時間に含まれないため、35%の割増賃金を支払う必要がありますが、法定外休日の勤務時間を総労働時間に含めるかどうかは労使協定で自由に定めることができます。
有給休暇の仕組み
さらに、フレックスタイム制を導入している企業の従業員も有給休暇を取得することができます。有給休暇を取得した場合は、労使協定で定められている1日の標準労働時間分働いたものとみなして賃金を支払います。
例えば、1日の標準労働時間が8時間の従業員が有給休暇を3日取得した場合、実労働時間に「8時間×3日=24時間」を加えて賃金を計算します。
フレックスタイム制のメリット
フレックスタイム制を導入するメリットは以下の通りです。
- 従業員が柔軟かつ効率的に働ける
- 企業の人材確保につながる
それぞれ具体的に解説します。
従業員が柔軟かつ効率的に働ける
フレックスタイム制の一番のメリットは、従業員が個人の都合に合わせて柔軟かつ効率的に働けることです。
始業時刻と終業時刻を自由に決められるため、仕事と育児・介護を両立したり、通勤ラッシュを避けて出社したりすることができるようになります。ワークライフバランスを保ち、プライベートを充実させることで企業に対する満足度も向上するでしょう。
また、フレキシブルタイムを設けることで、繁忙期は多く働き、閑散期ははやめに退勤するといった効率的な働き方を実現することも可能です。特に、季節によって業務量に波がある職種には効果的です。
企業の人材確保につながる
また、フレックスタイムを導入することで、企業側もメリットを得られます。
採用活動において、フレックスタイム制の自由度の高い働き方は、求職者に対する大きなアピールポイントとなります。ワークライフバランスを重視した、柔軟な働き方を望んでいる求職者にアプローチすることで、新たな人材の確保につなげることができます。
フレックスタイム制のデメリット
一方、フレックスタイム制には以下のようなデメリットも存在します。
- 企業の生産性が低下する恐れがある
- フレックスタイム制が不向きな職種もある
それぞれ具体的に解説します。
企業の生産性が低下する恐れがある
フレックスタイム制を導入すると、従業員が揃わない時間帯が増えるため、直接会ってコミュニケーションをとる機会が減少し、情報共有が難しくなります。これにより、業務がスムーズに進まなくなるリスクがあります。また、従業員の裁量が大きくなるため、自己管理が苦手な人は時間にルーズな働き方になる恐れもあります。
フレックスタイム制が不向きな職種もある
また、取引先や他部署の従業員と連絡をとる機会が多く、毎日決まった時間に働かなければならない職種は、フレックスタイム制の導入に不向きといえます。デザイナーやエンジニアなど、個人で業務が完結する専門職であれば、フレックスタイム制を導入してもこれまで通り働くことができますが、導入に向いていない職種があることに留意しましょう。
まとめ
フレックスタイム制とは、一定期間の総労働時間の範囲内で、労働者が始業時刻と終業時刻を自由に決められる制度のことを指します。要件を満たせば、その日の都合にあわせて柔軟に働けることが特長です。
フレックスタイム制の導入をアピールすることで、企業が人材を確保しやすくなるというメリットがある一方、フレックスタイム制が不向きな職場では生産性が低下する恐れもあります。また、休憩時間や残業、休日出勤などの仕組みは企業によって異なる部分もあるため、あらかじめ労働者に周知しておくことが大切です。
参考:
フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き
フレックスタイム制を簡単解説!調査に基づく84社の実態も紹介 | d’s JOURNAL(dsj)- 採用で組織をデザインする | 採用テクニック
フレックスタイム制の意味とは?コアタイムやメリット・デメリット
フレックスタイム制度Q&A|フレックス制度導入サポート|業務内容|ワークライフバランス研究所
ミキワメAI 適性検査は、候補者が活躍できる人材かどうかを見極める適性検査です。
社員分析もできる無料トライアルを実施中。まずお気軽にお問い合わせください。

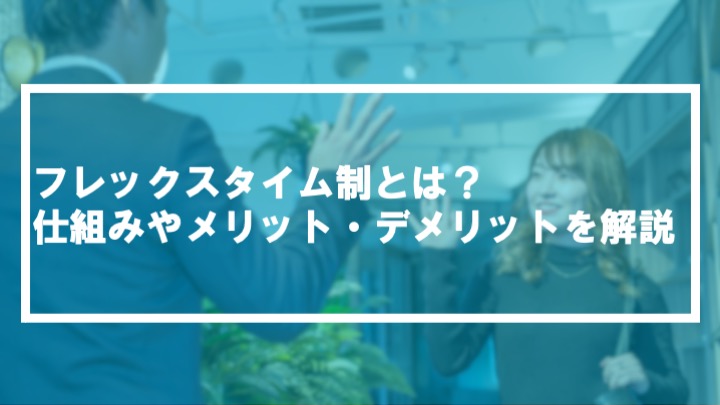
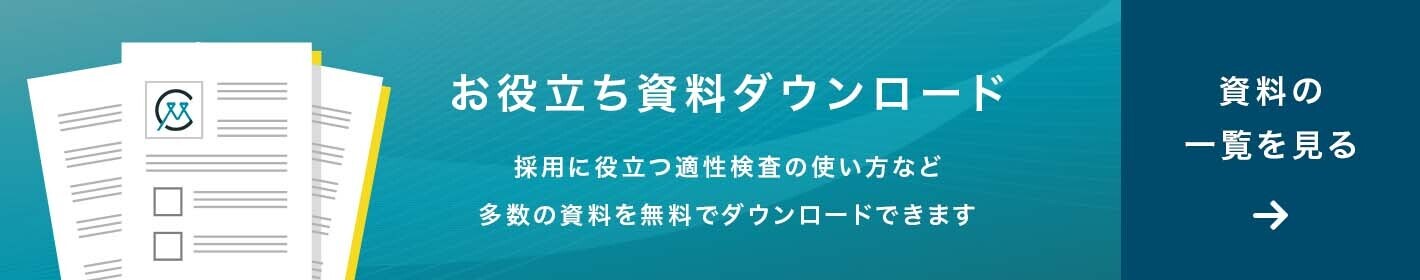
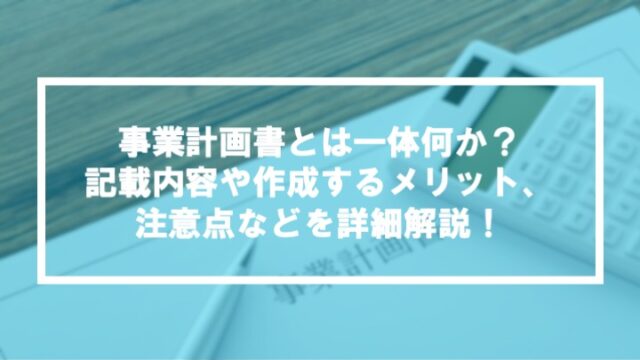
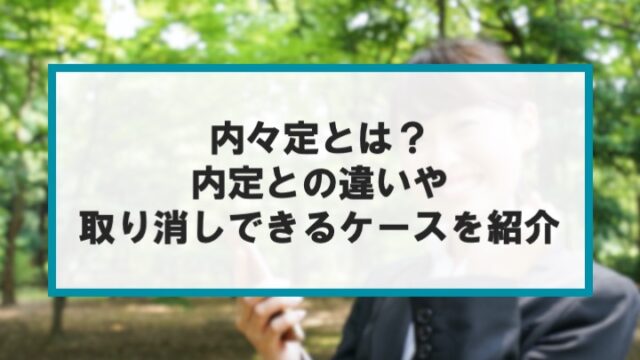
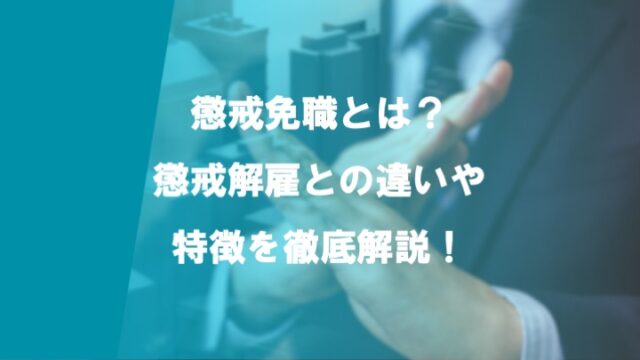

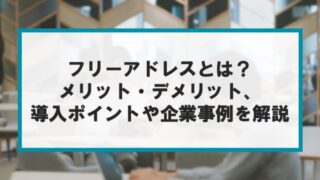
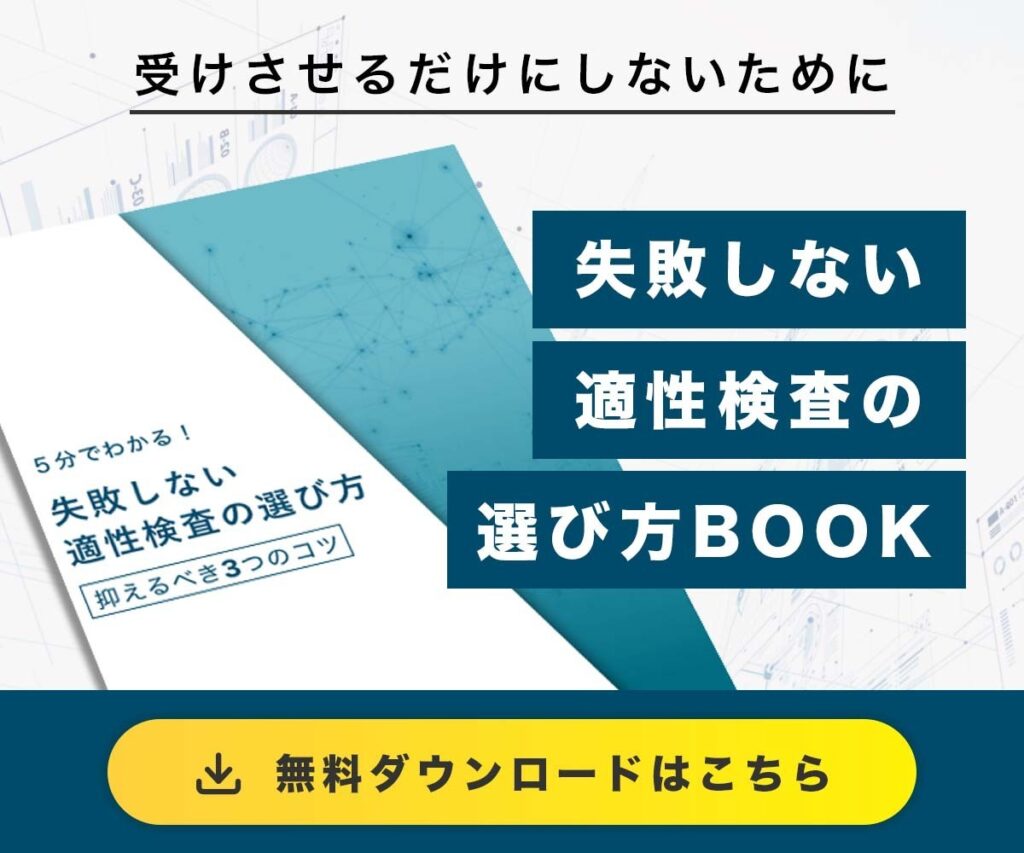

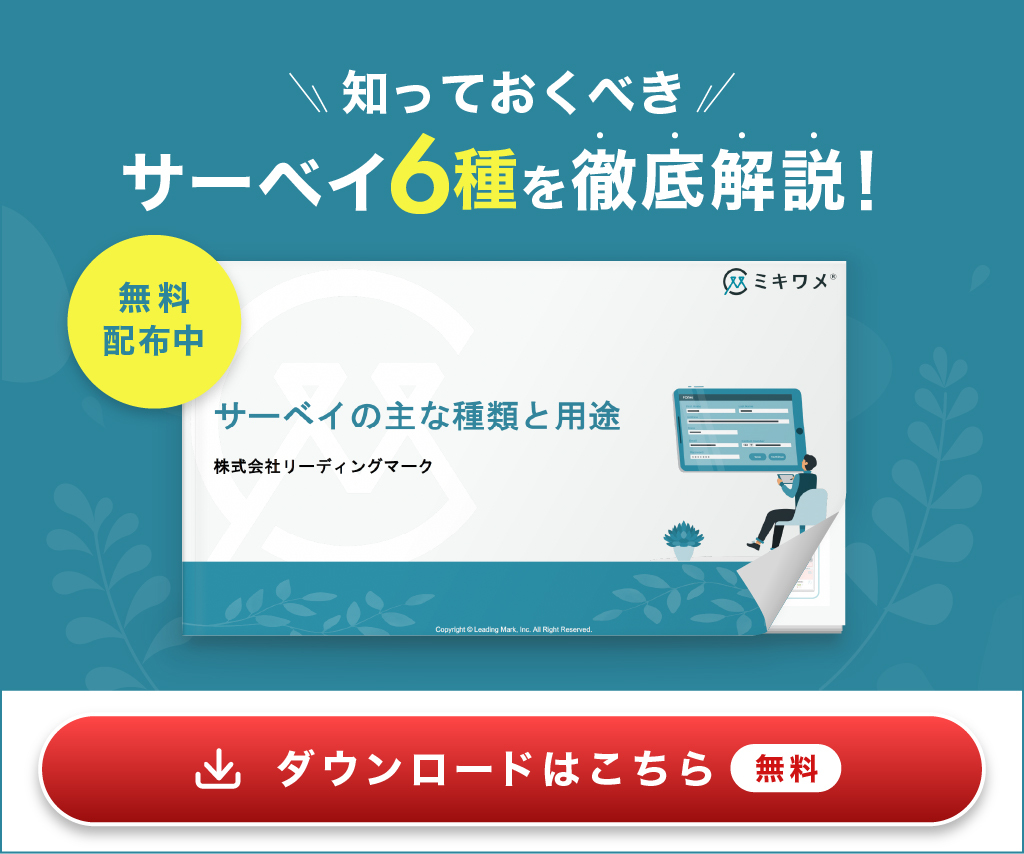

 ランキング1位
ランキング1位 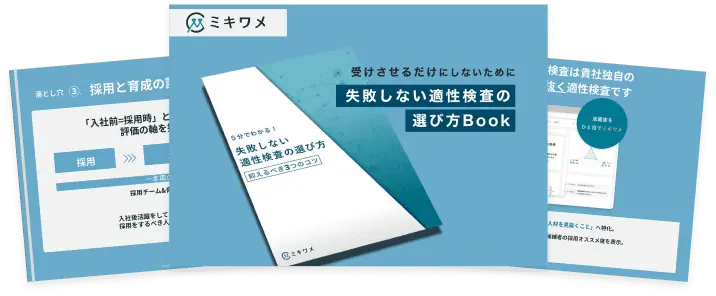
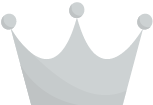 ランキング2位
ランキング2位 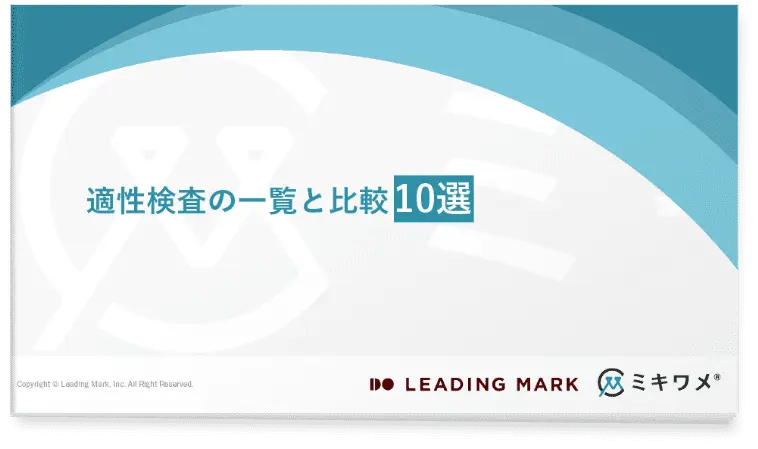
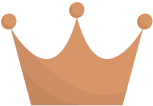 ランキング3位
ランキング3位