ストレスチェックとエンゲージメントサーベイは同じ「調査」でも、目的が異なります。ストレスチェックはメンタル不調の一次予防に役立ち、エンゲージメントサーベイは離職防止や組織力の向上を目的とした組織改善型の調査です。
そのため、どちらか一方だけを実施している企業では、従業員の健康リスクや離職要因を正確に把握できず、対策が後手に回る傾向があります。
本記事では、エンゲージメントサーベイとストレスチェックの違いをわかりやすく整理し、自社はどちらを導入すべきか、併用は必要かを判断できるよう解説します。
「年1回のストレスチェックが形式化している」「人的資本経営に向けてデータを活用したい」という企業の人事責任者の方は、ぜひ参考にしてください。

エンゲージメントサーベイとは?
エンゲージメントサーベイとは、従業員が「会社や仕事にどれだけ愛着や貢献意欲を持っているか(=エンゲージメント)」を測定し、離職防止や組織改善につなげるための調査(=サーベイ)です。
従業員満足度(ES)調査が「不満の有無」を測るのに対し、エンゲージメントサーベイは組織への貢献意欲や仕事への没頭感、企業との心理的結びつきなどを調査・評価する点が特徴です。
アメリカのGallup社が2023年に発表した調査によれば、エンゲージメントの高い企業は低い企業と比べて生産性が18%向上し、離職率は最大43%低い傾向があることが報告されています。
このことから、近年では国内外問わず、人的資本経営の基盤としてエンゲージメントサーベイの活用が進んでいます。
出典: State of the Global Workplace Report – Gallup
実施の目的
エンゲージメントサーベイを実施する最大の目的は、組織の課題を可視化し、従業員のモチベーション低下や離職リスクを早期に把握することです。
単なる満足度の調査では見えにくい、心理的安全性や働きがいの有無、マネジメントの質といった要因を明らかにすることで、改善アクションの優先順位が明確になります。
実施対象
管理職・一般社員を含む全従業員が主な対象です。
部署ごとに実施結果を比較し、組織全体の傾向を把握しながら、部門ごとの離職リスク分析や組織改善に活用します。
改善対象
エンゲージメントサーベイは、組織課題の改善を目的としたサーベイです。
改善対象となるのは個人のメンタルや感情だけではなく、職場環境・上司との関係・心理的安全性・人事制度・キャリア支援・働きがいなど、組織課題全般です。
たとえば、次のような従業員体験(EX)向上や離職防止、生産性向上に直結する課題の発見・解決に役立ちます。
- 上司のマネジメントスタイルに課題がある
- 評価制度・育成制度の不公平感がある
- 仕事の裁量がなく主体性が育ちにくい
- 会社のビジョンが浸透していない
- 職場に心理的安全性が欠けている
活用方法
エンゲージメントサーベイは、実施して終わりでは意味がありません。
結果を組織改善施策・マネジメント教育・人事戦略の設計に反映することが重要です。具体的には、
- 離職リスクの高い部門の特定
- マネジメント改善に向けた1on1推進
- 組織風土改革・心理的安全性の醸成
- サクセッションプラン(後継者育成計画)への活用
- 人的資本開示に向けたデータ活用
といった取り組みへ結びつけることができます。
質問・回答形式
エンゲージメントサーベイの質問項目は「仕事への熱意」「上司との関係」など多岐にわたり、回答は5~7段階のリッカート尺度(「まったくそう思わない」〜「非常にそう思う」)から選択するのが一般的です。
【質問形式】
| 質問項目のカテゴリ | 設問例 |
|---|---|
| 仕事への熱意 | 私は今の仕事にやりがいを感じている |
| 上司との関係 | 上司は私の意見に耳を傾けてくれる |
| 組織への信頼 | この会社は従業員を大切にしていると思う |
| チームの心理的安全性 | 職場では安心して意見を言える雰囲気がある |
| 成長機会 | この会社では成長の機会が与えられている |
| 働きやすさ | 業務量や働き方に無理がないと感じる |
【回答形式例(リッカート尺度)】
- 全くそう思わない
- ほとんどそう思わない
- あまりそう思わない
- どちらともいえない
- ややそう思う
- かなりそう思う
- 非常にそう思う
このような設問でデータを収集するため、感覚ではなく数値でエンゲージメントの推移や課題を分析できるのが大きな特徴です。
データの取得方法や分析方法
オンラインツールで定期的に実施し、部署別・属性別・年代別などの多軸分析(ピープルアナリティクス)が可能です。
組織の変化を継続的に追うことで、離職や不調の予兆を早期に察知できます。
ストレスチェックとは?
ストレスチェックとは、従業員の心理的ストレス状況を把握し、メンタルヘルス不調の一次予防(未然防止)を目的に実施される検査です。
労働安全衛生法に基づき、2015年12月から常時50人以上の労働者がいる事業場では、年1回以上の実施が義務付けられています。
近年では、健康管理だけではなく人的資本経営の観点からも、ストレスチェックの活用が求められています。
ただし、企業によっては実施が形式的になり、結果を活用せずに年1回のチェックで終わる点が課題です。
出典:厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」
実施の目的
ストレスチェックの目的は、従業員の心の健康リスクを早期に把握し、うつ病や適応障害などの発症を未然に防ぐことです。
厚生労働省は「個人のメンタルヘルス不調の予防」を一次予防の段階として重視しており、「従業員本人のストレスへの気づきの促進」「職場環境の改善」を目的としてストレスチェックを制度化しています。
出典:厚生労働省「改正労働安全衛⽣法に基づくストレスチェック制度の概要」
実施対象
ストレスチェックの対象となるのは、正社員だけではなく、契約社員やパートタイム労働者を含む「常時使用するすべての労働者」です。したがって、管理監督者にあたる管理職も対象に含まれます。
また、検査の実施は医師・保健師・一定の研修を受けた看護師または精神保健福祉士が担当し、人事部が個人の結果を閲覧することは法律で禁止されています(※)。
(※)本人の同意がある場合を除く
改善対象
ストレスチェックは、個人のメンタル不調リスクを発見するだけではなく、職場全体のストレス要因の分析にも活用可能です。
具体的には、次の2種類を発見・改善できます。
- 個人:長時間労働による疲労、睡眠不足、情緒不安、不安定なメンタル
- 組織:上司との関係悪化、職場の人間関係、業務過多、ハラスメント環境
活用方法
ストレスチェックの結果は、次のように活用できます。
- 高ストレス者へ産業医による面談を実施する
- 必要に応じて就業の配慮をおこなう(配置転換・勤務時間調整など)
- メンタル不調者を早期発見し、支援する
- 高ストレス部署を特定する
- 業務量・組織構造・コミュニケーションに関する職場改善施策を実施する
- ハラスメント・パワハラリスクを把握しケアする
質問・回答形式
厚生労働省が推奨する「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」が代表的で、仕事の負荷・人間関係・身体・感情の反応・職場の支援体制などを多角的に測定します。
回答形式は4〜5段階のリッカート尺度で、スコア化してリスク判定をおこないます。
【質問形式】
| 質問項目のカテゴリ | 設問例 |
|---|---|
| 仕事量 | 非常にたくさんの仕事をしなければならない |
| 心理的反応 | 気分が晴れず憂うつだ |
| サポートの有無 | 困ったときに相談できる同僚がいる |
【回答形式例(リッカート尺度)】
- まったくそう思わない
- あまりそう思わない
- どちらともいえない
- ややそう思う
- 非常にそう思う
データの取得方法や分析方法
ストレスチェックは通常、匿名式のWebまたは紙アンケートで実施され、集団分析結果は事業者に開示されます。
ただし制度上、
- 個人結果は本人の同意なしに企業が閲覧できない
- 集団分析は結果の活用方法が人事担当に委ねられている
という課題があるため、改善施策まで実施できない企業が多く、運用設計の質が成果を左右する制度といえます。
エンゲージメントサーベイとストレスチェックの違い【比較表あり】
エンゲージメントサーベイとストレスチェックはいずれも「従業員の状態を把握する調査」ですが、目的や対象、活用場面などが大きく異なります。
エンゲージメントサーベイが離職防止・組織改善・従業員体験(Employee Experience/EX)の向上を目的とするのに対し、ストレスチェックはメンタルヘルス不調の予防を目的とした制度です。
| 比較項目 | エンゲージメントサーベイ | ストレスチェック |
|---|---|---|
| 主な実施目的 | 従業員の働きがい・組織への貢献意欲を可視化し、組織改善につなげる | メンタル不調の一次予防と高ストレス者の早期把握 |
| 法的位置づけ | 任意 | 労働安全衛生法に基づき50人以上の事業場で実施義務あり |
| 対象者 | 全従業員・部署単位 | 全従業員(常時使用者) |
| 改善対象 | 個人・組織のエンゲージメントや心理的安全性、マネジメント課題など | 長時間労働による疲労、不安定なメンタル、職場の人間関係、業務過多など |
| 活用の効果 | 生産性向上・離職防止など | 休職・離職リスクの早期発見など |
| 実施頻度 | 半期〜四半期ごとが多い | 年1回以上(義務) |
このように、エンゲージメントサーベイは「組織の強化」を目的としているのに対し、ストレスチェックは「健康リスクの管理」が目的であり、そもそも役割が異なる調査です。
そのため、どちらが優れているかを比較するものではなく、役割に応じて使い分ける必要があります。
エンゲージメントサーベイとストレスチェックはどちらを導入すべき?
ストレスチェックは法令対応上で、エンゲージメントサーベイは組織改善に必須のツールです。
目的が異なるため「どちらかを選ぶ」という発想ではなく、役割に応じた導入が求められます。
まず、ストレスチェックは労働安全衛生法により、常時50人以上の労働者がいる事業場で年1回以上の実施が義務化されています。目的はメンタルヘルス不調の一次予防であり、法令遵守の観点から導入が欠かせません。
一方で、離職率の高さや組織の停滞感といった課題を感じている企業では、健康状態だけではなく社員の意欲・組織の健全性を把握するエンゲージメントサーベイの導入が不可欠です。
- 法令対応・メンタル不調の一次予防がしたい→ストレスチェック
- 離職率改善・組織改善・組織開発がしたい→エンゲージメントサーベイ
また、次のような状態に当てはまる場合、ストレスチェックだけでは不十分です。
- 離職率が高い、人材定着が課題になっている
- 評価制度やマネジメントに不満の声がある
- 組織の心理的安全性が低く意見が出にくい
- 人的資本経営や健康経営に取り組みたい
ここからは、両者を併用すべき理由を解説します。
エンゲージメントサーベイの導入率や市場動向について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。サーベイ導入による効果や、具体的な運用フローも解説しています。

エンゲージメントサーベイとストレスチェックは併用が効果的
企業はストレスチェックとエンゲージメントサーベイを併用すべきです。ストレスチェックは従業員の心理的負担を把握し、メンタル不調を未然に防ぐ一次予防を目的としています。しかし、高ストレスの原因や離職リスクの背景までは明らかにできません。
一方、エンゲージメントサーベイは職場環境やマネジメントの課題を可視化し、離職防止・組織改善に役立つデータを得られますが、健康リスクの高い層を把握する機能はありません。
したがって、両者を併用することで次のような相乗効果が生まれます。
- ①離職リスクを早期発見できる
高ストレス者だけではなく、モチベーションが低下している「要注意層」を可視化できる
- ②個人の不調と組織課題の因果関係を把握できる
職場環境・マネジメント・業務量など改善が必要な領域を特定しやすくなる
- ③人的資本経営・健康経営の両面をカバーできる
法令対応と組織戦略を同時に進められる
つまり、
- ストレスチェック=従業員を守るリスク管理(守り)
- エンゲージメントサーベイ=組織力を高める改善施策(攻め)
という位置づけです。両者の役割を組み合わせて活用することで、個人支援と組織改善を両立する健康経営を実現できます。
以下の記事では、労働安全衛生法に準拠した検査を、簡単な操作で実施できる『ミキワメ ストレスチェック』について詳しく解説しています。
ミキワメは、厚生労働省が推奨する57項目に加え、組織分析に活用できる全80項目の検査に対応している検査サービス(無料)です。ストレスチェック義務化に向けて進めている人事担当者の方は、ぜひミキワメを機能を確認してみてください。

エンゲージメントサーベイとストレスチェックを実施して健康経営を実現しよう
エンゲージメントサーベイが離職防止や組織改善の「推進」に役立つ一方、ストレスチェックは従業員のメンタル不調の「予防」に欠かせない調査です。
両者を併用することで、従業員のモチベーションと健康状態を継続的に可視化しつつ、個人ケアと組織改善を同時に進め、効率的な健康経営を実現できます。
「ミキワメ ウェルビーイングサーベイ」なら、サーベイ結果の集計だけで終わらせず、離職リスクの高い層やチームの課題領域を自動で特定できます。さらに、AIが結果をもとに具体的な改善アクションを提示するため「データは取れたが次に何をすべきかわからない」というサーベイ運用の課題を解消できます。
感覚や属人的な判断に頼らず、データに基づく組織改善と健康経営の実践を進めたい企業に最適なソリューションです。
詳細は以下からご確認いただけます。
従業員のメンタル状態の定期的な可視化・個々の性格に合わせたアドバイス提供を通じ、離職・休職を防ぐエンゲージメントサーベイ。無料トライアルの詳細は下記から。


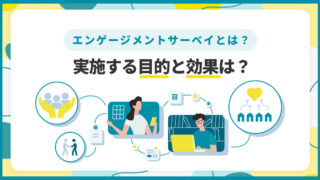












 ランキング1位
ランキング1位 
 ランキング2位
ランキング2位 
 ランキング3位
ランキング3位 