「最近、社員を採用してもすぐに辞めてしまう」「人材が育つ前に流出する」といったお悩みを抱える企業は少なくありません。
終身雇用が過去のものとなり、SNSや口コミサイトで企業の評判が可視化される今、優秀な人材を定着・活躍させるためには、従業員の体験全体を最適化する「Employee Experience(EX)」の向上が不可欠です。
本記事では、EXの定義からエンゲージメントとの違い、高めるメリットや具体的な取り組み、成功企業の事例まで網羅的に解説します。

- Employee Experience(EX)とは?エンゲージメントとの違いについて
- Employee Experience(EX)を高めるメリットや重要性
- Employee Experience(EX)が注目される社会的背景
- Employee Experience(EX)を高めるための取り組み
- Employee Experience(EX)向上に欠かせない「Employee Journey Map」とは
- Employee Journey Mapの作成方法
- Employee Experience(EX)の向上に成功している企業事例
- Employee Experience(EX)を高めて離職率低下を回避し生産性向上を図ろう
Employee Experience(EX)とは?エンゲージメントとの違いについて
Employee Experience(従業員エクスペリエンス、以下EX)とは、従業員が企業に在籍する間に得られるすべての体験を指す言葉です。
EXには、出来事やプロセス、スキルの獲得だけではなく、採用・オンボーディング・評価・昇進・退職といった各フェーズで、従業員が「感じたこと」や「考えたこと」といった心理的・感情的な体験も含まれます。
混同されやすい「エンゲージメント」とは、従業員が組織に対して持つ愛着や貢献意欲のことで、EXとは次のように特徴が異なります。
| 用語 | 意味 | 特徴 |
|---|---|---|
| EX | 従業員が企業内で体験するすべての出来事・プロセス・感情 | 環境・制度・文化など、組織側が設計することではじめて生まれる。EXが高いとエンゲージメントも高まりやすい |
| エンゲージメント | 従業員が組織に抱く愛着・信頼・貢献意欲 | 従業員の内面から自然に生まれる心理的な反応。EXの良し悪しによって大きく左右される |
つまり、EXは「企業によってもたらされる体験」、エンゲージメントはその結果として現れる「企業に対する愛着心」と考えるとわかりやすいでしょう。
Employee Experience(EX)を高めるメリットや重要性
EXを高めるメリットや重要性は次のとおりです。
- 会社への帰属意識が向上し離職率が低下する
- 企業イメージが向上し優秀な人材の確保につながる
- 業務の生産性が高まり利益につながる
それぞれ解説します。
会社への帰属意識が向上し離職率が低下する
EXを高めることは、従業員の「ここで働き続けたい」という帰属意識を高め、結果として離職率の低下につながります。帰属意識とは、従業員が組織の一員として受け入れられていると実感し、自らの存在価値を見出す感覚です。
帰属意識の高い従業員は「この会社の一部でありたい」「この職場で役に立ちたい」といった気持ちを抱くため、業務に対して主体的な姿勢で取り組み、同僚・上司との関係性を良好に保ちます。
ちょっとした不満や摩擦があっても「自分がこの職場を良くしたい」という前向きな行動に変換されやすく、離職しにくいのが特徴です。
離職率が高い企業では、採用・教育にかかるコストがかさみ、組織全体の生産性が低下します。従業員一人ひとりのEXを高めることは、こうしたコストを削減するためにも有効な施策といえるでしょう。
企業イメージが向上し優秀な人材の確保につながる
EXの高い職場で働く社員は、日常生活やSNS上で自社のポジティブなイメージを発信するため、企業の評判が自然と広がり、優秀な人材の確保につながります。
とくに近年では、就職・転職活動において企業の評判をSNSや口コミサイトでチェックする求職者が増えており、社員の生の声が採用活動に大きな影響を与えます。
たとえば「働きやすい」「成長を実感できる」といった投稿が目に留まれば、企業に対する信頼感や興味が醸成され、応募へのハードルが下がるでしょう。
逆に、ネガティブな体験が拡散された場合、企業イメージの毀損や内定辞退につながりかねません。そのため、日頃からEXの改善に取り組むことが、長期的な採用力の強化にも直結します。
「働きやすい会社」としてのブランディングが確立すれば、求職者の応募率や質が向上し、採用効率が飛躍的にアップするでしょう。
業務の生産性が高まり利益につながる
EX向上のため、従業員にとって働きやすい環境を整えることは業務の生産性に良い影響を与え、利益向上につながります。
従業員が安心して意見を出せる環境や、成長を実感できる制度が整っている職場ではエンゲージメントが高まり、モチベーション向上にもつながるため、結果として生産性が上がります。
実際にGallupの最新調査において、エンゲージメントの高い組織はそうでない組織と比べて、利益が最大23%高いという結果が出ました。
参考:World’s Largest Ongoing Study of the Employee Experience
Employee Experience(EX)が注目される社会的背景
近年、Employee Experience(EX)が注目されている社会的背景としては、次の4つが挙げられます。
- 人材不足により労働力が減少している
- 人材の流動化が激しい
- 働き方に関する価値観が変化している
- SNSや口コミサイトが普及している
それぞれ解説します。
人材不足により労働力が減少している
EXが注目される背景には、少子高齢化により労働力人口が減少し、企業にとって「人材の奪い合い」が常態化している現状があります。
中途・若手・女性・シニアといったあらゆる層での人材確保が難航するなか、EXを高めて企業価値や働きやすさを訴求することが採用戦略の鍵といえます。
また、労働力不足を補うためには、限られた人材リソースを有効活用していくことも重要です。
EX向上を図ることで従業員の定着を目指し、一人ひとりがパフォーマンスを発揮できる環境づくりが求められています。
人材の流動化が激しい
「終身雇用」の時代が終わり、現在ではひとつの会社に一生勤めるという考え方が薄れているため、人材の流動化が激しいこともEXが注目される要因です。
多様な働き方やキャリア志向が主流となり、副業や転職、副業・兼業が当たり前となった現在では、従業員が自発的に「この会社に残りたい」と感じられる体験設計の重要性が高まっています。
流動性の高い労働市場では、EX向上により従業員のエンゲージメントを育むことが、定着率と組織力の維持につながります。
働き方に関する価値観が変化している
リモートワーク、副業、時短勤務、週休3日など、従業員が求める働き方は多様化の一途をたどっています。
従来の画一的な制度では満足度を高めることが難しくなっており、個々のライフスタイルやキャリアプランに合わせた柔軟な制度の設計が必要です。
働き方の選択肢が広がるなかで、企業がEXを軸として一人ひとりに寄り添った職場環境を整えることは、エンゲージメントの向上と人材流出の防止に直結します。
SNSや口コミサイトが普及している
企業の評判は、もはや社外秘ではありません。SNSや口コミサイトの普及により、現職・元社員の声がリアルタイムに拡散され、企業選びの判断材料として大きな影響力を持つようになりました。
ネガティブな退職エピソードが炎上すれば採用・定着に深刻なダメージを与えかねません。一方、ポジティブな職場体験が広まれば企業イメージが向上し、応募数や質にも好影響をもたらします。
EXを改善することは、こうしたデジタル時代のレピュテーションリスクを回避するうえでも有効な手段です。
Employee Experience(EX)を高めるための取り組み
Employee Experience(EX)を高めるために有効な取り組みは次の5つです。
- コミュニケーションの機会を設ける
- 従業員の想いや意見を吸い上げる
- 働きやすい環境を整える
- 制度設計を見直す
- 成長をサポートする
それぞれ解説します。
コミュニケーションの機会を設ける
EXを向上させるためには、従業員とのコミュニケーションの機会を設けることが欠かせません。
1on1面談や社内チャット、社内報などを通じて従業員の声に耳を傾けることで、信頼関係や心理的安全性の構築を図れます。
たとえば、上司からの定期的なフィードバックがある環境だと、部下は不安や不満を抱え込みにくくなり、早期離職のリスクが下がります。
従業員の想いや意見を吸い上げる
従業員の想いや意見を吸い上げて現場に反映させる仕組みづくりも、EX向上のために重要です。
従業員の不満や違和感を早期に解消すれば「自分の意見が尊重されている」と実感してもらいやすく、働きやすさや満足度の向上につながります。
具体的には、定期的な社内アンケートや匿名の意見箱、1on1面談などを通じて従業員の声を集め、そのフィードバックをもとに制度や運営方針を見直すとよいでしょう。
意見が反映された経験を持つ従業員は、会社への信頼や愛着を抱き、エンゲージメントの向上とEXの底上げに寄与します。
働きやすい環境を整える
EX向上のためには、従業員が安心して働ける環境づくりが欠かせません。
なぜなら、物理的な働きやすさや心理的安全性の確保は、従業員の集中力や生産性に直結するからです。
たとえば、オフィスのレイアウト改善や、リラックスできる休憩スペースの設置、社内カフェや無料ドリンクの提供といった物理的な取り組みが挙げられます。加えて、ハラスメントのない風通しの良い風土づくりや、メンタルケアの仕組みなども重要です。
職場の「居心地の良さ」は、離職防止やエンゲージメント向上にも寄与します。
制度設計を見直す
従業員の働きやすさを支える制度を見直すことは、EX向上の土台となる重要な要素です。
なぜなら、個々のライフステージや価値観に合わない制度設計は、離職やモチベーション低下の原因になりうるからです。
たとえば、産休・育休制度、副業許可、フレックス制、リモート勤務の導入といった柔軟な制度設計を行えば、従業員は「自分らしい働き方ができる」と実感でき、長く働きたいという意欲にもつながります。
成長をサポートする
従業員の成長をサポートする仕組みを整えることも、EX向上において欠かせない要素です。
「この会社で成長できる」と実感できる環境は、従業員のエンゲージメントを高め、長期的な定着やモチベーション維持に直結します。
社内研修制度やeラーニング、資格取得支援などのスキルアップ施策をはじめ、ジョブローテーション制度やキャリア面談といった中長期的なキャリア支援を行うことで、従業員は将来像を描きながら前向きに働けるでしょう。
さらに、従業員の志向や適性に応じて成長機会を提供すれば「この会社にいれば自分はもっと高められる」といった自己実現感を得られ、結果として企業への愛着や信頼にもつながります。
Employee Experience(EX)向上に欠かせない「Employee Journey Map」とは
Employee Journey Map(エンプロイー・ジャーニー・マップ)とは、従業員が企業に在籍する間に経験する各フェーズを時系列で可視化し、課題や感情の変化を整理する手法です。
たとえば、オンボーディングの段階で従業員が「初日から放置された」と感じた場合、早期離職の引き金となる可能性があります。
一方、入社直後にウェルカムメッセージや個別面談などのフォローがあると、「この会社は自分を大切にしてくれている」という安心感が生まれ、帰属意識の醸成につながります。
Employee Journey Mapの作成により、採用前から退職後までの各フェーズにおいて従業員が「自分は会社から大切にされている」と実感できる体験を設計できれば、EX向上と職場定着率の改善を同時に実現可能です。
Employee Journey Mapの作成方法
Employee Journey Mapは次の6ステップで作成可能です。
- ペルソナ(自社の従業員像)を設定する
- フェーズを分類する
- ペルソナのやりたいことや心理を記入する
- フェーズごとにペルソナの動きを予想する
- 対策を記入する
- 分析結果をもとにEX向上の施策を設計する
各ステップについて解説します。
1.ペルソナ(自社の従業員像)を設定する
まずは、年齢・性別・役職・キャリア志向・価値観などをもとに、自社における従業員の典型像を設定します。
たとえば「30代前半の営業職で、マネジメント志向があり、ワークライフバランスを重視している」といった人物像を描くことで、現実的かつ具体的な視点から体験設計を進めやすくなります。
2.フェーズを分類する
次に、採用前から入社直後、試用期間、評価・昇進、異動、退職、そして退職後のフォローに至るまで、従業員が体験するフェーズを時系列で整理していきます。
「入社初日の配属ミスで不信感が高まる」「異動時に適切な引き継ぎがなく戸惑う」といったボトルネックを特定する視点が重要です。
3.ペルソナのやりたいことや心理を記入する
各フェーズにおいて、その従業員が期待していること、不安に思っていること、求めているサポートなどを想定し、記入します。
例として、入社直後のペルソナは「業務を早く覚えたい」「人間関係に不安がある」と感じていることが想定されます。
4.フェーズごとにペルソナの動きを予想する
どのような行動や反応を取りやすいか、モチベーションやストレスの変化などを可視化し、ボトルネックとなりうる箇所を明らかにします。
たとえば、上司との定期的な1on1がないと「自分の意見が聞かれていない」と感じてモチベーションが下がる、といった反応を予測します。
以下の記事では、社員の性格や心理状態を踏まえた対話ができる『ミキワメ マネジメント』について詳しく解説しています。ミキワメは、社員の成長と成果を最大化する仕組みを構築できる1on1ツールです。
「部下と効果的な1on1ができていない」と悩んでいる人事担当者の方は、ぜひ確認してみてください。

5.対策を記入する
4で記入した内容をもとに、従業員に対してどのようなアクションをとるべきかを記入します。
たとえば、入社初日の不安解消には「ウェルカムランチの実施」「バディ制度の導入」などが挙げられます。制度設計、環境整備、コミュニケーション施策など幅広い視点での改善が必要です。
6.分析結果をもとにEX向上の施策を設計する
可視化したEmployee Journey Mapをもとに、改善すべき課題を洗い出し、優先順位をつけて具体策に落とし込みます。
たとえば、離職率が高いフェーズには重点的な対策を講じ、満足度調査や従業員の声と連動させて継続的な改善サイクルを回していきます。
Employee Experience(EX)の向上に成功している企業事例
Employee Experience(EX)の向上に成功している主な企業は次の4つです。
- Employee Experience(EX)専門部署を置く「Airbnb」
- 充実した学習機会の提供でEX向上に寄与する「スターバックス」
- 自由な働き方が魅力の「Netflix」
- 従業員へのホスピタリティーを徹底する「ヒルトンホテル」
それぞれの事例について解説します。
Employee Experience(EX)専門部署を置く「Airbnb」
Airbnbでは、従業員の働きがいや幸福度を最優先にする企業文化の一環として、EX専門チームを設置しています。この部署は、入社後のオンボーディングや評価制度の設計、社内イベントなど、従業員が体験するあらゆるプロセスに関与しているのが特徴です。
その結果、従業員満足度は非常に高く、Glassdoorが発表する「働きがいのある企業ランキング」にもランクインするなど、EXを戦略的に設計する姿勢が社外からも高い評価を受けています。
充実した学習機会の提供でEX向上に寄与する「スターバックス」
スターバックスでは、バリスタとして入社した従業員にも広く教育・キャリア開発の機会を提供するなど、人材育成に力を注いでいます。
オンライン研修、社内大学制度、マネジメントトレーニングなどを通じて、成長を望む従業員を支援する文化が根づいているのが特徴です。
こうした環境のもと、従業員は「この会社で成長できる」という実感を持ちやすくなり、エンゲージメントの向上や長期的な定着にも良い影響を与えています。
自由な働き方が魅力の「Netflix」
Netflixでは「自由と責任」のカルチャーが徹底されており、休暇取得の自由度や裁量のある働き方を従業員に委ねています。
たとえば、有給取得は無制限とされ、成果に基づいて評価される制度を導入。これにより、従業員は高いモチベーションを維持しながら自律的な働き方を実現できます。
自己決定権を尊重する企業姿勢が、心理的安全性の高い職場づくりにもつながっている成功例です。
従業員へのホスピタリティーを徹底する「ヒルトンホテル」
ヒルトンホテルでは「従業員が幸せでなければ、お客様を幸せにできない」という理念のもと、従業員に対する手厚い福利厚生と働きやすい制度を導入しています。
無料のまかない食、宿泊優待、家族手当、キャリアアップ支援制度など、物心両面からのサポートが充実しており、従業員の満足度・定着率が非常に高いことでも知られています。
従業員自身が「おもてなし」を体感できる環境があるからこそ、その精神が顧客対応にも自然と反映されているといえるでしょう。
Employee Experience(EX)を高めて離職率低下を回避し生産性向上を図ろう
EXの向上は、離職率の低下や生産性向上、企業ブランドの強化につながる重要な取り組みです。
従業員の声をもとに課題を可視化し、制度や評価、コミュニケーション環境を整えることで、「ここで働きたい」と思える職場づくりが実現します。
そのためには、従業員の心理的安全性や満足度を継続的に測定するツールの導入が欠かせません。
「ミキワメ ウェルビーイングサーベイ」は社員の今の心の状態を可視化し、何に悩みを感じているのか、どうコミュニケーションをとるべきなのかを提示します。
ツールの導入によって身近な問題改善から着手し、持続的に選ばれる組織づくりと生産性の向上を図りましょう。
ミキワメ ウェルビーイングサーベイの詳細は以下からご覧ください。
従業員のメンタル状態の定期的な可視化・個々の性格に合わせたアドバイス提供を通じ、離職・休職を防ぐエンゲージメントサーベイ。無料トライアルの詳細は下記から。







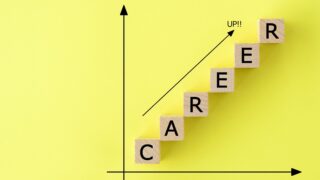









 ランキング1位
ランキング1位 
 ランキング2位
ランキング2位 
 ランキング3位
ランキング3位 