「Webテストを導入したいけど、替え玉受検されないか心配」
「オンラインの利便性を維持したまま、不正行為を防ぐ方法を知りたい」
採用活動を進める中で、このような課題に直面している人事担当者の方も多いでしょう。
近年、時間や場所を選ばず受検できるWeb適性検査が普及したことで、替え玉受検や生成AIの利用などの不正行為が増えています。
そこで本記事では、Web適性検査で実際に起きている不正の手口や、企業が行うべき具体的な対策をわかりやすく解説します。
- Web適性検査で起きている不正の現状・具体的な手口
- 不正が発覚した場合に受検者が負うリスク(内定取り消し など)
- 企業が導入すべき不正防止の方法(AI監視・本人確認 など)
この記事を読むことで、不正を未然に防ぐ具体的なポイントが明確になり、公正な選考フローを確立できるでしょう。ぜひ最後までご覧ください。
>>『ミキワメAI監視 in 適性検査』のお問い合わせはこちら
Web適性検査で不正は起きている?現状と背景

採用活動のオンライン化が進む中で、Web適性検査は多くの企業にとって必要不可欠なツールになりつつあります。時間・場所を問わず受検できる利便性が支持され、スムーズな選考を実現する手段として広く浸透しました。
しかし、監視のない環境で試験ができることを利用して、替え玉受検やカンニングなどの不正行為を行うケースが増えています。
以下では、Web適性検査における不正の現状と、そのような行為が増加している背景について詳しく解説します。
(現状)約45%が不正受検の経験あり
Web適性検査における不正は、一部の受検者に限った問題ではありません。実際の調査結果からも、不正の実態が明らかになっています。
株式会社サーティファイの調査によると、対象者591人のうち、45.5%にあたる269人がオンライン試験で「何らかのカンニングを実行した」と回答しました。具体的なカンニングの方法は、以下の図のとおりです。

出典:就活のWebテスト、45%が不正実行|株式会社サーティファイ
不正が増えている要因の一つは、採用試験のオンライン化によって受検環境の自由度が高まったことです。
自宅やカフェなど、監視の目が届かない場所で受検できるようになった結果、軽い気持ちでカンニングをしてしまうケースが増えています。
(背景)Webテストの普及と生成AIの登場
採用試験の不正受検が増えた背景には、Webテストの普及と生成AIの登場が大きく関係しています。
コロナ禍以降、企業の採用活動ではオンライン化が進み、会場で筆記試験や面接を実施する機会が減りました。
その結果、場所を選ばずいつでも受検できるWebテストが急速に広まり、多くの企業で標準的な選考手段として導入されています。
受検環境の利便性が高まり、スムーズな採用活動が可能になった一方で、受検者が替え玉受検やカンニングなどの不正を行いやすい環境にもなっています。
さらに近年は、ChatGPTをはじめとする生成AIの登場により、問題文を入力するだけで解答を瞬時に得られるようになりました。
このようにテクノロジーの進化と受検環境の変化が重なったことで、不正受検は以前よりも容易に行われるようになっているのです。
Web適性検査の詳細を確認したい方は、以下の記事をご覧ください。検査の種類や測定内容をわかりやすく解説しています。

Web適性検査における主な不正行為・手口
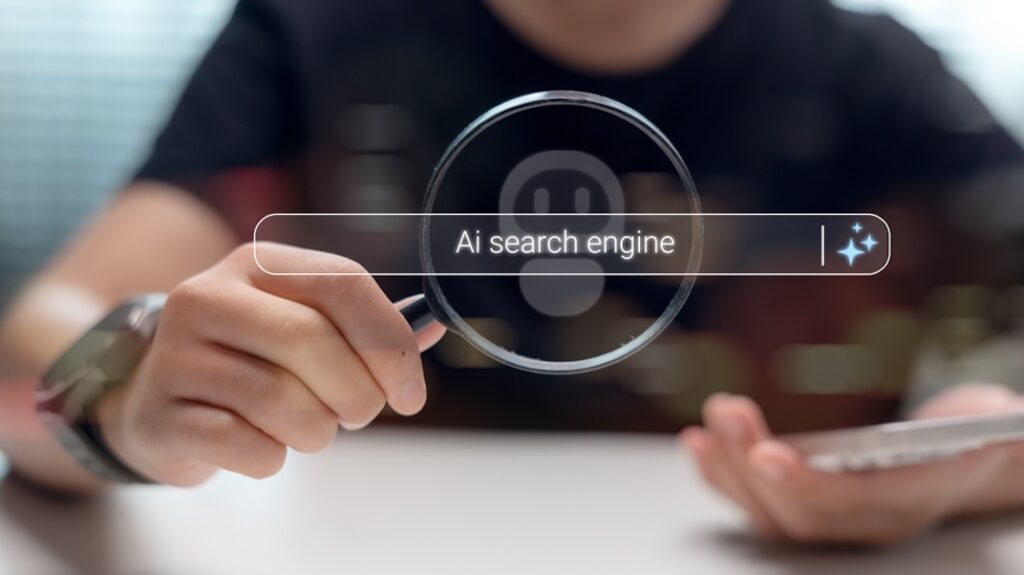
Web適性検査における不正は、企業側が対策を講じても、新しい手口が生まれているのが現状です。ここでは、主な不正行為や具体的な手口について解説します。
※以下の表は右にスクロールできます
| 不正行為 | 方法 | 不正の現状 (N=591)※ | 対策 |
|---|---|---|---|
| PC・スマホで情報を検索する | 問題文や選択肢の一部を検索エンジンに入力し、解説や答えを探す | 11.0%(PC) 17.6%(スマホ) | PCカメラ・マイクによる監視 |
| ChatGPTなどの生成AIを使う | ChatGPTやGeminiなどの生成AIを使って解答を導き出す | 11.5%(PC) 7.8%(スマホ) | |
| 書籍や資料でカンニングをする | 市販の対策本や問題集を使って答えを調べる | 9.3% | |
| 替え玉受検を行う(代行業者の利用) | 受検者の代わりに友人や知人、専門の代行業者が試験を受ける | 2.7% | 顔認証による本人確認 |
| 友人や知人に解答を教えてもらう | 通話アプリなどを使って、友人や知人から解答を教えてもらう | 4.1% | 質問や問題をランダムに出題 |
※:株式会社サーティファイの調査結果をもとに記載(54.5%は「不正行為をしたことがない」と回答)
以下より、実際に行われている不正行為や手口について詳しく見ていきましょう。
PC・スマホで情報を検索する
もっとも典型的な不正は、試験中にパソコンやスマートフォンを使ってインターネット検索を行う行為です。問題文や選択肢の一部を検索エンジン(Google、Yahoo! など)に入力し、解説や答えを探す手口が多く見られます。
とくに『SPI』や『玉手箱』などの有名な適性検査は、過去問題や解答例がまとめられたサイトが数多く存在し、短時間でも必要な情報を入手できてしまいます。
インターネット検索による不正は、パソコンの画面を切り替えるだけで簡単に行えてしまうことが大きな課題です。
試験画面の裏でブラウザを開き、問題文の一部を入力して検索するだけで、解答例や解説ページにたどり着けます。特別な知識や技術が必要ないため、誰でもすぐに実行できてしまうのです。
こうした不正を防ぐためには、遠隔監視や不正検知のシステムを導入し、監視体制を強化する必要があります。
ChatGPTなどの生成AIを使う
近年増加している不正行為の一つが、ChatGPTやGeminiなどの生成AIで解答を導き出す方法です。
従来のようにインターネット検索で答えを探す必要がなく、問題文をそのまま入力すれば、瞬時に解答や解説を表示してくれます。そのため、受検者にとっては効率的に正答できる不正手段となっています。
たとえば、文章理解や論理的思考などの難解な設問でも、精度の高い解答を導き出してくれるため、実力以上のスコアになってしまうケースも少なくありません。
生成AIによる不正は、企業が本来知りたい「思考力」や「判断力」を正しく評価できなくなる可能性があります。
企業側としては、不正が発覚した場合のルール(対応)を提示し、生成AIの使用を検知するシステムの導入が求められます。
書籍や資料でカンニングをする
Web適性検査における不正行為には、手元にある書籍や資料を使って答えを調べるケースもあります。
インターネット検索や生成AIの利用と比べると、アナログな手段で解答を導き出すため時間がかかりますが、実際にはよく使われている方法です。
とくに『SPI』や『CAB』といった定番の適性検査では、市販の対策本や問題集が多数販売されています。
これらの書籍を手元に置き、似た形式の問題や解法を確認しながら回答を進められるため、自宅受検など監視のない環境では不正をしやすい方法です。
企業側としては、受検環境のルールを明確化し、不正が発覚した場合の対応を事前に伝えることが重要です。加えて、PCカメラやマイクを活用した監視ツールを導入することで、試験中の不正を検知できます。
替え玉受検を行う(代行業者の利用)
Web適性検査における悪質な不正の一つが、本人ではなく他人に試験を受けさせる「替え玉受検」です。受検者の代わりに友人や知人、あるいは専門の代行業者が試験を受けるケースが実際に確認されています。
とくに、インターネット上では「SPI代行」や「Webテスト代行」などを掲げる業者が存在し、SNSや掲示板を通じて簡単に依頼できてしまうのが現状です。
企業は検査結果をもとに人物像や職務適性を判断しますが、他人が受けた結果で採用を進めてしまえば、当然ながら入社後にミスマッチが発生します。
また、不正が発覚すれば受検者本人は信用を失うだけでなく、内定取り消しや法的措置といった深刻な事態を招く可能性もあります。
替え玉受検を防ぐために、企業側としては顔認証や二段階認証などによる本人確認を徹底しなければなりません。不正が発覚した場合の対応を明確に定め、受検者に周知することも不正の抑止につながる重要な取り組みです。
友人や知人に解答を教えてもらう
Web適性検査の不正行為には、友人・知人の協力を得て、問題の解き方や答えを教えてもらうケースもあります。
この不正は、監視者のいないWebテストの盲点を突いた手口です。同じ部屋で受検している友人に解答を聞いたり、通話アプリでリアルタイムに連絡を取り合ったりできます。
他の人と協力して不正受検を行うため、「自分だけではない」という意識から、不正に対する罪悪感を抱きにくい傾向があります。
とくに、仲のよい友人同士の場合、軽い気持ちで不正をしてしまうケースも少なくありません。
企業側としては、試験中の通話や第三者との接触を禁止することを定め、試験前に受検者に伝えることが大切です。また、AI監視などのツールを活用すれば、試験中の不自然な音声や会話を検知できます。
企業は「公正な採用選考」と「不正防止」の両立が必要

企業の採用活動においては、受検の利便性を確保しつつ、公正な選考と不正防止を両立させることが重要です。とくにオンライン受検が可能なWeb適性検査では、便利さと不正のリスクが表裏一体となっています。
不正を恐れて監視体制を過度に強化すると、受検者に強いプレッシャーがかかり、本来の力を発揮できなくなる恐れがあります。一方で、監視を緩めすぎると不正のリスクが高まり、検査結果の信頼性が損なわれかねません。
企業側・受検者側ともに安心して受検できる環境を整えるためには、以下のような仕組みを取り入れる必要があります。
- 受検ルールの明確化と事前周知
- AIによる本人確認システムの導入
- 不正検知機能があるツールの活用
このように、AI技術による不正防止と受検者への理解促進を両立させることが、公正な採用選考を実現するカギとなります。
Web適性検査の不正を防ぐ5つの方法

Web適性検査での不正を完全に防ぐことは難しいものの、企業側の対策によって不正の抑止力を高めることは十分に可能です。具体的な対策として、5つの取り組みを紹介します。
以下より、詳しく見ていきましょう
顔認証による本人確認を徹底する
Web適性検査で不正を防ぐためには、顔認証システムを導入し、受検者本人が確実に受検しているかどうかを確認することが重要です。
具体的には、事前に提出してもらった顔写真と、受検開始時に撮影した画像を照合し、本人以外が受検していないかをチェックします。
受検中においても、一定の間隔でカメラを起動させ、表情や姿勢の変化を検知することで、途中で他人に代わるなどの不正行為も防げます。
また、パソコンのカメラやマイクをそのまま活用できるため、受検者に特別な機材を用意してもらう必要もありません。
本人確認の工程を自動化することで、監視員を配置する必要がなくなり、企業側の負担も大きく軽減できます。
ただし、照明やカメラの角度によって、うまく顔認証ができない場合もあります。そのため、受検時の注意点を事前に案内するようにしましょう。
PCカメラ・マイクで試験中の様子を監視する
Web適性検査の不正をより確実に防ぐには、PCカメラやマイクを活用して、試験中の様子を監視する対策が効果的です。
映像や音声を通して受検者の行動を分析することで、替え玉受検やカンニングなどの不正を早期に検知できます。
具体的には、受検中に視線が頻繁に画面から外れたり、誰かと会話する音声が検出されたりすると、AIが「不正の可能性がある」と報告するシステムです。
また、録画データを一定期間保存しておけば、不審な挙動があった場合でも受検後にいつでも確認できます。
AIを活用した監視システムを導入することで、監視員が常に画面を見張る必要がなくなり、人件費や運用コストの削減にもつながります。
Web適性検査の導入を検討している方は、AI監視機能を備えた『ミキワメ』をぜひご利用ください。受検中の映像と音声をAIが自動で解析し、不自然な動きや会話を検知します。
無料トライアルも実施中ですので、お気軽にお問い合わせください。
質問や問題をランダムに出題する
Web適性検査の不正受検を防ぐためには、質問や問題をランダムに出題する仕組みも有効です。
受検者全員に同じ問題・同じ順序で出題する形式では、事前に問題内容を共有したり、他人の解答を参考にしたりする不正が起こりやすくなります。
そのため、出題順序や問題パターンをランダムにすることで、不正行為が起きにくい試験環境をつくれます。具体的な対策は、以下のとおりです。
- 受検者全員が同じ問題でも、選択肢の順番をランダムに変更する
- 問題の数値や条件を自動的に入れ替える仕組みを導入する
- 複数の問題パターンを用意し、受検者ごとに異なる内容を出題する
このように出題内容を受検者ごとに変えることで、「事前に答えを準備する」「他人に解答を共有する」といった不正行為を抑止できます。
別の試験や面接と組み合わせて選考する
Web適性検査の結果だけで合否を判断すると、不正が行われた場合に誤った評価を行うリスクがあります。そのため、複数の選考手段を組み合わせて総合的に判断することが重要です。
たとえば、Web適性検査のあとにオンライン面接やグループディスカッションを行い、実際の受け答えが検査結果と一致しているかを確認する方法があります。面接で違和感を覚えた場合は、追加で適性検査を行うことも可能です。
厚生労働省の「公正な採用選考」の資料においても、適性検査の結果を絶対視したり、結果のみで合否を決定したりしないことを強調して示しています。
適性検査に加えて、面接や学力試験、作文などの選考方法を組み合わせることで、本来の適性や能力をより正確に把握できます。
具体的な適性検査の活用ポイントを知りたい方は、以下の資料をご覧ください。人事が知っておくべき内容をまとめています。
>>「人事のための適性検査活用BOOK」の資料をダウンロードする
不正による対応(ルール)を受検者に周知する
Web適性検査を実施するときは、不正行為が発覚したときの企業側の対応(ルール)を受検者に周知しておきましょう。
不正による処分内容や再受検の有無などを事前に伝えることで、受検者に対して「不正は悪質な行為」であることを強調できます。
たとえば、以下のようなルールを設定・周知しておくとよいでしょう。
- 不正行為が確認された場合は、その時点で選考対象外とする
- 不正の疑いがある場合は、再受検または面接での再評価を行う
- 重大な不正が発覚した場合は、内定取り消しなどの処分を行う場合がある
企業として「公正な採用選考を重視している」ことを明確に伝えることで、結果として不正の未然防止につながります。
受検者に伝えるべき不正行為による3つのリスク

不正行為で採用されたとしても、一時的に「合格」を得ただけに過ぎません。企業側としても、不正が発覚した場合のリスクを受検者に伝えておく必要があります。
【不正行為による主なリスク】
以下より、詳しく見ていきましょう。
不正が発覚すると内定取り消しになる
Web適性検査での不正が発覚した場合、多くの企業では「内定取り消し」や「選考対象からの除外」といった厳しい対応をとります。
採用活動において、企業は「公正な選考」を重視しています。そのため、不正行為はその信頼を根底から揺るがす重大な問題とみなされてしまうのです。
また、入社後に不正が発覚した場合は、懲戒処分(諭旨解雇、懲戒解雇 など)となる可能性もあります。
受検者が「不正はバレない」と考えていても、企業側はAI監視やログ解析などの仕組みを導入しており、不正の痕跡はデータとして残ります。
不正による一時的な成功よりも、誠実に取り組む姿勢が評価されることを、受検者に明確に伝えなければなりません。
刑事罰の対象となる可能性がある
Web適性検査での不正行為は、場合によっては刑事罰の対象となる可能性があります。
他人になりすまして受検を行う「替え玉受検」や「代行業者への依頼」は、刑法第161条の2第1項の「電磁的記録不正作出・同提供罪」に該当する恐れがあります。
実際に過去には、就活生から依頼を受けてWebテストの替え玉受検をしたとして、会社員が逮捕された事例がありました。また、依頼した学生も共犯容疑で書類送検される事態となっています。
安易な気持ちで不正を依頼することで、受検者は法的責任を問われたり、個人情報漏洩の被害に遭ったりするリスクがあります。
Web適性検査での不正は、単なるルール違反にとどまらず、法に触れる可能性があることを、受検者にしっかり理解してもらうことが大切です。
不正の事実が業界内で広まる
Web適性検査で不正が発覚すると、その情報が業界内で共有される場合があります。同業他社やグループ企業、採用支援会社など、担当者の間で情報共有が行われるケースです。
とくに、同一人物が複数の会社で「不正の可能性がある」と判断された場合、注意喚起として情報共有されることも珍しくありません。
「不正をした人」という印象が一度ついてしまうと、その後の選考や就職活動全体に大きな影響を及ぼす恐れがあります。
不正行為によって一時的によい結果を得ても、最終的には信頼や将来のチャンスを失いかねません。企業としては、その点を受検者にしっかりと説明する必要があります。
不正受検を防ぐなら『ミキワメAI監視 in 適性検査』

株式会社リーディングマークが提供する『ミキワメAI監視 in 適性検査』は、AIによる顔認証と不正検知機能を備えたWeb形式の適性検査です。
パソコンに搭載されているカメラやマイク、操作画面の情報を活用し、「替え玉受検」や「複数人での受検」などの不正行為をチェックします。主な機能と特徴は、以下のとおりです。
※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください
| 機能 | 特徴 |
|---|---|
| PCカメラで本人確認 | あらかじめ登録した顔写真と受検者の顔を照合し、本人が受検しているかどうかをチェック |
| 試験中のPC画面をチェック | 試験中のPC画面を監視し、別のアプリを起動したり、外部ディスプレイを接続したりする挙動をチェック |
| PCマイクで試験中の音声をチェック | PCマイクを通じて試験中の音声をAIが解析し、受検者以外の声や不自然な物音を検出 |
ミキワメを導入することで、Webテストの利便性を維持しながら不正行為を未然に防ぎ、公正な採用試験を実現できます。
『ミキワメAI監視 in 適性検査』の機能や特徴については、以下の記事で詳しく解説しています。導入を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

適性検査の不正に関するよくある質問(Q&A)
-1024x683.jpg)
適性検査の不正に関する4つの質問について、実務的な視点からわかりやすく回答します。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
Q1:替え玉受検がバレるとどうなる?
替え玉受検やカンニングなどの不正が発覚した場合、企業から「内定取り消し」や「選考対象からの除外」といった厳しい対応を受けることは避けられないでしょう。
とくに替え玉受検の場合は、刑法の「電磁的記録不正作出」に該当する恐れがあります。実際に、就活生になりすまして受検した人が逮捕された事例もありました。
また、入社後に不正が判明した場合でも、懲戒処分(諭旨解雇、懲戒解雇 など)の対象となる可能性もあります。
多くの企業では、本人確認やAI監視などのシステムを導入しているため、高い精度で不正行為を検知できる体制が整っています。
Q2:不正が発覚するきっかけは何?
不正行為が発覚するきっかけは、Webテストに搭載されている監視技術によって、不自然な挙動を自動的に検出するためです。
受検者の視線の動きや音声、パソコンの操作画面などをAIが解析します。たとえば、受検者の視線が頻繁に画面から外れたり、他人の声がマイクに入ったりすると、AIが「不正の可能性あり」と判断して企業に報告します。
また、受検中の映像やログデータは記録として残るため、受検後に不正の有無を確認することも可能です。
Q3:企業は不正を防ぐためにどうしたらいい?
企業が不正を防ぐためには、PCカメラやマイクを活用したAI監視など、技術的な対策が効果的です。しかし、それだけでは十分とは言えません。運用面でのルール整備も同様に重要です。
とくに、不正が発覚した場合の対応を明確に定め、事前に受検者へ周知しておくことで、不正を抑止する効果が期待できます。
【具体例】
- 不正行為が確認された場合は選考対象外とする
- 疑わしい場合は再受検や面接による再評価を行う
- 悪質な不正の場合は、内定取り消しなどの厳しい処分を行う
このような企業側の対応を事前に伝えることで、受検者のモラルを高め、公正な採用選考を実現できます。
Q4:適性検査の結果だけで合否を決めてもいい?
適性検査の結果だけで合否を決めてしまうと、入社後のミスマッチや早期離職につながる可能性があります。
そのため、検査結果は「受検者の特性を客観的に把握するための参考指標」として活用し、面接や筆記試験などの選考手段と組み合わせて、総合的に判断することが重要です。
検査結果を絶対視せず、採用プロセスの一つとして位置づけることが、公正な選考につながります。
また、適性検査は受検者の性格や行動特性を測定し、入社後の配属や育成方針にも活用できます。具体的な活用方法については、以下の記事で詳しく解説していますので、本記事と合わせて確認してみてください。
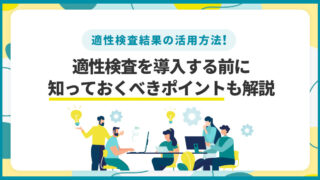
適性検査の不正を未然に防ぎ、公正な採用選考を実現しよう

適性検査は、受検者の能力や性格特性を測定し、活躍する人材を見極めるための有効な手段です。
しかし、採用試験のオンライン化が進む中で、替え玉受検やカンニングといった不正行為の増加が課題になっています。企業側としては、技術面と運用面の両方から不正防止策を講じる必要があります。
【不正を防ぐ方法】
これらの対策を行うことで、企業は受検者に過度な負担をかけることなく、公正な採用選考を実現できます。
まずは、既存の適性検査ツールを見直し、不正防止機能や監視体制が十分に整っているかを確認してみましょう。
>>『ミキワメAI監視 in 適性検査』のお問い合わせはこちら



-640x360.jpg)







 ランキング1位
ランキング1位 
 ランキング2位
ランキング2位 
 ランキング3位
ランキング3位 