サーベイのやりっぱなしは社員のモチベーション低下と現場改善の停滞を招き、組織の成長チャンスを失うことにつながります。
「変化を生み出さないサーベイなら、やらないほうがマシ」とまでいわれるのはこのためです。
逆にいうと、サーベイ結果を正しく活用できればこうしたデメリットを避け、従業員エンゲージメントや生産性の向上、離職防止や顧客満足度アップにつながります。
今回は、サーベイがやりっぱなしになる原因や問題点、効果的に運用する方法とポイントを解説しますので、人事担当者は参考にしてください。

従業員のエンゲージメント向上に欠かせない「サーベイ」とは?
サーベイ(従業員サーベイ)とは、社員の意識や職場環境に対する感じ方を定期的に調査し、組織の課題や従業員エンゲージメントの状態を「見える化」する仕組みです。
エンゲージメントとは社員の会社への愛着心や貢献意欲を指し、「自社のために力を尽くしたい」という前向きな姿勢を意味します。
従業員サーベイの実施は、社員の声を可視化して課題を早期に発見できるだけではなく、「会社が自分たちの意見を聞いている」という安心感を生み、エンゲージメント向上につながる重要な施策です。昨今では多くの企業が導入し、社内の声をデータで把握して職場改善に活用しています。
一方で、調査を実施しただけで「やりっぱなし」になり、せっかく集めた結果を十分に活かせていないケースも少なくありません。
以下の記事では、サーベイの導入率や市場動向について、調査データをもとに詳しく解説しています。サーベイ導入による効果や具体的な運用フローも紹介していますので、本記事と合わせて確認してみてください。

サーベイがやりっぱなしになる原因
サーベイがやりっぱなしになる原因は次の3つに分類されます。
- 構造的な問題:経営・人事主導で現場に共有されない
- 現場側の問題:管理職が活用スキルを持っていない
- 文化的な問題:サーベイ活用が組織に根付いていない
それぞれ解説します。
構造的な問題:経営・人事主導で現場に共有されない
サーベイの分析を経営層や人事部だけで行い、現場に結果を十分に共有しないケースは多く見られます。
結果がフィードバックされなければ、現場は課題を自分ごととして捉えられず、改善のためのアクションも生まれません。
こうした「上層部で止まってしまう構造」が、サーベイをやりっぱなしにしてしまう大きな要因です。
現場側の問題:管理職が活用スキルを持っていない
サーベイの結果が現場に届いたとしても、それをどう読み解き、どのような改善策を立案すべきかを理解していない管理職は少なくありません。
エンゲージメントに関する知識やノウハウが不足していると、せっかくのデータを活かせずに手が止まり、やはり「やりっぱなし」の状態に陥ります。管理職への教育や研修が欠かせない理由がここにあります。
文化的な問題:サーベイ活用が組織に根付いていない
サーベイの結果を改善活動につなげる文化が組織に根付いていないと、調査が単なる形式的なイベントになってしまいます。
サーベイは継続的な改善サイクルの一部であるにもかかわらず、分析・対話・改善という一連の流れが定着していなければ、結局「調べて終わり」で終わってしまうのです。
サーベイをやりっぱなしにするデメリット
サーベイ結果を放置すると、企業は重大な機会損失を被ります。さらに、社員のモチベーションや職場環境にも悪影響を及ぼしかねません。
サーベイをやりっぱなしにする主なデメリットは次のとおりです。
- 社員が学習性無気力の状態に陥る
- 職場ブラックボックス症候群を併発する
- 生産性向上のチャンスを逃す
それぞれ解説します。
社員が学習性無気力の状態に陥る
せっかく時間をかけてサーベイに回答しても、何の変化も生まれない状態が続くと、社員は次第に「答えてもムダだ」と感じるようになります。
これは心理学でいう「学習性無気力」の状態で、社員が組織改善への信頼を失い、意欲を喪失してしまう症状です。一度こうした無気力に陥った社員は、「どうせ何も変わらない」と諦めてしまい、二度とサーベイに真面目に答えなくなるおそれがあります。
職場ブラックボックス症候群を併発する
社員がサーベイに本音で答えないと、経営層や人事は現場で何が起こっているのかを把握できません。
組織の問題や社員の不満をサーベイではあぶり出せず、職場の実態が見えないままになる状態は、「職場ブラックボックス症候群」とも形容されます。
このように、サーベイのやりっぱなしは社員の無気力化や職場のブラックボックス化という深刻な合併症を引き起こし、組織に大きな悪影響を与えます。
生産性向上のチャンスを逃す
サーベイ結果を活用しないことで、組織改善や生産性向上の機会を逃してしまいます。
実際、従業員エンゲージメントの低下による経済的損失は莫大だとされ、従業員のエンゲージメント欠如は世界で年間約1.9兆ドル(約300兆円)もの生産性損失につながるとの試算があります。
つまり、サーベイ結果を活用せずエンゲージメント低下を放置することは、企業業績にも大きなマイナスとなるのです。
出典:従業員のエンゲージメント低下による損失は年間300兆円 | Business Insider Japan
サーベイの結果を正しく活用するメリット
業員サーベイを活用してエンゲージメントを向上させると、組織には多くのメリットがもたらされます。エンゲージメントが高い職場では社員が意欲的に働き、仕事の質や成果が向上するため、組織全体のパフォーマンス向上につながるでしょう。
サーベイ結果を正しく活用する主なメリットは次のとおりです。
- 生産性が向上する
- 離職率が低下する
- イノベーションが促進される
- 顧客満足度アップにつながる
それぞれ解説します。
なお、エンゲージメントサーベイの選び方(チェックリスト付き)を知りたい人事担当者の方は、以下の記事も合わせてご覧ください。導入前に知っておきたいポイントや、目的別のおすすめサービスを紹介しています。

生産性が向上する
エンゲージメントの高い職場では、社員一人ひとりが組織の一体感を持って仕事に取り組むため、生産性が高い傾向があります。
アメリカ・ギャラップ社の調査によると、エンゲージメント上位25%の企業は下位25%に比べて収益性が23%高く、生産性指標は18%も高いと報告されました。(※1)
厚生労働省の分析でも、ワークエンゲージメント(仕事への熱意)のスコアが1ポイント上がると労働生産性が1〜2%向上する可能性が示唆されており、エンゲージメントと生産性の間には明確な正の相関関係があることがわかっています。(※2)
サーベイの結果を正しく活用し、従業員エンゲージメントを高めることは、職場の生産性向上に寄与するでしょう。
出典:
※1 Gallup 2024 Q12 Meta-Analysis
※2 第2-(3)-12図 ワーク・エンゲイジメントと企業の労働生産性について|令和元年版 労働経済の分析 -人手不足の下での「働き方」をめぐる課題について-|厚生労働省
離職率が低下する
従業員のエンゲージメントが高まると会社への愛着心や帰属意識が強まるため、結果的に定着率が上がります。
実際、厚生労働省の調査では、エンゲージメントが低い社員の1年以内離職率が9.2%であるのに対し、エンゲージメントが高い社員では1.2%に留まったと報告されました。
サーベイ結果を正しく活用し、社員の職場定着率が上がれば採用育成コストの削減にもつながり、組織力の安定・向上に役立ちます。
出典:働きやすい・働きがいのある職場づくりに関する調査報告書-厚生労働省
イノベーションが促進される
エンゲージメントが高い組織では、前向きで積極的な社風が醸成されやすく、社員も自由な発想でチャレンジしやすくなります。その結果、新しいアイデアや改善提案が活発に生まれ、イノベーションの創出につながるでしょう。
実際に、心理的安全性が高く社員が安心して意見をいえる職場ほど、イノベーティブになり生産性も向上することがさまざまな研究で明らかとなっています。
サーベイ結果を活用し、エンゲージメント向上を図ることは単なる士気アップ対策ではなく、組織の競争力強化策ともいえるでしょう。
顧客満足度アップにつながる
従業員エンゲージメントを高めることは、顧客満足度の向上を通じて業績アップにも直結します。エンゲージメントが高い社員は仕事に誇りを持ち、主体的に質の高いサービスを提供しようとするためです。
実際に、エンゲージメントの高い職場では社員の熱意や丁寧な対応が顧客に伝わり、満足度の向上やリピーター獲得につながっています。
「サービス・プロフィット・チェーン」の理論によると、従業員満足度の向上がサービス品質の改善をもたらし、結果的に顧客満足度と業績が向上するという因果の構造が示されています。
つまり、サーベイ結果を活用してエンゲージメントを高めることは、顧客満足度の強化と企業の成長を同時に実現する有効な手段なのです。
脱やりっぱなし!サーベイを効果的に運用する方法とポイント
サーベイをやりっぱなしにしないためには、調査の段階から結果活用までを一貫したサイクルとして設計することが重要です。
サーベイを効果的に運用する主なポイントは次の4つ。
- 実施する目的を明確化し意義を周知する
- 調査では匿名性を確保する
- 結果は現場にフィードバックし対話を促す
- 担当者・管理職へのトレーニングを実施する
それぞれ解説します。
実施する目的を明確化し意義を周知する
サーベイを始める前に「何のために調査を行うのか」「結果をどう活かすのか」という目的とゴールを明確に設定しましょう。そのうえで、従業員にも事前にサーベイの意義や期待効果を伝達します。
目的がはっきりと示されれば、社員も「どうせ意味がない」といった無気力感を抱かず、前向きに協力する姿勢になりやすいためです。
反対に目的が曖昧なままだと、社員は「形だけの調査では?」と疑心暗鬼になり、熱意ある回答を得られません。ゴールを共有して社員を巻き込むことが成功への第一歩です。
調査では匿名性を確保する
サーベイは匿名形式で実施し、回答者が安心して本音を記入できる環境を整えます。
匿名が保証されていると社員は「正直に書いても身バレしない」と感じ、会社への本音を伝えやすくなるためです。
逆に実名だと「回答が人事評価に影響しないか」と不安になり、ネガティブな意見ほど隠されてしまうおそれがあります。一般に、匿名サーベイは回答率も高まりやすく、多くの率直なデータが集まる傾向があります。
ただし匿名である分、個人へのフォローは直接できないため、結果のまとめ方やフォローアップ施策で補う工夫が必要です。
結果は現場にフィードバックし対話を促す
調査後は速やかに結果を全社員・各職場に共有しましょう。結果を現場に共有して初めて、社員は自組織の課題や改善の必要性を認識できます。
データを社内でオープンにフィードバックすることで「会社が真剣に取り組んでいる」と社員も実感し、現場での対話や改善案の検討が始まります。特に、チーム単位で管理職とメンバーが結果を見ながら議論する場を設けると効果的です。
経営層・人事部門だけで抱え込まず、現場の当事者を巻き込んでアクションプランを立案することで、社員の主体的な協力を得られます。
以下の記事では、社員の性格や心理状態を踏まえた対話ができる『ミキワメAI マネジメント』について詳しく解説しています。
ミキワメAIは、社員の成長と成果を最大化する仕組みを構築できる1on1ツールです。「部下と効果的な1on1ができていない」と悩んでいる人事担当者の方は、ぜひ確認してみてください。

担当者・管理職へのトレーニングを実施する
サーベイ結果を活かすには、人事担当者や現場の管理職が適切な分析・対処スキルを持っていることが重要です。必要に応じて、サーベイ結果の読み取り方や組織開発の知見に関する研修を実施しましょう。
例えば「エンゲージメントを高める要因の理解」「部下との対話の進め方」「改善策の立案方法」などを学ぶ機会を設けるのが有効です。
管理職自身がエンゲージメントの意味やサーベイ活用法を正しく理解していれば、現場での対話もスムーズに進みます。
逆に知識・技能が不足したままだと、せっかく現場に任せても有効なアクションを起こせません。管理職に組織開発の知見と実践スキルを授けることが、サーベイ結果を正しく活用するための重要なポイントです。
サーベイ実施後に取り組むべきエンゲージメント向上の施策
サーベイ実施後は、結果から明らかになった課題に対して、具体的なエンゲージメント向上策を講じることが必要です。
最後に、主なエンゲージメント改善施策を紹介します。
- 待遇や環境を改善する
- 管理者向け研修を実施する
- 管理職と部下の間で1on1面談を実施する
- フレキシブルな働き方を導入する
- キャリア開発支援をおこなう
自社の状況に合わせ、適切なアクションを選択しましょう。
待遇や環境を改善する
サーベイで給与・福利厚生・働く環境への不満が見えた場合は、まず社員が自力では変えられない部分の改善に着手します。
例えば、給与水準の見直し、長時間労働の是正、ハラスメント対策、福利厚生の充実などです。
制度や報酬への不満を取り除くことはエンゲージメント向上の前提であり、こうした基本的な不満要因の改善によって、社員のモチベーション低下を防ぐ効果が期待できます。
管理者向け研修を実施する
従業員エンゲージメントを高めるうえで、直属の上司との関係は非常に重要です。
調査結果からマネジメント層に課題が見えた場合、管理職向けの研修やコーチングを提供しましょう。適切なフィードバックの仕方、メンバーのエンゲージメントを引き出すコミュニケーション法、部下を尊重するリーダーシップなど、良好な上司・部下関係を築くためのスキルを学んでもらいます。
管理職と部下の間で1on1面談を実施する
日常的な対話の機会を設けることで、社員の声を拾い上げ、信頼関係を強化できます。
たとえば月1回1on1ミーティングを実施し、仕事の悩みやキャリア希望を上司が傾聴する場を設けましょう。
サーベイ直後だけではなく継続的にコミュニケーションを図ることで、問題の早期発見・解決や社員の成長支援につながります。
上司と部下が向き合って対話する文化が根付けば、エンゲージメントが下がる前に手を打てる組織になります。
フレキシブルな働き方を導入する
サーベイでワークライフバランスへの不満や働き方に関する要望が得られた場合、リモートワークやフレックスタイム制度などの柔軟な働き方を検討しましょう。
社員が自分に合った働き方を選べるようにすることで、仕事と家庭の両立がしやすくなり、職場への満足感・定着率の向上が期待できます。
近年では、ハイブリッド勤務や短時間正社員制度など多様な働き方を認めることが、エンゲージメント維持に効果を上げています。
キャリア開発支援をおこなう
社員の成長機会の提供もエンゲージメント向上に欠かせません。
サーベイ結果から「成長実感が薄い」「キャリア展望が描けない」といった声があれば、人材育成策を強化しましょう。
具体的には、メンター制度の導入、社内公募制度、ジョブローテーション、研修受講支援、将来像を話し合うキャリア面談の実施などが有効です。
社員が「この会社で成長できている」「将来のキャリアが開けている」と感じられれば、仕事への意欲が増し、離職意向も下がります。
長期的なキャリア支援策はモチベーションアップと人材定着に大きく寄与するでしょう。
サーベイ結果を最大限活用して従業員のエンゲージメントを高めよう
従業員サーベイは社員の声やエンゲージメント状態を可視化する強力なツールですが、それ自体で組織が良くなるわけではありません。最も重要なのは、サーベイ結果を踏まえて適切な対応策を実行することです。
やりっぱなしでは本質的な意味がなく「改善活動こそが本番」という意識を持つ必要があります。
サーベイのやりっぱなしを防ぎ、真に効果を上げるためには『ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ』のようなサービスを活用するのも一案です。『ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ』は、従業員のモチベーションや心身の状態を可視化し、独自のAIが各社員の性格傾向も踏まえた改善アクションを提案します。
実名ベースで実施して社員の状態を定期的にチェックすることで「ケアを必要としている人」を自動でアラート表示し、重点フォローすべき社員を特定できる仕組みです。どの社員にどのようなケアをすればよいかが即座にわかるため、人事・管理職は注力すべき対象と対応策を明確に把握し、サーベイのやりっぱなしを防げます。
サーベイは社員の声という貴重な財産を集める機会です。「実施して終わり」にせず、必ずフィードバックと改善アクションに結び付けることで、従業員の信頼とエンゲージメントが向上し、組織はより強固で「働きがいのある会社」へと変わっていくでしょう。
従業員のメンタル状態の定期的な可視化・個々の性格に合わせたアドバイス提供を通じ、離職・休職を防ぐエンゲージメントサーベイ。無料トライアルの詳細は下記から。





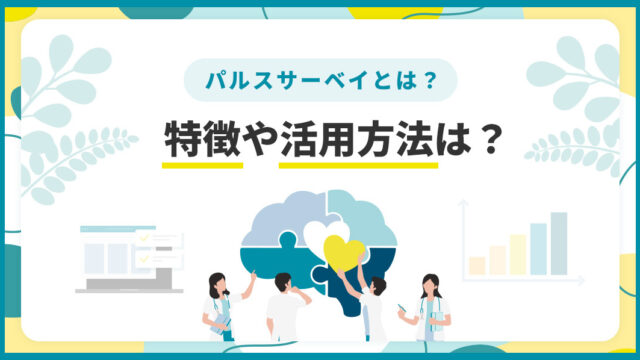
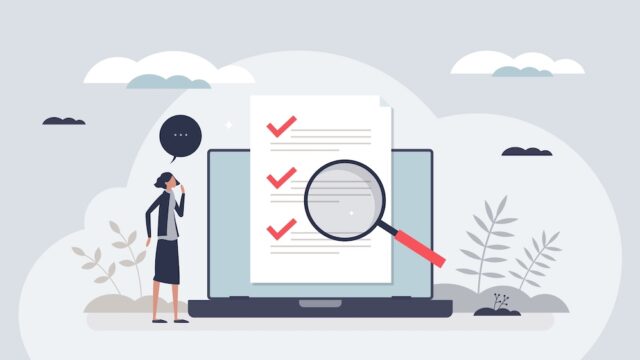
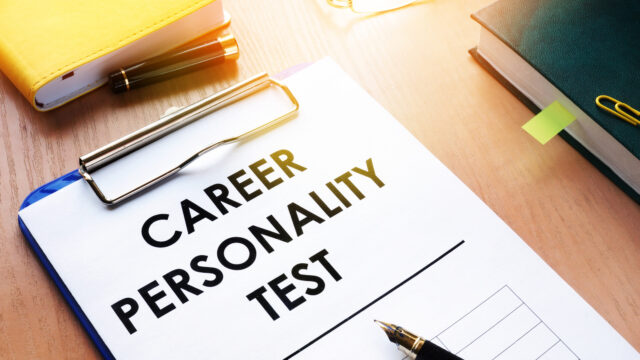






 ランキング1位
ランキング1位 
 ランキング2位
ランキング2位 
 ランキング3位
ランキング3位 