社員のやる気が低下すると、企業の業績にさまざまな悪影響を及ぼします。生産性やサービスの質が下がるだけではなく、離職率の上昇によって採用・育成コストの増大にもつながりかねません。
では、なぜ社員のやる気が下がってしまうのでしょうか。
本記事では、社員のモチベーションが低下する原因を3つの視点から分析し、やる気を引き出すための具体的な対策を紹介します。
記事の後半では、すぐに実践できる施策もまとめています。 「社員のやる気を引き出したい」「組織の活性化を目指したい」と考える経営者や人事担当の方は、ぜひ最後までご覧ください。

社員のやる気が下がる原因
社員のやる気が下がる主な原因は以下の3つです。
- 人事評価に不満がある
- 職場の人間関係が悪化する
- 仕事のやりがいがない
人事評価に不満がある
人事評価への不満は、社員のモチベーション低下につながる大きな要因です。自らの努力や成果が正しく評価されていないと感じると、仕事への意欲が失われてしまいます。
社員が人事評価に不満を抱く主な理由としては、以下が挙げられます。
- 評価基準が不明確で、納得できる根拠が提示されない
- 上司との面談が形式的で、十分なフィードバックを得られない
- 同僚と比較して評価に不公平感を抱いている
- 昇進や給与に評価結果が反映されない
こうした状況が続くと、社員は自身の貢献が軽視されていると感じ、組織への信頼を失ってしまいます。その結果、業務への取り組み姿勢が消極的になるだけではなく、離職するリスクも高まるでしょう。
このような課題を防ぐには、評価制度の透明性を高める取り組みが欠かせません。企業は評価基準を明示し、面談を通じて社員の納得感を得られるようなプロセスを整備する必要があります。
職場の人間関係が悪化する
職場の人間関係が悪化すると、社員のやる気に大きな影響を与えます。上司や同僚とのコミュニケーションが円滑ではなく、信頼関係を築けていない場合、以下のような問題が起こりやすくなります。
- ストレスが増加し、精神的な負担が大きくなる
- 仕事への集中力が低下し、パフォーマンスが下がる
- チームワークが機能せず、効率的な業務遂行が困難になる
- 孤立感を感じ、組織への帰属意識が薄れる
このような状況が続くと、社員はモチベーションを維持することが難しくなります。職場での人間関係の改善は、やる気を高めるための重要な要素です。
良好な人間関係を築くには、お互いを尊重し、積極的にコミュニケーションを図る必要があります。上司は部下の意見に耳を傾け、適切なフィードバックを与えるよう心がけましょう。また、同僚同士が協力し合える環境を整えることも大切です。
仕事のやりがいがない
単調な業務や自分のスキルを活かせない仕事が続くと、社員のモチベーションが下がってしまうおそれがあります。
例えば、以下のような問題が生じるケースが見られます。
- ルーティンワークに飽きてしまい、仕事への情熱が失われる
- 自分の能力を発揮する機会がなく、成長できていないと感じる
- 仕事の意義や目的が見えず、やりがいを感じられない
- 新しいことにチャレンジする意欲が湧かず、停滞感を抱く
仕事へのやりがいを感じられる体制づくりは、社員のやる気を高めるための重要な要素です。社員のスキルや興味に合った仕事を割り当て、適度なチャレンジを与える必要があります。
また、仕事の意義や目的を明確に伝え、社員が自分の役割を理解できるようにしましょう。定期的にフィードバックをおこない、成長の機会を提供することも重要です。
社員のやる気が低いことで起こる問題
社員のやる気が低いと、以下のようにさまざまな問題が発生します。
- 生産性の低下
- 職場の雰囲気悪化
- 人材流出のリスク増大
まず、生産性の低下が挙げられます。やる気のない社員は自発的に動こうとせず、業務への取り組み姿勢も消極的になりがちです。その結果、仕事の質が下がってミスやエラーが増え、納期遅れなど業務全体に悪影響を及ぼしかねません。
また、一部の社員のモチベーション低下が、職場の雰囲気を悪化させるケースもあります。無気力な態度は周りの社員にも伝染しやすく、チームワークや協力体制が損なわれるためです。コミュニケーション不足から、人間関係がギクシャクしてしまうかもしれません。
さらに、社員のやる気が低いと、人材流出のリスクも高まります。仕事にやりがいを感じられない社員は離職を考え始め、特に優秀な人材ほど、より良い環境を求めて会社を去る傾向があります。新たな人材採用・教育にかかるコストの増大は避けられません。
このように、社員のやる気低下は、会社経営に大きなデメリットをもたらします。社員のやる気を引き出し、維持していくことが、業績アップと安定した組織づくりには不可欠といえるでしょう。
社員のやる気を高める方法
ここでは、社員のやる気を高める方法を7つ解説します。
- 明確な目標設定とフィードバックをおこなう
- コミュニケーションを活発化させる
- 成長につながる機会を提供する
- 公正で透明性の高い評価制度を導入する
- 表彰制度を導入する
- モデルケースやキャリアパスを提示する
- 労働環境を見直す
明確な目標設定とフィードバックをおこなう
社員のやる気を引き出すためには、明確な目標設定とフィードバックが欠かせません。以下のような取り組みをおこなうことで、社員のモチベーションを高められるでしょう。
- 個人の強みや能力を考慮し、達成可能な目標を設定する
- 目標達成までのステップを具体的に示し、社員に理解してもらう
- 定期的に進捗状況を確認し、必要に応じてサポートを提供する
- 目標達成時には適切な評価とフィードバックを与える
- 建設的なフィードバックを通じて、社員の成長を促す
目標設定とフィードバックのプロセスを通して、社員は自分の役割と期待される成果を明確に理解できます。また、上司からの関心と支援を感じることで、仕事へのモチベーションを維持しやすくなります。
社員一人ひとりに対して丁寧に向き合い、適切な目標設定とフィードバックをおこなうことが、組織全体のパフォーマンス向上につながるのです。
コミュニケーションを活発化させる
社員同士や上司とのコミュニケーションが活発になると、信頼関係や心理的安全性が高まります。その結果、社員は前向きに業務を進めることができ、パフォーマンス向上が期待できます。
コミュニケーションを活発化させるためには、以下の取り組みが効果的です。
- 上司と部下、同僚間でのオープンな対話を奨励する
- 社員の意見や悩みを共有する場を設ける
- 社員のアイデアを積極的に取り入れる
まず、定期的な1対1ミーティングや、部署全体のミーティングを設け、社員一人ひとりが自由に意見を述べられる環境を整えましょう。上司は部下の話に耳を傾け、適切なフィードバックを与えることが重要です。
そして、社員同士が気軽に話し合えるような場を用意することで、お互いの理解を深め、信頼関係を築けるようになります。例えば、ランチミーティングや部署内の懇親会などを定期的に開催するのもよい方法です。
社員から出たアイデアは真摯に受け止め、実現可能なものは積極的に採用しましょう。社員は「自分の意見が尊重されている」と感じ、仕事へのモチベーションが高まります。
以下の記事では、社員の性格や心理状態を踏まえた対話ができる『ミキワメAI マネジメント』について詳しく解説しています。ミキワメAIは、社員の成長と成果を最大化する仕組みを構築できる1on1ツールです。
「部下と効果的な1on1ができていない」と悩んでいる人事担当者の方は、ぜひ確認してみてください。

成長につながる機会を提供する
社員の成長につながる機会を積極的に提供することで、モチベーションを高められます。具体的には、以下の取り組みが効果的です。
- 新規プロジェクトへの参加を奨励する
- 研修やトレーニングプログラムを充実させる
- 自主的な学習を支援する
例えば、新規プロジェクトへの参加を奨励すれば、社員が新しいスキルを身につけ、視野を広げられるチャンスを提供できます。新しい仕事にトライすることで、社員の成長意欲を刺激し、モチベーションアップにつなげられるでしょう。
また、自主的な学習を支援する環境を整えることも重要です。書籍の購入を促したり、Udemyなどの動画で学べるサイトの受け放題プランを用意したりと、社員が自発的に学べる体制を整えましょう。
社員一人ひとりの成長ニーズに寄り添い、適切な機会を提供することが、モチベーション向上の鍵となります。会社と社員がともに成長できる好循環を生み出していきましょう。
公正で透明性の高い評価制度を導入する
評価制度とは、社員の努力を正当に評価し、成長や貢献を見える化する仕組みです。
評価が曖昧だったり、不透明であったりすると、社員は「どこを目指せばよいのか」「どうすれば正しく評価されるのか」がわからず、モチベーションが下がってしまうおそれがあります。
一方、公正で透明性のある評価制度が整っていれば、社員は納得感を持って前向きに働けます。評価と報酬がしっかりと結びついていることで「頑張ればきちんと報われる」という安心感が生まれ、仕事への意欲が高まるのです。
こうした環境を整えるためには、以下の取り組みが有効です。
- 評価基準や昇進・昇給の条件を明確に定義し、全社員に周知徹底する
- 評価プロセスの透明性を確保し、社員からのフィードバックを積極的に取り入れる
- 定期的な面談を通じて、社員の目標達成度合いや課題をしっかりと把握する
- 優れた成果を上げた社員に対しては、適切な報酬やインセンティブを提供する
- 評価結果について、社員に丁寧なフィードバックをおこない、納得感を持ってもらう
社員一人ひとりの頑張りや成果をきちんと認め、それが待遇につながるような仕組みを整えることが大切です。評価の公平性と透明性が高まれば、社員のモチベーションが上がり、組織全体のパフォーマンス向上に直結します。
ただし、評価制度の導入にあたっては、十分な準備と丁寧なコミュニケーションが欠かせません。社員の理解と協力を得ながら、段階的に制度を整備していくことが重要です。
また、評価制度が形骸化せず実効性の高いものとなるよう、継続的な改善にも努めましょう。
表彰制度を導入する
優秀な成果を上げた社員を定期的に表彰することは、社員のモチベーションを高める効果的な方法の一つです。表彰制度の導入により、社員は自分の努力や成果が会社から認められていると実感でき、さらなる頑張りにつながります。
表彰制度の具体例は以下のとおりです。
- 月間MVPの選出
- 感謝イベントの開催
- 社内表彰制度の設置
月間MVPの選出では、毎月、もっとも優れた成果を上げた社員を表彰します。選出基準を明確にし、公平性を保つことが重要です。受賞者にはボーナスや特別な権利を付与するのも効果的でしょう。
感謝イベントの開催は、四半期や半年に一度、社員の頑張りに感謝の意を示す機会となります。社長から直接表彰状が授与されたり、豪華な食事会が催されたりすることで、社員は自分の貢献が評価されていると感じられます。
社内表彰制度の設置では、業績や貢献度に応じてポイントを付与し、一定のポイントに達した社員を表彰する仕組みをつくります。ポイントを金券や商品と交換できるようにすると、社員のやる気がさらに高まるでしょう。
表彰制度を効果的に機能させるためには、選出基準の明確化と公平性の担保が不可欠です。また、表彰の内容も、社員のモチベーションを刺激するものでなければなりません。
社員の努力を正当に評価して感謝の意を示すことでエンゲージメントを高め、組織の生産性向上につなげましょう。
モデルケースやキャリアパスを提示する
モデルケースやキャリアパスを会社から提示することも、社員のやる気アップにつながります。その理由は以下のとおりです。
- 目指すべき方向性が明確となる
- スキルアップの必要性を認識できる
- 会社への帰属意識が高まる
- 公平性の確保につながる
社員が自分のキャリアの目標を具体的にイメージできるようになると、日々の業務に対する意欲が高まります。また、キャリアアップに必要なスキルや経験が明らかになるため、自己研鑽に励む動機付けにもなるのです。
さらに、自分の将来とその会社での成長がリンクしていると感じられれば、会社に対するロイヤリティが向上します。能力次第で誰もがキャリアアップできるという状況は、社員の士気を高めることにつながるでしょう。
このように、会社がモデルケースやキャリアパスを提示することは、社員の目標設定、自己啓発、モチベーション向上などに大きく貢献します。結果として、社員一人ひとりが高い意欲を持って働ける職場環境の実現につながるのです。
労働環境を見直す
労働環境の見直しは、社員のモチベーションを高めるために重要です。以下のような取り組みをおこなうことで、社員の満足度を向上させ、やる気を引き出せるでしょう。
- 柔軟な勤務時間の導入
- リモートワークの推進
- 適切な休暇取得の推進
- 快適なオフィス環境の整備
柔軟な勤務時間の導入により、社員はライフスタイルに合わせた働き方ができるようになります。仕事と私生活のバランスを取りやすくなるため、ストレスが軽減されて仕事への集中力が高まります。
また、快適なオフィス環境を整備することも重要です。人間工学に基づいた機器(デスクやチェアなど)を導入したり、リラックスできるスペースを設置したりすることで、社員の心身の健康を促進できます。
これらの取り組みを通じて、会社が社員のウェルビーイングを大切にしていることを示し、社員のエンゲージメントを高めていきましょう。
社員のストレス状態を正確に把握するためには、定期的なストレスチェックの実施も必要です。
以下の記事では、ストレスチェックの具体的な取り組みを、「人事主導型」と「従業員参加型」に分けて詳しく解説しています。検査結果を活用するときのポイントも紹介していますので、本記事と合わせて確認してみてください。

社員のやる気を高めて生産性を上げよう
社員のやる気は、企業の生産性を左右する重要な要素です。社員のやる気が下がる主な原因としては「人事評価への不満」「職場の人間関係の悪化」「仕事のやりがい不足」が挙げられます。
本記事で紹介した方法を実践することで、社員一人ひとりのモチベーションを向上させ、活気あふれる組織づくりを目指していきましょう。
なお、社員のウェルビーイングを向上させ、組織を活性化させていくためには、社員の状態を定期的に把握し、適切な対策を講じる必要があります。そこでおすすめしたいのが『ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ』です。
『ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ』は、簡単なアンケートで社員のコンディションを可視化し、組織の課題を特定するのに役立ちます。早期に課題を発見し、対策を講じることで、社員の離職防止や生産性向上につながるでしょう。
組織全体の成長と社員一人ひとりの幸せなキャリアのために、『ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ』の導入を検討してみてはいかがでしょうか。
従業員のメンタル状態の定期的な可視化・個々の性格に合わせたアドバイス提供を通じ、離職・休職を防ぐエンゲージメントサーベイ。無料トライアルの詳細は下記から。



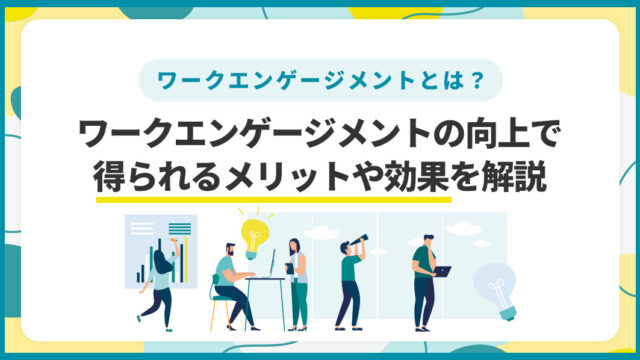
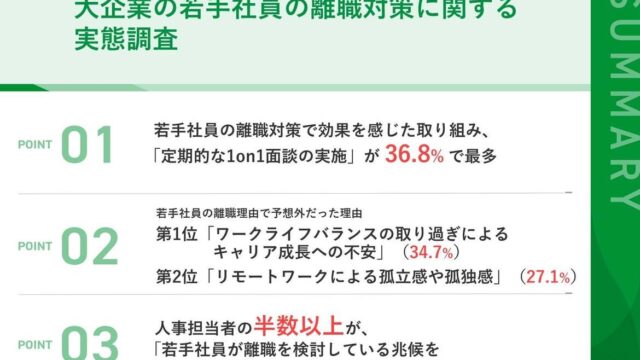







 ランキング1位
ランキング1位 
 ランキング2位
ランキング2位 
 ランキング3位
ランキング3位 