エンゲージメントサーベイは、近年多くの企業で導入が進む重要な人事施策です。その背景には、アメリカ発の理論的発展や日本企業への普及を後押しした政策的な動きがあります。
本記事では、エンゲージメントサーベイの誕生から現在に至るまでの歴史を整理し、日本で注目が高まっている理由を解説します。
導入の根拠を社内で説明したい人事担当者の方は、ぜひ参考にしてください。

エンゲージメントサーベイの歴史はアメリカで始まった
エンゲージメントという概念の起源は、1990年にアメリカの心理学者、ウィリアム・A・カーンが発表した論文にさかのぼります。
カーンは、
| 個人が仕事に感情・認知・身体のエネルギーをどれだけ投入している状態か |
を説明する概念として「エンゲージメント」を提唱しました。
その後、アメリカではエンゲージメントを科学的に測定しようとする研究が進み、特にフランク・L・シュミット博士らの研究グループは、エンゲージメントと業績・生産性・離職率との関連を統計的に証明。エンゲージメントが企業成果に影響を与える重要指標であることを示しました。
また、1990年代後半からアメリカの世論調査会社Gallup社が大規模な国際調査「Q12サーベイ」を開始したことが、エンゲージメントの概念を世界中の企業へ普及させるきっかけとなりました。
Gallup社も調査結果により、エンゲージメントの高さが離職率の低下や業績向上につながることを報告しています。
これらの流れから、従業員のエンゲージメント状態を定期的に数値化し、組織改善につなげる調査ツールとして普及したのが「エンゲージメントサーベイ」です。
出典:一般社団法人日本エンゲージメント協会「第26回エンゲージメント研究会『エンゲージメントの歴史』開催レポート」
従業員エンゲージメントとワークエンゲージメントの違い
エンゲージメントと呼ばれる概念には「従業員エンゲージメント」と「ワークエンゲージメント」という2つの学術的系統があります。
| 種類 | 提唱者 | 概要 |
|---|---|---|
| 従業員エンゲージメント | Gallup社によって概念が普及研究はフランク・L・シュミット博士らが貢献(アメリカ) | 組織やチームへの貢献意欲・愛着・自発性を示す離職防止・業績向上との関連が強い |
| ワークエンゲージメント | 心理学者ウィルマー・B・シャウフェリ教授ら(オランダ) | 仕事に対するポジティブで充実した心理状態「活力・熱意・没頭」で構成され、働きがい・生産性と関係 |
従業員エンゲージメントは、組織やチームの目標達成に貢献しようとする自発的な意欲を示し、離職率、生産性、業績との関連性が実証されています。そのため、多くの企業が経営戦略や人材マネジメントで活用すべき指標として採用しています。
一方、ワークエンゲージメントは仕事に対する活力・熱意・没頭といったポジティブな心理状態で、働きがいや生産性と関わる指標です。
エンゲージメントが重要視された背景
エンゲージメントが注目され始めた背景には、アメリカの労働市場構造の変化と文化的特性があります。
アメリカは日本と異なり、転職が一般的な流動型雇用社会であり、個人主義的な価値観が強いため、従業員は企業への帰属意識より「働きがい」や「自己成長」を重視する傾向があります。
企業は給与や福利厚生だけでは優秀人材を引き留められず、従業員の心理的エンゲージメントに注目する必要が高まりました。
Gallupの調査では、エンゲージメントの高い企業は低い企業に比べて離職率が最大43%低いことが報告されています。企業の競争力維持には働きがいのある職場設計と人材定着が不可欠であることが明らかです。
こうした背景から、従業員満足度(ES)に代わる組織状態の指標としてエンゲージメントが導入され、2000年代以降、科学的に測定するための「エンゲージメントサーベイ」が急速に普及していきました。
日本におけるエンゲージメントサーベイの歴史
日本にエンゲージメントの概念が本格的に紹介されたのは2000年代に入ってからです。
2003年にヒューマンバリュー社が日本で初めてエンゲージメントサーベイを提供したことが国内導入の出発点とされています。
その後、2017年に公開されたGallup社の国際調査で「日本の従業員エンゲージメントは世界最低水準の6%」であると報告され、注目が高まりました。
この結果を受け、日本企業でも「働きがい」「人材の定着」「人的資本経営」と関連づけてエンゲージメントの重要性が見直され、エンゲージメントサーベイの市場が急速に拡大しました。
出典:Dismal Employee Engagement Is a Sign of Global Mismanagement
出典:エンゲージメント・サーベイの活用|エンゲージメント向上支援|WHAT WE DO|HUMAN VALUE
経団連・経産省もエンゲージメントに注目
エンゲージメント向上の重要性は、近年、日本において国レベルで注目されています。
実際に経団連(日本経済団体連合会)は2019年の記者会見で次のように提言。
| 「現下の日本の最大の課題は、生産性向上である。(中略)働き方改革とエンゲージメント(やる気)を高める取り組みをセットで強力に進めていくことも必要である。」 |
引用:日本経済団体連合会「2019年11月25日 記者会見」
また、経済産業省は2020年発表の「人材版伊藤レポート」において、人的資本経営の重要性を正式に打ち出し、その中で従業員エンゲージメントを企業価値を向上させる中核指標として位置づけています。
経済産業省推奨のエンゲージメント向上のための取り組みとは
経済産業省が2022年に発表した「人材版伊藤レポート2.0」では、エンゲージメント向上のために取り組むべき施策を次のように提示しています。
| 取り組むべき内容 | 目的 | 具体的な施策例 |
|---|---|---|
| エンゲージメントレベルの可視化・把握 | 離職防止・組織状態の可視化・業績向上の基盤づくり | エンゲージメントサーベイを定期実施し、スコア推移を経営会議でレビューする |
| ストレッチアサインメント | 成長実感の創出による離職防止・次世代リーダー育成 | 個人のキャリア意向を把握し、挑戦機会となる業務を計画的に割り当てる |
| 社内公募制度の導入 | 自律的キャリア形成・エンゲージメント向上 | 部署異動希望を社員が申請できる社内公募制度を設置する |
| 副業・兼業の推進 | 人材成長・越境学習による組織活性化 | 副業制度や越境学習制度を導入し、外部での経験獲得を奨励する |
| 健康経営とウェルビーイングの推進 | 心身のパフォーマンス維持・持続的な組織運営 | メンタル支援・産業医体制の整備、ストレス分析と職場改善を実施する |
これを受け、日本の各企業ではエンゲージメントサーベイの導入・運用が進んでいます。
出典:経済産業省「人的資本経営の実現に向けた検討会 報告書 ~ 人材版伊藤レポート2.0~」
日本ではエンゲージメントサーベイの市場規模が拡大中
日本企業においてエンゲージメントサーベイの導入は急速に進んでおり、市場規模は今後さらに拡大すると予測されています。
2024年の矢野経済研究所の市場調査によると、日本のエンゲージメント向上支援市場は2028年に150億円規模へ成長する見込み。
つまり、エンゲージメント向上の取り組みは一過性の流行ではなく、中長期的な経営課題として位置づけられていることがわかります。
市場が急成長した最大の要因は、コロナ禍をきっかけとした働き方の変化です。リモートワークの普及により、従来のように「職場の空気感」や「管理職の観察」に頼るマネジメントが難しくなり、従業員のコンディションを定量的に把握するニーズが高まりました。
このような環境変化を受け、エンゲージメントサーベイは単なるアンケートではなく、人材戦略や経営指標と連動する意思決定ツールとして活用されるようになっています。
出典:従業員エンゲージメント市場に関する調査を実施(2024年) | ニュース・トピックス | 市場調査とマーケティングの矢野経済研究所
持続可能な企業運営のためにはエンゲージメントサーベイの導入・活用が不可欠
エンゲージメントサーベイは国内での歴史こそ浅いものの、市場規模は拡大を続け、人的資本経営・健康経営の文脈でも重要な経営指標として位置づけられています。しかし、導入企業のなかには「実施して終わり」となり、結果を活用しきれていないケースも少なくありません。
実際には、サーベイ結果を起点に改善アクションへつなげた企業の約7割が、生産性向上や離職率低下などの効果を実感しているという調査結果もあります。
出典:【エンゲージメントサーベイ】サーベイ後に“アクションを起こした”企業の方が「生産性」・「業績」が向上している結果に|人事のプロを支援するHRプロ
つまり、重要なのはサーベイの実施そのものではなく、活用と改善につなげる運用設計です。
「ミキワメ ウェルビーイングサーベイ」は、結果の可視化だけで終わらせず、離職リスクの検知や課題領域の特定、改善アクション提案までを可能とする次世代型サーベイです。
人材データを活かした組織づくりを進めたい企業に最適なソリューションといえるでしょう。
詳細は以下からご確認ください。
従業員のメンタル状態の定期的な可視化・個々の性格に合わせたアドバイス提供を通じ、離職・休職を防ぐエンゲージメントサーベイ。無料トライアルの詳細は下記から。

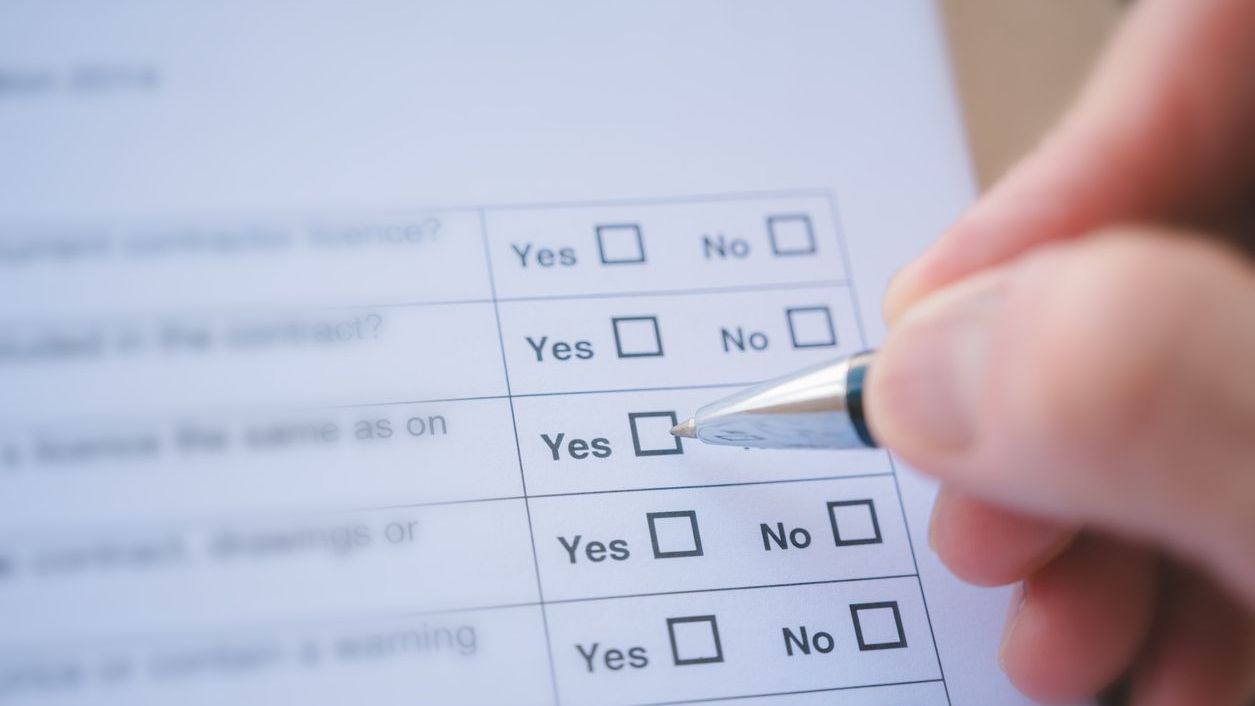



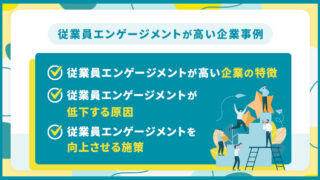


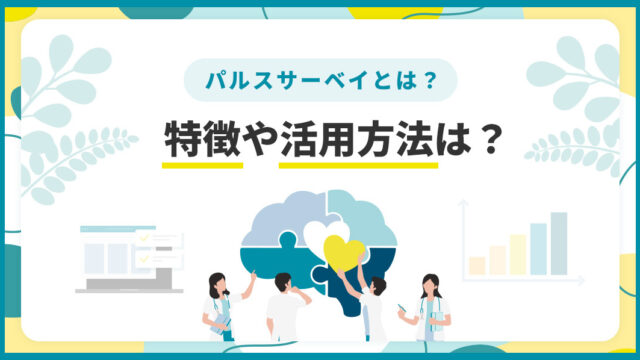







 ランキング1位
ランキング1位 
 ランキング2位
ランキング2位 
 ランキング3位
ランキング3位 