社員の仕事への活力を高めることは、個人の意欲向上だけではなく、チーム全体の士気向上にもつながります。仕事に貢献したいという姿勢が育まれ、企業の持続的な発展に好影響を与えるためです。
反対に、活力のない社員がいると、その影響がチームに広がり、チーム全体の生産性が低下しかねません。離職を選択する社員が増え、優秀な人材の流出を招くおそれもあります。
今回の記事では、社員の仕事への活力を高めるメリットや具体的な方法を解説します。組織内の活力向上を目指す人事担当者様は、ぜひ参考にしてください。

ビジネスにおける活力の位置づけ
ビジネスにおける活力とは、身体面と精神面の両方において発揮されるエネルギーです。活力のある社員は仕事をすることで力がみなぎり、疲労からの回復も早くなります。
活力は業務を遂行するための原動力であり、車にたとえるならエンジンやガソリンです。しかし、それらだけでは、車は目的地にたどり着けません。安全かつ的確に進むためには、ハンドルやブレーキによるコントロールが必要です。
このコントロールにあたるのが、仕事に対するポジティブな姿勢です。社員は業務にあたって前向きな気持ちをもつことで活力を適切に調整し、モチベーションを高く保てます。
活力に関連する概念
ビジネスにおける活力への理解を深めるためには、関連する以下の3つの概念についても把握しておくことが重要です。
- ワークエンゲージメント
- ワーカホリズム
- バーンアウト
詳しく見ていきましょう。
ワークエンゲージメント
ワークエンゲージメントとは、仕事に対してポジティブな姿勢で取り組み、高い成果を発揮できる状態を指します。「活力」は、このワークエンゲージメントを構成する要素の一つです。
- 活力:仕事に対するエネルギーが高く、前向きに取り組める状態
- 熱意:仕事にやりがいを感じ、主体的に取り組める状態
- 没頭:仕事に深く集中し、時間を忘れて取り組める状態
ワーカホリズム
ワーカホリズムとは、一見活力があり活動水準も高いものの、常に時間や業務に追われ、心に余裕がない状態を指します。こうした社員はプライベートよりも仕事を優先し、休日出勤や長時間労働をしがちです。
短期的には高い生産性を発揮し、成果を上げることができますが、長期的には心身に不調をきたし、最終的には「バーンアウト(燃え尽き症候群)」に陥るおそれがあります。
バーンアウト
バーンアウト(燃え尽き症候群)とは、活力を失い、仕事への意欲が著しく低下した状態です。主な原因としては、企業や仕事に対する不信感、心身の不調、過重労働による疲労、人間関係の悩みなどが挙げられます。
これらの要因が重なることで、ワーカホリズムの状態からバーンアウトに陥ってしまうケースも少なくありません。
仕事への活力を高めるメリット
社員の仕事への活力を高めることは、個人だけではなく組織全体にも多くのメリットをもたらします。
- 業務効率が上がる
- チーム全体の士気が向上する
- 新たな価値の創出につながる
- 対外的な企業イメージがよくなる
それぞれのメリットについて詳しく解説します。
業務効率が上がる
活力に満ちた社員が多い組織では、業務効率の向上が期待できます。社員一人ひとりが意欲的に業務に取り組むことで、集中力や判断力が高まり、業務をスムーズに進められるためです。
また、組織や自己成長のためにスキルアップにも積極的に取り組むことから、通常業務や課題解決を効率的に行えます。結果として、生産性の向上やワークライフバランスの改善につながるでしょう。
チームの士気が向上する
活力のある社員は周囲にもポジティブな影響を与えるため、チームの士気が向上します。意見交換が活発に行われることから、生産性の向上に加え、新しいアイデアの創出も期待できるでしょう。
また、活力のある上司は部下に対して積極的に教育や指導を行う傾向があり、その結果、知識や技術の引き継ぎも円滑に行われます。さらに、部下もそうした上司の姿勢を見習うため、人材育成においても好循環が生まれるのです。
新たな価値の創出につながる
仕事への活力は新たな価値の創造をもたらします。業務を遂行するエネルギーが十分にあることで思考が広がり、新しい発想が生まれやすくなるためです。
また、チーム内の士気が高まることで、メンバー同士が刺激し合う機会も増えます。何気ない雑談のなかからも生産的なアイデアが生まれやすくなり、イノベーションや課題解決につながるヒントが見つかる可能性もあります。
対外的な企業イメージが良くなる
社員の仕事への活力を高めることは、対外的な企業イメージアップやブランティングの確立にもつながります。取引先やマスコミ、候補者が企業を訪れた際、活力のある社員が多いと「元気な会社」という好印象をもってもらえるためです。
また、活力の高い社員は、自信をもって自社の商品やサービスをアピールできます。自社製品の良さを十分に把握したうえでの営業が可能となり、取引先の満足度や信頼感が高まります。
仕事への活力が高まる要因と具体的施策
仕事への活力を高める主な要因は以下の4つです。
- 身体的健康
- メンタルヘルス
- 働きやすさや労働条件
- 仕事へのモチベーション
それぞれの要因について、詳細と具体的な対策をご紹介します。
身体的健康
身体的健康は活力を高めるための土台です。ケガや病気は社員の気力を奪い、活力を低下させる要因となります。離職や休職につながるケースもあるため、企業としても優先的に取り組むべき課題です。
近年では、社員の健康を経営課題と捉えて戦略的に取り組む「健康経営」が注目されています。社員の健康を守ることは企業の義務であると同時に、生産性や定着率の向上にもつながる重要な経営施策です。
具体的な施策
身体的健康を守るための具体的な対策としては、以下が挙げられます。
長時間労働の是正
たとえ労働意欲が高くても、長時間労働が慢性化すると身体的な負担が蓄積していきます。また、自分自身をケアする時間が減り、生活リズムや栄養バランスが乱れることも、体調を崩す原因の一つです。
業務分担の見直しや業務効率の改善、フレックスタイム制度の導入などにより長時間労働を解消することで、社員の身体的健康を維持しやすくなります。
定期的な健康診断
定期的な健康診断の実施も、社員の健康を守るために有効な手段です。
体調不良は、本人の自覚がないまま進行している場合も少なくありません。病気が顕在化してからの対処では、治療に時間を要し、社員の経済的・身体的な負担も大きくなってしまいます。
健康診断によって不調を早期に発見することで、病気の予防につながり、社員の健康を継続的に守れます。
休憩所や仮眠スペースの設置
社員がゆっくり体を休められる休憩所や仮眠スペースを設けることも、健康維持に有効な取り組みです。
睡眠不足による免疫力の低下やストレスの蓄積は、生活習慣病のリスクを高める要因となるほか、判断力や集中力の低下により、労災事故を引き起こす危険性もあります。
十分な休息や睡眠を確保できる環境を整えることで、社員の病気やケガを未然に防げるでしょう。
メンタルヘルス
身体的な健康に加え、精神的な健康(メンタルヘルス)の維持も、社員の活力に大きく影響します。強い不安やストレスを抱えたまま業務を続けると、生産性が低下するだけではなく、休職や離職につながるリスクも高まります。
身体的健康と同様に、メンタルヘルスにおいても「早期発見」が重要です。社員のメンタル状態を適切に把握し、迅速に対応することで、活力の低下を防ぎ、健全な労働環境を維持できます。
具体的な施策
メンタルヘルスを維持するための具体的な対策は以下のとおりです。
1on1による聞き取り
1on1とは、上司と部下が1対1で定期的に行うミーティングです。業務の進捗状況、人間関係の悩み、心身の不調などについて気軽に相談できる機会を設けることで、信頼関係の構築やモチベーションの維持につながります。
1on1を通じてメンタルの不調を早期に把握できれば、悩みの原因を取り除いたり、産業医と連携したりするなど、適切な対応を講じることが可能です。
定期的なストレスチェックの実施
ストレスチェックとは、いわばメンタルヘルスの健康診断です。社員がストレスに関する質問票に回答し、その結果を点数化することにより、現在のメンタル状態を客観的に評価できます。
高ストレスと判定された社員に対しては、業務の割り振りの見直しや専門家によるサポートを行うと、メンタル不調による活力の低下、休職や離職の予防が期待できます。
また、特定の部署にストレスが集中している場合は、人間関係や業務負荷に課題がある可能性があるため、部署全体の状況を見直し、活力の維持と士気の向上につなげていくことが重要です。
以下の記事では、ストレスチェックの具体的な取り組みを、「人事主導型」と「従業員参加型」に分けて詳しく解説しています。検査結果を活用するときのポイントも紹介していますので、本記事と合わせて確認してみてください。

産業医や看護師などの専門家によるサポート
産業医や看護師、カウンセラーなど、専門家によるサポート体制を充実させることも、社員のメンタルヘルスを守るための重要な取り組みです。社内では相談しづらい悩みも話しやすくなり、専門的な視点から的確なアドバイスを受けられます。
これにより、メンタル不調の早期発見が可能となるだけではなく、休職中の社員に対しても復職に向けた実践的な支援ができます。
メンタル不調の社員を適切に支援することで、個人の活力維持にとどまらず、チーム全体のモチベーション向上にもつながるでしょう。
働きやすさや労働条件
仕事量の適正化や裁量の確保、サポート体制の充実は、活力の維持や向上において欠かせない要素です。「無理なく仕事ができている」「自分が主体的に業務に取り組めている」といった安心感や自己肯定感が、社員の活力を高める原動力となります。
労働環境を改善するには、社員の適性や関心に合った業務を適切に配分し、働きやすい職場づくりに向けた施策を進めることが重要です。
具体的な施策
働きやすさや労働条件を改善するための具体的な施策は以下のとおりです。
仕事量の調節や業務効率化
過重労働は心身の不調を引き起こし、意欲を失わせる要因となります。社員一人ひとりの業務を再分担し、仕事量を調整することで、過重労働を是正できます。
また、現在の業務内容やその工数を見直すことも重要な施策です。不要もしくは非効率な業務を中止または簡略化して、社員の負担を軽減しましょう。
業務量の削減や効率化を始めとした業務の見直しについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
裁量権の付与
裁量権とは、社員が自らの判断で行動を決定する権利です。裁量権を付与することで、社員の自主性が養われ、成長の機会が増えます。自分の意志で業務に取り組み、組織に貢献できる喜びは、社員の活力を高めます。
一方で、裁量権が負担となり、メンタルに不調をきたす社員もいるため注意が必要です。社員の性格や適性を理解し、適切な範囲で裁量権を付与しましょう。
上司を始めとした周囲からのサポート
業務を行うなかで、とくに活力を低下させる要因として孤独感が挙げられます。「仕事や人間関係の悩みを相談できる相手がいない」「雑談ができず寂しい」といった孤独感は、社員の心理的安定を低下させ、活力を損なう原因となります。
現在導入が進んでいるテレワークも、孤立感を助長する要因の一つです。テレワークには、通勤時間の削減や集中力の向上といったメリットがある一方で、コミュニケーションやチームの連携が不足するデメリットもあります。
上司をはじめ、社員同士が積極的にコミュニケーションを取り合い、互いにサポートすることで孤独感をやわらげ、社員の活力の維持や向上につなげられます。
仕事へのモチベーション
明確な目標が設定されていること、適切なフィードバックが得られること、そして自身の成長を実感できることは、仕事へのモチベーションを高める重要な要素です。働きがいが生まれ、社員の活力も自然と向上します。
具体的な施策
モチベーションを高めるには、以下のような施策が効果的です。
キャリアデザインのサポート
キャリアデザインとは、社員自身が将来のビジョンを明確にし、その実現に向けたステップを設計することです。企業が社員のキャリアデザインを積極的にサポートすることで、社員のモチベーションや活力を向上させる効果が期待できます。
さらに、社員の興味や適性の方向性を把握しやすくなるため、適材適所の人材配置が実現しやすくなる点も大きなメリットです。
適切なフィードバックと人事評価
努力や成果に対して適切なフィードバックを行い、人事評価に反映させることも、活力向上のための重要な施策です。努力すれば報われる環境を整えることは、社員の意欲を引き出し、企業成長への積極的な貢献につながります。
たとえば、1on1を通じて部下の成長を支援したり、成果に応じて昇進・昇給を決定する評価制度を導入したりする施策が効果的です。
研修やセミナーの実施
研修やセミナーの実施は、社員の自己成長を促進し、活力を高めるために有効です。学びによって身についた知識やスキルは、業務へのより深い理解や前向きな姿勢を育みます。
また、学ぶ機会を与えられているという実感が、企業への信頼や帰属意識の向上につながり、組織全体の活力向上にも寄与します。
仕事の活力を高める施策を行う際の注意点
仕事の活力を高めるためには、企業が積極的に介入し、適切な施策を講じることが重要です。しかし、やみくもに施策を実施するだけでは、十分な成果を得られず、かえって費用や手間ばかりがかかってしまいます。
仕事の活力を高める施策を行う際には、以下の2点に注意しましょう。
- 業務の目的や意義への理解を深める
- 活力の測定・可視化を行う
それぞれの具体的なポイントをご紹介します。
業務の目的や意義への理解を深める
たとえ社員に活力があったとしても、仕事の目的や意義を十分に理解していなかったり、それを肯定的に捉えていなかったりすると、ワーカホリズムに陥りやすく、最終的にはバーンアウトに至るリスクがあります。
そのため、活力を高めるための施策を実施する際は、業務の目的や意義を明確に伝えることが重要です。
経営層や管理職が「なぜこの仕事が必要なのか」「どのように社会や顧客に貢献しているのか」を言語化し、社員へ丁寧に説明することで、仕事に対する納得感や自発的なやりがいを高められます。
活力の測定・可視化を行う
社員の活力を定期的に測定することは、組織の現状を正しく把握し、課題を明確にするために有効です。活力の状態を把握することで、どの部署や業務で活力が低下しているのかといった傾向を分析し、それに基づいた具体的な施策の立案に活かせます。
また、施策を実施したあとの効果を検証するためにも、活力の測定は欠かせません。施策前後の変化を比較することで、取り組みがどの程度成果を上げているのかを客観的かつ定量的に評価できます。
このような測定に活用できるツールが「エンゲージメントサーベイ」です。社員の意識や感情に関するデータを簡便かつ継続的に収集でき、分析にも手間がかかりません。結果として、より実態に即した対策の立案と改善が可能となります。
以下の記事では、導入前に知っておきたいエンゲージメントサーベイの選び方を5ステップで解説しています。すぐに活用できるチェックリストもありますので、本記事と合わせて確認してみてください。

従業員の仕事への活力を高め、ポジティブな会社づくりを目指そう
活力は、仕事をする上で「エンジン」とも言える重要な要素です。活力を高めることで、組織全体がポジティブな雰囲気になり、生産性や士気の向上だけではなく、対外的なイメージアップも期待できます。
活力を向上させるためには、社員の心身の健康維持や働きやすい環境づくり、そしてモチベーションの向上が欠かせません。さらに、活力の状態を定量的に把握することで、効果的な施策の立案や実施後の評価を行いやすくなります。
「ミキワメ ウェルビーイングサーベイ」では、月に一度の調査を通じて、従業員の仕事への活力を組織全体・部署単位・個人単位で可視化できます。活力向上施策の一環として、ミキワメ ウェルビーイングサーベイの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
興味のある方は、以下より詳細をご覧ください。
従業員のメンタル状態の定期的な可視化・個々の性格に合わせたアドバイス提供を通じ、離職・休職を防ぐエンゲージメントサーベイ。無料トライアルの詳細は下記から。





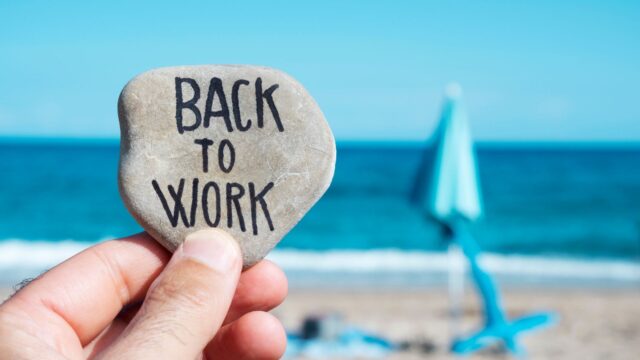







 ランキング1位
ランキング1位 
 ランキング2位
ランキング2位 
 ランキング3位
ランキング3位 